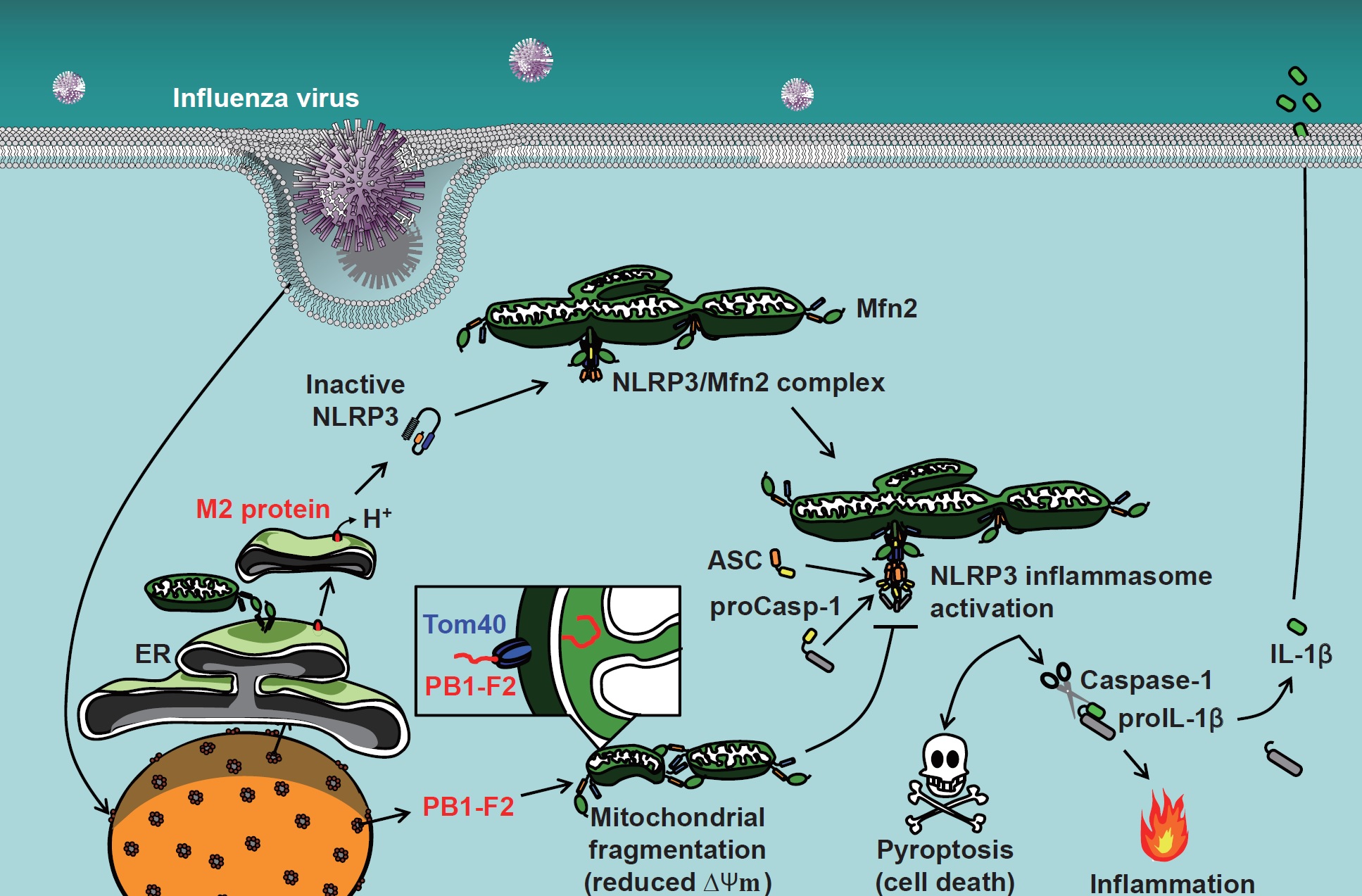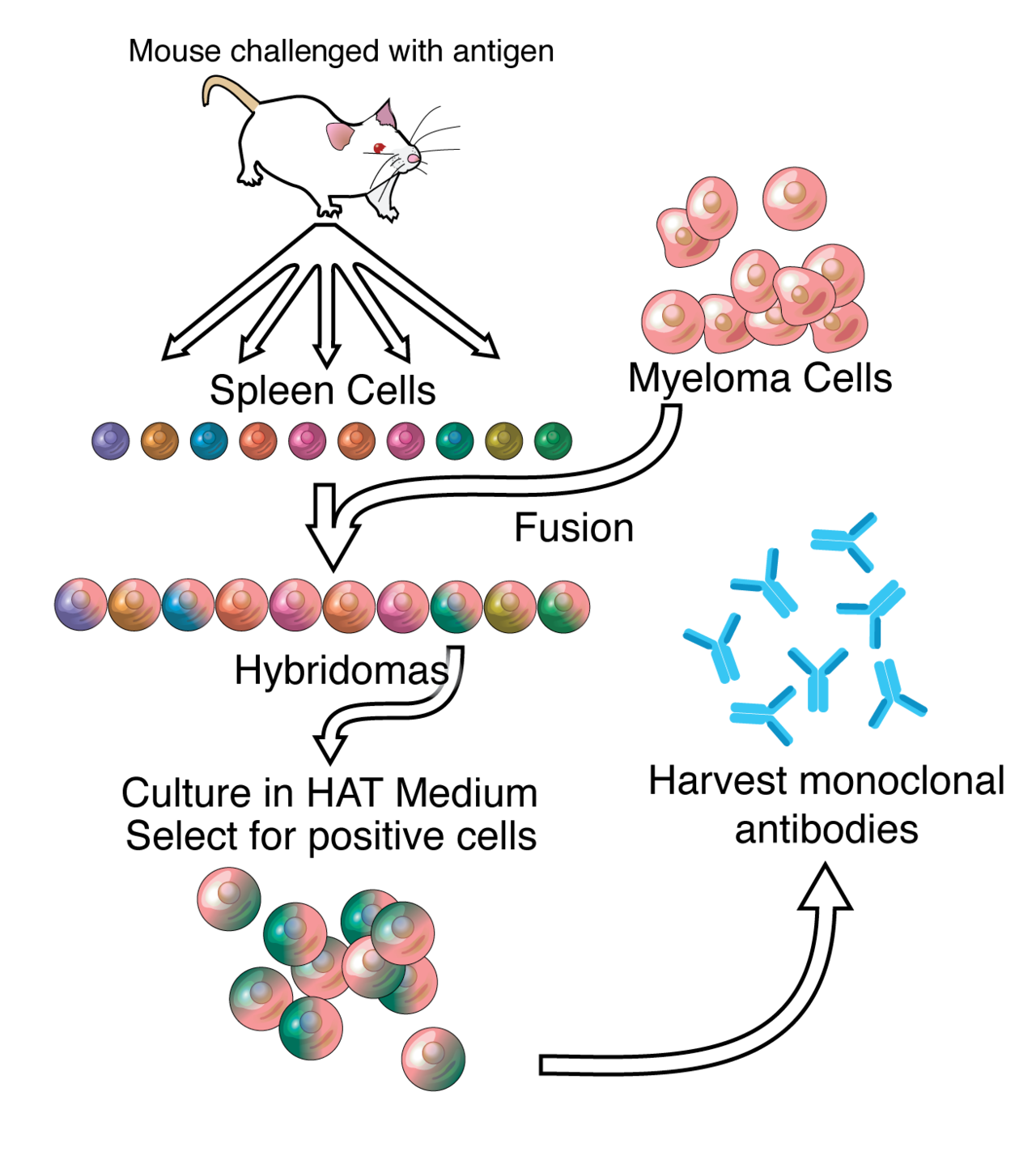もどる
ウイルスの抗体
2021.6.6日曜日
5月3日から再開して、一か月経った。コロナワクチンのことを調べてみる。
日本の接種率は徐々に増えてきているのがありがたいが、世界はまだまだこれから。頑張ってほしい。
引用:https://www.rnaj.org/newsletters/item/856-furuichi-28
引用:Wikipedia pseudo uridine
mRNAによるワクチンについてカリコ博士が説明した中で、uridineをpseudo uridineに置き換えたら炎症が起きなかったとあったので、
日本RNA学会の古市氏の論文を読んで、理解できたことがたくさんありました。
「Pseudo-uridineを含むmRNAは細胞内へ導入しても、自然免疫に基づくeIF2のリン酸化などによる、蛋白合成の停止を誘導しないことを発見していた。」
pseudo uridineは、tRNAの配列の中にもあるようですが、今回のmRNAのuridineの全部がpseudo uridineに置き換えられているのかは説明されていませんが、生命作用の神秘をうかがわせます。
2021.5.3 及び現在
12:08 2023/03/13
Johns Hopkins大学のデータ更新が2023/3/10をもって終了したため、このページのデータの更新は終了します。
こちらは、以前書いていた内容:
------------------------------------------
唾液と鼻粘液の中には多量のIgA抗体が含まれている。
IgA抗体は口腔内と鼻腔内のウイルスや細菌を取り囲み、胃酸の中で死滅させる。
よく噛んで、鼻から息を吸って、夜寝るときは口の中を乾かさないように口マスクをして、疲れたら体を休ませ、寝不足しないように気をつける。
疲れるとIgA抗体が少なくなる。
こうして時は過ぎ、春からやがて夏が来て、秋になった。
------------------------------------------
-------------------------------
「胸部CTで肺病変があれば,発症後6日にはアビガン治療を開始していただきたい」という開発者の見解を尊重する。
-------------------------------
--------------------------------------
国立感染症研究所でワクチンの開発を進める発表があった。経鼻ワクチンなのだろうか。期待したい。
DNAワクチンのようだ。体内細胞にSタンパク質を産生させ抗原とする。
--------------------------------------
--------------------------------------
エンベロープのSタンパク質の遺伝子をプラスミドで大腸菌に移入してSタンパク質を産生し、それを経鼻ワクチンとして使用して、IgAの産生を誘導するのは有効ではないだろうか。
--------------------------------------
新型コロナウイルスの感染状況
2020.11.4調べ
増加率を毎日値から週平均値に変更した。(2020.8.5)
厚生労働省の資料と2020.10.18まで読売新聞のデータを利用しています。
「世界:感染者、死亡、回復」のworld,death,recovered,I+S+G+F+E,USは、それぞれ世界の感染者、死亡、回復者の合計、およびイタリア、スペイン、ドイツ、フランス、イギリスの感染者の合計、アメリカの感染者を表し、下記サイトのデータ等を参照しています。
引用:Johns Hopkins University & Medicine
各国合計は急上昇中。中国は飽和に向かっている。
北海道は先に進んでいて、飽和に向かいつつある。
東京は3.24から急上昇し、その後飽和に向かう兆候が見えたが、6月上旬以降増加し、7.1から急上昇してきた。
大阪、埼玉、神奈川は上昇している。
K値(週発生数を累積数で除した値)によれば:
感染者のK値が大きいのは、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、イギリス、スウェーデン。
感染者数から死亡と快復者を差し引いた数値で推測すると:
ブラジルは11月上旬に終息する(均衡する)。
日本は微増している。
ロシア、ベラルーシは徐々に増加している。
フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ドイツ、アメリカは急増している。
---------------------------------------------------
2021.5.3
2021.5.3
5か月ぶりに再開した。深刻な状況だが、世界と日本に注目したい。
2022.1.1より、データソースをジョンズ・ホプキンス大学、厚生労働省、NHK及び読売新聞としています。
2023.3.11(土)
8波は増加傾向になり、感染者の増加数は世界の5分の1~3分の1になっている。
一方、人口に対する感染率は26.4%であり、欧米に比べ低いが、米国の31.7%に近づいてきた。
日本の特徴は死亡率が低いこと。
急激に減少してきたが、再び急増し、急に減少。
(今日は9,117、明日土曜日は9,000くらいか。)
今日は9,083、明日日曜日は7,000くらいか。
増減の周期が変化している。
12:08 2023/03/13
Johns Hopkins大学のデータ更新が2023/3/10をもって終了したため、感染データ等の更新は終了します。
日本の状況は読売新聞のデータにより引き続き記録します。
日本の毎日のデータの提供は2023/5/8で終了。
日本の状況
感染者増 感染者合計 増加傾向
2022.1.9日 + 8249 1,766,713
2022.1.10月 + 6435 1,773,140 0.780
2022.1.11火 + 6368 1,779,508 0.989
2022.1.12水 +13244 1,792,752 2.079
2022.1.13木 +18860 1,811,616 1.424
2022.1.14金 +22045 1,834,361 1.168
2022.1.15土 +25742 1,860,094 1.167
2022.1.16日 +25658 1,885,748 0.996
2022.1.17月 +20991 1,906,727 0.818
2022.1.18火 +32187 1,938,914 1.533
2022.1.19水 +41485 1,980,399 1.288
2022.1.20木 +46199 2,026,598 1.113
2022.1.21金 +49855 2,076,412 1.079
2022.1.22土 +54581 2,130,975 1.094
2022.1.23日 +50030 2,180,985 0.916
2022.1.24月 +44787 2,225,772 0.895
2022.1.25火 +62596 2,288,368 1.397
2022.1.26水 +71633 2,359,970 1.144
2022.1.27木 +78897 2,438,867 1.101
2022.1.28金 +81788 2,520,655 1.036
2022.1.29土 +84891 2,605,546 1.038
2022.1.30日 +78103 2,683,649 0.920
2022.1.31月 +61033 2,744,682 0.781
2022.2.1火 +81629 2,826,311 1.337
2022.2.2水 +94930 2,921,241 1.162
2022.2.3木 +96846 3,025,620 1.020
2022.2.4金 +95453 3,123,885 0.985
2022.2.5土 +100949 3,226,201 1.057
2022.2.6日 +89145 3,316,122 0.883
2022.2.7月 +68039 3,384,116 0.763
2022.2.8火 +92078 3,485,245 1.353
2022.2.9水 +97833 3,583,100 1.062
2022.2.10木 +99695 3,682,771 1.019
2022.2.11金 +98370 3,781,116 0.986
2022.2.12土 +68470 3,848,837 0.696
2022.2.13日 +77450 3,926,984 1.131
2022.2.14月 +60142 3,987,095 0.776
2022.2.15火 +84221 4,071,290 1.400
2022.2.16水 +91051 4,162,219 1.081
2022.2.17木 +95208 4,257,404 1.045
2022.2.18金 +87723 4,345,097 0.921
2022.2.19土 +81612 4,426,691 0.930
2022.2.20日 +71488 4,498,175 0.875
2022.2.21月 +51987 4,550,142 0.727
2022.2.22火 +69523 4,619,636 1.337
2022.2.23水 +80364 4,699,987 1.156
2022.2.24木 +61259 4,761,209 0.762
2022.2.25金 +65663 4,826,849 1.071
2022.2.26土 +72170 4,898,285 1.099
2022.2.27日 +63703 4,962,693 0.882
2022.2.28月 +51338 5,013,787 0.805
2022.3.1火 +65434 5,079,190 1.274
2022.3.2水 +72646 5,151,814 1.110
2022.3.3木 +70348 5,222,139 0.968
2022.3.4金 +63746 5,285,782 0.906
2022.3.5土 +63673 5,349,435 0.998
2022.3.6日 +53969 5,403,393 0.847
2022.3.7月 +37083 5,440,459 0.687
2022.3.8火 +54024 5,494,467 1.456
2022.3.9水 +63742 5,558,186 1.179
2022.3.10木 +61155 5,619,329 0.959
2022.3.11金 +55882 5,675,188 0.913
2022.3.12土 +55328 5,730,502 0.990
2022.3.13日 +50948 5,781,440 0.920
2022.3.14月 +32471 5,813,893 0.637
2022.3.15火 +50781 5,864,662 1.563
2022.3.16水 +57922 5,922,567 1.140
2022.3.17木 +53587 5,976,126 0.925
2022.3.18金 +49210 6,025,301 0.925
2022.3.19土 +44711 6,069,994 0.908
2022.3.20日 +39659 6,109,637 0.887
2022.3.21月 +27701 6,137,328 0.698
2022.3.22火 +20231 6,157,542 0.730
2022.3.23水 +41038 6,198,553 2.028
2022.3.24木 +49929 6,248,211 1.216
2022.3.25金 +47470 6,295,648 0.950
2022.3.26土 +47338 6,342,978 0.997
2022.3.27日 +43665 6,386,327 0.922
2022.3.28月 +29881 6,416,185 0.684
2022.3.29火 +44466 6,460,638 1.488
2022.3.30水 +53753 6,514,343 1.208
2022.3.31木 +51913 6,566,014 0.965
2022.4. 1金 +49266 6,615,269 0.949
2022.4. 2土 +48825 6,664,086 0.991
2022.4. 3日 +47345 6,711,418 0.969
2022.4. 4月 +30157 6,741,562 0.637
2022.4. 5火 +45684 6,787,233 1.514
2022.4. 6水 +54884 6,842,103 1.201
2022.4. 7木 +54995 6,897,077 1.004
2022.4. 8金 +51953 6,949,007 0.944
2022.4. 9土 +52741 7,001,730 1.015
2022.4.10日 +49172 7,050,897 0.932
2022.4.11月 +33205 7,084,093 0.675
2022.4.12火 +49773 7,133,852 1.499
2022.4.13水 +57758 7,191,589 1.160
2022.4.14木 +55294 7,246,874 0.957
2022.4.15金 +49761 7,296,628 0.900
2022.4.16土 +47598 7,344,207 0.956
2022.4.17日 +39291 7,383,489 0.825
2022.4.18月 +24258 7,407,725 0.617
2022.4.19火 +40893 7,448,617 1.685
2022.4.20水 +47899 7,496,489 1.171
2022.4.21木 +47131 7,543,609 0.984
2022.4.22金 +43003 7,586,563 0.912
2022.4.23土 +43967 7,630,516 1.022
2022.4.24日 +38579 7,669,087 0.877
2022.4.25月 +24839 7,693,911 0.643
2022.4.26火 +40500 7,734,400 1.630
2022.4.27水 +46267 7,780,654 1.142
2022.4.28木 +41756 7,822,395 0.902
2022.4.29金 +36672 7,859,047 0.878
2022.4.30土 +29584 7,884,101 0.806
2022.5.1 日 +26960 7,911,056 0.911
2022.5.2 月 +19353 7,930,400 0.911
2022.5.3 火 +30481 7,960,875 1.575
2022.5.4 水 +26469 7,987,337 0.868
2022.5.5 木 +20779 8,008,126 0.785
2022.5.6 金 +21628 8,029,737 1.040
2022.5.7 土 +39327 8,069,053 1.818
2022.5.8 日 +42538 8,111,582 1.081
2022.5.9 月 +29864 8,140,077 0.702
2022.5.10火 +42160 8,182,182 1.411
2022.5.11水 +45955 8,228,124 1.090
2022.5.12木 +41741 8,269,856 0.908
2022.5.13金 +39647 8,309,491 0.949
2022.5.14土 +39416 8,348,909 0.994
2022.5.15日 +35008 8,383,903 0.888
2022.5.16月 +21784 8,405,684 0.624
2022.5.17火 +36903 8,442,581 1.694
2022.5.18水 +42161 8,484,020 1.142
2022.5.19木 +39642 8,524,359 0.940
2022.5.20金 +37438 8,561,791 0.944
2022.5.21土 +35922 8,597,702 0.959
2022.5.22日 +31457 8,629,157 0.875
2022.5.23月 +18510 8,647,662 0.588
2022.5.24火 +32382 8,680,040 1.749
2022.5.25水 +35190 8,715,214 1.086
2022.5.26木 +31008 8,746,204 0.881
2022.5.27金 +27549 8,773,744 0.888
2022.5.28土 +25759 8,799,502 0.935
2022.5.29日 +20828 8,820,330 0.808
2022.5.30月 +12207 8,832,528 0.586
2022.5.31火 +22122 8,854,551 1.812
2022.6.1 水 +22768 8,877,216 1.029
2022.6.2 木 +20680 8,897,890 0.908
2022.6.3 金 +19271 8,916,572 0.931
2022.6.4 土 +18252 8,934,822 0.947
2022.6.5 日 +15109 8,949,926 0.827
2022.6.6 月 + 9106 8,959,017 0.602
2022.6.7 火 +17039 8,976,051 1.871
2022.6.8 水 +18416 8,994,452 1.080
2022.6.9 木 +16813 9,011,259 0.913
2022.6.10金 +15600 9,026,853 0.927
2022.6.11土 +15351 9,042,203 0.984
2022.6.12日 +13394 9,055,596 0.872
2022.6.13月 + 7956 9,063,549 0.594
2022.6.14火 +15331 9,078,876 1.927
2022.6.15水 +16592 9,095,432 1.082
2022.6.16木 +15515 9,110,940 0.935
2022.6.17金 +14709 9,125,637 0.948
2022.6.18土 +14837 9,140,474 1.008
2022.6.19日 +13160 9,153,632 0.887
2022.6.20月 + 7800 9,161,428 0.592
2022.6.21火 +15384 9,176,804 0.592
2022.6.22水 +17285 9,194,082 1.123
2022.6.23木 +16676 9,210,751 0.964
2022.6.24金 +15815 9,226,717 0.948
2022.6.25土 +16593 9,243,307 1.049
2022.6.26日 +14238 9,257,537 0.858
2022.6.27月 + 9572 9,266,392 0.672
2022.6.28火 +19386 9,286,486 2.025
2022.6.29水 +23346 9,309,827 1.204
2022.6.30木 +23447 9,333,179 1.004
2022.7.1 金 +23156 9,356,340 0.987
2022.7.2 土 +24903 9,381,222 1.075
2022.7.3 日 +23299 9,404.520 0.935
2022.7.4 月 +16808 9,421.322 0.721
2022.7.5 火 +36189 9,457.508 2.153
2022.7.6 水 +45821 9,503,326 1.266
2022.7.7 木 +47977 9,551,285 1.047
2022.7.8 金 +50107 9,601,248 1.044
2022.7.9 土 +55019 9,656,257 1.098
2022.7.10日 +54068 9,710,340 0.982
2022.7.11月 +37143 9,747,472 0.687
2022.7.12火 +76011 9,823,455 2.046
2022.7.13水 +94493 9,917,935 1.243
2022.7.14木 +97788 10,015,712 1.034
2022.7.15金+103311 10,119,009 1.056
2022.7.16土+110675 10,229,671 1.071
2022.7.17日+105584 10,335,243 0.954
2022.7.18月 +76200 10,411,428 0.721
2022.7.19火 +66745 10,478,140 0.876
2022.7.20水+152536 10,630,647 2.285
2022.7.21木+186246 10,816,840 1.221
2022.7.22金+195160 11,011,955 1.047
2022.7.23土+200975 11,212,862 1.029
2022.7.24日+176554 11,389.392 0.878
2022.7.25月+126575 11,515,894 0.717
2022.7.26火+196494 11,712,297 1.552
2022.7.27水+209694 11,921,934 1.067
2022.7.28木+233094 12,154,959 1.111
2022.7.29金+221442 12,376,290 0.950
2022.7.30土+222305 12,598,551 1.003
2022.7.31日+197792 12,796,260 0.889
2022.8.1 月+139687 12,935,888 0.706
2022.8.2 火+211058 13,146,805 1.510
2022.8.3 水+249830 13,396,555 1.183
2022.8.4 木+238735 13,635,212 0.955
2022.8.5 金+233769 13,868,907 0.979
2022.8.6 土+227563 14,096,470 0.973
2022.8.7 日+206495 14,302,864 0.907
2022.8.8 月+137859 14,440,619 0.667
2022.8.9 火+212552 14,653,073 1.541
2022.8.10水+250403 14,903,387 1.178
2022.8.11木+240205 15,143,532 0.959
2022.8.12金+168826 15,312,283 0.702
2022.8.13土+183609 15,495,831 1.087
2022.8.14日+178356 15,674,150 0.971
2022.8.15月+138613 15,812,661 0.777
2022.8.16火+166205 15,978,785 1.199
2022.8.17水+231499 16,210,173 1.392
2022.8.18木+255534 16,465,626 1.103
2022.8.19金+261029 16,726,599 1.021
2022.8.20土+253265 16,979,808 0.970
2022.8.21日+226171 17,205,939 0.893
2022.8.22月+141059 17,346,900 0.623
2022.8.23火+208551 17,555,387 1.478
2022.8.24水+243483 17,798,800 1.167
2022.8.25木+220955 18,019,685 0.907
2022.8.26金+192413 18,212,025 0.870
2022.8.27土+180138 18,392,098 0.936
2022.8.28日+157817 18,549,883 0.876
2022.8.29月+ 95916 18,645,730 0.607
2022.8.30火+152546 18,798,234 1.590
2022.8.31水+169800 18,967,755 1.113
2022.9.1 木+149906 19,117,599 0.882
2022.9.2 金+128728 19,247,818 0.858
2022.9.3 土+123100 19,370,883 0.956
2022.9.4 日+107803 19,478,674 0.875
2022.9.5 月+ 68043 19,546,660 0.631
2022.9.6 火+112198 19,658,800 1.649
2022.9.7 水+129793 19,788,559 1.156
2022.9.8 木+112404 19,900,917 0.866
2022.9.9 金+ 99491 20,000,343 0.885
2022.9.10土+ 92741 20,093,062 0.932
2022.9.11日+ 81491 20,174,553 0.878
2022.9.12月+ 52918 20,227,410 0.649
2022.9.13火+ 87572 20,314,960 1.654
2022.9.14水+100277 20,415,217 1.145
2022.9.15木+ 85867 20,501,065 0.856
2022.9.16金+ 75966 20,577,005 0.884
2022.9.17土+ 70975 20,647,967 0.934
2022.9.18日+ 64044 20,712,002 0.902
2022.9.19月+ 38057 20,750,048 0.594
2022.9.20火+ 31747 20,781,769 0.834
2022.9.21水+ 69832 20,851,584 2.199
2022.9.22木+ 77383 20,928,946 1.108
2022.9.23金+ 63871 20,992,806 0.825
2022.9.24土+ 39218 21,032,017 0.614
2022.9.25日+ 46788 21,078,759 1.193
2022.9.26月+ 43587 21,122,314 0.931
2022.9.27火+ 43594 21,174,936 1.000
2022.9.28水+ 49304 21,224,252 1.131
2022.9.29木+ 42181 21,266,435 0.855
2022.9.30金+ 35997 21,301,608 0.853
2022.10.1土+ 35644 21,337,204 0.990
2022.10.2日+ 29171 21,366,371 0.818
2022.10.3月+ 14809 21,381,184 0.507
2022.10.4火+ 40671 21,421,835 2.746
2022.10.5水+ 41018 21,462,853 1.008
2022.10.6木+ 33827 21,496,595 0.824
2022.10.7金+ 29133 21,525,597 0.861
2022.10.8土+ 26725 21,552,308 0.917
2022.10.9日+ 22613 21,574,921 0.846
2022.10.10月+13038 21,552,357 0.576
2022.10.11火+13055 21,600,789 1.001
2022.10.12水+46389 21,647,189 3.553
2022.10.13木+45652 21,692,838 0.984
2022.10.14金+36277 21,729,116 0.794
2022.10.15土+35342 21,764,424 0.974
2022.10.16日+29415 21,793,839 0.832
2022.10.17月+14888 21,808,729 0.506
2022.10.18火+43272 21,852,002 2.906
2022.10.19水+43384 21,895,322 1.002
2022.10.20木+35948 21,931,271 0.828
2022.10.21金+31802 21,963,069 0.884
2022.10.22土+33874 21,996,941 1.065
2022.10.23日+30822 22,027,763 0.909
2022.10.24月+16507 22,044,273 0.535
2022.10.25火+48670 22,092,929 2.948
2022.10.26水+50146 22,142,938 1.030
2022.10.27木+42398 22,185,337 0.845
2022.10.28金+39280 22,224,618 0.926
2022.10.29土+44632 22,269,258 1.136
2022.10.30日+40407 22,309,665 0.905
2022.10.31月+21860 22,331,419 0.541
2022.11.1 火+66618 22,398,035 3.047
2022.11.2 水+70258 22,469,405 1.054
2022.11.3 木+67605 22,536,996 0.962
2022.11.4 金+32919 22,569,919 0.486
2022.11.5 土+75645 22,645,654 2.297
2022.11.6 日+65915 22,711,567 0.871
2022.11.7 月+30684 22,742,250 0.465
2022.11.8 火+83253 22,825,505 2.713
2022.11.9 水+87009 22,912,576 1.045
2022.11.14月+36581 23,249,777 0.420
2022.11.15火+105188 23,354,987 2.875
2022.11.16水+106689 23,461,673 1.014
2022.11.17木+ 92789 23,554,478 0.869
2022.11.18金+ 84272 23,638,752 0.908
2022.11.19土+ 90542 23,729,293 1.074
2022.11.20日+ 76938 23,806,281 0.849
2022.11.21月+ 41454 23,847,735 0.538
2022.11.22火+124005 23,971,740 2.991
2022.11.23水+133095 24,104,835 1.073
2022.11.24木+ 57895 24,162,730 0.435
2022.11.25金+118767 24,289,707 2.051
2022.11.26土+125387 24,415,093 1.055
2022.11.27日+ 97679 24,512,776 0.779
2022.11.28月+ 47814 24,560,589 0.489
2022.11.29火+129903 24,690,390 2.716
2022.11.30水+138116 24,828,451 1.063
2022.12.1 木+117778 24,946,231 0.852
2022.12.2 金+109596 25,055,827 0.930
2022.12.3 土+109825 25,165,653 1.002
2022.12.4 日+ 88752 25,254,425 0.808
2022.12.5 月+ 46846 25,301,276 0.527
2022.12.6 火+140279 25,441,555 2.994
2022.12.7 水+148797 25,590,250 1.060
2022.12.8 木+132989 25,723,242 0.893
2022.12.9 金+127292 25,850,600 0.957
2022.12.10土+136249 25,986,759 1.070
2022.12.11日+105662 26,092,421 0.775
2022.12.12月+ 60957 26,166,190 0.576
2022.12.13火+179409 26,345,590 2.943
2022.12.14水+190383 26,535,860 1.061
2022.12.15木+167979 26,703,839 0.882
2022.12.16金+153423 26,857,199 0.913
2022.12.17土+158807 27,016,003 1.035
2022.12.18日+135522 27,151,525 0.853
2022.12.19月+ 69140 27,220,667 0.510
2022.12.20火+189986 27,410,660 2.747
2022.12.21水+206415 27,616,982 1.086
2022.12.22木+183883 27,800,850 0.890
2022.12.23金+174082 27,974,931 0.946
2022.12.24土+177739 28,152,671 1.021
2022.12.25日+148810 28,301,479 0.837
2022.12.26月+ 75039 28,376,500 0.504
2022.12.27火+208248 28,585,193 2.775
2022.12.28水+215964 28,801,080 1.037
2022.12.29木+191948 28,993,032 0.888
2022.12.30金+148076 29,141,107 0.771
2022.12.31土+106412 29,247,521 0.718
2023.1.1 日+ 86442 29,333,963 0.696
2023.1.2 月+ 75883 29,409,846 0.877
2023.1.3 火+ 90436 29,500,282 1.191
2023.1.4 水+104616 29,604,896 1.156
2023.1.5 木+231022 29,835,917 2.208
2023.1.6 金+246510 30,083,561 1.067
2023.1.7 土+238650 30,322,255 0.968
2023.1.8 日+188607 30,510,863 0.790
2023.1.9 月+ 92723 30,603,585 0.491
2023.1.10 火+ 74717 30,678,527 0.805
2023.1.11 水+203378 30,882,703 2.722
2023.1.12 木+183224 31,065,927 0.901
2023.1.13 金+143383 31,209,299 0.782
2023.1.14 土+132373 31,341,673 0.923
2023.1.15 日+107138 31,448,811 0.809
2023.1.16 月+ 52608 31,501,881 0.491
2023.1.17 火+129829 31,631,728 2.468
2023.1.18 水+123650 31,755,373 0.952
2023.1.19 木+ 95971 31,851,344 0.776
2023.1.20 金+ 82260 31,933,875 0.857
2023.1.21 土+ 79033 32,012,830 0.960
2023.1.22 日+ 63844 32,076,731 0.807
2023.1.23 月+ 31664 32,108,402 0.495
2023.1.24 火+ 83353 32,191,662 2.632
2023.1.25 水+ 78796 32,270,472 0.945
2023.1.26 木+ 60130 32,330,721 0.763
2023.1.27 金+ 53863 32,387,781 0.895
2023.1.28 土+ 54845 32,442,626 1.018
2023.1.29 日+ 44294 32,486,920 0.807
2023.1.30 月+ 20830 32,507,759 0.470
2023.1.31 火+ 58596 32,566,313 2.813
2023.2.1 水+ 55012 32,621,333 0.938
2023.2.2 木+ 45500 32,666,832 0.827
2023.2.3 金+ 39830 32,706,852 0.875
2023.2.4 土+ 38594 32,745,546 0.969
2023.2.5 日+ 32142 32,777,588 0.832
2023.2.6 月+ 15254 32,792,854 0.474
2023.2.7 火+ 42314 32,835,171 2.774
2023.2.8 水+ 41253 32,876,313 0.974
2023.2.9 木+ 32797 32,908,794 0.795
2023.2.10 金+ 28521 32,937,315 0.869
2023.2.11 土+ 27468 32,964,781 0.962
2023.2.12 日+ 13203 32,977,984 0.480
2023.2.13 月+ 9380 32,987,364 0.710
2023.2.14 火+ 32426 33,019,790 3.456
2023.2.15 水+ 28432 33,048,221 0.876
2023.2.16 木+ 21271 33,069,491 0.748
2023.2.17 金+ 18463 33,087,953 0.868
2023.2.18 土+ 17132 33,105,085 0.927
2023.2.19 日+ 14164 33,119,249 0.826
2023.2.20 月+ 6793 33,125,044 0.479
2023.2.21 火+ 19642 33,145,696 2.891
2023.2.22 水+ 18625 33,164,322 0.948
2023.2.23 木+ 15029 33,179,351 0.806
2023.2.24 金+ 6281 33,185,632 0.417
2023.2.25 土+ 15226 33,200,858 2.425
2023.2.26 日+ 12192 33,213,050 0.800
2023.2.27 月+ 5191 33,218,245 0.425
2023.2.28 火+ 15004 33,233,249 2.890
2023.3.1 水+ 13799 33,247,054 0.919
2023.3.2 木+ 11515 33,258,568 0.834
2023.3.3 金+ 10486 33,269,054 0.910
2023.3.4 土+ 10378 33,279,432 0.990
2023.3.5 日+ 8668 33,288,102 0.835
2023.3.6 月+ 4150 33,292,256 0.478
2023.3.7 火+ 12312 33,304,567 2.966
2023.3.8 水+ 11722 33,316,289 0.952
2023.3.9 木+ 9833 33,326,123 0.838
2023.3.10 金+ 9117 33,335,240 0.927
2023.3.11 土+ 9083 33,344,323 0.996
2023.3.12 日+ 6987 33,351,310 0.769
2023.3.13 月+ 3236 33,354,546 0.463
2023.3.14 火+ 10328 33,364,873 3.191
2023.3.15 水+ 9406 33,374,191 0.910
2023.3.16 木+ 7667 33,381,858 0.815
2023.3.17 金+ 6906 33,388,764 0.900
2023.3.18 土+ 7123 33,395,887 1.031
2023.3.19 日+ 5911 33,401,798 0.829
2023.3.20 月+ 2617 33,404,416 0.442
2023.3.21 火+ 9001 33,413,417 3.439
2023.3.22 水+ 4181 33,417,598 0.464
2023.3.23 木+ 8815 33,426,412 2.108
2023.3.24 金+ 8536 33,434,948 0.968
2023.3.25 土+ 8299 33,443,246 0.972
2023.3.26 日+ 6167 33,449,413 0.743
2023.3.27 月+ 2775 33,452,130 0.445
2023.3.28 火+ 8371 33,460,499 3.016
2023.3.29 水+ 8246 33,468,738 0.985
2023.3.30 木+ 7179 33,476,359 0.870
2023.3.31 金+ 6745 33,483,384 0.939
2023.4.1 土+ 7426 33,490,810 1.100
2023.4.2 日+ 6262 33,497,076 0.843
2023.4.3 月+ 3110 33,500,186 0.496
2023.4.4 火+ 9701 33,509,887 3.119
2023.4.5 水+ 9520 33,519,414 0.981
2023.4.6 木+ 8580 33,527,994 0.901
2023.4.7 金+ 8300 33,536,294 0.967
2023.4.8 土+ 8484 33,544,778 1.022
2023.4.9 日+ 7012 33,551,790 0.826
2023.4.10 月+ 3176 33,554,968 0.452
2023.4.11 火+ 10219 33,565,187 3.217
2023.4.12 水+ 10068 33,575,254 0.985
2023.4.13 木+ 9162 33,584,417 0.910
2023.4.14 金+ 8351 33,592,769 0.911
2023.4.15 土+ 8550 33,601,319 1.023
2023.4.16 日+ 6993 33,608,312 0.817
2023.4.17 月+ 3379 33,611,691 0.483
2023.4.18 火+ 11901 33,623,591 3.522
2023.4.19 水+ 12022 33,635,586 1.010
2023.4.20 木+ 10521 33,646,107 0.875
2023.4.21 金+ 10104 33,656,213 0.960
2023.4.22 土+ 10716 33,666,931 1.060
2023.4.23 日+ 8484 33,675,415 0.791
2023.4.24 月+ 4046 33,679,462 0.476
2023.4.25 火+ 12847 33,692,308 3.175
2023.4.26 水+ 13094 33,705,402 1.019
2023.4.27 木+ 11844 33,717,247 0.904
2023.4.28 金+ 11402 33,728,648 0.962
2023.4.29 土+ 13177 33,741,825 1.155
2023.4.30 日+ 6466 33,748,291 0.490
2023.5.1 月+ 5041 33,753,332 0.779
2023.5.2 火+ 17349 33,770,684 3.441
2023.5.3 水+ 16505 33,787,190 0.951
2023.5.4 木+ 7079 33,794,269 0.428
2023.5.5 金+ 5819 33,800,088 0.822
2023.5.6 土+ 6267 33,806,355 1.077
2023.5.7 日+ 14637 33,820,992 2.335
2023.5.8 月+ 9401 33,830,420 0.642
日本の感染者増加と死亡増加の状況は、世界合計と酷似していたが、最近の状況は変化している。
急に減少してきたが、また急激に増加して再び7波よりも急に減少してきた。
曜日ごとの増加率は前週と似てはいるが、多少増えている。
4月に入ってから微増し、4月末からさらに微増してきた。
(注):世界の状況は2023年3月10日まで表示。
日本の状況は引き続き表示。
日本の毎日のデータの提供は2023/5/8で終了。
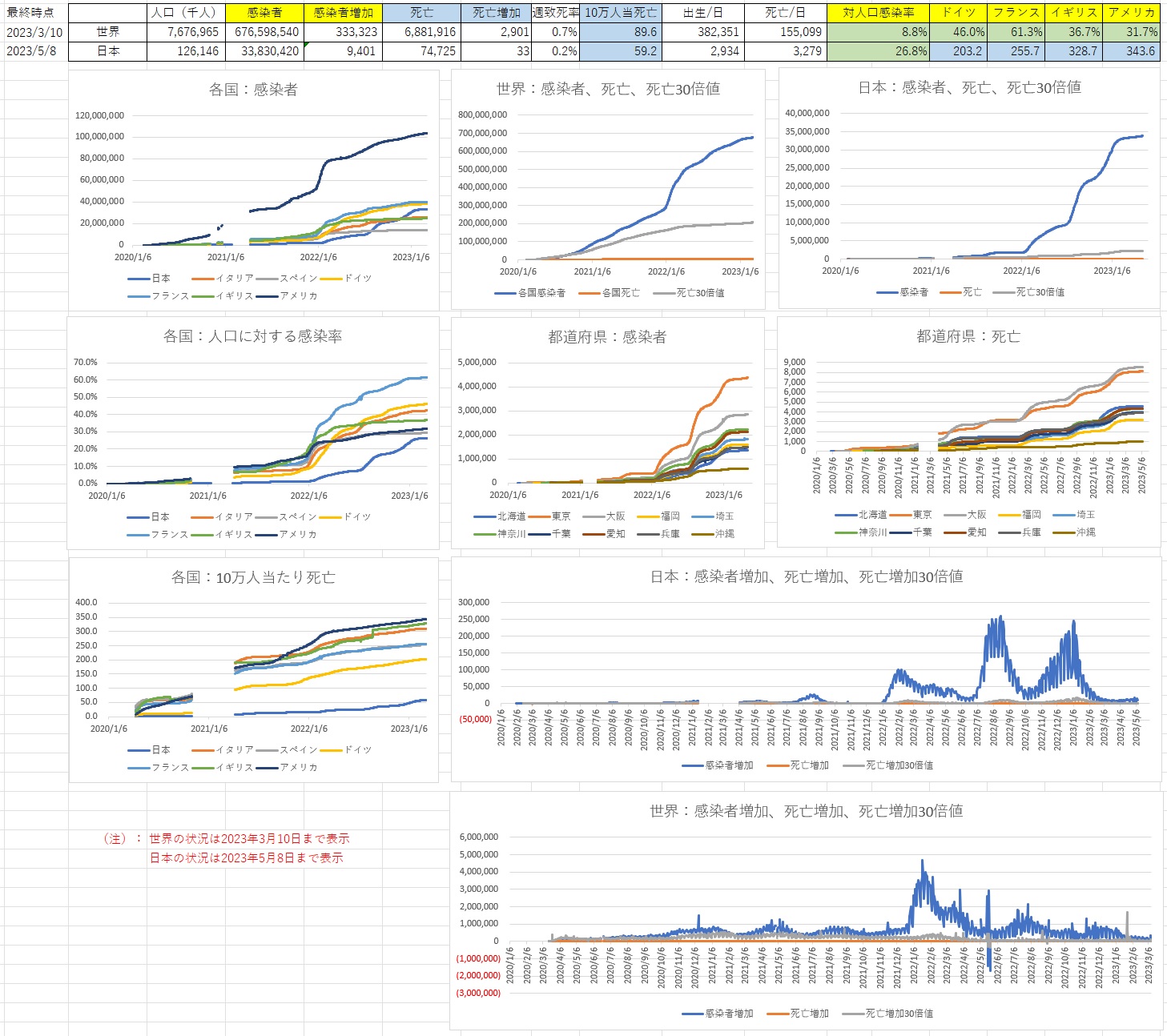
--------------------------------------
2020.2.15土曜日、新型コロナウイルスの抗体を調べてみたいと思う。
目 次
2022.1.25
2020.2.15
2020.2.16 IgA
2020.2.18
2020.2.19 ウイルスになったつもりで
2020.2.20
2020.2.21
2020.2.22 アビガン
2020.2.23
2020.3.1
2020.3.3
2020.3.4
2020.3.5 IgA
2020.3.10 レムデシベル アビガン
2020.3.13 プラスミド、DNAワクチン
2020.3.18
2020.3.23 RNA
2020.3.24
2020.3.26 免疫グロブリン
2020.3.26_2
2020.3.27
2020.3.28 アビガン カレトラ レムデシベル
2020.3.29
2020.4.2 肺炎
2020.4.3
2020.4.4 肺胞
2020.4.5
2020.4.7 肺の発生
2020.4.8 マクロファージ
2020.4.9
2020.4.10 間質性肺炎
2020.4.13
2020.4.15
2020.4.17 経鼻粘膜投与型ワクチン
2020.4.18 カテキン、スパイクタンパク質
2020.4.19
2020.4.20 アビガン(ファビピラビル)
2020.4.26 IgA
2020.4.29 COVID-19 spike
2020.5.4 アクテムラ
2020.5.5 ヒドロキシクロロキン
2020.5.6 イベルメクチン
2020.5.9 フサン
2020.5.16 四量体のIgA抗体
2020.5.20 抗体
2020.6.1 インフルエンザウイルス認識機構、IgA抗体
2020.10.22 モノクロナール抗体
2022.1.25
目次へ
引用:Wikipeda
オミクロン株には多数の変異が存在し、科学者はいくつかの変異を懸念している。
32の変異は、感染によって生成された抗体や広く投与されている多くのワクチンの主な抗原の標的となっている、スパイクタンパク質に影響がある。
これらの変異の多くは、他の株では観察されていないものである。
変異株は、30のアミノ酸の変化で特徴付けられる。元のウイルスと比較して、スパイクタンパク質に3つの小さな欠失と1つの小さな挿入がある。
そのうち15個は受容体結合ドメイン (RBD)(残基319-541)にある。
また、他のゲノム領域でも多くの変更や削除が行われている。
注目すべき点は、SARS-CoV-2の感染力を増加させるフーリン切断部位に3つの変異を持っていることである。
フーリンはタンパク質であり、ヒトではFURIN遺伝子にコードされている。
その遺伝子は、FESとして知られているがん遺伝子の上流にあるので、FUR(FES Upstream Region)と呼ばれ、そのためそのタンパク質はフーリン(furin)と名付けられた。
その遺伝子によってコードされるタンパク質は、酵素であり、サブチリシン様プロタンパク質転換酵素ファミリーに属する。
このファミリーを構成するタンパク質は、活性がないタンパク質前駆体を生物学的に活性のある産物に加工するプロタンパク質転換酵素である。
このコードされたタンパク質はカルシウム依存セリンエンドプロテアーゼであり、活性部位の対となる塩基性アミノ酸のところでタンパク質前駆体を効率的に切断する。
フーリンはまたHIVウイルスの構築に先立ち、HIVエンベロープのポリプロテイン前駆体のgp160をgp120とgp41に切断するタンパク質分解酵素の一つであると考えられている。
この遺伝子は腫瘍の進行でも役割を果たすと考えられている。
2020.2.15
目次へ
12月から感染が始まっている新型コロナウイルスは急速に感染者が増加し、SARS、MERSをはるかに上回る勢いで広まっているようだ。
ウイルスが生体に感染したとき、抗体反応はどうなっているのだろう。
引用:https://kotobank.jp/word/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%8A%97%E4%BD%93%E4%BE%A1-2121212
ウイルス抗体価というものがあるそうだ。
体の中に侵入してきた、あるウイルス(抗原)に対して対抗する物質(抗体)の力価(量や強さ)のこと。
ウイルスの大きさは、20~450nm。例えば風疹ウイルスは直径約70nm。
ウイルスに感染すると、侵入ウイルスは標的臓器で増殖し、感染症が発症する。
発症とほぼ時を同じくしてIgM抗体が、続いてIgG抗体が出現、血液中で上昇する。
引用:https://ruo.mbl.co.jp/bio/support/method/antibody-isotype.html
ヒトでは抗体は大別してIgM、IgD、IgG、IgA、IgEの5種類があり、これを抗体のアイソタイプと呼びます。
アイソタイプはH鎖によって決定されます。
このH鎖の違いによって、各アイソタイプの性質や役割は大きく異なります。
IgG
血液(血漿中)に最も多い抗体です。
ヒト免疫グロブリン(抗体)の70-75%を占めます。
危険因子の無毒化、白血球やマクロファージによる抗原・抗体複合体の認識に重要です。
胎児には血液を介してIgGが供給され、赤ちゃんの免疫が発達するまで子供を守ります。
IgM
ヒト免疫グロブリンの約10%を占めます。
通常血液中に存在します。
基本のY構造が5つ結合した格好をしています。
感染微生物に対してまず最初にB細胞から産生されます。
抗原の侵入に際して最初にB細胞から産生されます。
IgMの抗原に対する親和性は一般的にIgGに比べて弱いとされていますが、5-6量体化することでその結合力を補っています。
また細胞表面上の膜分子に結合することでシグナルを入力する活性を発揮することもあります。
IgA
ヒト免疫グロブリンの10-15%を占めます。
IgAは2つのIgAが結合した格好をしています。
血清、鼻汁、唾液、母乳中、腸液に多く存在します。
母乳に含まれるIgAが新生児の消化管を病原体から守っています。
IgE
ヒト免疫グロブリンの0.001%以下と極微量しか存在しません。
本来、寄生虫に対する免疫応答のために存在すると考えられていますが、寄生虫感染がまれな地域ではアレルギーに大きく関与しています。
IgD
ヒト免疫グロブリンの1%以下です。
B細胞による抗体産生の誘導に関与すると言われてますが、正確な機能はよくわかっていません。
----------------------------------------
これによると、IgG、IgM、IgAがコロナウイルスに関係ありそうだ。
鼻汁に付着したウイルスは、まず、IgAが反応するのだろうか。
次いで、血液中のIgM、そして最後に、ウイルスの無毒化、白血球やマクロファージによる抗原・抗体複合体の認識が始まる。
----------------------------------------
引用:https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/life-science/antibodies/antibodies-learning-center/antibodies-resource-library/antibody-methods/immunoglobulin-igm-class.html
血清 IgM は、哺乳類において五量体として存在し、正常ヒト血清 Ig 含量の約 10% を占めます。
ほとんどの抗原に対して優れた一次免疫応答を示し、最も効率的な補体固定能を持つ免疫グロブリンです。
また、IgM は単量体として B リンパ球の細胞膜上にも発現します。
この形態では、B細胞抗原受容体がH鎖とともに細胞膜上に発現しており、それぞれには膜に固定するための付加的な疎水性ドメインが含まれます。
血清 IgM の各単量体は、ジスルフィド結合および結合 (J) 鎖によって互いに結合します。
五量体構造内の 5 つの各単量体は、2 つの軽鎖 (κ または λ) および 2 つの重鎖から構成されます。
IgG (および上記の一般構造) とは異なり、IgM 単量体の重鎖は、1 つの可変領域と 4 つの定常領域からなり、ヒンジ領域は付加的な定常ドメインにより置換されます。
IgM は侵入した微生物上のエピトープを認識し、細胞凝集を生じさせます。
その後、この抗体-抗原免疫複合体は、補体固定またはマクロファージによる受容体媒介エンドサイトーシスによって破壊されます。
IgM は、最初に新生児で合成される免疫グロブリンクラスであり、自己免疫疾患の病態形成において役割を果たします。
・免疫グロブリン M は、次の 2 つのうち 1 つの形態を取ります:
・全ての重鎖が同一であり、全ての軽鎖が同一である五量体
・単量体 (例えば、B 細胞受容体として B リンパ球上に見られる)
大きな五量体構造では、連結可能な距離にある、より小さい IgG 抗体の分子上のエピトープ間で架橋が構築されています。
IgM は、免疫応答の間に形成される最初の抗体です。
理論上、その五量体構造には 10ヵ所の遊離抗原結合部位があり、高い結合活性を持つことから、IgM は凝集や細胞溶解反応に関係しています。
10 個の Fab 部分の間には立体配座の制約があるため、IgM の抗体価は 5 価しかありません。
また、IgM は IgG ほど汎用性がありません。
しかしながら、IgM は補体活性化および凝集に極めて重要です。
IgM は主にリンパ液と血液中に見られ、疾患の初期段階における非常に効果的な中和剤です。
IgM レベルの上昇は、細菌の感染または抗原への曝露の兆候である可能性があります。
----------------------------------------
これによると、IgMは、ウイルスの表面を五量体構造で覆って、凝集させるようだ。
----------------------------------------
引用:https://ja.strephonsays.com/difference-between-igg-and-igm
主な違い - IgGとIgM
外来物質の抗原に結合する免疫系のタンパク質は、免疫グロブリン(Ig)または抗体として知られています。
それらはバクテリア、ウイルス、寄生虫などの病原体と戦うために作られています。
Igの主な機能は、外来病原体の破壊を促進することです。
IgGおよびIgMは2つのクラスの免疫グロブリンです。
IgGとIgMの違いは、 IgGは疾患に対する後期段階の反応を表し、一方、IgMは特定の抗原への曝露の直後に産生される。
IgGは体全体に見られ、主に体液中に見られ、一方IgMは血液およびリンパ液中に見いだされる。
IgGは特定の抗原に対する長期的な応答を確立して長期にわたる免疫を提供し、IgMは短期間の反応を確立する。
----------------------------------------
これによると、IgMで初期対応し、IgGで長期対応するようだ。
----------------------------------------
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E4%BD%93
抗体(こうたい、英: antibody)とは、リンパ球のうちB細胞の産生する糖タンパク分子で、特定のタンパク質などの分子(抗原)を認識して結合する働きをもつ。
抗体は主に血液中や体液中に存在し、例えば、体内に侵入してきた細菌やウイルス、微生物に感染した細胞を抗原として認識して結合する。
抗体が抗原へ結合すると、その抗原と抗体の複合体を白血球やマクロファージといった食細胞が認識・貪食して体内から除去するように働いたり、リンパ球などの免疫細胞が結合して免疫反応を引き起こしたりする。
これらの働きを通じ、脊椎動物の感染防御機構において重要な役割を担っている(無脊椎動物は抗体を産生しない)。
1種類のB細胞は1種類の抗体しか作れないうえ、1種類の抗体は1種類の抗原しか認識できないため、ヒト体内では数百万~数億種類といった単位のB細胞がそれぞれ異なる抗体を作り出し、あらゆる抗原に対処しようとしている。
すべての抗体は基本的には同じ構造を持っており、"Y"字型の4本鎖構造(軽鎖・重鎖の2つのポリペプチド鎖が2本ずつ)を基本構造としている。
軽鎖(またはL鎖)にはλ鎖とκ鎖の2種類があり、すべての免疫グロブリンはこのどちらかを持つが、分子量は約25,000で共通である。
重鎖(またはH鎖)には、γ鎖、μ鎖、α鎖、δ鎖、ε鎖の、構造の異なる5種類があり、この重鎖の違いによって免疫グロブリンの種類(アイソタイプと呼ぶ)が変わる。
分子量は50,000~77,000である。
この軽鎖と重鎖がジスルフィド結合(SS結合)で結びついてヘテロダイマーを形成し、さらにこのヘテロダイマーが左右2つジスルフィド結合で結合して "Y"字型のヘテロテトラマーを形成する。
2本の軽鎖同士、あるいは2本の重鎖同士は全く同一のポリペプチド鎖である。
Fc領域とFab領域
"Y"字の下半分の縦棒部分にあたる場所をFc領域 (Fragment, crystallizable) と呼ぶ。左右2つの重鎖からなる。
白血球やマクロファージなどの食細胞はこのFc領域と結合できる受容体(Fc受容体)を持っており、このFc受容体を介して抗原と結合した抗体を認識して抗原を貪食する(オプソニン作用)。
その他Fc領域は、補体の活性化や抗体依存性細胞傷害作用など、免疫反応の媒介となる。
このようにFc領域は抗体が抗原に結合した後の反応を惹起する「エフェクター機能」をもつ。免疫グロブリンのエフェクター機能は、免疫グロブリンの種類(アイソタイプ)によって異なる。
"Y"字の上半分の"V"字の部分をFab領域 (Fragment,antigen binding) と呼ぶ。
この2つのFab領域の先端の部分で抗原と結合する。2本の軽鎖と2本の重鎖からなる。
重鎖のFab領域とFc領域はヒンジ部でつながっている。
左右の重鎖はこのヒンジ部がジスルフィド結合している。パパイヤに含まれるタンパク分解酵素パパインはこのヒンジ部を分解して、2つのFabと1つのFc領域に切断する。
またタンパク分解酵素のペプシンはヒンジ部のジスルフィド結合のFc側で切断し、大きなFabが2個くっついたF(ab')2を1つと、多数の小さなFc断片を生成する。
Fc断片のうち、CH3領域に相当する最も大きな断片はpFc'と呼ばれる。
F(ab')2は、ジスルフィド結合部を含むため、Fabよりも構造が大きいため、Fabと区別するため ab' としている。
このF(ab')2は抗原に結合するが、Fc領域を持たないためその後の免疫反応を引き起こさない。このことを利用して抗原の標識に用いられる。
ヒト免疫グロブリンの分類
重鎖は定常領域の違いにより、γ鎖、μ鎖、α鎖、δ鎖、ε鎖に分けられ、この違いによりそれぞれIgG、IgM、IgA、IgD、IgEの5種類のクラス(アイソタイプ)の免疫グロブリンが形成される。
これらの分泌型の免疫グロブリンの他、B細胞表面に結合したものがある。
これは、分泌型免疫グロブリンが細胞表面に接着しているのではなく、細胞膜貫通部分をもったものであり、B細胞受容体 (B cell receptor; BCR) と呼ばれる。
BCRは2本の重鎖と2本の軽鎖を持ち、細胞膜貫通部分にIgα/Igβヘテロ二量体を持つ。アイソタイプの違いにより、免疫グロブリンの持つ「エフェクター機能」が異なる。
IgG免疫グロブリンG(IgG)はヒト免疫グロブリンの70-75%を占め、血漿中に最も多い単量体の抗体である。
軽鎖2本と重鎖2本の4本鎖構造をもつ。
IgG1、IgG2、IgG4は分子量は約146,000であるが、IgG3はFab領域とFc領域をつなぐヒンジ部が長く、分子量も170,000と大きい。
IgG1はIgGの65%程度、IgG2は25%程度、IgG3は7%程度、IgG4は3%程度を占める。
血管内外に平均して分布する。
IgM免疫グロブリンM(IgM)はヒト免疫グロブリンの約10%を占める、基本の4本鎖構造が5つ結合した五量体の抗体である。分子量は970,000。
通常血中のみに存在し、感染微生物に対して最初に産生され、初期免疫を司る免疫グロブリンである。
IgA免疫グロブリンA(IgA)はヒト免疫グロブリンの10-15%を占める。分子量は160,000。
分泌型IgAは2つのIgAが結合した二量体の抗体になっている。
IgA1は血清、鼻汁、唾液、母乳中に存在し、腸液にはIgA2が多く存在する。
IgD免疫グロブリンD(IgD)はヒト免疫グロブリンの1%以下の単量体の抗体である。
B細胞表面に存在し、抗体産生の誘導に関与する。
IgE免疫グロブリンE(IgE)はヒト免疫グロブリンの0.001%以下と極微量しか存在しない単量体の抗体である。寄生虫に対する免疫反応に関与していると考えられるが、寄生虫の稀な先進国においては、特に気管支喘息やアレルギーに大きく関与している。
その他の生物での分類
免疫グロブリンは無脊椎動物には見られず、軟骨魚類以降の脊椎動物で見つかっている。それぞれの生物ごとに複数のクラスの免疫グロブリンを持つが、その種類は綱ごとに違いが見られる。
IgMのみがそのすべてで共通に見られる。
軟骨魚類IgMの他にIgW、IgW (long)、IgNARと呼ばれるクラスを持つ硬骨魚類IgMとIgDを持つハイギョIgM, IgW, IgW (long) を持つ両生類(アフリカツメガエル)IgMの他、IgXとIgYと呼ばれるクラスを持つ鳥類(ニワトリ)IgM、IgA、IgYを持つ哺乳類IgM、IgD、IgG、IgA、IgEの5種類を持つ。
また、同じ哺乳類でもサブクラスの種類には種ごとに違いが見られる。例えばヒトIgGのサブクラスがIgG1?IgG4の4種類であるのに対し、マウスIgGではIgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3の4種類である。
働き
抗体は血液中や体液中に遊離型として存在するか、またはB細胞表面上にB細胞受容体として存在する。
特定の抗原と結合する機能が抗体の最も重要な機能である。
抗体はウイルスや細菌などの微生物、あるいは毒素などを抗原として結合するが、抗原と抗体が結合すると、凝集反応(免疫沈降)をおこし、その凝集した抗原抗体複合体は、マクロファージやその他の食細胞が認識し貪食する。
その際、抗体はそのFc領域をもってマクロファージ等に認識され貪食されやすくする役割をする(オプソニン作用)。
そしてマクロファージに貪食された抗原は、マクロファージ内で分解され、T細胞にペプチド-MHC複合体として提示され、さらなる免疫反応がおこる。
また抗体は補体活性化作用を通した免疫反応もおこす。
抗体の中には、結合するだけで微生物の感染力を低下させたり、毒性を減少させたりする働きをもつものもある(中和作用)。
これらの機構により、抗体は体内に侵入してきた細菌・ウイルスなどの微生物・毒素や、微生物に感染した細胞を認識して体内から排除しようとする。
B細胞表面に存在するBCRは、B細胞の抗原認識受容体として働き、特異的な抗原が結合することで、抗体産生細胞(形質細胞)や体細胞超変異、クラススイッチ組み換え等を経た後の、より抗原に対する親和性の高いBCRをもった抗体産生細胞や記憶B細胞への分化を引き起こす。
抗体産生細胞はBCRと同じ抗原特異性、アイソタイプを持つ抗体を産生する。
抗体が抗原と結合する際、抗原の一部分(エピトープ)のみを認識して結合する。
抗体はエピトープの立体構造を厳密に認識して結合し、エピトープのアミノ酸配列の違いはもちろんのこと、荷電の差、光学異性体、立体異性体の違いでも結合しなくなる。
エピトープと結合する抗体側の部分をパラトープという。
エピトープとパラトープの間には、水素結合、静電気力、ファンデルワールス力、疎水結合などの引力がかかり、これらの力により安定して結合する。
このエピトープとパラトープの間の結合力のことをアフィニティ affinity という。
ただし、抗体は基本の4本鎖構造においては、抗原と結合する部位は2カ所であるが、IgMは五量体、IgAは二量体を形成するのでさらに多くの抗原認識部位を持っている。
また、抗原によってはエピトープを複数もつ。
このため抗体によっては、抗原と抗体は1か所で結合したり(1価)、同時に複数か所で認識したりする(多価)。
このように抗原と抗体が結合するときの結合力の総和をアビディティ avidity と呼ぶ。
多価の結合の際、結合力が相乗的に働くため、アビディティはアフィニティよりも高くなる。
オプソニン作用
マクロファージや好中球といった食細胞は、もともと細菌や死んだ細胞に結合する能力を持っているが、こういった細菌や死細胞に抗体や補体が結合すると、食細胞がもつ補体受容体やFc受容体を介して結合し、食作用を促進する。
これをオプソニン作用という。
抗体は補体の古典経路によって補体を活性化し、抗体の結合した細菌に補体を結合させて細菌の細胞膜を破壊し、溶菌する。
またオプソニン作用で食細胞による抗原の食作用を促進させる。
IgG1、IgG3、IgMがもつ機能である。
IgG2は補体活性化能は低く、IgG4、IgA、IgD、IgEはこの機能をもたない。
中和作用
細菌やウイルスなどの微生物や、ヘビや虫などの毒素は、自らの構造の一部を細胞表面に結合させて細胞内に侵入し、毒性を示す。
細胞に侵入する際に結合させる部分に抗体が結合してしまえば、微生物や毒素は細胞に結合できず、毒性を示せない。
このように抗体は、結合することによって微生物の感染力を低下させたり、毒素の毒性を減少させたりすることがある。
****************************************************
例えばインフルエンザウイルスは、ウイルス表面のヘマグルチニンを気道上皮細胞のシアル酸残基に結合させて細胞内に侵入するため、ヘマグルチニンに対する抗体はインフルエンザの感染力を低下させる。
このことを中和作用という。
****************************************************
---------------------------------------
これだ、気道上皮細胞が最初に接触するんだ。
---------------------------------------
引用:http://www.seibutsushi.net/blog/2009/05/769.html
赤血球凝集素(HA)は、インフルエンザが宿主細胞に「くっつく」ために使います(増殖の際にも関与している)。
●HA=ヘマグルチニンがくっつくための条件
結合するための条件
1)とりつく細胞表面に糖タンパク質の糖鎖の「シアル酸残基」があること
2)シアル酸に結合している「ガラクトース」の結合様式(結合位置)が認識可能であること
この二つの条件が両方とも整わないとくっつけません。
インフルエンザウィルスがくっつくのは「シアル酸残基」ですが、ウィルスが「これはくっつけるものだ」と認識するためには「シアル酸とガラクトースの結合様式」が一定のものではないといけないわけです。
シアル酸とガラクトースの結合様式は専門的に「α2→6結合」や「α2→3結合」などと呼ばれているのですが、
・ヒト由来のインフルエンザウィルスは、「α2→6結合」しか認識できない。
・トリ由来のインフルエンザウィルスは、「α2→3結合」しか認識できない。
この違いが、鳥インフルエンザが人に感染しないと言われている理由です。
●ヒト・トリ・ブタ 各々のシアル酸とガラクトースの結合様式
人の気道上皮細胞(喉の粘膜)には、「α2→6結合」したガラクトースとシアル酸が多く分布しています。したがって、ここがまず第一の感染地帯になります。
鳥の場合は、場所が違って、大腸上皮細胞に「α2→3結合」したガラクトースとシアル酸が多く分布しているので、ここが感染地帯になります。
しかし、ブタは気道上皮細胞に「α2→6結合」と「α2→3結合」の両方を持っています。したがって、ヒト型、トリ型両方のインフルエンザに感染するというわけです。
また、人間でも一部に気道上皮細胞に「α2→3結合」(←鳥インフルエンザが認識出来る結合様式)を持つ人がいます。
その人の喉の粘膜には、鳥インフルエンザウィルスがくっつけますから、不幸にも鳥インフルエンザウィルスに感染しやすい体質となってしまいます。香港などで鳥インフルエンザの感染例が報告されたのは、そのような人たち(=限定的)であると見られています。
●「くっつく」→侵入→ウィルスの増殖
引用:Wikipedia ウイルス
ウイルスは、それ自身単独では増殖できず、他の生物の細胞内に感染して初めて増殖可能となる。このような性質を偏性細胞内寄生性と呼ぶ。また、一般的な生物の細胞が2分裂によって 2n で対数的に数を増やす(対数増殖)のに対し、ウイルスは1つの粒子が、感染した宿主細胞内で一気に数を増やして放出(一段階増殖)する。また感染したウイルスは細胞内で一度分解されるため、見かけ上ウイルス粒子の存在しない期間(暗黒期)がある。
ウイルスの増殖は以下のようなステップで行われる。
①細胞表面への吸着 → ②細胞内への侵入 → ③脱殻(だっかく) → ④部品の合成 → ⑤部品の集合 → ⑥感染細胞からの放出
①細胞表面への吸着
ウイルス感染の最初のステップはその細胞表面に吸着することである。
ウイルスが宿主細胞に接触すると、ウイルスの表面にあるタンパク質が宿主細胞の表面に露出しているいずれかの分子を標的にして吸着する。
このときの細胞側にある標的分子をそのウイルスに対するレセプターと呼ぶ。
ウイルスが感染するかどうかは、そのウイルスに対するレセプターを細胞が持っているかどうかに依存する。
代表的なウイルスレセプターとしては、インフルエンザウイルスに対する気道上皮細胞のシアル酸糖鎖や、ヒト免疫不全ウイルスに対するヘルパーT細胞表面のCD4分子などが知られている。
②細胞内への侵入
細胞表面に吸着したウイルス粒子は、次に実際の増殖の場になる細胞内部へ侵入する。侵入のメカニズムはウイルスによってさまざまだが、代表的なものに以下のようなものがある。
●エンドサイトーシスによる取り込み細胞自身が持っているエンドサイトーシスの機構によって、エンドソーム小胞として細胞内に取り込まれ、その後でそこから細胞質へと抜け出すもの。
エンベロープを持たないウイルスの多くや、インフルエンザウイルスなどに見られる。
●膜融合吸着したウイルスのエンベロープが細胞の細胞膜と融合し、粒子内部のヌクレオカプシドが細胞質内に送り込まれるもの。
多くの、エンベロープを持つウイルスに見られる。
●能動的な遺伝子の注入
Tファージなどのバクテリオファージに見られ、吸着したウイルスの粒子から尾部の管を通してウイルス核酸が細胞質に注入される。
注入とは言っても、ウイルス粒子の尾部が細菌の細胞壁を貫通した後の遺伝子の移動は、細菌細胞が生きていないと起こらないため、細菌の細胞自体の作用によって吸い込まれるのではないかと言われている。
③脱殻
細胞内に侵入したウイルスは、そこで一旦カプシドが分解されて、その内部からウイルス核酸が遊離する。
この過程を脱殻と呼ぶ。
脱殻が起こってから粒子が再構成されるまでの期間は、ビリオン(感染性のある完全なウイルス粒子)がどこにも存在しないことになり、この時期を暗黒期、あるいは日食や月食になぞらえてエクリプス期(eclipse period)と呼ぶ。
④部品の合成
脱殻により遊離したウイルス核酸は、次代のウイルス(娘ウイルス)の作成のために大量に複製されると同時に、さらにそこからmRNAを経て、カプソマーなどのウイルス独自のタンパク質が大量に合成される。すなわちウイルスの合成は、その部品となる核酸とタンパク質を別々に大量生産し、その後で組み立てるという方式で行われる。
ウイルス核酸は宿主細胞の核酸とは性質的に異なる点が多いために、その複製は宿主の持つ酵素だけではまかなえないため、それぞれのウイルスが独自に持つDNAポリメラーゼ、RNAポリメラーゼなど、転写・複製に関わる酵素が使われる。また逆転写酵素を持つレトロウイルスでは、宿主のDNAに自分の遺伝子を組み込むことで、宿主のDNA複製機構も利用する。
タンパク質の合成には、そのタンパク質をコードするmRNAを作成するためにウイルス独自の酵素を必要とする場合がある。mRNAからタンパク質への翻訳は、宿主細胞の持つ、リボソームなどのタンパク質合成系を利用して行われる。
⑤部品の集合と⑥ウイルス粒子の放出
別々に大量生産されたウイルス核酸とタンパク質は細胞内で集合する。
最終的にはカプソマーがウイルス核酸を包み込み、ヌクレオカプシドが形成される。この機構はウイルスによってまちまちであり、まだ研究の進んでないものも多い。
細胞内で集合したウイルスは、細胞から出芽したり、あるいは感染細胞が死ぬことによって放出される。
このときエンベロープを持つウイルスの一部は、出芽する際に被っていた宿主の細胞膜の一部をエンベロープとして獲得する。
●ウィルスは細胞の外に出る
細胞内(宿主)に進入したウィルスは、その中で増殖します。
しかし、宿主の外に出なければ意味がありません。当然、外に出ようとします。
このとき、細胞にくっつくときに使ったHA=ヘマグルチニンが悪さをします。
宿主の細胞膜から外に出ようとした瞬間、自分がもっているHAが宿主の細胞表面のシアル酸残基とくっついてしまうのです。
インフルエンザウィルスにとっては、「くっつく」という可能性をもたらしたHAが、拡散過程の一等最初でアダとなってしまった格好です。
これでは、細胞表面から離れられません。
●NA=ノイラミニダーゼでくっついたHAを「切る」
大変困ったことになりましたが、インフルエンザウィルスはそのための対策をちゃんと備えています。
それがNA=ノイラミニダーゼです。
NAは、不用意にくっついてしまった自分側のHAと、宿主細胞表面のシアル酸残基を切り離す役割をします。
イメージ的には、くっついて離れなくなっている部分をハサミでチョッキンと切るヤツがNAだと思えばいいでしょう。
結果、インフルエンザウィルスは、細胞表面から離れて別の細胞にくっつく=感染する旅に出て行きます。
●NAの「切る」役割を阻害する薬=タミフル
タミフル(オセルタミビル)は、NAの役割である「切る」ことを阻害する薬です。
正確には、ノイラミニダーゼ阻害薬と呼ばれます。
タミフルに含まれるオセルタミビルリン酸塩という物質がインフルエンザウィルスのNA(ノイラミニダーゼ)と結合した結果、「切る」機能が阻害されます。
結果として、インフルエンザウィルスは宿主細胞から離れられなくなり、拡散・増殖できないという具合です。
離れられなくてモジモジしている間に、免疫系が新しい抗体をつくるなどしてインフルエンザを撃退し、完治に至ります。
したがって、タミフルはインフルエンザウィルスそのものを破壊するような薬ではないとわかるでしょう。特効薬というより、かなり消極的で免疫依存の時間稼ぎ戦法といったところです。
感染後48時間以上断つと効かないといわれているのは、その時点ではウィルスが増殖しすぎて、全てのウィルスのNAと結合することが出来ない(多くのウィルスを取り逃がす)ためと思われます。
発病以前に服用すると予防的に効くといわれているのは、潜伏中のウィルスのNAを予め無効化しておくことを以ってそのようにいわれているようです。(理論的には可能ですが実態はどうか?)
●亜型=HAとNAの変異が意味するもの
通常のインフルエンザウィルスのHAは、同一の結合様式しか認識できないといわれています。
しかし、もしも、HAが変異して色々な結合様式(α2→6結合以外の結合様式)を認識できるようになったら・・・?もしくは、NAが変異して、いかなるときでも「切る」ことができるようになったら・・・?
それらが、恐れられている新型インフルエンザにつながっていきます。
「α2→6結合」(ヒト)と「α2→3結合」(トリ)の両方にくっつくHA認識機能を持ったインフルエンザウィルスで、感染箇所が広く、増殖性の強いもののが、今恐れられている新型インフルエンザです。
そのために、政府はタミフルをたくさん備蓄していますが、既にタミフル耐性、すなわち、オセルタミビルリン酸塩と結合しないNAを持ったインフルエンザウィルスが登場しています。
引用:http://www.ekouhou.net/%E3%83%98%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%97%E4%BD%93%E3%80%81%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6%E6%8A%97%E5%8E%9F%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%B3%A6%E6%B4%BB%E6%80%A7%E6%8B%85%E4%BD%93%E7%B5%90%E5%90%88%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA/disp-A,2012-502652.html
インフルエンザウイルスは、世界的に最も重要な呼吸器系病原体の1つである。
インフルエンザウイルスは、典型的には、季節的な流行の間に世界の人口全体の10?20%に感染し、年間、3~5百万件の重度の疾病、および250,000?500,000の死者をもたらす。
米国において、インフルエンザは、平均で年間20,000名を死亡させるが、平均で114,000件のインフルエンザに関連する入院が、推定で年間120億ドルの経済的コストをもたらす。
さらに、新規なインフルエンザ株がヒト集団において時折出現して、汎流行病の原因となる。
1917年~1920年のスペイン風邪汎流行病の死亡者数は、世界的に5千万を超える死者となり、新しいインフルエンザ汎流行病の危険性は常に存在する。
ワクチン接種は、インフルエンザを制御するために最良の方法である。
しかし、ワクチンが生涯で1~3回だけ与えられる多くの他の病原体に対するワクチン接種とは対照的に、インフルエンザワクチンは、毎年投与されなければならない。
インフルエンザは、その2つの主要な膜タンパク質であるヘマグルチニン(HA)およびノイラミニダーゼ(NA)の抗原の特徴を変化させる特別な能力を示す。
これは、ヒト集団において確立される適応免疫応答から逃れる連続的選択により生じる。
ウイルスの高い変異率を原因として、特定のワクチン製剤は、通常、約1年しか作用しない。
世界保健機構は、ワクチンの内容を毎年調整して、次の年に攻撃する最も可能性のあるウイルスの株を含むようにする。
今日では、従来のワクチンは、3つの不活化インフルエンザウイルス(2つのA株と1つのB)からなるワクチンである。
この3価インフルエンザワクチンは、来るインフルエンザの季節に流行するとWHOにより予測されるインフルエンザ株に基づいて毎年再処方される。
例えば、2007年?2008年の季節に年次的に更新された3価インフルエンザワクチンは、インフルエンザH3N2、H1N1およびBインフルエンザウイルスからのヘマグルチニン(HA)表面糖タンパク質成分からなる。
インフルエンザワクチンは、ウイルスの主要な糖タンパク質であるそれらのHA含量に基づいて投薬される。
毎年250百万用量を超えるインフルエンザワクチンが生産され、小児および高齢者における保護効力は、60%?80%の範囲である。
よって、小児および高齢者のような攻撃を受けやすい標的群において特に、改良されたインフルエンザワクチンに対する、まだ対処されていない必要性がある。
インフルエンザワクチンを改良するための現在のアプローチは:
a.アジュバントの組み込み
b.さらなるインフルエンザ抗原成分の組み込み
c.体内のウイルス侵入部位での局所的な免疫応答を惹起して、ワクチンによる追加の防衛線を提供するストラテジーを含む。
インフルエンザワクチンは、今日では、有胚ニワトリ卵または組織培養で成長させたウイルスに由来する。
ほとんどのインフルエンザワクチンは、弱毒化生ウイルス、不活化ウイルス、スプリットウイルスまたはHAサブユニットを含有する。
例えば昆虫細胞を用いることによりHAサブユニット材料を生成する新しい技術が出現している。
ワクチン成分、特にサブユニットワクチンの免疫原性を増加させる一般的な方法は、アジュバントを加えることである。
ワクチン成分(抗原)を共有結合または非共有結合のいずれかでアジュバントに吸着または付着させることが有利であるとも一般的に考えられている。
アルミニウム塩(ミョウバン)は、この目的のために用いられるヒトワクチンにおける最も一般的に用いられるアジュバントである。
しかし、ミョウバンに吸着されたインフルエンザワクチンは毒性であり、よって、ヒトへの使用が認可されたインフルエンザワクチンは、本来、アジュバント化されていない。
--------------------------------------
インフルエンザワクチンは、ウイルスの主要な糖タンパク質であるそれらのHA含量に基づいて投薬される。
ということは、このようなワクチンができれば、ウイルスは細胞に接着できない。
--------------------------------------
引用:https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/flu/vaccine/201307/531383.html
感染予防効果を持つ安全なインフルエンザワクチンの開発が強く望まれている。
感染をより効果的に阻止するには、感染の場である気道粘膜上に、中和能力の高い分泌型IgA抗体を誘導する必要がある。
分泌型IgA抗体を誘導する経鼻粘膜投与型インフルエンザワクチンの開発を進めている、国立感染症研究所感染病理部の長谷川秀樹氏は、第54回日本臨床ウイルス学会(6月8~9日、開催地:倉敷市)で、経鼻粘膜投与型インフルエンザワクチンにより鼻腔内に誘導される、多量体化した分泌型IgA抗体が、高いインフルエンザウイルス中和能を示すことを明らかにした。
現在、感染予防効果のみならず、流行株がワクチン株と一致しない変異株である場合に必要な交叉防御能も併せ持つワクチンの研究が盛んに進められている。
そのアプローチの1つとして、大いに期待されているのが経鼻粘膜投与型ワクチンだ。
長谷川氏によると、インフルエンザウイルスの自然感染においては、液性免疫として血中にIgG抗体が誘導されると同時に、粘膜下にIgA抗体産生細胞が誘導される。
ここで産生されたIgA抗体は、polymeric Ig receptorを介して粘膜表面に分泌される。
こうした獲得免疫応答はしばらく維持され、また一部は免疫記憶として残る。
このため、再びウイルスがやってきたとき、速やかに抗体応答と細胞障害性T細胞が誘導され、ウイルスを効率的に排除する。
特に上気道粘膜に分泌されるIgA抗体は、上皮細胞に取り付く前のウイルスを中和できるため、感染そのものを阻止することができる。
このような感染防御のメカニズムを応用したのが経鼻粘膜投与型ワクチンだ。分泌型IgA抗体の誘導により、感染予防のみならず、抗原性が変化したウイルスに対しても高い感染阻止効果を示すことが明らかにされている。
*****************************************
一方、現行の皮下注射ワクチンでは、IgG抗体のみが誘導され、IgA抗体は誘導されない。
*****************************************
したがって、感染成立後の拡散する時点で効果が現れる。
重症化予防には有効であっても、感染そのものを阻止することはできない。
欧米ではすでに、経鼻粘膜投与型ワクチンとして、弱毒生インフルエンザウイルスを用いたワクチンが承認されている。小児に対して高い効果を発揮することが報告されている。
****************************************
ただし、感染性が保持されているため、リスクの高い幼児、高齢者、免疫不全患者などには使用できない。
****************************************
長谷川氏らが開発しているワクチンでは、安全性の高い不活化ワクチンを使用する。
それによる粘膜免疫を効率的に誘導するために、抗原とともに抗原提示細胞を活性化するアジュバントも用いる。
------------------------------------------
免疫学の分野ではアジュバントは抗原性補強剤とも呼ばれ、抗原と一緒に注射され、その抗原性を増強するために用いる物質。
純粋なタンパク質単独では免疫応答が弱いときに、微生物やその分解産物を混合することがアジュバントとして機能する原因は、微生物由来の因子で表面の受容体が刺激されて初めて、マクロファージや樹状細胞といった抗原提示細胞表面にB7分子が発現するためと考えられている。
1926年以降、最初に使用されたアジュバントは、硫酸アルミニウムカリウムであったが、後に水酸化アルミニウムとリン酸アルミニウムに完全に置き換えられた。(Wikipedia)
------------------------------------------
ウイルスが増殖するときに産生する2本鎖RNAをアジュバントとした経鼻粘膜投与型ワクチンを用いて、マウス感染実験を行ったところ、感染の兆候はまったく見られず、マウスは100%生存していた。
さらに、ヒトに応用可能なアジュバントとして、内因性のインターフェロン誘導薬である2本鎖RNA製剤を用いた経鼻粘膜投与型ワクチンで感染実験を行った。
感染3日後の鼻粘膜のウイルス量は、皮下接種ワクチン群ではコントロール群の約10分の1低下しただけだった。
これに対して、経鼻粘膜投与型ワクチン群ではウイルスがまったく認められなかった。
すなわち、感染が完全に阻止され、生存率は100%だった。
2本鎖RNA製剤をアジュバントとした経鼻粘膜投与型ワクチンは、皮下接種ワクチンと異なり、交叉防御能をも有することがマウス、およびヒトに近い免疫系を持つカニクイザルの実験で確認された。
長谷川氏らは、臨床研究からも多くの知見を明らかにしている。
例えば、季節性インフルエンザH3N2ウイルスの不活化全粒子ワクチンの経鼻粘膜投与により、血中のみならず鼻腔粘液中にも中和抗体を誘導することができた。
また、鼻腔粘液中のウイルス中和効果は、分泌型IgA抗体によるものであることが確認された。
さらに今回、新しい知見として、経鼻粘膜投与型ワクチンによって鼻腔内に誘導される分泌型IgA抗体は二量体、四量体といった高次構造をとることが明らかにされた。
鼻腔内には、単量体、二量体、四量体、四量体超の多量体を形成する抗体が存在し、二量体以上の多量体抗体の大部分はIgA抗体より構成されていた。
また、四量体以上に多量体化した抗体のインフルエンザウイルス中和能は、単量体抗体や二量体抗体よりも高かった。
二量体、四量体、多量体IgA抗体は、単量体IgA抗体よりも抗原特異抗体の含有量が多いことも分かったという。
これらの結果から、長谷川氏は「ヒトの鼻粘膜上に存在する分泌型多量体IgA抗体は、インフルエンザウイルスに対する感染防御に寄与していると考えられる。
良く効くワクチンとは、このような分泌型多量体IgA抗体を粘膜上に準備できるワクチンだろう」と言及した。
------------------------------
これだ。鼻粘膜上に存在する分泌型多量体IgA抗体で自然に防御する。
------------------------------
2020.2.16
目次へ
引用:https://www.otsuka.co.jp/b240/mechanism/mechanism2.html
IgAは鼻汁、唾液や消化管などの表面の粘膜中に分泌され、これらの粘膜表面で外敵の侵入を阻止します。
IgAは特に腸に多く存在します。これは、食べ物とともにウイルスや細菌などが侵入しやすい事や膨大な数の微生物が腸管に共生している事も大きな要因と考えられています。
ヒトの外分泌液中のIgA量(μg/ml)
涙腺:80~400
鼻汁:70~846
耳下腺性唾液:15~319
唾液:194~206
気管支肺胞分泌液:3
初乳・母乳:470~12340
十二指腸分泌液:313
空腸分泌液:32~276
結腸分泌液:166
腸管分泌液:3~133
粘膜中の免疫グロブリンにはIgAのほか、IgG、IgM、IgEなどがあるが、粘膜面ではIgAが主体として働く。
---------------
鼻汁にはIgAはたくさんあるが、気管支肺胞分泌液にはほとんどない!
---------------
小腸の表面積はテニスコート1面分(約200平方メートル)に匹敵する広さで、感染防御の最前線として働く。小腸粘膜には消化吸収効率を高めるための「絨毛」があるが、絨毛がなく平らな「パイエル板」という免疫組織もある。パイエル板上皮には病原体を取り込む「M細胞」があり、病原体を取り込むとマクロファージや樹状細胞がヘルパーT細胞に「抗原」としてその情報を提示。ヘルパーT細胞から情報を受け取ったB細胞が活性化し、抗体産生細胞(形質細胞)に分化し、IgAを産生。病原体は分泌されたIgAによって動けなくなり、便として排出。あるいは、体内に入った場合にマクロファージに食べられやすくなる。
----------------
感染の最初からIgAがあるわけではなく、まず、マクロファージなどが病原体を取り込んで、抗原情報をT細胞に伝え、T細胞から情報がB細胞に伝えられて、B細胞は抗体産生細胞に分化してIgAを産生し、これが病原体を取り囲み、凝縮させる。ということのようだ。
----------------
IgAは、特定のウイルスや細菌だけに反応するのではなく、さまざまな種類の病原体に反応する(くっつく)という、守備範囲の広さが特徴です。
IgAが低下すると病気にかかりやすくなります。このことは、上気道感染症(風邪)の発症と唾液中のIgA濃度の関係を調べた研究でも確かめられています。同時に、IgAが低いときは、疲労感も高まっています。
アメリカズカップのヨットレース選手の男性38人を対象に、トレーニング期間の50週間にわたって毎週、唾液サンプルを採取。その結果、上気道感染症を発症する3週間前から唾液IgAレベルが低下し始め、発症時は有意に低下。また唾液中のIgAレベルが低下しているときは、疲労感が強かった。
「粘膜免疫」は粘膜組織で病原体などの異物が侵入しないよう働きます。実際に、その仕組みが正常に働くことで病原体の侵入を防いだ例として、プロの口腔ケアを受けて口の中を健康に保った高齢者は、インフルエンザの発症率が低かったという研究があります。
190人の高齢者男女を、プロによる口腔ケアを受ける群、独自の口腔ケア群に分けた。6ヶ月後、プロケア群はインフルエンザ発症率、風邪発症率が有意に低かった。
----------------
プロの口腔ケアとはなにかな。
----------------
引用:https://pro.saraya.com/fukushi/kokucare/jissai/
歯ブラシの選び方
1)ブラシの大きさは「小さめ」
1度に歯が2本ずつ磨ける大きさ(指1.5?2本分)奥歯や歯並びの悪いブラシの届きにくいところには子ども用を使用する
2)ブラシの毛の硬さは「軟らかめ」
歯と歯の間、歯と歯茎の間に毛が入っていく程度
3)毛束の量は「少なめ」
毛束は2、3列(汚れを落としやすく、乾燥させやすい)
.4)ブラシの柄は「ストレートハンドル」
力を調整して、小さく動かしやすい
歯磨き剤・洗口剤
1回分の歯磨き剤は「大豆1粒分」が適量です。
フッ素入り歯磨き剤・洗口剤は虫歯予防効果があります。
歯磨き剤の口臭効果はあくまで一時的です。
.
注意。口腔ケアは、あくまでブラシをつかった歯磨きが基本です。
含嗽剤(うがい薬)
クロルヘキシジン入り含嗽剤は歯磨き後に使うと効果的です。
その他にデンタルリンスと呼ばれているものも良いでしょう。
口腔ケアの方法
歯ブラシの持ち方
1.歯磨き
歯ブラシは鉛筆を持つように持ちます。
歯の汚れの残りやすい部分を丁寧に磨きます。
歯ブラシの当て方はソフトタッチ、揺らすように。
一度に、1、2本ずつ磨きます。
2.含嗽法(うがい)
口唇をしっかり閉じて
大きく頬を膨らませて
口に含んだ水を勢いよく動かします。
2020.2.18
目次へ
IgAを生成する細胞は何だろう。
引用:Wikipedia
免疫グロブリンA(めんえきグロブリンA、英: Immunoglobulin A, IgA)は、哺乳類および鳥類に存在する免疫グロブリンの一種であり、2つの重鎖(α鎖)と2つの軽鎖(κ鎖およびλ鎖)から構成される。
IgA分子は2つの抗原結合部位を有しているが、気道や腸管などの外分泌液中ではJ鎖(英語版)と呼ばれるポリペプチドを介して結合することにより2量体を形成して存在しているため4箇所の抗原結合部位を持つ。
2量体IgA(分泌型IgA、SIgA)は粘膜免疫の主役であり、消化管や呼吸器における免疫機構の最前線として機能している。
IgAをコードする遺伝子にはIgA1とIgA2の2種類が存在するが、血清中に存在する単量体あるいは2量体IgA(血清型IgA)にはIgA1が約90%と圧倒的に多い。
その一方で分泌型IgAではIgA2の割合が30-50%と血清型に比べて多くなっている。
全IgA中における血清IgAの占める割合は10-20%程度であり、IgAのほとんどは二量体として存在している。
また、分泌型IgAは初乳中に含有され、新生児の消化管を細菌・ウイルス感染から守る働きを有している(母子免疫)。母子免疫には免疫グロブリンGも関与していることが知られているが、こちらは胎盤を介して胎児に移行する。ヒトにおけるIgAの産生量は各種免疫グロブリンの中でもIgGに次いで2番目に多い。
分子量16万(単量体)。
粘膜は常時抗原や微生物にさらされており、これらから粘膜面を防御する局所免疫機構が存在する。
これを粘膜免疫防御系(英: Mucosa-associated Lymphoid Tissue, MALT)と呼び、分泌型IgAがその一部を構成している。
代表的なMALTとして消化管免疫防御系(GALT)、気道免疫防御系(BALT)および鼻腔免疫防御系(NALT)が知られている。
粘膜免疫機構はIgAの産生誘導を行う誘導組織とIgAが分泌・機能する実効組織、そしてそれらをつなぐ帰巣経路から構成され、これらを合わせてCMIS(Common Mucosal Immune System)と呼ぶ。
誘導組織において粘膜面に存在する抗原提示細胞はリンパ球を活性化させ、遊走させる働きを持っている。
リンパ球はリンパ節で分化した後に実効組織に到達し、IgAを産生する。この際、一度誘導組織を離れたリンパ球は再び同じ組織に戻ってくる傾向を持ち、これをリンパ球のホーミング(帰巣現象)と呼ぶ。
IgAは実効組織の粘膜固有層に存在するIgA産生形質細胞(プラズマ細胞)により二量体として産生され、分泌される。
形質細胞はリンパ球の一種であるB細胞から分化し抗体産生能を持つ細胞であり、通常IgMを産生する能力を持っている。
この細胞がIgA産生能を獲得するためにはサイトカインの刺激を受ける必要があり、B細胞がトランスフォーミング増殖因子(TGF)-βやインターロイキン-4の作用を受けることにより免疫グロブリンのクラススイッチが誘導される。
クラススイッチを終えた細胞はさらにインターロイキン-5およびインターロイキン-6の刺激を受けてIgA産生能を持つ形質細胞に分化する。
これらの過程を通して見るとIgA産生形質細胞への分化にはTh2サイトカインが重要な働きをしていることが分かる。
IgAは同様に形質細胞により産生されるJ鎖と結合し2量体として分泌される。
2量体IgAはその後粘膜上皮細胞の基底膜側に発現している分泌成分(英: Secretory Component, SC)と結合して上皮細胞内へ取り込まれ、管腔側へと分泌される。
分泌成分はIgAをタンパク質分解酵素による分解から保護する役割を有している。IgAはこれらの系を介して粘膜面への微生物の侵入を防ぎ、生体防御機構において重要な役割を果たしている。
血清中IgAは好酸球やマクロファージ等の細胞表面に存在するFcαRを介して細胞活性化を引き起こし、食作用や抗体依存性細胞傷害(ADCC)、炎症メディエータの遊離促進などの機構を介して免疫反応に関与していることが示唆されている。
------------------------------
IgAの生成は単純ではないな。なによりも身体全体が正常に機能している必要がある。
生成されたIgAがタンパク質分解酵素に分解されないように、分泌成分に結合するとは、なんという生体の巧妙な仕組みだろう!
------------------------------
2020.2.19
目次へ
ひとつ、ウイルスになったつもりで見てみよう。
引用:Wikipedia
一本鎖の+鎖RNAウイルスはゲノム自体がmRNAとして機能し得る。SARSの原因であるコロナウイルスはこれに含まれる。レトロウイルスもここに含まれるが、いったんDNAに遺伝情報を移す。
引用:https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/9303-coronavirus.html
電子顕微鏡で観察されるコロナウイルスは、直径約100nmの球形で、表面には突起が見られる。
形態が王冠“crown”に似ていることからギリシャ語で王冠を意味する“corona”という名前が付けられた。
ウイルス学的には、ニドウイルス目・コロナウイルス亜科・コロナウイルス科に分類される。
脂質二重膜のエンベロープの中にNucleocapsid(N)蛋白に巻きついたプラス鎖の一本鎖RNAのゲノムがあり、エンベロープ表面にはSpike(S)蛋白、Envelope(E)蛋白、Membrane(M)蛋白が配置されている。
ウイルスゲノムの大きさはRNAウイルスの中では最大サイズの30kbである。遺伝学的特徴からα、β、γ、δのグループに分類される。HCoV-229EとHCoV-NL63はαコロナウイルスに、MERS-CoV、SARS-CoV、HCoV-OC43、HCoV-HKU1はβコロナウイルスに分類されている。
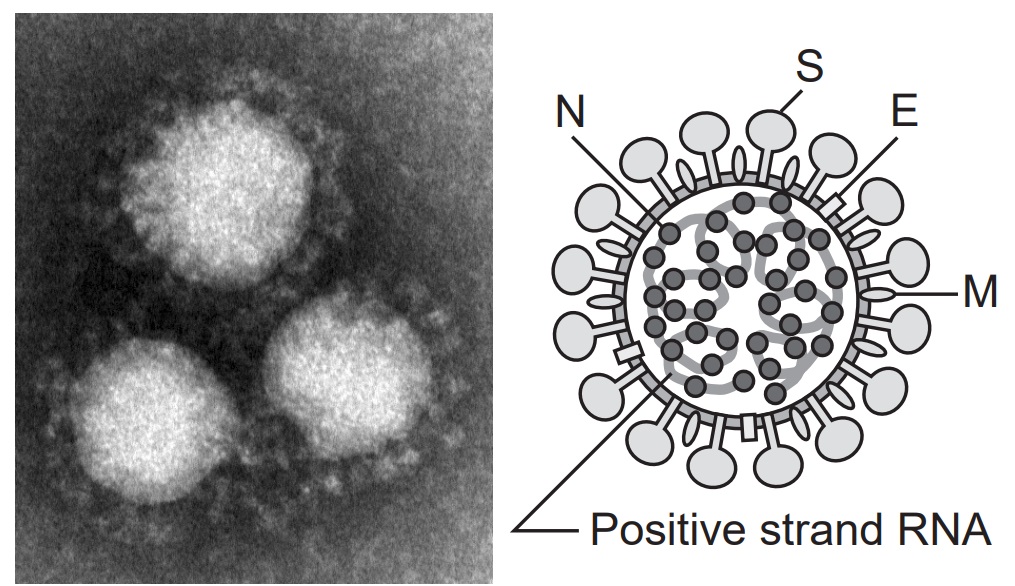
-----------------------
脂質二重膜のエンベロープに3種類のタンパク質が整然と並んでいる。一番大きいのはSタンパク。
さて、どのタンパクで細胞膜に接着するか。
-----------------------
引用:https://www.niid.go.jp/niid/ja/basic-science/immunology/6149-imm-2015-002.html
生体内において最も産生量の多い抗体であるIgA抗体は分泌型IgA抗体としてインフルエンザ等の粘膜組織を標的とした感染症に対する生体防御の最前線を担っており、現在、世界中で分泌型IgA抗体の誘導を目指した経鼻投与型粘膜ワクチンの開発が進んでいる。
分泌型IgA抗体は血液中に存在するIgG抗体とは異なり多量体を形成している。
その多くは二量体であることが広く知られているが、微量ながら二量体よりも大きな多量体を形成した分泌型IgA抗体が存在する事が半世紀ほど前から知られていた。
しかしながら、これらの二量体よりも大きな多量体の分泌型IgA抗体の四次構造と生体内における役割については全く明らかにされていなかった。
本研究では、経鼻不活化インフルエンザワクチンのヒトにおける有効性発現機序を理解するためにワクチン接種によりヒトの気道粘膜上に誘導される抗体の四次構造と機能を解析し、ヒトの呼吸器粘膜には二量体に加え、三量体、四量体、四量体よりも大きな多量体を形成する分泌型IgA抗体が存在することと、それらの大きな分泌型IgA抗体は二量体よりも高いウイルス中和活性を有しているほか、抗原性の離れたウイルスに対しても中和活性を持っていることを明らかにした。
さらに、高速原子間力顕微鏡(HS-AFM)により抗体分子を1分子レベルで解析することにより、アスタリスクもしくは四葉のクローバーのような形状をした三量体、四量体の分泌型IgA抗体が抗体外周部に存在する多数の抗原結合部位でウイルス抗原を効率良く捕らえていることも明らかにした。
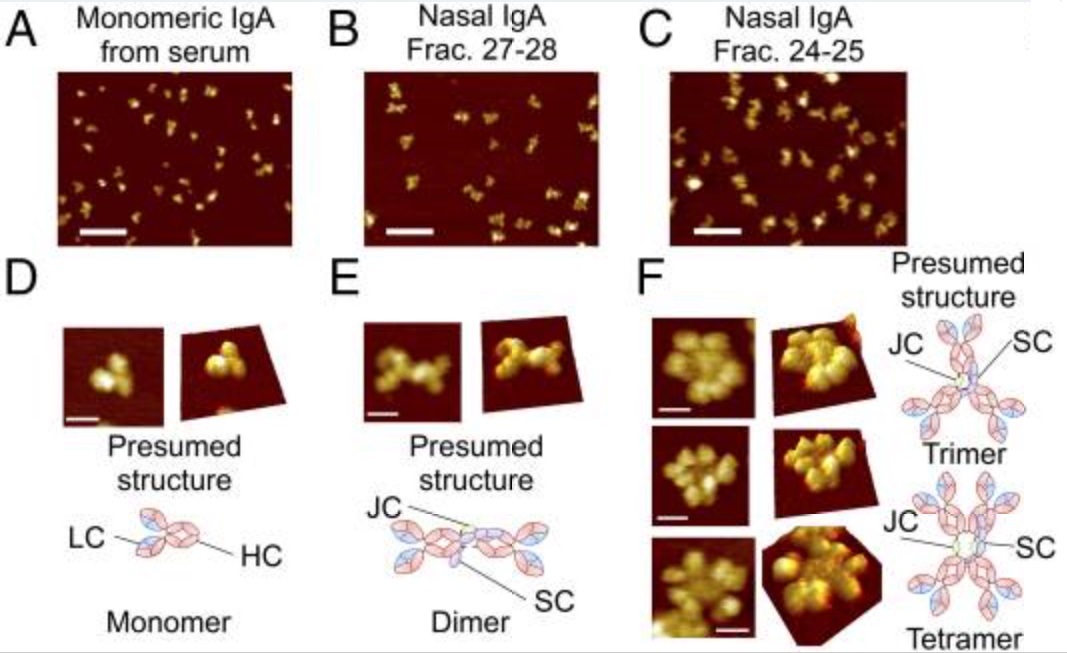
高速原子間力顕微鏡で撮影したIgA抗体 D:単量体、E:二量体、F:三量体、四量体
------------------------
IgAが不特定の抗原に接着するのかがわからないが、とりあえず、IgMとIgGについて見てみる。
------------------------
引用:https://www.jst.go.jp/crest/immunesystem/result/02.html
私たちの体は、1度出会った細菌やウイルスなどの抗原に再び出会うと、1度目よりも大量の抗体を迅速に作り出して速やかにその抗原を除去し生体を防御します。
抗原に初めて出会うと、IgM型B細胞抗原受容体(BCR)を持つB細胞(IgM型ナイーブB細胞が対応して抗原を記憶します。
次回からは1度目の免疫反応で抗原を記憶したIgG型注2)BCRを持つB細胞(IgG型メモリーB細胞注4))が素早く反応するためです。
つまり、IgM型ナイーブB細胞は抗原に出会うと胚中心B細胞へ分化し、一部が抗体産生細胞に分化する。
一方、IgG型メモリーB細胞は、抗体産生細胞へ迅速に大量に分化する。
IgM型ナイーブB細胞は細菌やウイルスといった抗原に出会うと活性化し、胚中心B細胞と呼ばれる活発に増殖し細胞の数を増やし、質の良いBCRを作り出す状態へと変化する。
その後その一部は、メモリーB細胞となる。この過程で、BCRの型がIgM型からIgG型へと変化する。
------------------------
IgM型B細胞は抗原に特異的に反応して、その記憶はIgG型B細胞として、抗原が出現したときに増殖する。
IgMとIgGは構造がどのように違うのだろう。
------------------------br>
引用:https://ja.strephonsays.com/difference-between-igg-and-igm
IgMは免疫反応の初期段階で産生されます。
IgMにはサブクラスがありません。
IgMはサイズが大きい(970kDa)。
IgMは五量体です。
IgMは10個の抗原結合部位からなる。
IgMはIgGより豊富ではない。
IgMは胎盤を通過できません。
IgMは血液とリンパ液に含まれています。
IgMは一時的な抗体であり、IgGに置き換えられます。
IgMは体内で新たに出現する病原体に対する防御を提供します。
IgMは、適応免疫応答中に最初に出現した抗体であるため、凝集反応および細胞質ゾル反応に関与しています。
IgGは免疫反応の最新の段階で産生されます。
IgGの4つのサブクラスは、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4です。
IgGはIgM(150kDa)より小さい。
IgGはモノマーです。
IgGは2つの抗原結合部位からなる。
IgGは最も豊富な種類の免疫グロブリンです。
IgGは、母親から子供へと胎盤を通過することができます。
IgGはすべての体液に含まれています。
IgGは長持ちする免疫グロブリンです。
IgGは細菌感染およびウイルス感染に対する防御を提供する。
IgGはエピトープに結合し、後に適応免疫応答の間に出現するので補体系を活性化する。
引用:https://kusuri-jouhou.com/immunity/hijiko.html
自己と非自己の認識
抗原決定基、抗原受容体
リンパ球が自己と非自己を認識できるのは抗原決定基が存在するからである。リンパ球はこの抗原決定基を認識するのである。
抗原決定基は抗原性の最小単位であり、エピトープともいう。
リンパ球の中でB細胞は細胞表面にある抗原受容体で抗原決定基を認識する。B細胞の抗原受容体なのでBCR(B cell receptor)という。
B細胞では抗体分子とほとんど同じ構造のものが細胞表面に出ている。これがBCR(抗原受容体)であり、特定の抗原決定基と結合する性質がある。
BCRと抗原決定基が結合するとB細胞は活性化する。ただし、2つ以上のBCRと抗原が結合して架橋という形をとらないと活性化しない。BCRと抗原が一ヶ所で結合しても活性化は起こらない。
また、一つのB細胞は一種類の抗原受容体しかもっていない。そのため、B細胞が作る抗体も一種類である。
あらゆる抗原に対応するため、B細胞を作り出すときには莫大な数の抗原受容体の中から、その抗原に対応するB細胞クローンだけが選択され増殖する。この考えをクローン説という。
抗原受容体の種類は10^8個に対応していると言われている。つまり、莫大な数の抗原に対応する抗体産出環境が既に整っているのである。
細胞がウイルスに感染するとウイルスは細胞を乗っ取ろうとする。細胞はウイルスに乗っ取られる前に抗原(ウイルス)を切断して、抗原の一部を細胞表面に提示する。T細胞はこの提示された断片を認識するのである。
しかし、抗原だけを提示したのではダメである。抗原はMHC(主要組織適合遺伝子複合体)と結合させて提示しないと意味がない。(MHC 抗原ペプチド)
MHCには2種類あり、それぞれクラスⅠとクラスⅡが存在する。クラスⅠのMHCはキラーT細胞に関与し、クラスⅡのMHCはヘルパーT細胞に関与している。
つまり、「MHCクラスⅠ 抗原ペプチド」と「MHCクラスⅡ 抗原ペプチド」は全く別のものである。
クラスⅠとクラスⅡの何が違うかというと、「T細胞上に存在するどのCD抗原と親和性をもつか」が異なっているのである。
「血球の細胞表面に存在する抗原分子」をCD(cluster of differentiation)といい、CDにはCD1,CD2 … という具合に何種類も存在する。
クラスⅠのMHCはCD8と親和性があり、クラスⅡのMHCはCD4と親和性がある。「CD8 T細胞=キラーT細胞」であり、「CD4 T細胞=ヘルパーT細胞」である。
また、クラスⅠのMHCは8~10個の抗原ペプチドを認識し、クラスⅡのMHCは13~17個のペプチドを認識する。
・クラスⅠでの抗原の処理
細胞がウイルスに感染すると、その細胞で合成されるタンパク質はウイルス由来のものへと変わってしまう。
MHCクラスⅠで抗原を提示するときは、この合成されたタンパク質抗原を使用する。合成された抗原タンパクはプロテアソームによって小さいペプチドにまで分解される。
ペプチド断片はタンパク質輸送体(TAP)によって小胞体内へ運ばれると、小胞体で合成されたMHCクラスⅠ分子と結合して複合体を形成する。その後、ゴルジ体を経て細胞表面へと運ばれる。
つまり、クラスⅠで抗原を提示するときは細胞内で合成されたペプチドを提示する。
・クラスⅡでの抗原の処理
MHCクラスⅡで提示するための抗原はエンドサイトーシスによって取り込まれる。取り込まれた外来性タンパク質はリソソームによってペプチド断片に分解される。
MHCクラスⅡ分子は小胞体で合成され、他のペプチドとの結合を防ぐためにインバリアント鎖と結合する。
クラスⅡ分子がエンドソーム内に入ってインバリアント鎖が切れると、抗原ペプチドと複合体を作る。その後、細胞表面へと運ばれる。
つまり、クラスⅡで抗原を提示するときは細胞外から来たペプチドを提示する。
・T細胞受容体
T細胞受容体はT細胞表面に存在する。この受容体は抗原分子(CD)とMHCの複合体に結合する。成熟したキラーT細胞がウイルスに感染した細胞を認識すると感染した細胞は破壊される。
MHCの多様性
T細胞にはさまざまなMHCに噛み合うT細胞受容体(TCR)がある。
ただし、自己のMHCに合う受容体だけはもっていない。T細胞は自己だけでは応答しないが、非自己の抗原と合わさると認識する。
普通、遺伝子は父親か母親のどちらかが受け継がれる。しかし、MHCでは父母両方由来の遺伝子が細胞表面に提示される。つまり、MHCには非常に多くの種類が存在する。MHCがこれだけ多型なのには理由がある。
例えば、ヒトのMHCが一種類であるとする。自己のMHCにはT細胞は応答しないので、自己のMHCと全く同じMHCをもつウイルスが現れたとしたら、ヒトの免疫はそのウイルスに対して全く応答しないので、ヒトは絶滅の一途をたどることになる。
こうならないためにMHCは非常に多型となっている。これは動物が生き延びていくのにとても大事なことである。
・拒絶反応の問題
MHCの多様性は、臓器移植の際の拒絶反応の点ではマイナスとなる。前述の通りMHCは多型であり、MHCの構造が似ているヒトは1万人に1人の割合である。細胞表面のMHCが異なるとT細胞はその細胞を攻撃してしまう。これが拒絶反応の起こる仕組みである。
抗原提示細胞(APC)
抗原提示細胞(APC)にはマクロファージ、樹状細胞、B細胞などがある。抗原提示細胞とは、抗原をT細胞に提示することでT細胞を活性化させる細胞のことである。
抗原提示細胞はヘルパーT細胞を活性化するとき、抗原提示細胞のMHCクラスⅡとT細胞のCD4を結合させる。これが第一シグナルとなる。
しかし、T細胞が活性化するにはもう一回刺激がないといけない。最後に抗原提示細胞のB7とT細胞のCD28が結合し、これが第二シグナルとなってヘルパーT細胞が活性化する。
・マクロファージ
マクロファージは血中では単球とよばれ、抗原をT細胞に提示して活性化させる働きをする。そのため、マクロファージの細胞表面にはFc受容体、補体受容体、MHCクラスⅠ、MHCクラスⅡ分子が存在する。
マクロファージは抗原提示の作用だけではなくウイルス細胞などの粒子を取り込む貪食作用(ファゴサイトーシス)や細胞外液などの溶液を取り込む飲作用(ピノサイトーシス)の作用がある。
・樹状細胞
樹状細胞は皮膚、肺、胃、鼻腔などの生体各組織に広く分布している。樹状細胞はリンパ器官に移行する能力があり、抗原を捕らえると提示できるように分解してリンパ管内へ移動する。移行した後はT細胞に抗原を提示する。
樹状細胞の一番の特徴は「抗原提示細胞の中で最も抗原を提示する能力が高いこと」である。
この性質を利用して樹状細胞を取り出して腫瘍の抗原ペプチドを認識させた後、この樹状細胞を再び患者に戻してT細胞を活性化させようという試みがある。これを免疫療法という。
---------------------------------
B細胞などの抗原提示細胞は、MHC(主要組織適合遺伝子複合体)をウイルスなどの抗原に結合して、T細胞に提示する。
MHCには、抗原を細胞内に取り込んで(感染して)抗原を合成して細胞膜上に提示するクラスⅠと、抗原と結合したまま細胞膜に提示するクラスⅡがある。
MHCと結合した抗原が、T細胞の細胞膜にある受容体と結合すると、T細胞が活性化する。
---------------------------------
2020.2.20
目次へ
実際、ウイルスはどうやって細胞膜にくっつくのだろう。
引用:https://next-pharmacist.net/archives/3995
ウイルスがすべての細胞に侵入できるわけではありません。ウイルスが侵入できるのは「自分が結合できる特定の蛋白を表面にもっている細胞」だけです。
各細胞は、ウイルスのためにそれらの蛋白をつくっているわけではないのですが、偶然不幸にもウイルスの侵入する玄関口となってしまうことがあるのです。
例として、かぜの原因となるライノウイルスは、CD54という表面蛋白に結合して細胞内に侵入します。
CD54とは細胞と細胞を結合させる接着分子でありICAM-1とも呼ばれ、気道上皮細胞や血管内皮細胞などの細胞表面に多く存在しています。
かぜが急性上気道炎とよばれ、かぜウイルスが気道上皮から侵入しやすいのはそのためだったのです!
引用:http://www.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/036110923j.pdf
ICAM-1(CD 54)は,分子量80~110 kD のglycoproteinで,immunoglobulin superfamily に属している.
ICAM-1 は,インテグリンlymphocyte-function-associatedantigen-1(LFA-1,CD 11,CD 18)のリガンドである.
受容体LFA-1 が白血球に限局して存在するのに対し,ICAM-1 は血管内皮や気道上皮を含めて,種々の細胞に広範に存在する.
従って,ICAM-1�LFA-1 系は炎症の発症メカニズムに重要な役割を果たしていることが予想される.
引用:Wikipedia ICAM-1
ICAM-1とも呼ばれるCD54は、ヒトにおいてICAM1遺伝子によってコードされるタンパク質である。
この遺伝子は、免疫系の内皮細胞および細胞上で典型的に発現される細胞表面糖タンパク質をコードする。
ICAM-1は、細胞間相互作用を安定化し、白血球内皮内皮移動を促進する上でその重要性を長く知られている内皮および白血球関連膜貫通タンパク質である。
最近では、ICAM-1はヒトライノウイルスの細胞感染部位として特徴付けられている。
CD11a/CD18型、またはCD11b/CD18のインテグリンに結合し、呼吸上皮への侵入の受容体としてライノウイルスによっても利用される。
呼吸器上皮細胞で発現するICAM-1は、ライノウイルスの結合部位でもあり、最も一般的な風邪の原因物質である.
---------------------
呼吸器上皮細胞で発現するICAM-1は、本来、細胞間相互作用を安定化し、白血球内皮内皮移動を促進する内皮および白血球関連膜貫通タンパク質であるが、ライノウイルスの結合部位でもある!
---------------------
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsv/61/1/61_1_109/_pdf/-char/ja
重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV)のエンベロープ糖蛋白(S蛋白)は,宿主プロテアーゼ(トリプシン,エラスターゼ,カテプシン,TMPRSS2)に切られて活性化される.
インフルエンザウイルス等多くのエンベロープウイルスもプロテアーゼを利用するが,プロテアーゼの作用する様式がSARS-CoVとは異なる.
インフルエンザウイルスの場合は細胞でウイルスが作られるときエンベロープ糖蛋白(HA)がプロテアーゼに切られ「膜融合誘導可能な形」になるが,SARS-CoVの場合は「細胞侵入の瞬間」にS蛋白が切られて膜融合開始の引き金が引かれる.
コロナウイルスは,エンベロープをもつ直径60~220nmの楕円形あるいは多形成のウイルスである.
ウイルスゲノムはポジティブ一本鎖RNAで,27~32kbのサイズであり,RNAウイルスの中では最大サイズである.
ヒトに感染するコロナウイルスHuman coronavirus(HCoV)としては,1960年代にHCoV-229EとHCoV-OC43が風邪の原因ウイルスとして分離された.
また2003年にHCoV-NL63,2005年にはHCoV-NHが呼吸器症状を示す患者から分離された.
さらに2003年に分離された重症急性呼吸器症候群の原因病原体(SARS-CoV)はキクガシラコウモリを自然宿主とするコロナウイルスであったが,ハクビシンを経由してヒトに感染することで,肺炎を引き起こすウイルスに変化したと考えられている.
インフルエンザ,HIV等の多くのエンベロープウイルスは細胞内でウイルスが作られる時,エンベロープ糖蛋白がプロテアーゼによる開裂を受け,「膜融合誘導可能」な形に活性化される.
一方,SARS-CoVのエンベロープ糖蛋白(S)は細胞侵入の瞬間に宿主プロテアーゼによる開裂を受け,膜融合活性が発揮される.
これまでによく研究されているコロナウイルス,MHV-JHM株,MHV-A59株はHIVと同様の「ウイルスが作られるとき」に切られるS蛋白をもっている.
約180kDaのS蛋白は一本の蛋白として合成され,細胞内のFurinにより約90kDaのS1及びS2サブユニットに開裂される.
一方,SARS-CoV,229E及びMHV-2株のS蛋白はFurin切断サイトが欠損しているため,180kDaの一本の蛋白として合成された後,開裂を受けず180kDaのままウイルス粒子上に乗っている.
この未開裂S蛋白は「膜融合誘導可能な形」になっておらず,感染時,レセプター結合の後に上記の宿主プロテアーゼによる開裂を受けて活性化すると考えられている.
SARS-CoVはエンドソームで膜融合する経路と,細胞表面で膜融合する経路の,二通りの経路から細胞侵入することができる.
ウイルスは感染する細胞によって経路を選ぶ可能性がある.
SARS-CoVは感染初期に肺胞上皮表面のTMPRSS2を利用して,また重症肺炎時には免疫細胞が作るエラスターゼを利用して細胞に侵入する可能性がある.
--------------------------
細胞が持っている酵素を利用して巧妙に侵入するようだ。
--------------------------
2020.2.21
目次へ
SARS-CoVのエンベロープ糖蛋白(S:spikeという一番大きなタンパク質)は細胞侵入の瞬間に宿主プロテアーゼによる開裂を受け,膜融合活性が発揮される、というが、プロテアーゼとはなんだろう。
引用:Wikipedia プロテアーゼ
プロテアーゼ(Protease、EC 3.4群)とはペプチド結合加水分解酵素の総称で、プロテイナーゼ(proteinase)とも呼ばれる。広義のペプチダーゼ(Peptidase)のこと。
タンパク質やポリペプチドの加水分解酵素で、それらを加水分解して異化する。収斂進化により、全く異なる触媒機能を持つプロテアーゼが似たような働きを持つ。
プロテアーゼは動物、植物、バクテリア、古細菌、ウイルスなどにある。ヒトでは小腸上皮細胞から分泌する。
アミノ酸がペプチド結合によって鎖状に連結したペプチド(一般に100残基未満、比較的分子量が小さい)やタンパク質(一般に100残基以上、比較的分子量が大きい)のペプチド結合を加水分解する酵素で、様々な種類のものが、生理的役割として、栄養吸収、タンパク質の廃棄とリサイクル、生体防御、活性の調節、などの幅広い分野で働いている。
プロテアーゼには切断する配列をあまり選ばない(基質特異性が低い)ものや、特定のタンパク質・ペプチドの特定の部位だけを特異的に切断するという切断する配列に対する高度な選択性を持つ(基質特異性が高い)タイプのものがある。
ペプシン(pepsin)やキモトリプシン(chymotrypsin)などが前者の、ケキシン(Kexin)やフューリン(Furin)のようなプロセッシングプロテアーゼ、Xa因子のような血液凝固因子などが後者の例として典型的なものである。
引用:http://lifesciencedb.jp/dbsearch/Literature/get_pne_cgpdf.php?year=1997&number=4206&file=0MnKqc5GLayyPejV1AyCSA==
ポリオウイルス、エイズウイルスなどは、自らプロテアーゼ遺伝子を持っている。これを用いてつくったプロテアーゼで自分の一本鎖RNAを所定の場所で切断し、ウイルスの構造タンパク質をつくる。
ウイルスのエンベロープはそのままでは標的細胞の中に入れない。エンベロープにある赤血球凝集タンパク質(HA)が特定のプロテアーゼによって分解されると、細胞膜と融合できる。
インフルエンザウイルスはヒトでは上気道で増殖するので、そこにプロテアーゼが存在することが増殖の条件となる。
このため、プロテアーゼ阻害剤が抗ウイルス薬となる。
引用:https://www.kuba.jp/syoseki/PDF/3073.pdf
細胞内のタンパク質分解には2 つの大きな特徴があります。
第1 は、タンパク質は固有の寿命をもつということです。
例えば、もっとも寿命の短いタンパク質であるオルニチン脱炭酸酵素の半減期はわずか十数分であるのに対し、寿命が長いものでは半減期が数ヵ月にいたり、寿命の差は1 万倍程度に達しています。
このことは、タンパク質が選択的に分解されていることを示唆しています。
それに対して、細胞外のタンパク質分解は、基質であるタンパク質と、これをこわすプロテ
アーゼがたんにぶつかることで起こりますが、この場合、選択性はほとんどありません。
細胞内で選択的なタンパク質分解が起こる原因として、2 つの可能性が考えられます。
第1 は、細胞中のプロテアーゼ活性が制御されている可能性です。
第2 は、分解されるべき標的タンパク質に分解シグナルがあり、この分解シグナルの有無によってタンパク質分解が行われている可能性です。
細胞内のタンパク質分解の第2 の特徴は、タンパク質分解によって細胞機能が修飾される
ということです。
もちろん、新しい機能を発揮するタンパク質ができれば機能に影響を及ぼすのは当然ですが、タンパク質が分解してなくなることによっても大きな影響をうけます。
これらをあわせてバイオモジュレータ作用と呼んでいます。
分解シグナルはタンパク質分子のなかに存在し、タンパク質分子の構造変化により分解シグナルが分子の表面にでて識別され、タンパク質が分解されるものと考えられます。
引用:Wikipedia CD4
CD4(cluster of differentiation 4)とはいわゆるヘルパーT細胞、単球、マクロファージ、樹状細胞などの免疫系細胞が細胞表面に発現している糖タンパクで細胞表面抗原の1つである。1970年代後半に発見されたこの分子は、1984年にCD4と名付けられるまではleu-3、T4として知られていた。ヒトの場合、CD4遺伝子にコードされている。
CD4陽性T細胞はヒトの免疫系において必要不可欠な白血球である。
しばしばCD4細胞、Th細胞、T4細胞と呼ばれることもある(以下CD4細胞)。
この細胞の主要な役割はCD8陽性T細胞(いわゆるキラーT細胞、もしくは細胞傷害性T細胞、以下CD8細胞)などの他の免疫系細胞にシグナルを送ることであり、このことからCD4細胞はヘルパー細胞と呼ばれる。
CD4細胞がシグナルを送ると、CD8細胞はそれを受けて感染細胞を破壊しこれを殺す。
無治療のHIV-1感染患者や臓器移植前の免疫抑制状態のようにCD4細胞が枯渇してしまうと、健康な人では感染症を起こさないような様々な病原体に対して感染を起こしやすい状態になってしまう(日和見感染)。
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/27/12/27_12_816/_pdf/-char/ja
レセプターにせよ,プロテアーゼにせよ,ウイルスは宿主個体の生理的分子を巧妙に使っているにすぎない.
しかし,その背景には,ウイルスの進化,新しい宿主への感染性と病原性の獲得などの観点から見逃せない問題があるように思われる.VAP-Iが凝固因子FXaであったり,HIVレセプターがCD 4であったりするのは単なる偶然だろうか?
RNAウイルスの塩基置換は通常のDNAゲノムのそれとは桁違いに高率に起こる.CD 4やFXaはウイルスと宿主の間をとりもつ,
おそらく最も重要な位置にあり,したがって選択圧要因の最たるものであろう.多様な生存変異株のプールの中から,これら分子に相補的構造をもったウイルス分子の選択が,おそらく新しい宿主特異性,臓器向性をもったウイルスの出現へと導いた可能性がある.
--------------------------------
ウイルスは細胞表面抗原を利用している!
わからないのは、極めて多種類のウイルスのエンベロープを1対1で識別できる仕組み。
ワクチンのことを見てみよう。
--------------------------------
引用:https://www.japan-who.or.jp/library/2010/book4204.pdf
ヒトでインフルエンザの流行を起こすのは、インフルエンザウイルスのA 型とB 型の2 種類である。
A 型は、ウイルス表面上にある2 種類の糖蛋白質、ヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ
(NA)の抗原性により、多くの亜型に分類される。
HA はH1 からH16 の16 種類、NA はN1 からN9 までの9 種類の亜型に分かれる。B 型は、はっきりと区別できる2 つの系統に分かれるが、亜型に分類できるほどの大きな違いではない。
1977 年にA 型のH1N1(A ソ連型)が出現して以降、この亜型とA 型のH3N2(A 香港型)、
それにB 型の3 種類が流行している。
ウイルス表面抗原、特にHA に対する免疫は感染を抑える。しかし、一つの型、あるいは亜型に対する抗体は、別の型、あるいは亜型の感染をほとんど阻止できない。
さらに、同じ亜型のウイルスであっても、大きな抗原変異を起こせば免疫は有効ではない。インフルエンザが毎年流行し、ワクチン株を毎年選択する必要があるのは、HA の抗原性が変化するためである。
抗原変異は、大きく連続変異(小変異)と不連続変異( 大変異) に分けられる。
同じ亜型の中で少しずつ変異を繰り返すのが連続変異で、流行を繰り返す度に起こっている。
HA あるいはNA がまったく別の亜型に変わる変異が不連続変異である。すなわちこれは新
型インフルエンザの出現ということで、パンデミックを心配しなければならない。
現行の不活化インフルエンザワクチンの製造工程:
まずワクチン株を孵化鶏卵に接種し、33 ~ 35℃で2 日間培養する。
培養後、4℃の冷蔵室で一晩放置し、感染尿膜腔液を採取する。
次いで、限外濾過法、化学的方法などで濃縮し、蔗糖密度勾配遠心法(以下ゾーナルという)で精製する。
ゾーナル精製の場合、0 ~ 60%の蔗糖の密度勾配中で濃縮ウイルスを超遠心(35,000rpm)
し、蔗糖密度が40%前後の画分を採取する。
ここには高度に精製されたウイルスが含まれており、電子顕微鏡で観察すると多数のウイルス粒子が見える。
精製ウイルスをホルマリンで不活化したのが全粒子型ワクチンで、一部アメリカなどで使用されている。
副反応の主な原因と考えられているエンベロープ中の脂質をエーテルで取り除き、主にHA 画分を集めたのが現行のスプリットワクチンである。
エーテル処理後にホルマリンを添加し、ゾーナル精製してHA 画分を採取したものがHAワクチン原液となる。
ここにはロゼット状(バラの花の形)になったHA とNA の集合体が観察されるが、それ以外のウイルス蛋白成分も少量ではあるが含まれている。
------------------------------
ウイルスのエンベロープの一番大きいタンパク質HAを精製して、ワクチンとするようだ。
HAに変異が多発し、その変異型ごとに、抗体が必要となる。
HAの形状にオスメス的にぴったりはまる抗体を作れば、ウイルスを捕獲できる。
------------------------------
2020.2.22
目次へ
2.22の読売新聞朝刊に、新型インフル薬投与へ、という記事があり、アビガンという治療薬のことが紹介されていた。
アビガンを調べてみたら、ウイルスのRNAの複製を阻害する薬だという。
そこで、ウイルスが細胞に侵入して、自分のmRNAを使ってリボゾームにタンパク質を作らせる仕組みを調べてみた。
引用:https://www.amed.go.jp/news/release_20190514.html
真核生物のmRNAの末端には「キャップ」という構造が付加されており、ここに翻訳の開始に関わるタンパク質「翻訳開始因子」群(数十種類よりなる)と、40Sサブユニット、60Sサブユニットが集まります。こうして、60Sサブユニットと40Sサブユニットに挟まれた形で、mRNA上の翻訳開始点から翻訳反応が始まります。
一方、HCVをはじめとするある種のウイルス由来のRNAはキャップ構造を持たず、リボソームと限られた種類の翻訳開始因子のみを用いてウイルスタンパク質の合成を効率良く開始します。
C型肝炎ウイルス(HCV)HCVは、ゲノム1本鎖RNAがそのままmRNAとして機能しますが、その末端に存在する「IRES」と呼ばれる配列が、効率の良い翻訳開始を担っています。
IRESの役割については、多くの研究が精力的に進められています。
これまでの知見では、IRESと翻訳開始因子のリボソーム上の結合部位が同じ場所であることから、宿主のmRNAの翻訳反応に使われていない空の40SサブユニットにIRESが結合することによって、HCVゲノムRNAの翻訳開始が誘導されると考えられてきました。
HCVのIRESがどのような状態のリボソームに結合しているかを解析しました。
その結果、従来から唱えられていた通り、HCVのIRESは40Sサブユニットに結合していましたが、意外なことに、すでに他のmRNAを翻訳中のリボソームにも結合していることを見いだしました。
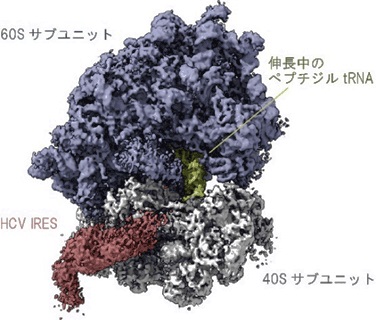
そこで、その状態を詳しく調べるために、通常のヒト細胞の中で起こっているのと同じように、キャップ構造を持つmRNAと翻訳中のリボソームを試験管内に準備し、そこにHCVのIRESを加えた試料をクライオ電子顕微鏡で観察しました。
するとIRESが、進行中のmRNAの翻訳反応を邪魔することなく、40Sサブユニットに結合している構造を捉えることに成功しました。
生化学的な実験により、HCVゲノム自身の翻訳(IRESに依存した翻訳)の開始は、キャップ構造を持つmRNAを翻訳中のリボソームを用いた方が、翻訳反応に使われていない空のリボソームを用いるよりも、迅速に進むことが明らかになりました。
この結果とクライオ電子顕微鏡による観察結果と併せると、従来の「使われていない40SサブユニットにHCVのIRESが結合して、HCVのタンパク質合成が開始される」モデルよりも、「細胞のmRNAを翻訳中のリボソームにHCVのIRESが結合し乗っ取る」(場合の方が、より効率よく頻繁に起こると考えられます。
さらに、HCVゲノムの翻訳に使われている40Sサブユニットを、次のラウンドの翻訳の際にもう一度使う(図2のⅤ→Ⅲ)といったシステムも存在しうることが示されました。
クライオ電子顕微鏡をはじめとした先端的な計測手法と、試験管内再構成という生化学的な手法の組み合わせは、日本の構造生物学研究の強みの一つです。
本研究は、HCVのIRESが、これまで想定されていなかった方法で反応中の翻訳装置リボソームを乗っ取っていることを示した点で画期的です。
今回明らかになった機構は、HCVのIRESと同じような構造を持つウイルスに共通すると考えられます。
従って、IRESとリボソームの40Sサブユニットとの相互作用を阻害する薬剤を開発できれば、効果的な抗ウイルス薬になる可能性があります。
-----------------------------
タミフルは:
ウイルスのエンベロープにあるNAは、不用意にくっついてしまった自分側のHAと、宿主細胞表面のシアル酸残基を切り離す役割をする。
タミフル(オセルタミビル)は、NAの役割である「切る」ことを阻害する薬。
タミフルに含まれるオセルタミビルリン酸塩という物質がインフルエンザウィルスのNA(ノイラミニダーゼ)と結合した結果、「切る」機能が阻害され、結果として、インフルエンザウィルスは宿主細胞から離れられなくなり、拡散・増殖できない。
------------------------------
アビガンは:
引用:Wikipedia ファビピラビル
ファビピラビル (Favipiravir) は、富山大学医学部教授の白木公康と富士フイルムホールディングス傘下の富山化学工業(現:富士フイルム富山化学)が共同研究で開発したRNA依存性RNAポリメラーゼ阻害剤である。開発コードのT-705、あるいは商品名であるアビガン錠 (Avigan Tablet) の名前でも呼ばれる。
Favipiravirの作用機序
RNA合成酵素にプリン(アデニン、グアニン)類似体として、RNA鎖に取り込まれるが、取り込まれた部位でRNA合成を停止させるChain terminator(伸長阻止薬)として、ウイルスRNA合成を阻止する。
アビガン
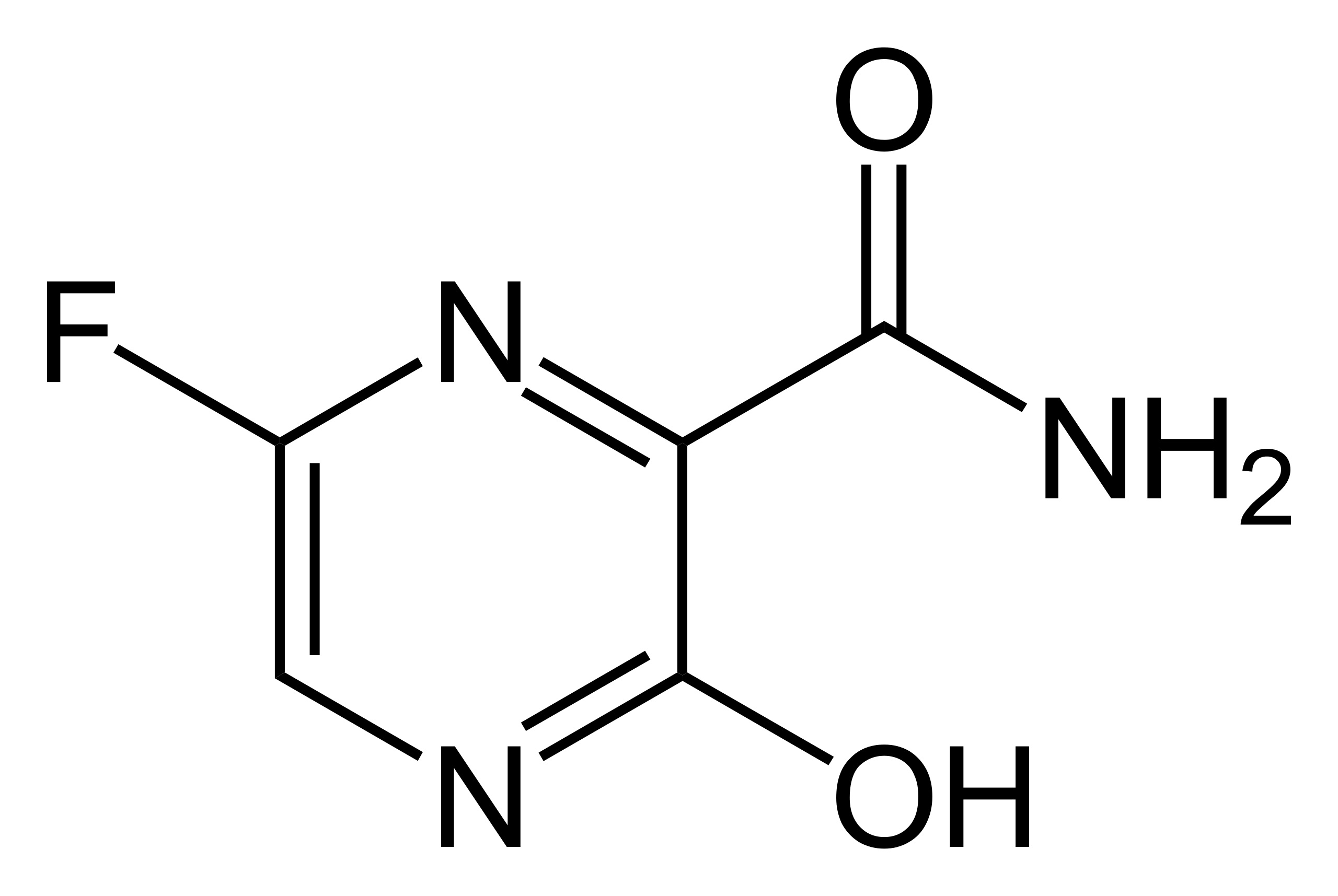
アデニン
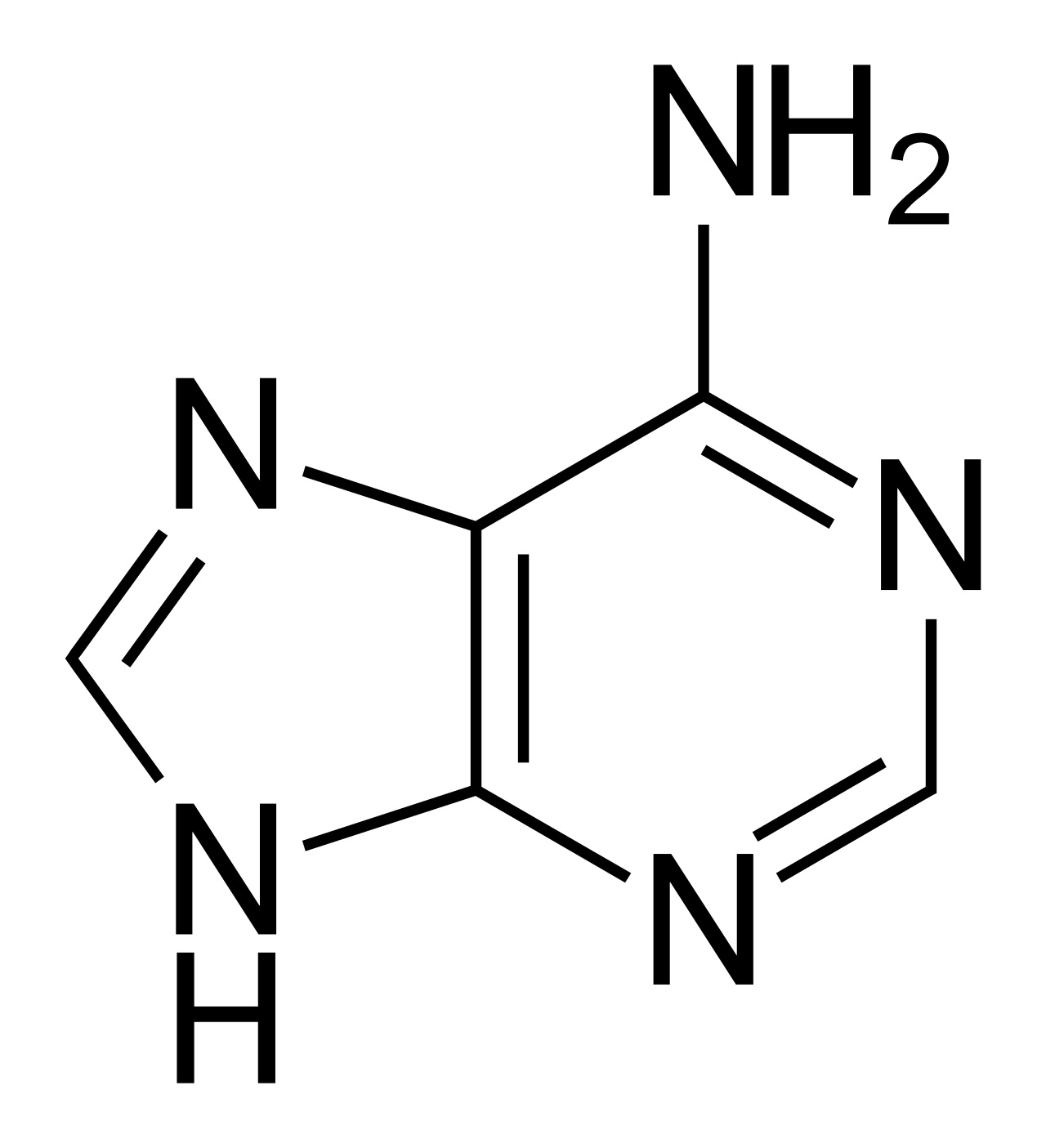
グアニン
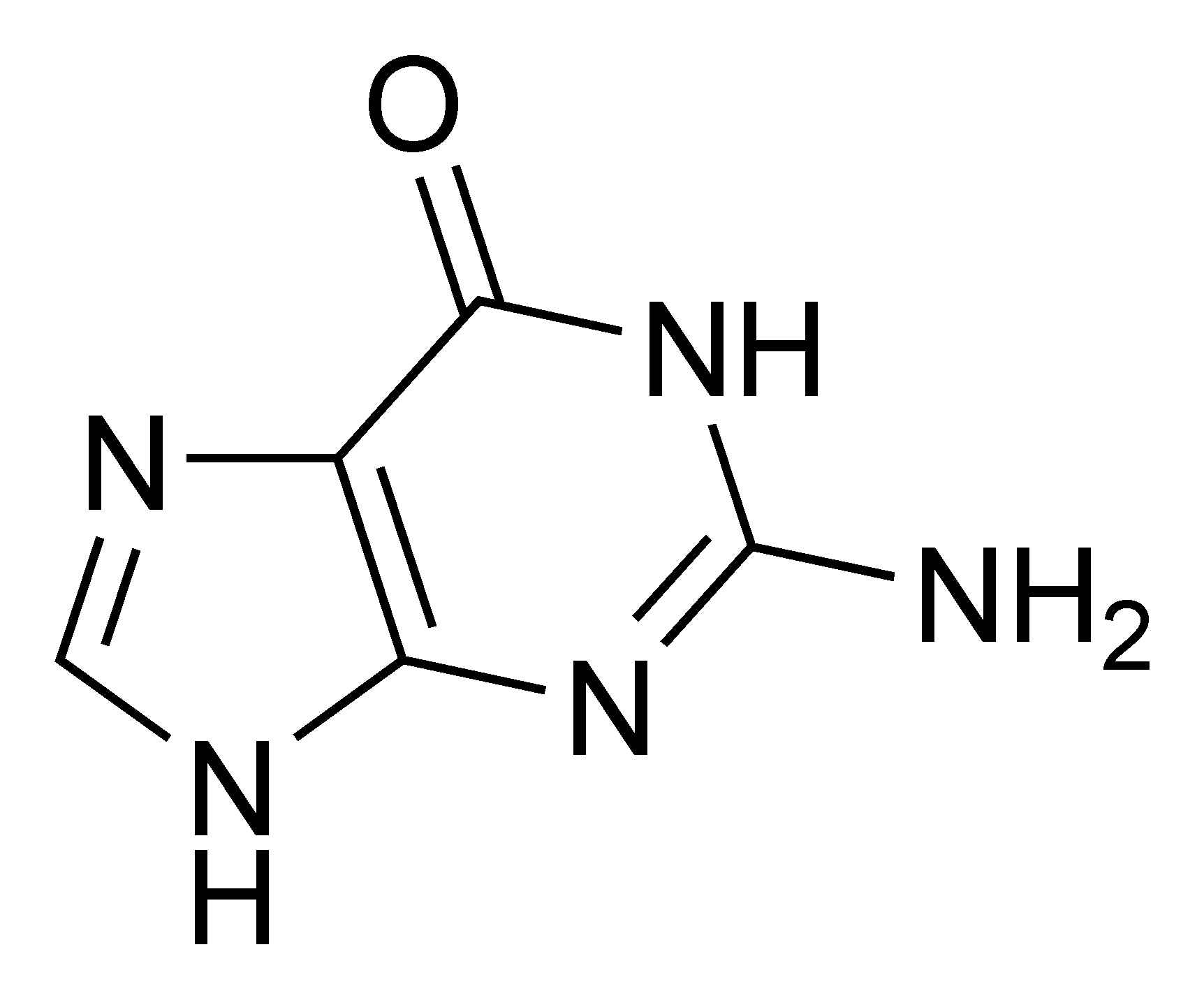
本来は抗インフルエンザウイルス薬で、ウイルスの細胞内での遺伝子複製を防ぐことで増殖を防ぐ仕組み。
そのためインフルエンザウイルスの種類を問わず抗ウイルス作用が期待できる。
またインフルエンザウイルスのみならず、エボラ出血熱ウイルス(後述)やノロウイルスなどへの適用性に関する試験・研究も行われており、ケンブリッジ大学教授のイアン・グッドフェローらの研究チームは2014年10月21日、マウスを使った実験でノロウイルスの減少・消失を確認したとの発表を行った。
さらにウエストナイル熱ウイルス、黄熱ウイルスなどのRNAウイルスにも効果があると考えられており、同研究チームは「治療だけでなく感染予防にも効果的である可能性がある」とコメントしている。
-----------------------------
タミフルやアビガンのほか、リボソームに付着するウイルスのRNAに着目した薬が開発されるのだろう。
-----------------------------
2020.2.23
目次へ
生物が外敵から身を守る仕組みは完璧で、ヒトもヒトデの幼虫も同じに見える。
引用:細胞紳士録 藤田恒夫、牛木辰男著 岩波新書
マクロファージは1883年、メチニコフによって発見された。透明なヒトデの幼虫の体内にアメーバのように動き回る細胞があり、棘を幼虫にさすと、翌朝、この細胞が棘のまわりをびっしり囲んでいた。哺乳動物まで調べると、炎症が起きると小型の細胞が多数現れて細菌を食べだし、ついで大型の細胞がでてきた。前者は白血球(好中球)で、後者をマクロファージと呼んだ。
ヒトには外敵の侵入を感知する細胞がある。これはヒトの皮膚にあるランゲルハンス細胞で、1868年、ランゲルハンスによって発見され、100年後、その役割が明らかにされた。
抗原となるような物質が表皮の表層から深部に侵入してくると、ランゲルハンス細胞の突起がこれを捕えて取り込み、表皮を抜け出して真皮のリンパ管に入り、リンパ節に流れ着いて、T細胞に抗原提示する。
思うに、免疫反応の起源は生物進化の初期にあり、多くの細胞は役割分担して共生しているようだ。
細菌やウイルスが細胞の中に侵入するのは、進化の過程に潜り込もうとしているのではないかと感じる。
2020.3.1
目次へ
コロナウイルスを調べてみる。
引用:http://jsv.umin.jp/microbiology/main_015.htm
15-2-1:プラス鎖RNAウイルス
15-2-1-1:RNAから1つの蛋白前駆体が出来るウイルス
RNAから巨大な前駆蛋白が出来て、それがウイルスのコードするプロテアーゼにより切断(processing)され、成熟蛋白となる。エンベロープを持たないpicornavirus、エンベロープを持つflavivirusが代表である。
ピコルナウイルス(picornavirus)
小児まひの原因であるポリオウイルスがその代表である。エンテロウイルスの仲間であり、腸管感染を起こす。10日位の潜伏期を置いて発熱倦怠感などの不特定症状の後急性弛緩性まひが現れる。ウイルスの便中への排出は発病から2週間迄が最大である。弛緩性麻痺はギランバレ症候群など他の原因でも起こるので、適切な便検体をとりウイルス分離をして診断しなければならない。ヒトにしか感染しない為、天然痘同様ワクチンによる根絶が可能である。WHOはこれを強く推進し、わが国は西太平洋地区での活動に大きく貢献した。1988年には世界で3.5万人の患者が出ていたのを1994年には7千人にまで減らす事に成功している。ECHOウイルス、コクサッキーウイルス、2000-2001年に英国を中心に家畜に大被害を与えた foot and mouth disease virus もこの仲間である。ポリオ同様神経症状を来す株もある。
遺伝子構造を見ると、5'側に構造遺伝子、3'側にRNAポリメラーゼやproteaseなどの非構造遺伝子がある。5'非コード領域は細胞のmRNAに比較し異常に長く600-1200塩基もある。
翻訳は、5'端より内側に入った処にあるIRES(internal ribosomal entrysite)から開始する。RNAの5'端にはCapの代わりにVPgというウイルスのコードする蛋白がついている。(2重鎖DNAウイルスのB型肝炎ウイルスやアデノウイルスの末端にも蛋白が結合している。B型肝炎ウイルスの場合には蛋白はDNAの環状化に与る。)
前駆体蛋白は翻訳されながらウイルスproteaseで切られ成熟蛋白となる。しかし、ただ切られたのでは、全部の蛋白は同じモル数になってしまう。実際は構造蛋白などはより大量の分子を必要とする。ポリメラーゼ蛋白などは不安定性で、蛋白の安定性がこの調節に関わると考えられる。
picoravirusではないがこのウイルスに似たウイルスとしては、A型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルスなどがある。腸管感染をするので胃を通過しなければならず、この為いずれも酸に強い。風邪をおこすrhinovirusはpicoravirusに入るが、気道の感染であることから酸に強い性質を持たない。
フラビウイルス(flavivirus)
構造遺伝子が5'側にある点では、picoravirus に良く似ているが、ウイルス粒子はエンベロープを被っている。黄熱、デング熱、日本脳炎、1999年頃から米国で流行し問題となっているウエストナイルウイルスなどがある。この仲間にヒトのC型肝炎ウイルスがいる。flavivirus の5'非コード領域は100塩基くらいだが、HCVの方は350もあり、IRES を利用し本翻訳が開始する点は寧ろ picoravirus に似ている。日本のHCV感染者は人口の1ー2%で、慢性肝炎を経て、肝臓がんに至る。インターフェロンが一部の患者に有効で、有効性は感染しているウイルスの遺伝子型で可成り左右され
15-2-1-2:相補RNA(-RNA)を鋳型とし subgenomicなmRNAが転写されるウイルス群。
+の極性を持つ1本鎖RNAウイルスで、エンベロープを被っているトガウイルス、コロナウイルス、エンベロープを持たない植物ウイルスのタバコモザイクウイルスがこの群にはいる。
トガウイルス
Togavirus科には、Semliki forest virus、西部馬脳炎ウイルス(以上 alphavirus属で昆虫が媒介する)、風疹、などがある。風疹はヒトで流産や奇形の原因となる。生ワクチンが予防に有効である。これ等の alphavirusは12kb位のゲノムサイズである。
picornavirusなどとは異なり、非構造遺伝子が5'側に、構造遺伝子が3'側にある。ゲノムサイズのRNAからはポリメラーゼなどの非構造蛋白が読まれ、右半分の subgenomic RNA からは構造蛋白が読まれる。いずれも前駆体蛋白をコードしてプロテアーゼで切断され成熟蛋白となる。
これにやや似ているのが、coronavirusである。ヒトの「かぜ」にもこの仲間のウイルスによるものがある。ゲノムサイズのRNAに加え、subgenomic RNAが出来る。subgenomicRNAそれぞれは単一の蛋白をコードしそれ以上の processingは起こらない。各 subgenomic RNA は5'端を共有する。遺伝子の配列は非構造遺伝子、構造遺伝子入り交じって位置する。
中国広東省にはじまり、2003年前半世界に広がった重症急性呼吸器症候群(SARS)の原因ウイルス、SARSコロナウイルスもこの仲間である。
植物ウイルスであるたばこモザイクウイルスはゲノム構造からは、この仲間に入る。しかし、エンベロープは持たない。 subgenomic RNA から全部で5つの蛋白を作る。
---------------------------
細胞の中に入り、核の中や、細胞質で宿主細胞の機能を利用して増殖する。
すごい世界だ。
---------------------------
2020.3.3
目次へ
コロナウイルスが細胞に侵入する様子を知りたい。
引用:http://jsv.umin.jp/journal/v56-2pdf/virus56-2_165-172.pdf
コロナウイルスにはヒト,家畜,実験動物など様々な動物に感染するウイルスが知られている.
その中で,マウス肝炎ウイルス(MHV)はマウスに急性致死性肝炎,脱随性脳脊髄炎などを引き起こし,ヒトの疾患モデルとして研究が進んでいる.
一方,SARS コロナウイルス(SARS-CoV)は重症急性呼吸器症候群(SARS)の病原体であり,2003 年に発見された新しいウイルスである.
コロナウイルス粒子は形態学的に特徴のある“王冠(コロナ)様”突起(スパイク)を持つ1).スパイクは最外部が球状で,その下の棒状部位でエンベロープに埋め込まれている.
スパイクはウイルスの受容体結合及び細胞内侵入を司り,一本のスパイクは3 分子のS 蛋白から構成されている.
S 蛋白は分子量約180kDa のクラスI のfusion 蛋白である.
MHV S 蛋白は,分子中程の塩基性アミノ酸部位が細胞の蛋白分解酵素により解裂され,N 末端S1 とC 末端S2 の2 サブユニットになる.
S1 とS2 は共有結合で結ばれている訳ではなく,その結合は弱い.スパイク最外部
の球状部分はS1 が,その下の棒状部分はS2 が構成すると考えられている.
S1 のN 末端330 個からなる領域(S1N330)は受容体結合部位であり,特にMHV 株間で保
存されている2 か所が受容体結合に重要である.
MHV は受容体CEACAM1 に結合後,細胞表面から細胞内へと侵入する.
一方,SARS-CoV はACE2 に結合し,endosome に輸送され,酸性環境下で活性のあるプロテアーゼ, cathepsinL によりS 蛋白の解裂及び細胞融合活性が誘導され,endosome から細胞質内へ侵入する.
SARSCoVは細胞表面の受容体ACE2 に結合し,endosome へと輸送され,endosome 内の酸性環境下で活性を示すプロテアーゼによりS 蛋白の膜融合能が活性化され,エンベロープとendosome 膜融合が起き,ゲノムが細胞内に侵入するという細胞侵入機構が提唱された.
更に,SARS-CoV のS 蛋白活性化には細胞内のシステインプロテアーゼが関与することを突き止め,cathepsin L が受容体結合後のS 蛋白の膜融合能を活性化することを明らかにし
た.
最近,Weiss 等は培養細胞での感染で合胞性巨細胞を誘導しないMHV-2 株もSARS-CoV と同様の機構により細胞内侵入を果たすことを報告しているが,この場合
cathepsin L とcathepsin B がS 蛋白の活性化に必要である.
MHV とSARS-CoV では細胞内侵入経路及びS 蛋白の融合能活性化機構は異なるが,細胞膜とエンベロープの融合は同様のメカにズムによって起こると思われる.
これはコロナウイルス特有の細胞内侵入機構というよりクラス1 のエンベロープ蛋白を持つウイルスに共通している.
MHV S1N330 が細胞表面のCEACAM1-N ドメインに結合すると,S1 がS2 から離脱する.露出したS2 のFP が標的細胞の細胞膜に挿入され,S2 蛋白の構造変化が誘導される.
この変化はS2 分子がヘアピン構造を取ることにより,3 量体のHR1 の外側に3 本のHR2 が覆い被さるように位置する構造(6 helix bundles)になることである.
6 helix bundles 形成により,エンベロープと標的細胞膜が隣接し,2 種類の膜間で融合が起こり,最終的にウイルスゲノムが細胞質内へと侵入する.
この過程の中で6 helix bundles 形成が極めて重要である.MHV 及びSARS-CoV でもHR1,HR2 に相当するペプチドを用いて,両者がantipararell様式で結合し電子顕微鏡下では棒状構造として観察され,また,HIV 感染で報告されているように,HR2 ペプチドでウイルスの細胞内侵入が押さえられることなどが明らかにされている.
2020.3.4
目次へ
UTFコードにしているので、漢字の変換誤りになる場合がある。例えば、”ふかのう”が不可能になり、”なまえ”が名前に、閉じ鍵かっこが」、”しょくぶつ”が植物になる。
SARSCoVは細胞表面の受容体ACE2 に結合し,endosome へと輸送され,endosome 内の酸性環境下で活性を示すプロテアーゼによりS 蛋白の膜融合能が活性化され,エンベロープとendosome 膜融合が起き,ゲノムが細胞内に侵入する、というのがあまりにも不思議。
SARS-CoV のS 蛋白活性化には細胞内のシステインプロテアーゼが関与することを突き止め,cathepsin L が受容体結合後のS 蛋白の膜融合能を活性化することを明らかにした.
-----------------------------
細胞内のシステインプロテアーゼは、本来、なんのために働いているのだろう。
-----------------------------
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj1944/105/1/105_1_1/_pdf/-char/ja
細胞内プロテアーゼは一般にタンパク質のペプチド結合を不可逆的に分解する酵素であり,本来の消化酵素としてのいわゆる"分解作用"と,生体内の種々の機能を担う生理活性物質を生みだすための"モジュレーター作用"を有している.
このため,細胞内プロテアーゼは厳密な発現調節系や活性調節系の制御を受けながら生理機能を果たしており,いったんこれらの制御系に不調が生じると酵素活性の異常な増大や低下が起こり,細胞構成成分の機能に重大な影響を与えると考えられる.
また,細胞内プロテアーゼがエンドヌクレアーゼと共にアポトーシスにおけるクロマチンDNAの断片化に関与する可能性も考えられる.
引用:Wikipedia プロテアーゼ
プロテアーゼ(Protease、EC 3.4群)とはペプチド結合加水分解酵素の総称で、プロテイナーゼ(proteinase)とも呼ばれる。
広義のペプチダーゼ(Peptidase)のこと。タンパク質やポリペプチドの加水分解酵素で、それらを加水分解して異化する。
収斂進化により、全く異なる触媒機能を持つプロテアーゼが似たような働きを持つ。
プロテアーゼは動物、植物、バクテリア、古細菌、ウイルスなどにある。
ヒトでは小腸上皮細胞から分泌する。
引用:https://medley.life/medicines/article/5677569c5595b353107966f1/
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)は、免疫の中心的な役割を担うリンパ球(主にCD4というタンパク質を発現しているリンパ球)やマクロファージに感染し、免疫系を徐々に破壊することでHIV感染症を引き起こす。
HIV感染症の治療は一般的に、抗HIV薬を複数の種類(複数の成分)併用した強力な多剤併用療法(ART)を行う。
(なお、ARTは、HIVを抑制する効果がより強力な「キードラッグ」と呼ばれる薬とキードラッグを補いウイルス抑制効果を高める「バックボーン」と呼ばれる薬を組み合わせて実施することが一般的だが、近年では「キードラッグ」を2剤(2成分)組み合わせて行う方法なども治療の選択肢となっている)。
抗HIV薬はその作用機序により、NRTI(核酸系逆転写酵素阻害薬)、NNRTI(非核酸系逆転転写酵素阻害薬)、PI(プロテアーゼ阻害薬)、INSTI(インテグラーゼ阻害薬)などに分かれる。
HIVは標的細胞に吸着し細胞内に侵入した後、いくつかの工程を経て自身の遺伝子を宿主の染色体に組み込み感染を成立させる。その後、ウイルス粒子に必要な複合タンパク質が合成されるが、この複合タンパク質が機能するタンパク質になるにはプロテアーゼという酵素によって切断される必要がある。
本剤はプロテアーゼを阻害し、機能タンパク質の産生を抑える作用をあらわす。これによりウイルス粒子の組み立てが阻害され感染性ウイルス粒子を産生させないため、感染拡大が阻止される。
----------------------------------
HIVの場合は、細胞内に侵入してから、プロテアーゼが作用する。
細胞に侵入する際に作用するプロテアーゼではない。
----------------------------------
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsv/61/1/61_1_109/_pdf/-char/ja
重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV)のエンベロープ糖蛋白(S蛋白)は,宿主プロテアーゼ(トリプシン,エラスターゼ,カテプシン,TMPRSS2)に切られて活性化される.
インフルエンザウイルス等多くのエンベロープウイルスもプロテアーゼを利用するが,プロテアーゼの作用する様式がSARS-CoVとは異なる。
インフルエンザウイルスの場合は細胞でウイルスが作られるときエンベロープ糖蛋白(HA)がプロテアーゼに切られ「膜融合誘導可能な形」になるが,SARS-CoVの場合は「細胞侵入の瞬間」にS蛋白が切られて膜融合開始の引き金が引かれる.
我々はSARS-CoVによく似たS蛋白を持つマウス肝炎ウイルス(MHV-2)を用いて,S蛋白は二段階の構造変化をすることを検出した.まずS蛋白はレセプターに結合すると安定した三量体を形成し,Fusion Peptideを露出させ,細胞膜に突き刺さる.続いてプロテアーゼにより開裂を受け,内部のヘリックス構造を引きつけることによりウイルスと細胞の膜を引き寄せ,融合させると考えられる.このメカニズムはウイルスにとって標的細胞で確実に膜融合を誘導できる効率の良い仕組みである.
コロナウイルスは,エンベロープをもつ直径60~220nmの楕円形あるいは多形成のウイルスである.
ウイルスゲノムはポジティブ一本鎖RNAで,27~32kbのサイズであり,RNAウイルスの中では最大サイズである.
ヒトに感染するコロナウイルスHuman coronavirus(HCoV)としては1960年代にHCoV-229EとHCoV-OC43が風邪の原因ウイルスとして分離された.
エンベロープウイルスが細胞に侵入する時,エンベロープの脂質二重膜と細胞の脂質二重膜が融合する必要がある.
ウイルス表面のエンベロープ糖蛋白がこの膜融合反応を仲介するが,多くのウイルスのエンベロープ糖蛋白は宿主のプロテアーゼに切られて「膜融合誘導可能な形」になる.
プロテアーゼがウイルスに作用する様式は大きく二つに分けられる.
① HIVやインフルエンザ等の多くのウイルスは,エンベロープ糖蛋白が「ウイルスが作られるとき」あるいは「ウイルスが標的組織に到達したとき」にプロテアーゼに切られて開裂し,「膜融合誘導可能な形」になると考えられている.
② SARS-CoVのS蛋白を活性化する宿主プロテアーゼは,トリプシン,エラスターゼ,カテプシン,TMPRSS2であり, 「細胞侵入の瞬間」に働くことが報告されている.
コロナウイルス,MHV-JHM株,MHV-A59株はHIVと同様の「ウイルスが作られるとき」に切られるS蛋白をもっている.
約180kDaのS蛋白は一本の蛋白として合成され,細胞内のFurinにより約90kDaのS1及びS2サブユニットに開裂される.
一方,SARS-CoV,229E及びMHV-2株のS蛋白はFurin切断サイトが欠損しているため,180kDaの一本の蛋白として合成された後,開裂を受けず180kDaのままウイルス粒子上に乗っている.
この未開裂S蛋白は「膜融合誘導可能な形」になっておらず,感染時,レセプター結合の後に宿主プロテアーゼによる開裂を受けて活性化すると考えられている.
トリプシンは,SARS-CoVとMHV-2のS蛋白に対して,上記の細胞-細胞融合,ウイルス-細胞融合のどちらの方法でも,強く膜融合を誘導するので,正にS蛋白の活性化因子であるといえる.
またエラスターゼもトリプシンと同様に膜融合を誘導できることが確認されている.
エラスターゼは炎症組織で好中球が大量に放出するプロテアーゼであり,肺炎が重症化する時のウイルス増殖に関与する可能性が予想される.
現在までに報告されている膜貫通型セリンプロテアーゼ(TMPRSS2)を利用するウイルスは,インフルエンザ,メタニューモ,SARS,ヒトコロナウイルスNL63である.
引用:http://www.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/ajrs/005040172j.pdf
インフルエンザウイルスのエンベロープに存在するヘマグルチニンは,気道上皮細胞に発現する膜貫通結合型セリンプロテアーゼの作用で開裂を受けて活性化され,ウイルスRNAの細胞質内進入を促進し,ウイルス増殖に関与する.
ウイルスの増殖と炎症性サイトカインの放出は発熱などの症状や重症化,慢性閉塞性肺疾患や気管支喘息の増悪に関与する.
インフルエンザウイルスの気道上皮細胞への感染および増殖は接着,進入,脱殻,複製,再集合,発芽の経路を経て行われ,増殖したウイルスは細胞外に放出される.
この過程が繰り返されてウイルス増殖の連鎖が生じ,インフルエンザ感染症として発症する.インフルエンザウイルスはエンベロープ表面に突出する糖蛋白ヘマグルチニン(hemagglutinin:HA)が受容体に結合することにより気道上皮細胞に接着し,小胞に取り込まれて細胞内に進入する.
さらに,開裂・活性化したHA を持つウイルスだけがエンベロープを細胞膜に融合させて細
胞質内にRNA を放出し(脱殻),ウイルスの増殖に進むことができる.
HA を介して受容体に接着したインフルエンザウイルスは,感染細胞の細胞膜のくぼみから形成される小胞に取り込まれ,この小胞がエンドサイトーシス(endocytosis)によって細胞内に輸送され,さらに小胞はエンドソームと膜融合を起こして,ウイルスがエンドソームに
取り込まれる.
エンドソーム内が酸性になることで(この時点で酸性エンドソームと呼ばれる)ウイルスのエンベロープと感染細胞の細胞膜(=酸性エンドソームを構成する膜)が融合し,ウイルスRNA
が細胞質内に放出され(脱殻),以降のウイルス複製につながる.
-------------------------------
セリンプロテアーゼの本来の役割とは?
-------------------------------
引用:Wikipedia セリンプロテアーゼ
ペプチド結合を加水分解する酵素で、様々な種類のものが、栄養吸収、タンパク質の廃棄とリサイクル、生体防御、活性の調節、などの幅広い分野で働いている。
セリンプロテアーゼ (Serine Protease) とは触媒残基として求核攻撃を行うセリン残基をもつプロテアーゼ(タンパク質分解酵素)のこと。EC[3.4.21.-]。多くは触媒残基としてセリン (Serine, Ser)、ヒスチジン (Histidine, His)、アスパラギン酸 (Aspartic acid, Asp) の3残基を有しているが、ヒスチジンおよびアスパラギン酸残基は他のアミノ酸残基で代用されているものもまれにある。
これら3残基はアミノ酸配列上は隣接していないが、空間的にはSer-His-Asp酸の順に水素結合で結ばれるように配置されており、セリン残基側鎖のγ位の酸素原子の求核性が高められている。
このγ位の酸素原子が基質ペプチドの主鎖のカルボニル炭素に求核攻撃することから加水分解反応が始まる。
------------------
ふーむ、本来、細胞の生存にとって必須な酵素であるらしい。
細胞膜上にあって細胞外を監視し、栄養となる分子を取り込むための分解のほか、有害なタンパク質の分解の役割を担っているようだ。
------------------
食品加工・生産、皮革加工、学術研究など様々な方面で利用されている。
特にスブチリシン様のセリンプロテアーゼのうちアルカリ性条件で高い活性を示すものはタンパク質汚れを分解するために洗剤に配合されており、日本国内でも年間数千トン生産されている。
-------------------------
ウイルスは細胞のこの酵素を利用して細胞に侵入しようとしている。
細胞は、ウイルスのタンパク質を栄養として取り込もうとするが、タンパク質を分解したら、その中に格納されていたRNAやDNAが露出するという想定外の危険性があった。
-------------------------
2020.3.5
目次へ
もう一度、IgAのことを調べてみたい。
引用:https://katosei.jsbba.or.jp/view_html.php?aid=850
腸管粘膜組織表面は,腸内常在細菌はもとより,病原性微生物やアレルゲンなどの抗原の生体内への侵入経路の一つであるが,これらの抗原に対する認識と応答を担っているのが,腸管免疫系である.
腸内細菌叢と宿主は共生関係を築いており,この共生関係が崩れると,腸管免疫系が過剰に刺激されることにより炎症性腸疾患や大腸がん,アレルギー,喘息,肥満などといった多くの疾患が誘発される.
腸管免疫系は病原体などを排除するだけではなく,腸内環境の維持に重要な役割を担っていると言える.
その腸管免疫系の中で主要な要素の一つであるIgA抗体がこの2つの機能を担っている.
腸管粘膜固有層から腸管腔に分泌されたIgA抗体は,腸管腔内で病原菌やその毒素と結合し中和したり,あるいは,粘膜固有層内に侵入した病原体と結合することで体外に排出する.
そのIgA抗体の機能で特徴的なことは,全身免疫系の抗体反応とは異なり,敵を殺すための炎症反応を起こさずに静かに敵を排除して防御を行うことである.
さらに,腸管由来のIgA抗体は病原菌だけではなく腸内常在細菌も認識してそれらと結合し,腸内常在細菌と宿主との共生関係を維持している.
このように,IgA抗体は,単に腸管腔内に分泌されるだけではなく,腸管粘膜上皮細胞上のムチン層内でも維持され,腸内常在細菌の腸管粘膜上皮細胞への接触や侵入を防いで,腸管免疫系が過剰に刺激されないように調節しているとも考えられている.
さまざまな抗原から生体を守るために,私たちの免疫細胞の抗体遺伝子では体細胞突然変異とクラススイッチが起きている.
体細胞突然変異は,抗体遺伝子の抗原結合部位に変異を入れることにより結合部位の微調整を行い,抗原に対して高親和性,つまり,より強く結合する抗体を産生するための機構である.
クラススイッチは,抗体の抗原認識能力は変化させずに抗体分子の定常領域の構造を変化させ,IgM抗体からIgG抗体,IgA抗体,IgE抗体に変化させる機構で,抗体の攻撃力を変化させる.
これら2つの機構が組み合わさることにより,多様な抗原結合部位を有する多くの種類の抗体が産生され,私たちの体は病原菌などから守られている.
この体細胞突然変異とクラススイッチが起こるには,共にActivation-induced cytidine deaminase(AID)タンパク質が必要であり,AIDタンパク質のN末端側が体細胞突然変異に関与し,C末端側がクラススイッチに関与していることが知られている.
野生型マウスの小腸粘膜固有層の腸管IgA産生細胞から多くのハイブリドーマを作製し,そのなかで,16種類のハイブリドーマIgA抗体を選び,培養可能な腸内常在細菌14種類に対しての結合性を調べた.その結果,多くのモノクローナルIgA抗体が多種類の細菌に対して結合することがわかった.
それらのなかで,高産生される抗体の4クローンを選び,Escherichia coliとLactobacillus caseiに対する結合力を比較した結果,W27 IgAと命名した抗体はほかのIgA抗体と比較して,E. coliに対して,最も強い結合力を示した.
W27 IgA抗体は腸内細菌をランダムに認識しているのではなく,善玉菌と悪玉菌を識別することができる抗体であると考えた.
W27 IgA抗体は腸内細菌を識別したが,腸内細菌のどのような分子を認識して識別しているかは明らかでなかった.そこで私たちは,各種腸内細菌のタンパク質を抽出し,W27 IgA抗体によるウエスタンブロットを行い,ターゲット分子を探索した.
その結果,W27 IgA抗体は,DH5α株(E. coli K12株)と私たちが野生型マウスの糞便から単離したE. coliとPseudomonas fulvaの約50?kDaの分子を特異的に認識した.
2次元電気泳動によりDH5α株のターゲット分子を単離し質量分析を行った結果,この分子はE.coliのSerine hydroxylmethyltransferase(SHMT)であることがわかった.
SHMTのエピトープ部位にEEHI配列をもつ細菌種を調べたところ,Haemophilus influenzaeやKlebsiella pneumoniae, Salmonella paratyphi Aなどの病原菌が多く,Proteobacteria門に属している細菌であることがわかった.
多くの病原菌がEEHI配列をもっていることから,宿主が病原菌を排除するために,SHMTのEEHI配列をエピトープとして認識するW27 IgA抗体が体内で選択されてきたのではないかと考えられる.
SHMTは葉酸やアミノ酸代謝に重要であり,SHMTを欠損させたE. coli株は,増殖が遅くなることが報告されている.
W27 IgA抗体は非特異的に細菌に結合するだけではなく,細菌のSHMTを特異的に認識し結合することが増殖抑制効果を起こすためには重要であると考えられる.
W27 IgA抗体はE. coliなどには強く結合するが,善玉菌として知られているL. caseiやB. bifidumに対しては強い反応を示さなかった.
これは宿主がIgA抗体を使って,単に侵入者として,すべての腸内細菌を排除するのではなく,自己を利する細菌を能動的に選択している可能性が考えられる.
--------------------------------
「さまざまな抗原から生体を守るために,私たちの免疫細胞の抗体遺伝子では体細胞突然変異とクラススイッチが起きている.
体細胞突然変異は,抗体遺伝子の抗原結合部位に変異を入れることにより結合部位の微調整を行い,抗原に対して高親和性,つまり,より強く結合する抗体を産生するための機構である.」
IgA抗体は、細菌やウイルスと遭遇すると、エピトープの特別の部位に吸着する、ということ、体細胞突然変異がそれを可能にしている。
--------------------------------
2020.3.10
目次へ
IgAと唾液の関係。
引用:https://kenko100.jp/articles/191125004977/
唾液は「機能性の高い物質の宝庫」
唾液を分泌する唾液腺でつくられた10種類以上の成長因子や抗菌物質が含まれている。
成長因子とは、細胞の活性化や修復を促す蛋白質の総称で、傷を治すのに活躍するものや美白効果をもたらすもの、肝臓を保護するものなどがある。
唾液中の有効成分による効果は口の中だけではない。唾液腺から分泌される物質は全身をめぐっている。
また、唾液は血液からつくられるため、多くの血液成分が含まれ、それらを調べることで全身の健康状態がかなり把握できる。
唾液には多くの有効物質が含まれるが、中でも重要なのが免疫グロブリンA(IgA)である。
IgAは、細菌やウイルスと結合してそれら病原体の働きを中和してくれる蛋白質「抗体」の1つで、唾液、母乳、涙、鼻汁に含まれる。
口は病原体の入り口。つまり、唾液中のIgAは病原体に対する最初の"バリア"となり、われわれを守っている。
またIgAは、虫歯の原因となるミュータンス菌や歯周病菌もシャットアウトすることが分かっている。
この唾液が持つ「唾液力」が弱まると、かぜやインフルエンザなどにかかりやすくなり、逆に高めることができればかかりにくくなる。
唾液は口腔内(口の中)を洗い流して清潔な状態に保つ自浄作用を担っているため、ある程度の「量」が必要となる。
一方、「質」的にはIgAをはじめとする抗菌物質が多く含まれるほど、菌やウイルスなどを防ぐ力が強まると考えられる。
唾液量を減らしてしまう最も大きな要因は「脱水」である。実は、夏よりもかぜやインフルエンザが流行する冬の方が脱水状態になりやすい。
空気が乾燥し、体の水分を失っている自覚がなく水分補給が不足しがちになる。
唾液量が減少すると口腔内が乾燥し、IgAも十分な働きができなくなる。
冬こそこまめな水分摂取が大事だ。ただし、カフェイン入り飲料やアルコールは利尿作用があるため要注意。
一方、唾液中のIgA量は過度の運動やストレスにより減少する。
IgAを増やす食品としては、乳酸菌を含む食品(ヨーグルトなど)やオリゴ糖、食物繊維などが挙げられる。いずれも腸内環境を整える働きを持ち、結果的に唾液中のIgAを増加させる。
また、食べ方を工夫することでも唾液力はアップする。食べ物をかむ(咀嚼)運動は唾液量とIgA量をともに増加させるため、よくかんで食べるよう心がける。食材を少し大き目に切ったり、歯ごたえのあるものを加えたりするのも効果的だ。
食べ方を工夫することでも唾液力はアップする。食べ物をかむ(咀嚼)運動は唾液量とIgA量をともに増加させるため、よくかんで食べるよう心がける。食材を少し大き目に切ったり、歯ごたえのあるものを加えたりするのも効果的だという。
--------------------------
水分を取ることと、よく噛むこと。気をつけよう。
--------------------------
薬の状況を見てみよう。
引用:Wikipedia レムデシベル
レムデシビル(remdesivir、開発コードGS-5734、レムデジビル)は、新規ヌクレオチドアナログのプロドラッグで、抗ウイルス薬。
ギリアド・サイエンシズが開発し、エボラ出血熱及びマールブルグウイルス感染症の治療薬として、後に、一本鎖RNAウイルス(RSウイルス、フニンウイルス、ラッサ熱ウイルス、ニパウイルス、ヘンドラウイルス、コロナウイルス(MERSおよびSARSウイルスを含む))に対して抗ウイルス活性を示すことが見出された。
追跡調査により、2019-nCoVを含む複数のコロナウイルスおよびニパウイルスとヘンドラウイルス感染症での抗ウイルス活性が明らかとなった。
GS-441524のモノホスホルアミデートプロドラッグ (monophosphoramidate prodrug)は2020年2月現在、米国で開発中の新薬であり、承認薬として日本で使うことができるのは「緊急性を考えて特例扱いだとしても、最短でも2020年内」とされている。
レムデシビルは代謝されてその活性型GS-441524になる。
GS-441524は、ウイルスRNAポリメラーゼを混乱させ、ウイルスエキソヌクレアーゼ (ExoN) googによる校正(新たに正しい塩基に正すこと)を回避するアデノシンヌクレオチドアナログであり、ウイルスRNA産生の減少を引き起こす。
RNA鎖を終わらせるか、突然変異を引き起こすかは不明。
部分耐性を引き起こすマウス肝炎ウイルスRNAレプリカーゼの変異は2018年に確認された。
これらの変異により、ウイルスの性質が低下し、薬剤が使用されていない場所では持続しない可能性が高いと研究者は考えている。
引用:Wikipedia ファビピラビル
ファビピラビル (英: Favipiravir、中: 法匹拉?、法匹拉韋) は、富山大学医学部教授の白木公康と富士フイルムホールディングス傘下の富山化学工業(現:富士フイルム富山化学)が共同研究で開発した核酸アナログでRNA依存性RNAポリメラーゼ阻害剤である。
開発コードのT-705、あるいは商品名であるアビガン錠 (Avigan Tablet) の名前でも呼ばれる。
ファビピラビルはRNA合成酵素にプリンヌクレオシド(アデノシンおよびグアノシン)と競合して取り込まれ、取り込まれた部位以降のRNA鎖の伸長を阻害する Chain terminator (伸長阻止薬)として作用する。
抗インフルエンザウイルス薬としては細胞内におけるウイルスRNAの複製を妨げることで増殖を防ぐ仕組みで、タミフルなどの既存薬とは作用機序が異なる。
そのためインフルエンザウイルスの種類を問わず抗ウイルス作用が期待できる (たとえばタミフルはB型インフルエンザウイルスに対しては効果が劣り、C型インフルエンザウイルスには効果がない)。
またインフルエンザウイルスのみならず、エボラ出血熱ウイルス(後述)やノロウイルスなどへの適用性に関する試験・研究も行われており、ケンブリッジ大学教授のイアン・グッドフェローらの研究チームは2014年10月21日、マウスを使った実験でノロウイルスの減少・消失を確認したとの発表を行った。
さらにウエストナイル熱ウイルス、黄熱ウイルスなどのRNAウイルスにも効果があると考えられており、同研究チームは「治療だけでなく感染予防にも効果的である可能性がある」とコメントしている。
2020年2月22日、厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症の治療の一環として、投与する考えを示した。
--------------------
ファビピラビルは、ウイルスRNAの複製中の伸長を妨げる。
レムデシベルは、ウイルスRNAの複製時の校正を妨げて、ウイルスの産生を減らす。
--------------------
2020.3.13
目次へ
気になる用語がある。プラスミド。調べてみよう。
引用:http://www.kenq.net/dic/78.html
プラスミド(plasmid)とは、大腸菌などの細菌や酵母の核外に存在し、細胞分裂によって娘細胞へ引き継がれるDNA分子の総称です。
一般的に環状の2本鎖構造をとり、染色体のDNAからは独立して複製を行います。
プラスミドには、薬剤に対する耐性を示す蛋白質の遺伝子を持つものやFプラスミドと呼ばれる細菌の接合を起こし他の細菌を形質転換させるものなど、さまざまな役割を持つものがあります。
細菌の中には複数のプラスミドを持つものがありますが、プラスミドには不和合性があり、複製機構が似ているものは同じ宿主の中では共存ができません。
細胞増殖など菌が生育していくための遺伝情報は、染色体のDNAにあります。
プラスミドは通常の生命活動に必要な遺伝子はもっていません。
しかし、細菌が特殊な環境(高温、乾燥、高塩分など)に置かれた場合や病原性を発揮する場合などに、プラスミドの遺伝子が独自に働きます。
特に大型プラスミド(Rプラスミド,Fプラスミド)の中には、接合に関わる遺伝情報をもつものがあります。
これらと共存することにより、本来接合できない小型プラスミドも他の固体に遺伝情報を伝えることができ、無性生殖をする種の多様性において、重要な役割を果たしています。
また、プラスミドには薬剤耐性や酵素などの様々な遺伝子がありますが、作用が確認されているものは少なく、大半のプラスミドがどのような働きをしているのかはわかっていません。このようなプラスミドをcryptic plasmidと呼びます。
自然界では青色のバラは存在しません。
サントリーは、青花のパンジーから花弁を青くする酵素を支配する遺伝子を取り出し、このアグロバクテリウム法を用いて遺伝子導入を行い、青いバラの開発に成功しました。
引用:https://iyakutsushinsha.com/2020/02/20/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9dna%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%AE%E4%BD%9C%E8%A3%BD%E3%81%AB%E7%9D%80%E6%89%8B-%E3%80%80%E5%A4%A7/
新型コロナウイルス感染が国内に広がりつつある中、大阪大学の研究グループが「新型コロナウイルスプラスミドDNAワクチン」の作製に着手した。
同ワクチンの作製を手掛けているのは、 森下竜一寄附講座教授(大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学)と中神啓徳寄附講座教授(大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学)のグループ。
森下教授らは、従来より鳥インフルエンザウイルスのパンデミック用に構築された技術(DNAプラスミド法)をベースに、新型コロナウイルスDNAワクチン開発に乗り出した。
ワクチン完成は2~3カ月後を目途としている。
プラスミドDNAワクチンの製造施設は、既に国内のバイオベンチャーなどが有しており、新型コロナワクチン完成後には実用化に向けて提携するバイオベンチャーを模索し、オールジャパンでの実用化を目指す。
中国湖北省の武漢市で発生した新型コロナウイルスは、中国を中心に拡大し感染防御ができないまま海外に流失し、わが国でも広がりつつあるのが現状だ。その致死率は2%程度(中国以外は約0.2%)で、潜伏期間はおおよそ10日前後とみられている。風邪の症状や37.5℃以上の発熱、倦怠感、呼吸困難の症状を特徴としており、感染力は高いが約8割が軽症であるものの、治療方法が確定されていないため社会不安が高まっている。感染者には対症療法を講じながら、また感染の疑いがある場合は、迅速な感染防御策をもっての感染拡大阻止が極めて重要である。
こうした中、森下氏らが開発に着手した新型コロナDNAワクチンは、新型コロナウイルスの遺伝子をプラスミドに挿入して作製するもの。
もともと鳥インフルエンザウイルスのパンデミック用に構築されたDNAプラスミド法が活用される。
DNAプラスミド法の特徴について森下氏は、
「抗原特異的な抗体産生及びTリンパ球活性を惹起」、
「様々な抗原に対し、容易に対応できる」、
「良好な安全性を確認済」を挙げる。
安全性の確認に関しては、「鳥インフルエンザ、エボラ、炭疽菌などの臨床試験が実施されており、良好な安全性が示されている」(森下氏)。
製造関連のメリットとしては、
「製造期間が短い(6~8週間)」、
「病原ウイルスを扱う必要がない」、
「抗原蛋白質の遺伝子配列さえ分かれば製造可能」、
「原薬(プラスミドDNA)生産には一般的な培養、精製施設で製造可」、
「製剤の安定性に優れる」、
「長期備蓄が可能」などがある。
DNAプラスミド法と従来の鶏卵法のワクチン製造法の比較では、製造期間は前者の6~8週間に対して、後者は6~8カ月要する。
新型コロナウイルスなど、異なるウイルスにすぐに対応できるのもDNAプラスミド法の特徴だ。
森下氏は、「米国では、鳥インフルエンザウイルスに対する水際対策としてDNAワクチンを活用して発生した変異型の強毒ウイルスに世界最速で対応した」と説明する。
その上で、「わが国でも、新型コロナウイルスプラスミドDNAワクチンによる迅速な対応策が重要になると考えている」と強調する。
-----------------------
プラスミドDNAワクチンは、実際、どういう成分なんだろう。
免疫源のタンパク質は体内の細胞で産生させるということのようだ。
-----------------------
引用:https://www.primate.or.jp/serialization/106%ef%bc%8e%e6%9c%9f%e5%be%85%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%be%e3%82%8bdna%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3/
これまでのワクチンは、不活化ワクチン、弱毒生ワクチン、サブユニットワクチン、ベクターワクチンといった形で、免疫源となるウイルスタンパク質を、接種して免疫を誘導してきた。
このような体外から投与する、ワクチンとは異なり、DNAワクチンは、ウイルスタンパク質遺伝子を投与することにより、免疫源のタンパク質は体内の細胞で産生させるという、まったく異なるタイプになる。
DNAワクチンは、ワクチン遺伝子を組み込んだプラスミドを、大腸菌などの細菌をタンク培養で増殖させて製造する。
プラスミドは細胞質内で自律的に増殖するDNAである。
プラスミドを遺伝子の運び屋としたのが、プラスミドベクターで、遺伝子治療で広く用いられている。
プラスミドベクターでは、GMP(医薬品の適性製造基準)にもとづく製造方式や、ヒトでの安全性を確認するための条件が確立されている。
DNAワクチンは、プラスミドベクターにワクチン遺伝子を組み込んだものであるため、実用化の条件はほとんど揃っている。
DNAワクチンには、いくつかの利点がある。細胞培養や卵で製造するワクチンと異なり、DNAワクチンは、タンク培養で迅速に大量生産できる。
たとえば、インフルエンザワクチンは前年の流行から予測したウイルス株を用いて製造されているため、出来上がったワクチンが翌年の流行ウイルスに対応するとは限らないが、DNAワクチンであれば、直ちに流行株を用いたワクチンが製造できる。
製造法が単純で容易なため、いくつもの候補抗原のDNA をすぐにワクチンとすることができる。DNAは熱に強く、冷蔵保存の必要がない。
DNAワクチンの投与法としては、筋肉内注射が一般に用いられてきた。
最近では、電気パルスによるエレクトロポレーションも行われている。
これは、筋肉内注射後に針電極でミリ秒の電気パルスをかけて、細胞膜の透過性を高めて、DNAの細胞内への取り込みを高めるものである。
多くの利点があるため、DNA ワクチンは理想的なものとして、1990年代から数多く開発されてきたが、人体用に承認されたワクチンはまだない。
現在、トリインフルエンザ、エボラ、C型肝炎、HIV、乳ガン、肺ガン、前立腺がンなどのDNAワクチンについて臨床試験が行われている。
特記すべき例として、ジカウイルスDNAワクチンは、2016年2月にWHOがジカウイルス感染の緊急事態を発表して、半年後には臨床試験が始められるという、急速な進展を見せている。
獣医領域では、すでにいくつかのDNAワクチンが承認されている。
2005年カナダでは、養殖サケの伝染性造血壊死病ウイルスに対するDNAワクチンが承認された。
2008年、オーストラリアでは、繁殖期の雌豚の成長ホルモン分泌促進のためのDNAワクチンが承認された。
米国では、馬用のウエストナイルウイルスDNAワクチンが農務省(USDA)から2008年に承認された。
イヌのメラノーマDNAワクチンは、2007年に条件付きで承認され、摘出手術後に用いられてきたが、2010年に正式承認された。
2017年11月にはニワトリ用の高病原性トリインフルエンザDNAワクチンが初めて承認された。
--------------------------
ヒトに対して、プラスミドDNAワクチンが実用化されるのを期待したい。
--------------------------
2020.3.18
目次へ
プラスミドDNAワクチンは、ヒトの体内の細胞で、ウイルスのエンベロープを作成するというが、体外で作成して、それを注入するのは意味があるだろうか。
引用:http://lifesciencedb.jp/dbsearch/Literature/get_pne_cgpdf.php?year=2006&number=5101&file=LDj6i7AMxaHah5X6689XBg==
センダイウイルスは、1本のマイナス鎖RNAをゲノムに持つ直径200nm前後の円形のエンベロープウイルスで、麻疹ウイルス、エボラウイルスなどが含まれる。
最外側には2種の糖タンパク質がスパイク状に突き出ていて、その根元には細胞膜成分と同じ脂質二重層にうずまっている。このような膜構造をエンベロープという。
エンベロープとRNP(ヌクレオカプシドタンパク質に包装されたRNA)との間には、マトリクスタンパク質が存在し、スパイク糖タンパク質の根元に結合し、脂質二重層に浮かんでいる糖タンパク質を固定すると同時に、RNPとも結合して内部構造と外部構造を架橋する。
2020.3.23
目次へ
RNAの複製が不思議だ。RNAそのものの特性なのか。タンパク質が必須だと思うが、そのタンパク質はRNAに由来する。
引用:http://lifesciencedb.jp/dbsearch/Literature/get_pne_cgpdf.php?year=2004&number=4908&file=k8hsrUj93gebRCeSGTpnqA==
インフルエンザウイルスのRNAポリメラーゼは、宿主細胞のmRNAを切断して形成したキャップを含む断片をプライマーとして開始する転写と、プライマーを利用しない複製の両方に関わる多機能酵素である。
3種類のウイルスタンパク質(PB1,PB2,PA)からなるRNAポリメラーゼは、ウイルスRNAエフェクターとの会合で活性化され、転写機能を獲得する。
転写酵素はさらに、宿主因子との相互作用で複製酵素に変換する。
植物に感染するウイルスはほとんどがRNAウイルスであり、動物でも半分以上はRNAウイルスである。SARSや鳥インフルエンザウイルスなどの新興・再興ウイルスのほとんどがRNAウイルスである。
RNAウイルスの大多数は一本鎖RNAで、プラス鎖RNAとマイナス鎖RNAがあり、プラス鎖RNAはそのままmRNAとして機能する。
インフルエンザウイルスはマイナス鎖RNAであり、8本のRNA断片からなる。
コロナウイルスはプラス鎖RNAなので、インフルエンザウイルスよりもタンパク質合成が直接的であるようだ。
コロナウイルスのプラス鎖RNAは、宿主細胞のリボソームを利用して一つの巨大なタンパク質を合成し、その後、切断される。
「RNAから巨大な前駆蛋白が出来て、それがウイルスのコードするプロテアーゼにより切断(processing)され、成熟蛋白となる。」
マイナス鎖RNAのインフルエンザウイルスは、プラス鎖RNAを作らなければいけないが、マイナス鎖RNAのゲノムは、転写(プラス鎖RNAを作る)と、複製(マイナス鎖RNAを作る)の、両方の過程を行うように構成されているようだ。
(動物細胞にはRNAをRNAに転写する酵素はない。)
転写の場合、真核生物のmRNAと同じように、5'末端にはキャップ構造が付加され、3'末端には長いポリA鎖(多数のAMPから構成されており、RNAをアデニン塩基で伸長することに相当する)がついている。
(マイナス鎖RNAのインフルエンザウイルスのゲノムの末端にはキャップ構造や長いポリA鎖がついていない。)
マイナス鎖であるため、感染後直接タンパク質が翻訳されない。ウイルスに結合したRNAポリメラーゼがウイルスのゲノムRNAとともに感染細胞に導入されて、まずプラス鎖mRNAを転写し、それが翻訳されてウイルスタンパク質が合成される。
--------------------------
プラスRNA鎖ゲノムをもつコロナウイルスは、直接タンパク質を合成できるわけだ。
--------------------------
インフルエンザウイルスのゲノムは8本のRNA断片(分節ゲノム)からなっているので、分節ゲノムの交換が起きるとさまざまの組み合わせの交雑体ウイルスが産生され、変異能力が多様化する。
--------------------------
生物に在来種と外来種があるように、RNAの在来種と外来種が区別できて、外来種のみを撃退できればよいが。
宿主細胞のリボソームにはそういう識別機能はないのだろうか。
--------------------------
引用:https://shingi.jst.go.jp/past_abst/abst/p/15/tokai3/tokai08.pdf
ウイルスのポリメラーゼを標的とする抗インフルエンザウイルス剤
インフルエンザウイルスはRNAウイルスであり、粒子内にRNA依存性RNAポリメラーゼ(タンパク質PA,PB1,PB2)を持つ。
株間でもよく保存されており、変異が起こりにくく耐性株が出現しにくいと考えられる。
PB2は宿主mRNAのキャップ構造を認識する役割を持つ。
低分子化合物が蛋白質の表面に結合することで、RNAの結合を阻害し、ポリメラーゼ活性を抑制できると予想した。
PB2サブユニットを標的としてコンピュータースクリーニングを行い、PB2と結合エネルギーの高い化合物を見出した。プラークアッセイでの化合物のIC50は69~103 μMで、核酸類縁体であるRibavirinと同程度の活性を示す。
化合物がPB2の構造を不安定化させることで、ウイルスポリメラーゼの酵素活性を阻害し、インフルエンザウイルスの増殖を抑制している可能性が考えられる。
・ウイルスポリメラーゼの構造を基に作られているため、従来のノイラミニダーゼ阻害薬と比べて耐性株が出現しにくいと考えられる。
・標的のRNAポリメラーゼはウイルス由来の蛋白質なので、薬の特異性を高めることで副作用の低減が期待できる。
引用:https://www.weblio.jp/wkpja/content/RNA依存性RNAポリメラーゼ
RNA依存性RNAポリメラーゼ (RdRp) はRNAのゲノムを保有し、かつ増殖ステップにDNAが関わらないウイルスにおいて必須のタンパク質である。
この酵素は鋳型のRNAと相補的となるRNAの合成を触媒する。
RNAの複製機構は2段階からなる。最初のステップは複製の開始であり、RNAの複製は鋳型RNAの3'末端、もしくはその近傍から始まる。
複製開始はプライマーを必要としない方法(de novo合成)と、VPgなどのプライマーを必要とする方法とに分かれる。
また、de novoの複製開始は最初のヌクレオシド三リン酸 (NTP) の3'-OHに付加される次のNTPの有無に左右される。
複製開始に続く伸長過程においては、次のNTPを付加する核酸転移反応が繰り返され、最終的に相補的なRNAを生じる。
2020.3.24
目次へ
ウイルスのエンベロープだけでワクチンにできないかと思うが、こんな論文が見つかった。
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/dds/24/6/24_6_599/_pdf/-char/ja
弱毒化麻疹ウイルスは、世界中でワクチンとして利用され、その効果と高い安全性が確認されている。このウイルスは種々のがんに選択的に感染し、増殖することによって強力な腫瘍溶解性を発揮する。
弱毒化麻疹ウイルスは、
・ウイルスゲノム中に外来遺伝子を挿入することができる。
・ウイルス自体が腫瘍細胞を死滅させる特性を持っている。
・標的細胞へ特異的に感染するように改変できる。
1971年、バーキットリンパ腫を呈する8歳の少年が、偶然に野生型麻疹ウイルスに感染したところ、腫瘍の完全な退縮がみられた。
がん細胞と正常細胞にワクチン株麻疹ウイルスを感染させると、がん細胞のみで細胞同士の融合とそれに伴ったアポトーシスが観察される。
ヒト正常細胞と比較してすべてのがん細胞は、CD46レセプターを顕著に発現している。
腫瘍溶解性VSVウイルスは、インターフェロンによって活性化された酵素プロテインキナーゼRの抗ウイルス作用により、正常細胞では増殖できないが、腫瘍細胞ではインターフェロンの経路に欠陥があるため、ウイルスは選択的にがん細胞で増殖できる。
引用:Wikipedia CD46
この遺伝子は、補体系の構造成分をコードする他の遺伝子を有する染色体1q32のクラスターに見られる。この遺伝子には、少なくとも14種類の異なるアイソフォームをコードする転写変異体が見つかっている。
この遺伝子によってコードされるタンパク質はI型膜タンパク質であり、補体系の調節部分である.
このコード化されたタンパク質は、補体成分C3bおよびC4bの不活性化(切断を通じて)の補因子活性を血清因子Iによって有し、補体による損傷から宿主細胞を保護する。
この遺伝子によってコードされるタンパク質は、受精中に精子と卵母細胞の融合に関与し得る。
このコード化されたタンパク質は、麻疹ウイルスのエドモンストン株の受容体として作用し得るが、ヒトヘルペスウイルス-6(HHV-6)、B群アデノウイルス、および病原性ナイセリアのIV型ピリが挙げられる。
CD46の細胞外領域には、柔軟なループに囲まれたコンパクトなβバレルドメインに折り畳まれる約60個のアミノ酸の4つの短いコンセンサスリピート(SCR)が含まれている。
他のリガンドを用いた CD46 について実証されているように、この CD46 タンパク質構造は、HHV-6 を結合した際に線形化すると考えられる。
正確な相互作用はまだ決定されていないが、第2および第3のSCRドメインは、HHV-6受容体結合および細胞の侵入に必要であることが実証されている。
樹立された髄芽腫(小児期に一般的な悪性脳腫瘍)標本はCD46を発現し、患者から取り除かれた髄芽腫標本はCD46発現の高いレベルを有していた。
したがって、はしかウイルスのエドモンストン株で作られたワクチンは、髄芽腫を治療することができる。このようなワクチンは、1種類の成人脳腫瘍を含むCD46の発現が高い他の腫瘍タイプを含む多くの試験で既に試験されている。
-------------------------
ウイルスをもってがん細胞をアポトーシスさせる、すばらしい方法だ。
-------------------------
2020.3.26
目次へ
ウイルスの初期感染を防ぐための最初の防波堤は唾液や鼻粘液中のIgAなので、最近はこまめに水分をとったり、ガムをかんだりしている。
免疫グロブリンのことをもう一度理解したい。
引用:http://www.ketsukyo.or.jp/plasma/globulin/glo_03.html
免疫の中で大きな役割を担っているのが免疫グロブリン(Immunoglobulin、略称Ig)で、血液中や組織液中に存在しています。
免疫グロブリンには、IgG、IgA、IgM、IgD、IgEの5種類があり、それぞれの分子量、その働く場所・時期にも違いがあります。これら5種類の免疫グロブリンの基本的な形はY字型をしています。
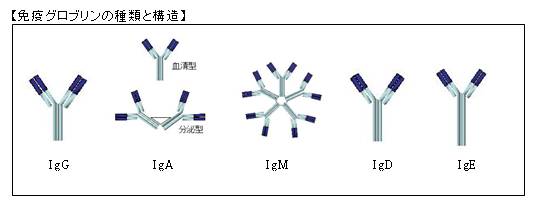
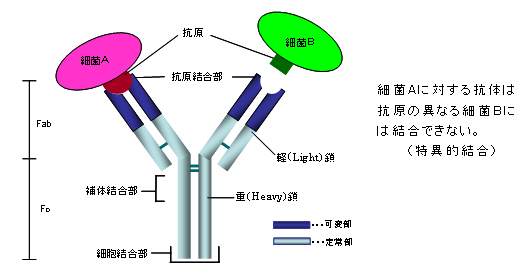
・IgG
血液中に最も多く含まれる免疫グロブリンです。分子量は約16万ダルトン、健常成人では血漿中に約1,200mg/dL含まれ、種々の抗原(細菌、ウイルスなど)に対する抗体を含んでいます。
IgGは、血液中に最も多く存在し、量的には免疫グロブリン全体の約80%を占め、液性免疫の主役です。
IgGは2本の軽鎖〔けいさ〕と2本の重鎖〔じゅうさ〕が結合したY字型をしています。このY字構造は、角度で0から180度近くまで開閉でき、大きな細菌・ウイルスとの結合にも柔軟に対応できます。
先端部分(抗原結合部=Fab部)で細菌やウイルスなどと結合し、それら病原体の動きを止めます。これを「中和」と呼んでいます。免疫グロブリンの先端部分が病原体と結合する時、「カギ」と「カギ穴」のように、両方の形がぴったり対になり、結合します。そのため、この結合は特異的結合と呼ばれます。
またIgGの幹の部分は、Fc部と呼ばれます。IgGの先端の部分で細菌やウイルスと結合すると、引き続いてY字型の幹のFc部が活性化します。その結果、①補体と呼ばれるタンパク質がFc部に付着し、活性化し、細菌を破壊します。②Fc部は、単球や好中球などの貪食細胞と結合し、これら細胞を活性化して貪食作用を強めます(オプソニン効果)。
・IgA
人の腸管、気道などの粘膜や初乳に多くあって、局所で細菌やウイルス感染の予防に役立っています。IgAは血液中ではY字型をしていますが、粘膜や初乳中ではY字構造が2つ結合した形をしています。
・IgM
私たちが細菌やウイルスに感染したとき、最初に作られる抗体です。そしてIgMが作られた後に、本格的にIgGが作られます。このため、血中のIgMを調べる事で今どんな感染症にかかっているかがわかります。IgMは5つのY字構造が互いに結合していて、Y字構造一つで出来ているIgGより効果的に病原体に結合すると考えられています。
・IgD
Y字型をしていますが、量的にも少なく、その役割はよくわかっていません。
IgE
免疫グロブリンとしては最も量が少なく、喘息〔ぜんそく〕や花粉症などのアレルギーを起こす抗体です。
2020.3.26_2
目次へ
今日、偶然、テレビの特集で、ビタミンB12の欠乏による病状を知った。調べてみたい。
引用:Wikipedia シアノコバラミン
シアノコバラミン(cyanocobalamin)は、ヒドロキソコバラミンなどと共にビタミンB12とも呼ばれる代表的なコバラミンの一種であり、ビタミンの中で水溶性ビタミンに分類される生理活性物質である。コバルトを含むため赤色又はピンク色を呈する。
シアノコバラミンは化合物を単離する際に得られる人工産物で、喫煙者などの特殊な場合を除き、人間の体内ではシアノコバラミンは合成できない。
草食動物は腸内細菌としてプロピオン酸生産菌(プロピオニバクテリウム属)等を保有し、これがビタミンB12を生産するので、これらの菌からビタミンB12を摂取している。
アミノ酸や脂肪酸の代謝および葉酸の生合成に用いられる。
これ自体に補酵素活性はなく、生体内で補酵素型であるメチルコバラミンおよびアデノシルコバラミンに変換される。
ポルフィリン類似のコリン環とヌクレオチドの構造をもつ、コバルトの錯体である。
シアノコバラミンは合成が極めて困難であるため、現在は放線菌(プロピオニバクテリウム属)などの細菌の培養液から生産されている。
ビタミンB12は代謝に関与しており、特にDNA合成と調整に加え脂肪酸の合成とエネルギー産生に関与している。
しかしながら、体内でビタミンB12が葉酸(ビタミンB9)の再生産に利用されているため、全てではないが多くのビタミンB12の機能は十分な量の葉酸によって代替される。
チミンやプリン体の合成のための十分な量の葉酸が体内に存在しない場合にはDNA合成障害を引き起こし、その葉酸欠乏症状は悪性貧血症状や巨赤芽球性貧血を引き起こすため、ほとんどのビタミンB12欠乏症状は実際には葉酸欠乏症状である。
十分な量の葉酸が利用できる場合には、メチルマロン酸(MMA)を代謝するビタミンB12依存酵素であるメチルマロニルCoAムターゼ(MUT)やホモシステインを基質としてメチオニンを合成する酵素として知られている5-メチルテトラヒドロ葉酸-ホモシステインメチルトランスフェラーゼ(MTR)を助けることになり、ビタミンB12欠乏症として知られるほとんどの症状は正常化される。
ビタミンB12補酵素の反応性の高いC-Co結合が3つの主な酵素反応に関連している。
① 異性化酵素反応
1番目の置換基である水素原子と酸素原子、アルコール基、アミノ基などと、1番目の置換基と隣り合った2番目の置換基である炭素原子(X基)を直接移動させる再配置である。
例として、メチルマロニルCoAをスクシニルCoAに変換する反応である。
② メチル基転移反応
メチル基が2つの分子間を移動する。
例として5-メチルテトラヒドロ葉酸を脱メチル化してテトラヒドロ葉酸に変化させると同時に、ホモシステインをメチル化してメチオニンへ変換させる。
③ 脱ハロゲン反応
有機化合物からハロゲン原子が離脱される反応である。この種の酵素はヒトからは発見されていない。
ヒトにおいては、上記最初の2つの反応に対応した2つの主要なビタミンB12依存酵素が知られている。
海洋性食品である海苔、貝、動物性食品の肝に30-60μgと非常に多く含有される。
魚類には、0.5-30μgほど含まれる。
畜産食品では、肝臓と舌以外に、肉類は0.3-2.5μg、生卵は0.9μg、普通牛乳は0.3μgほどが含まれる。
穀類、芋類、砂糖類、豆類、野菜類、果実にはほとんど含有されない。
ビタミンB12は、特定の真正細菌及び古細菌による原核生物によってのみ天然に産生され、多細胞または単細胞の真核生物によって産生されたものではないと主張されている。
プロピオニバクテリウム属の菌種は、ビタミンB12の産生や同ビタミンによる代謝の関わりが深いプロピオン酸などの産生ができる。
ヒトや他の動物のいくつかの腸内細菌によって合成されるが、内因子と結びついたビタミンB12が吸収される回腸の部位からさらに遠位の大腸でビタミンB12が産生されているので、ヒトは大腸で作られたビタミンB12を十分に吸収することができない。
しかし、牛や羊のような反芻動物は細菌を第一胃と第二胃で培養し産生されたビタミンB12を小腸内で吸収することができる。
反芻動物の腸内細菌がビタミンB12を産生するには、動物は十分な量のコバルトを細菌に提供しなければならない。
反芻動物以外の反芻胃を有さない草食の放牧動物はビタミンB12とそれを産生する細菌をそれらの動物が食べる植物の根に付着した土壌から摂取することになる。
ビタミンB12あるいは葉酸が不足して、葉酸が触媒的に再生産されないとDNA合成に異常が起こり細胞の成熟が正常に行われなくなるのは巨赤芽球を呈する赤芽球だけではなく、顆粒球系や巨核球系、さらに他の細胞とくに増殖の盛んな上皮や精子など細胞にも同様の影響をあたえる。
ビタミンB12の吸収不足の原因となる萎縮性胃炎では大球性高色素性貧血 (平均赤血球容積(MCH)の高値)が認められることがある。
胃全摘や高度な萎縮性胃炎では、内因子が不足するためビタミンB12の吸収障害が起こる。
赤血球のDNAの合成が阻害され大球性貧血(巨赤芽球性貧血)が起こることがあり、悪性貧血と呼ばれている。
ビタミンB12欠乏症
・ 潜在的に深刻で不可逆的な障害を脳と神経にもたらしうる。
・ 躁病や精神病、疲労、記憶障害、神経過敏、抑うつ、運動失調及び人格変化の症状を引き起こす可能性もある。
B12
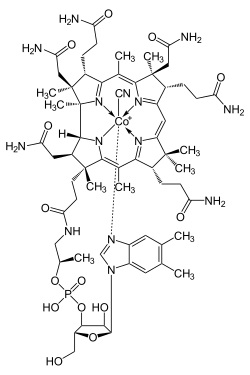
hemoglobin
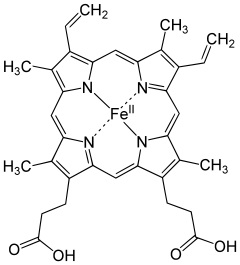
葉酸
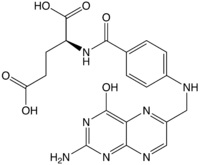
--------------------------
ビタミンB12のコバルト錯体のところは、ヘモグロビンに似ている。
海苔と貝に多量に含まれているというので安心。
--------------------------
2020.3.27
目次へ
ウイルスを排除する最善の方法は、細胞内に取り込まないことだが、なぜそれができないのだろう。
引用:http://jsv.umin.jp/journal/v59-2pdf/virus59-2_215-222.pdf
コロナウイルスは粒子表面に他のウイルスとは異なる“王冠(コロナ)様”突起(スパイク)を持つウイルス群として命名された.
スパイクは最外部が大きく膨らんでいる形状をなし,下部の棒状部位で粒子のエンベロープに埋め込まれている.
スパイクは3 分子のS 蛋白から成り,S蛋白は標的細胞表面にある受容体結合及びそれに引き続く細胞侵入に中心的な役割を果たしている.
S 蛋白は分子量約180kDa のクラスI のfusion 蛋白(糖蛋白)である.
多くのMHV 株のS 蛋白は,分子中程の塩基性アミノ酸部位が細胞由来の蛋白分解酵素フリンに認識,解裂され,N 末端S1 とC 末端側のエンベロープに結合するS2 サブユニットになる.
スパイク最外部の膨らんだ部分はS1 が,棒状部分はS2 が構成すると考えられている.
S1 のN 末端330個からなる領域(S1N330)は受容体結合部位であり,特にMHV 株間で保存されている2 か所が受容体結合に重要である.
S1N330 の下流にはMHV 株間で最も大きく相違する領域があり,超可変部部位と呼ばれている.
MHVの膜貫通性サブユニットS2 は,ヒト免疫不全ウイルス(HIV)やインフルエンザウイルス(IFV)など他のウイルスの膜貫通性サブユニットと構造的に類似性が高く,分子内にはα-へリックス構造の2 種類のheptad repeat(HR)及び疎水性アミノ酸領域からなるfusion peptide(FP)が存在する.
HIV gp41 やIFV HA2 では,N 末端の疎水性アミノ酸領域がFP として同定されているが,HVのFP はS2 分子内部に存在し,その部位は明らかではない.
S2 は膜貫通領域でエンベロープと結合し,その下流C末端の20-30 個からなる細胞内領域は他のウイルス構造蛋白である膜蛋白M との相互作用に関与する.
一方,SARS-CoV のS 蛋白もMHV 同様の大きな糖蛋白であるが,細胞内でもウイルス粒子上でも解裂型S 蛋白は検出されていない.
この非解裂性はヒトコロナウイルスHCoV-229E や猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)等と同じ性状であり,また,MHV の中でも,MHV-2 株はSARS-CoV と同様非解裂性のS 蛋白を持つ.
これらのウイルスは,一般的なMHV と同様の塩基性アミノ酸からなる領域も存在するが,領域内の塩基性残基数が少なく,非解裂性となると考えられる.
塩基性アミノ酸に富む領域を持つ組み換え変異SARS-S 蛋白は,細胞内で解裂を受け,
細胞融合活性を示すことが報告されている.
SARS-CoVS 蛋白上の受容体結合部位は,MHV と異なりS 蛋白N 末端ではなく,S1 に相当する部位の中程(S 蛋白N 末端から318 から510 番目のアミノ酸)にあり,その中で424-494 番アミノ酸が受容体との結合に直接関与する.
229E やFIPV もS 蛋白N 末端部位ではなく,むしろSARS-CoV S蛋白と同様,S1 内部に受容体結合部位を持っている.
S2相当部位の基本的な構造はMHV S2 や他のクラスI fusion蛋白と同様で,2 個のHR とFP が存在し,FP はHR1 の上流に位置していて,膜融合に関与すると考えられる.
コロナウイルスの受容体として最初に報告されたのはMHV 受容体である.
MHV 受容体のCEACAM1(carcinoembryonic antigen cell adhesion molecule は免疫グロブリンスーパーファミリーに属する蛋白である.
4個(N 末端からN, A1, B, A2 )又は2 個(N 及びA2)の細胞外ドメイン,その下流の膜貫通領域(TM)と長さの異なる2 種類の細胞内領域(Cy)を持ち,細胞外ドメイン数,Cy の長さの組み合わせで,4 種類のsplice variantsが報告されている.
また最近,TM を欠損する可溶性CEACAM1 も存在することが報告された.
CEACAM1には2 種類のallelic form があり,MHV 感受性マウスはCEACAM1a,MHV 抵抗性(感受生の低い)SJL マウスはCEACAM1b を持っている.
1b は1a に比べて受容体活性が10-100 倍低く,そのため感受性が低いのではないかと推測
されている.
CEACAM1 の受容体活性はN ドメインに存在し,N 単独でウイルス結合活性,ウイルス中和活性,S 蛋白の構造変化誘導活性を持つが,N ドメイン単独で細胞表面に発現されたN + TM + Cy 蛋白は受容体活性を示さない.
SARS-CoV の受容体は,angiotensin converting enzyme-2(ACE2)である.
ACE2 はカルボキシペプチダーゼ活性を持つタイプI の膜内在性蛋白であり,分子量約110 kDaの糖蛋白で様々な組織で発現されている.
その主な機能は、angiotensin(AT)I のAT1-9 への変換である.
AT1-9は更にACE によりAT1-7 に変換され,血管拡張機能を獲得する.
ACE2 の酵素活性はSARS-CoV の受容体活性には必要ない.
ACE2 のS 蛋白結合部位は,細胞膜から最外部に位置し,酵素活性部位に隣接するところに存在すると報告されている.
コロナウイルスの細胞侵入経路:
培養細胞に感染し融合を引き起こすエンベロ-プウイルスは,細胞膜-細胞膜融合活性を示すことから,エンベロープ-細胞膜融合も誘導し,細胞表面から侵入する.
一方,感染細胞に融合を引き起こさないウイルス(例えばIFV 等)は,感染細胞を酸性溶液で処理することにより細胞融合が誘導されることから,感染後細胞内エンドゾームに輸送されエンドゾーム内の酸性環境下で膜融合が起こり,細胞内へと侵入すると考えられている.
神経親和性株MHV - JHM 株感染細胞では細胞融合が観察されるが,非解裂性S 蛋白を持つMHV-2 感染細胞には細胞融合が見られない.
JHM の感染は,bafilomycin やNH4Cl のようなendosome/lysosome 内環境の酸化阻害剤の影響を受けないことから,JHM の細胞への侵入はendosome を経由することなく直接細胞膜から侵入することが示唆されている.
MHV-JHM 株の持続感染細胞から分離された変異株OBLV60 は細胞融合活性を欠くが,感染細胞を酸性溶液で処理することにより細胞融合が誘導され,また,感染はlysosome 酸化阻害剤により著しく抑えられることから,この感染様式は,IFV と酷似していて,endosome 内の酸性環境がウイルス融合活性を惹起するというendosome 経路による細胞侵入機構が考えられる.
一方,SARS-CoV 感染はlysosome 酸化阻害剤の影響を受けること,更に,SARS-S 発現細胞の酸性溶液処理では細胞融合は誘導されないが,トリプシン処理することによ
り誘導でき,同時にS 蛋白の解裂も引き起こすという実験結果から,SARS-CoV は細胞表面の受容体ACE2 に結合し, endosome へと輸送され,endosome 内の酸性環境下で活性
を示すプロテアーゼによりS 蛋白の膜融合能が活性化され,エンベロープとendosome 膜融合が起き,ゲノムが細胞内に侵入するという細胞侵入機構が提唱された.
更に,SARS-S 蛋白の活性化には細胞内のシステインプロテアーゼが関与することが示唆され,cathepsin L が受容体結合後のS 蛋白の膜融合能を活性化することが明らかにされた.
その後,cathepsin L が実際にSARS-CoVS 蛋白の解裂を誘導することが,精製したSARS-S 蛋白を用いて報告されている.
これらの一連の実験から,SARSCoVではendosome 経由,cathepsin 依存性の細胞侵入機
構が考えられる.
一方,培養細胞での感染で細胞融合を誘導しないMHV-2 株もSARS-CoV と同様の機構により細胞内侵入を果たすことが明らかにされたが,この場合cathepsin L とcathepsin B がS 蛋白の活性化に必要である.
また,HCoV-229E はカベオリン経由で細胞内に侵入することが報告されているが25),我々は,229E もSARS-CoV やMHV-2 と同様に,endosome に輸送され,その環境下でcathepsin L 等によりS 蛋白の活性化を受け,細胞質内に侵入することを報告した.
このように,非解裂性S 蛋白を持つMHV-2,HCoV-229E の細胞内侵入機構はSARS-CoV と極めて類似していることが明らかにされた.
我々は,トリプシン以外にもエラスアーゼなどのプロテアーゼがSARS-CoV 感染細胞の融合を惹起し,同時にS 蛋白の解裂も誘導することを報告した.
プロテアーゼによる感染細胞融合の誘導は,細胞表面のACE2 に結合したウイルス粒子S 蛋白がプロテアーゼ処理により活性化され,細胞膜と融合後ゲノムが直接細胞表面から細胞内侵入する可能性を暗示している.
我々はbafilomycin 処理によりendosome 経路感染を遮断した細胞にSARS-CoV を吸着さ
せ,その後トリプシンなどのプロテアーゼ処理により,ウイルスが細胞内侵入することを明らかにした.
即ち,受容体結合した粒子はプロテアーゼ処理により直接細胞表面から侵入することを示唆した.
これらの結果から,SARS-CoVはプロテアーゼの有無により異なる経路から細胞に侵入で
き,S 蛋白の解裂誘導能のあるプロテアーゼが侵入経路決定に大きく働いていることが推測された.
更に,興味ある点は,細胞表面からの感染の方がendosome 経路での感染より効率が極めて高く,プロテアーゼ存在下ではSARSCoVが迅速により高く増殖することである27).これらの実験結果から,プロテアーゼ存在下でのSARS-CoV 増殖の亢進は,肺や腸管などの標的組織での高い増殖と強い組織障害の原因ではなかと考えられた.
そこで,マウスに弱病原性呼吸器細菌を感染させエラスターゼ産生を惹起しSARSCoV
を感染させると,その感染は著しく増強され,その結果,致死的な肺炎の重症化が観察された.
このことは,SARS の重症化肺炎の病態発生にSARS-CoVS 蛋白の融合活性能を促進するプロテアーゼが関与している可能性を強く示唆していると思われる.
コロナウイルス細胞侵入の分子機構
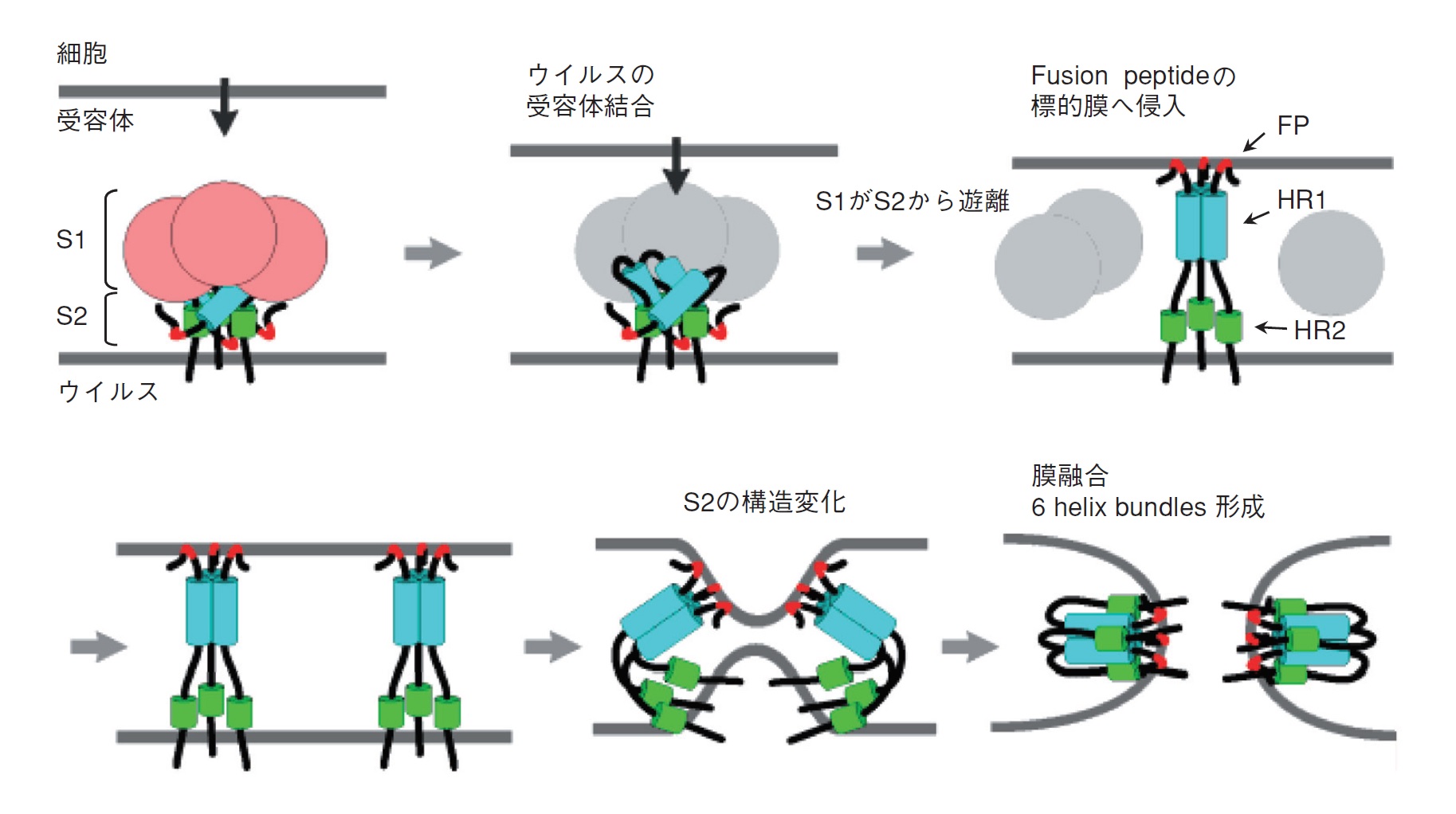
MHV とSARS-CoV は細胞侵入径路及びS 蛋白の融合活性化機構は異なるが,活性化された膜貫通性S2 による膜融合は同じメカニズムで起こると推測されている.
MHV ではS1 が受容体に結合するとS2 から遊離し,それに伴いS2 に存在するFP が露出し,標的細胞膜に挿入される.
その後S2 の構造変化(6 HB の形成)が起こり,隣接したウイルスエンベロープと細胞膜の融合に至る.
SARS-CoV-S 蛋白はendosome 内で解裂を受け,FP がendosome 膜に挿入され,エンベロープとendosome膜の融合が起こり,細胞侵入すると考えられている.
MHV-JHM と他のコロナウイルス(SARSCoV,MHV-2,HCoV229E)の間では細胞内侵入経路及びS 蛋白の融合能活性化機構は異なるが,細胞膜とエンベロープの融合は同様のメカにズムによって起こると思われる.
これはコロナウイルスS 蛋白による特有の細胞内侵入機構というよりクラスI fusion 蛋白を持つウイルスに共通していると考えられる.
S1 とS2 の解裂したS 蛋白を持つJHM の細胞侵入機構もHIV やIFV の侵入機構をモデルとして組み立てられたものである29.
最近,HIVのエントリーに関して細胞表面から直接侵入するのではなく,endosome 経由であることが報告されたが,どのような因子が必要なのかは明らかでない.
JHM ではS1N330 が細胞表面のCEACAM1-N ドメインに結合すると,S1 がS2 から離脱する.
露出したS2 のFP が標的細胞の細胞膜に挿入され,S2 蛋白の構造変化が誘導される.
この変化は,3 量体のHR1 の外側に3 本のHR2 が覆い被さるように位置する構造(6 helix bundles, 6HB),即ちS2 分子がヘアピン構造を取ることである.
6HB 形成により,エンベロープと標的細胞膜が隣接し,2 種類の膜間で融合が起こり,最終的にウイルスゲノムが細胞質内へと侵入する.
この過程の中で6HB 形成が極めて重要である.
S1 とS2 が解裂したMHV-A59 株では,HR1, HR2 に相当するペプチドを用いて,両者がanti-pararell 様式で結合し電子顕微鏡下では棒状構造として観察され,またHIV 感染で報告されているように,HR2 ペプチドでウイルスの細胞内侵入が押さえられることなどが明らかにされている.
我々は非解裂性親株SARS-S 蛋白を持つpseudotype ウイルスの感染はSARAS-S HR2 ペプチドで阻害されないが,解裂性S 蛋白を持つウイルスの細胞表面からの感染は強く阻害されることを報告した.
このことは,HR2 ペプチドによる細胞侵入阻害はendosome 経路で感染する場合には働かないことを示唆している.
これまでの報告は,S1 とS2 が非解裂性のS を持つSARS-CoV 及びMHV-2 では,侵入最終過程でのS 蛋白の解裂の必要性を示している.
即ち,endosome 内におけるcathepsins によるS 蛋白解裂である.
最近我々はMHV-2を用いて,ウイルスのレセプター結合から細胞膜との融合に至る過程で,S 蛋白が膜融合活性を発揮するための一連の構造変化を解析した.
MHV-2 粒子上のS 蛋白は可溶性受容体の結合により構造変化を開始し,fusion ペプチドを
標的膜に差し込む.
続いて,膜融合能を活性化させるトリプシン処理により,S 蛋白の解裂が起こり,解裂されたS2により6HB が形成され,ウイルスエンベロープと細胞の融合が引き起こされることが示された.
つまり,MHV-2のS 蛋白は,受容体とプロテアーゼによって誘導される二段階の構造変化を必要とすることが明らかとなった.
この現象はSARS-CoV では証明されていないが,S 蛋白の性状を考慮するとMHV-2 と同様の機構でS 蛋白の構造変化が起こり細胞内侵入することが予測される.
--------------------------------
ずいぶんむずかしいが、ウイルスが標的細胞に膜融合する過程は、段階的に行われるようだ。
--------------------------------
2020.3.28
目次へ
アビガンとカレトラの記事が載っていたので、調べてみる。
引用:https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14305
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療候補薬アビガンの特徴(白木公康)
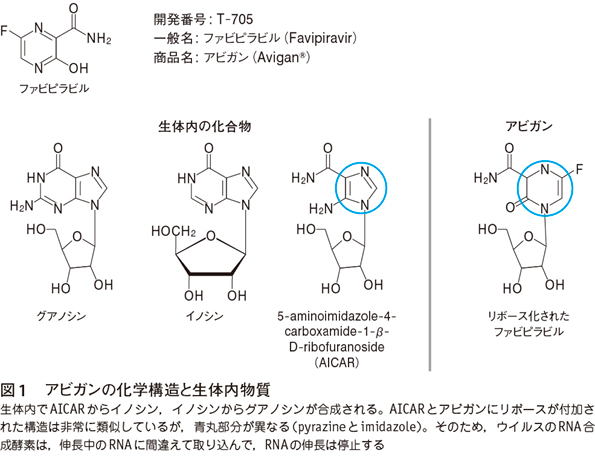
アビガンの化学構造は図1に示したように,アビガンにリボースが付加されると,生体内に存在するAICARに構造が似る。
AICARはRNAの材料となるグアノシンやアデノシンの前段階のイノシンに至る前駆物質である。
そのため,ウイルスのRNA依存性RNA合成酵素(RdRp)は,伸長中のウイルスRNAに,アビガンをグアノシンやアデノシンと間違えて取り込んでしまい,そこで,RNA合成が停止する。
すなわち,アビガンは,RNAウイルスのRNA複製の際に,RNA鎖に取り込まれたところで,RNAの伸長を停止する。
この機構は,アシクロビルと同じように,伸長阻止薬(chain terminator)として作用する。
そして,アビガンの阻害活性はインフルエンザウイルスだけでなく,ほとんどのRNAウイルスのRdRpに対して,伸長を停止する活性を有する。
このような活性を有するアビガンがインフルエンザ感染動物で治療効果を示すことを確認した後,この抗インフルエンザ活性は他の抗インフルエンザ薬に比べて優れているのか,優れているのはどのような点か,という差別化の試験を行った。
インフルエンザ感染動物を用いた試験では,軽症の感染ではタミフルとアビガンの治療効果に差異は認めなかった。
一方,致死性の高力価インフルエンザ感染モデルでは,タミフル治療で3日ほどの延命は得られるが多くのマウスが死亡する。
しかしアビガンは,すべてのマウスを生存させるという強い治療効果を示した。
このRNAウイルスの致死性感染症に対する生存効果は,その後,エボラ出血熱等への治療の際に効果を発揮した。
米国国防総省は,新型インフルエンザや致死性RNAウイルス感染症に対するアビガンの効果を期待して,季節性インフルエンザに対するアビガンの治験を行った。
わが国でも季節性インフルエンザに対するアビガンの治験を行い,抗インフルエンザ薬としての臨床効果が認められ,2014年3月,承認を得ることとなった。
これらヒトでの国内臨床試験および国際共同第Ⅲ相試験(承認用法および用量より低用量で実施された試験)において,安全性評価対象症例501例中,副作用が100例(19.96%)に認められた(臨床検査値異常を含む)。
主な副作用は,血中尿酸増加24例(4.79%),下痢24例(4.79%),好中球数減少9例(1.80%),AST(GOT)増加9例(1.80%),ALT(GPT)増加8例(1.60%)等であった。
この結果からは,試験対象者に対して強い毒性があるようには思われない。
アビガンは,主に水酸化体として尿中に排泄される腎排泄性薬剤であり,1日1回の投与では血中濃度を保つことは難しい。
治験の際,アビガン投与前後で,57ペアのインフルエンザウイルスの感受性に変化はなく,タミフルやバロキサビル マルボキシル(商品名:ゾフルーザ)のように耐性ウイルスは分離されなかった。
アビガンに耐性が生じないことはインフルエンザウイルスのほか,ポリオウイルスで確認した。
致死性インフルエンザ感染でも全マウスが生存するという優れた治療効果,そして,耐性ウイルスができず,流行の最初から最後の患者まで,同じ有効性で治療できるという特性は,致死性感染症に対する抗ウイルス薬として理想的である。
カレトラ
HIVプロテアーゼ阻害薬のカレトラは治療効果が期待されたが,十分な効果は確認されていない。
重症COVID-19患者の有意な改善,死亡率の低下,ウイルス消失が認められなかった。
さらに,アビガン群はカレトラ群に比べ,ウイルス消失が有意に早く,胸部CTの改善率が有意に高いと報告されている。
レムデシビル
レムデシベルは,細胞培養レベルでは低濃度でエボラウイルスや新型コロナウイルスの増殖を抑えることから効果が期待される。
ただ,エボラ出血熱に対しては,2種の抗体療法の方がレムデシビルより優れていたと報告されている。
無治療群との比較はなく,抗体療法との比較なので,レムデシビルの有効性評価は難しいと思われる。
COVID-19に対する有効性に関しては現在,中国をはじめとした国際共同治験等が進行中である。
COVID-19は,感染者の20%が重症肺炎となり2%が死に至る感染症である。
したがって,身近に重症者が出る可能性が高いことから,抗ウイルス薬について実地医家の先生方が患者に説明できることを目的に本稿を作成した。
前回(No.5004「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のウイルス学的特徴と感染様式の考察」)の考察と中国の臨床試験から,発症6日までにアビガン治療を開始すれば,ウイルスの早期消失,咳嗽の軽減,肺炎の進行や重症化が阻止され,それにより死亡率が激減するであろう。
さらに,若年者でも肺炎の後遺症である線維化や瘢痕化を最小限にすることができ,将来の呼吸機能の低下が避けられる。
テドロスWHO事務局長が“kill”という表現を使ったように,COVID-19に殺されないためには,ハイリスクの年齢であったり基礎疾患を有しているのであれば,労作性呼吸困難(息切れや呼吸回数の増加)により肺合併症を早期に発見して,胸部CTで肺病変があれば,発症後6日にはアビガン治療を開始していただきたい。
呼吸機能に予備能のない方を除けば,患者のADLを保ち,人工呼吸器装着者は減り,医療崩壊に至る可能性がなくなることが期待できると考えている。
--------------------------------
この論文では、アビガンの有効性が報告されている。
「胸部CTで肺病変があれば,発症後6日にはアビガン治療を開始していただきたい」
カレトラについては、3.28読売新聞に記事がある。
--------------------------------
引用:読売新聞3.28朝刊
2月16日から4日間、発熱と下熱を繰り返した男性が、20日、旭川市内の病院に受診。
CT検査で淡く白い影が見つかり肺炎と診断され、新型ウイルス検査で感染が判明した。
市内の感染症指定医療機関に入院し、せきを抑える薬や抗生物質の点滴薬を使い、鼻から酸素吸入をする処置も施したが、せきはひどくなり、38度台の熱が続いた。
医師は患者の同意を得て、エイズ治療薬「カレトラ」を28日に使い始め、翌日、熱が36度台まで下がった。
男性の妻も感染して入院していたが、カレトラを投与して改善し、二人はその後のウイルス検査で陰性となって3月11日に退院した。
---------------------------------
この事例では、カレトラが重症患者に対して有効だった。
---------------------------------
引用:Wikipedia ロピナビル
ロピナビル(Lopinavir、治験番号 ABT-378、略号LPV)はHIV感染症のHAART療法に用いられるプロテアーゼ阻害薬(英語版)の一つである。
リトナビルとの合剤(英語版)として市場に流通している。
リトナビル合剤の商品名はカレトラで、略号LPV/r。
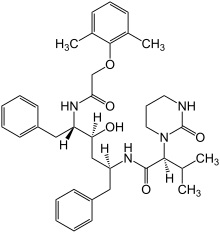
引用:http://www.interq.or.jp/ox/dwm/se/se62/se6250101.html
主成分の‘ロピナビル’は、エイズウイルスのプロテアーゼという酵素の働きを阻害することで、感染性をもつ成熟ウイルスへの移行を阻止します。これにより、新たな細胞への感染が起こらなくなり、エイズウイルスの増殖が抑制されるのです。このような作用から「プロテアーゼ阻害薬」と呼ばれています。
2020.3.29
目次へ
ウイルスが細胞に侵入するところを詳しく調べたい。
引用:http://cmri.sakura.ne.jp/wp/2020/03/01/sars%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%ad%a6%e3%81%b6%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%9a%84%e5%8f%97%e5%ae%b9%e4%bd%93ace2%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%af%e8%b3%aa/
SARSコロナウイルスに学ぶ機能的受容体ACE2タンパク質の組織分布
最近、アンジオテンシン変換酵素2(ACE2)という名前のメタロペプチダーゼが、SARS -CoVの機能的受容体として同定されました。
ACE2 mRNAは事実上すべての臓器に存在することが知られていますが、そのタンパク質発現はほとんど知られていません。
本研究では、さまざまなヒト臓器(口腔粘膜、鼻粘膜、鼻咽頭、肺、胃、小腸、結腸、皮膚、リンパ節、胸腺、骨髄、脾臓、肝臓、腎臓、脳)におけるACE2タンパク質の局在を調査しました。
ACE2は、調査したすべての臓器の動脈および静脈内皮細胞と動脈平滑筋細胞に存在していました。
ヒト組織におけるSARS-CoVの機能的受容体であるアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)の免疫局在性について、最も顕著な発見は、肺胞上皮細胞および小腸の腸細胞、すなわち外部環境と接触している細胞でのACE2タンパク質の表面発現です。
ACE2は、心臓機能および血圧制御の必須の調節因子であると考えられているものの、ほとんどの組織におけるACE2の生理的な役割は、解明されていない。ACE2は最近、SARS‐CoV 7の機能的受容体として同定されました。
引用:https://www.akita-u.ac.jp/honbu/event/img/pro30857_01_dl.pdf
新型コロナウイルス受容体ACE2と同じ機能を持つ微生物酵素 B38-CAP
ヒトACE2 は SARS 2 や新型コロナウイルス感染の受容体であることで知られていますが、2000 年の発見当初は、血圧上昇物質アンジオテンシン II を分解することにより血圧を降下させる酵素として見出されました。
ヒトアンジオテンシン変 換酵素 2 (ACE2)
ヒトの血圧を上昇させる作用をもつホルモンであるアンジオテンシン を分解し、血圧を下降させる 役割を有する酵素。心不全の症状改善や肺の炎症抑制にも寄与する。
アンジオテンシン
引用:Wikipedia アンジオテンシン
アンジオテンシンにはI~IVの4種が存在し、これらのうち、アンジオテンシンII?IVは心臓の収縮力を高め、細動脈を収縮させることで血圧を上昇させる。なお、アンジオテンシンIには血圧を上昇させる効果は無い。
アンジオテンシンの原料となるアンジオテンシノゲン (angiotensinogen) は肝臓や肥大化した脂肪細胞から産生・分泌される。
このアンジオテンシノゲンは、腎臓の傍糸球体細胞から分泌されるタンパク質分解酵素であるレニンの作用によって、アミノ酸10残基から成るアンジオテンシンI が作り出される。
その後、これがアンジオテンシン変換酵素(ACE)、キマーゼ、カテプシンGの働きによってC末端の2残基が切り離され、アンジオテンシンII に変換される。
アンジオテンシンIIはACE2により、血管拡張作用と抗増殖作用を有するヘプタペプチドであるアンジオテンシン-(1-7)へと変換される。
アンジオテンシンII は副腎皮質にある受容体に結合すると、副腎皮質からアルドステロンの合成・分泌が促進される。このアルドステロンの働きによって、腎臓の集合管でのナトリウムの再吸収を促進し、これによって体液量が増加する事により、血圧上昇作用をもたらす。
また、バソプレッシン(ADH)の分泌を促進し、水分の再吸収を促進することにより、血圧上昇作用をもたらす。
2020.4.2
目次へ
肺炎で呼吸が苦しくなるということは、肺のどこが具合悪くなるからなのだろう。
引用:https://www.fnn.jp/articles/-/22895
余昌平医師:
一般的な肺炎は片側だけ炎症することが多いのですが、新型肺炎は両側が炎症することがほとんど。片側だけ炎症しても、最終的には両側になります。このようなレベルまでくると、非常にひどい病状で、呼吸をするのすら、つらくなってくることでしょう。
余医師によると、通常の肺炎の多くは片側の炎症のため、もう一つの肺で呼吸ができる。しかし新型コロナウイルスの場合、その炎症が急激に両側に及ぶため、呼吸困難に陥りやすいのだという。
引用:https://karada-plan.com/disease-and-symtoms/what-is-pneumonia/
肺炎とは肺に何らかの原因で炎症が起きている状態になります。
肺で炎症が起こることにより、肺胞に白血球などや水が溜まり、呼吸が出来なくなってしまう状態です。
それは、ちょうど水に溺れているようで、とても苦しいです。
肺で病原体が、体の免疫力が追いつかないぐらいの増殖をすることで、排除するのに時間がかかってしまいます。
肺で炎症が起きると肺や肺の周りにある神経を刺激して、呼吸や咳の度に痛みを感じる事があります(胸痛)。
肺に酸素が入りづらくなってしまって、やはり呼吸が苦しいと感じる事があります(呼吸苦)。
肺炎の原因には、細菌が原因となることがあります。
肺炎球菌や黄色ブドウ球菌、緑膿菌などの細菌が原因になって起こる肺炎を細菌性肺炎と言います。
免疫力が低下していてなってしまう肺炎もあれば、免疫力に関係なくかかってしまう肺炎もあります。
細菌性肺炎は、細菌に対して効果のある抗生剤を使って治療をします。
サイトメガロウイルスやRSウイルスなどの、ウイルスによる肺炎を、ウイルス性肺炎と言います。
これも同様に、免疫力が低下しているためになってしまう肺炎もあれば、免疫力の強弱に関係なくかかってしまう肺炎もあります。
ウイルス性肺炎に抗生剤は効かないので、安静にして、水分をしっかりとるなどの対症療法を中心に治療をします。
引用:https://www.ishamachi.com/?p=26884
風邪の症状に加えて、以下のような症状がみられます。
1.高熱が続く
2.咳・痰が続く
3.胸が痛い、息苦しい
4.食欲不振
5.倦怠感
6.悪寒がする
7.頭痛
8.筋肉痛、関節痛
など
このような症状が1週間以上続いた場合、肺炎が疑われます。
たいてい38度以上の高熱が出ますが、高齢者の場合は熱が出ないこともあります。
肺炎の特徴は激しい咳です。痰を伴わない乾いた咳が長く続くことが多いのですが、黄色や緑色の痰を伴う湿った咳が出ることもあります。
肺炎を起こす病原体の種類や炎症を起こしている部位によって、症状は少しずつ異なってきます。
炎症が肺を包む胸膜に及ぶと、胸が痛くなったり、血液の中の成分などが染み出して肺と胸壁の間の胸腔の中に水がたまって胸膜炎を生じたりすることがあります。
そのほか、悪化すると血液中の酸素が不足してチアノーゼ(顔や唇が紫色になること)が現れ、呼吸数や脈が早くなることもあります。
肺炎を起こす主な病原体
細菌性肺炎:肺炎球菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌などの細菌
非定型肺炎:マイコプラズマ、クラミドフィラなどの微生物
ウイルス性肺炎:インフルエンザウイルス、麻疹ウイルス、水痘ウイルスなどのウイルス
感染する環境による分類
市中肺炎:日常生活を送っている人が病院、診療所の外で感染して発病する。
風邪やインフルエンザをこじらせた時に多く起こる
院内肺炎:何らかの病気のために病院に入院してから48時間以降に発病する。
気管内挿管で人工呼吸器をつけていたり、抵抗力が低くなっていたりするときに発病することが多い
その他の肺炎
高齢者に多く起こるのが、誤嚥性(ごえんせい)肺炎です。
年を取るにつれて、咳をすることや、飲み込む運動がうまくできなくなり、誤って唾液や食物が気管に入ってしまうことがあります。それを誤嚥と呼びます。
誤嚥性肺炎とは、細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎のことをいいます。
-----------------------------
肺はまことに精密な器官だ。空気を吸い込んで酸素を血液に取り込むという離れ業を行っている。膨大な数の細胞が、肺胞という器官を構成して、無意識に行っている。
この作用がないと、1分も耐えられない。
-----------------------------
引用:Wikipedia 肺胞
肺胞(はいほう、英: alveolus)は、血液‐ガス交換の場。肺の容積の85%を占め、成人の場合、その表面積の総計は100m2に近い。
肺胞は終末細気管支から繋がる外気と血液のガス交換をあずかる器官である[1]。肺胞を持つ細気管支を呼吸細気管支という。
肺胞はガスを溜める肺胞腔と、これを囲む肺胞上皮からなる。
肺胞上皮はI型肺胞上皮細胞とII型肺胞上皮細胞からなる。
前者は、肺胞を取り囲む毛細血管内皮細胞と基底膜を介して血液空気関門を形成し、肺胞内ガスと血液ガスの交換を行う。
後者は、層板小体を多く含み、肺サーファクタント(肺胞界面活性剤)を開口分泌し、肺胞被覆層を形成している。
肺胞一つの大きさは100~200μmくらい。肺胞は中隔孔により互いに交通している。
赤血球中のヘモグロビン(Hb)は酸素分圧に応じて酸素と結合する性質を有しており、酸素分圧が高い肺砲内で酸素と結合し、酸素分圧が低い末梢組織で酸素を遊離する。
二酸化炭素は一部はヘモグロビンと結合しているが、これは二酸化炭素の運搬というよりもヘモグロビンと酸素との親和性を変化させることにより効率よく酸素を運搬させる役割を持っている。
二酸化炭素は酸素よりも水に溶解しやすく、二酸化炭素の運搬は専ら血漿への溶解→赤血球内での水和(炭酸に変化)によるイオン化によって血漿中に拡散して運搬される。
血漿中にはフリーの二酸化炭素と炭酸イオンが共存し化学平衡に達しているが、二酸化炭素分圧の低い肺胞に血液が到達すると、まず二酸化炭素が肺胞気中に拡散し、血漿の二酸化炭素分圧が下がることによって炭酸が脱水されて二酸化炭素となり、さらに肺胞気中に拡散して排泄される。
一方、一酸化炭素やシアン化水素は、ヘモグロビンとの親和性が酸素より高いため、酸素運搬を阻害して毒性を発揮する。
なお、血液と空気のガス交換は血液‐ガス分配係数で表される。
これは、ガスが溶ける血液の分布容積を求めるものであり、吸入麻酔薬の選択や調整に使用される。
臨床においては、肺胞気・動脈血酸素分圧較差(AaDO2)が肺胞における換気能の指標として重視される。
引用:Wikipedia 肺炎
肺炎(はいえん、英: Pneumonia)とは、肺の炎症性疾患の総称である。
治療法はその原因によって異なり、細菌性のものであれば抗生物質が用いられる。
重症の場合は一般的に入院となる。
酸素レベルが低い場合は酸素吸入を行う。
肺炎の予防法に関しては、ある種の肺炎に限ればワクチンによって予防可能ではある。
他の予防法としては、手洗い、禁煙などがある。
肺炎は世界で年間4.5億人(人口の7%)が発症しており、うち400万人が死亡している。
日本の死亡統計においても、肺炎は死亡原因の第4位である。
肺炎は19世紀にはウイリアム・オスラーに「男性死因の代表格」として描かれていたが、20世紀には抗生物質とワクチンの普及により生存率が改善されはした。
しかしながら途上国では、現在も主要な死因の一つとされ、高齢者と若年者において代表的な慢性疾患である。
現代日本の全世代の死亡統計でも死因の第4位であり、しかも85~89歳では死因第3位、90~99歳では第2位、と年齢が上がるにつれ次第に順位が上がる。
肺炎は、成人では1/3、児童では15%がウイルスを原因としている。
一般的にはライノウイルス、コロナウイルス、インフルエンザウイルス、RSウイルス、アデノウイルス、パラインフルエンザなど。
単純ヘルペスウイルスではめったに起こらないが、例外として新生児、がん患者、臓器移植レシピエント、重度熱傷が挙げられる。
サイトメガロウイルスは、臓器移植患者や免疫不全患者に起こり得る。
-----------------------------------
肺胞についてもう少し知りたい。
-----------------------------------
引用:http://nurse-kyoukasyo.com/vitalkiso/haihoukei.html
終末細気管支より先は、呼吸細気管支になり、その先が肺胞です。
肺胞系の仕組み:
呼吸細気管支より先は、気道が無数に分かれ始めます。
吸気の流れは一気に遅くなるので、細かい塵は終末細気管支付近で沈着し、呼吸細気管支より先には入ってこないような仕組みになっています。
また、万が一塵やほこりなどの異物が入ってきてしまったとしても、肺胞で肺胞マクロファージと呼ばれる貪食細胞が食べてくれます。
呼吸細気管支から肺胞までの道のり:
呼吸細気管支(約1~0.5mm)→肺胞管(約0.4mm)→肺胞道(約0.5mm)→肺胞(約0.1mm)
気管支から肺胞までの形状は、よくブドウに例えられます。
気管支はブドウの幹と太い枝、肺胞管は房の枝、肺胞のうは房、肺胞は粒に相当します。
成人の肺の肺胞道の数は約1400万個。1つの肺胞道にはおよそ20個の肺胞がくっついているため、肺胞の数は両肺でおよそ6億個にもなります。
その表面積は、なんとテニスコート2面分にも相当します。
肺胞
肺胞では、二酸化炭素と酸素の交換、すなわちガス交換が行われています。
ガス交換の場は、肺胞道、肺胞です。
<「肺実質」と「肺間質」>
肺胞は、その内側と外側でそれぞれ「肺実質」と「肺間質」に分けられます。
肺実質:肺胞の内側部分のこと。
ガス交換に実際にかかわっている部分のことで、肺胞上皮細胞(肺胞の内側にある細胞)と肺胞腔(肺胞の中の空間)があります。
肺間質:肺胞の外側部分のこと。
肺胞と肺胞の隙間を埋める結合組織で満たされています。
<肺サーファクタント>
肺サーファクタントとは、肺胞がしぼまないように肺胞を守ってくれる物質のことです。
肺胞内の肺胞上皮細胞から分泌されており、肺胞上皮細胞の上を薄く覆っています。
肺サーファクタントがないと、肺胞はしぼんでしまいます。
-----------------------------------
肺胞は微細な美しい風船のようだ。大事にしないといけないな。
-----------------------------------
引用:細胞紳士録 藤田恒夫、牛木辰男著 岩波新書
空気の通う肺胞腔と、血液の流れる毛細血管腔とは、厚さ0.5ミクロンに満たない壁で仕切られている。
この壁が「血液空気関門」で、酸素と二酸化炭素の受け渡しの場所である。
関門をつくるのは、血管の内皮細胞と基底膜と肺胞の上皮細胞である。
肺胞は水の表面張力でしぼもうとするのを防ぐため、表面活性剤(サーファクタント)が塗られている。
サーファクタントを合成して分泌するのは、Ⅱ型肺胞上皮細胞という厚ぼったい細胞であり、サーファクタントはタマネギ状の層板小体に含まれ、肺胞腔へ開口分泌される。
肺胞がふくらめばサーファクタントの分泌が抑制され、縮めば分泌が促進される。
2020.4.3
目次へ
久しぶりに国際的に前向きな記事があった。
引用:読売新聞
菅官房長官は3日の記者会見で、新型コロナウイルス感染症の治療薬として効果が期待される新型インフルエンザ治療薬「アビガン」について、希望する各国に無償提供する方針を明らかにした。
菅氏は「現時点で約30か国から提供要請がある。所要の量を日本政府から無償で供与すべく調整している」と述べた。
菅氏は「希望する国々と協議しながらアビガンの臨床研究を拡大する考えだ」とも語り、早期の正式承認に向け、効果や安全性の確認を急ぐ考えを示した。
2020.4.4
目次へ
肺胞のことをもっと知りたい。
引用:http://www.pap-guide.jp/about/about.html
健常肺では、II型肺胞上皮細胞から放出されるGM-CSFが未熟な肺胞マクロファージのGM-CSF受容体に結合し、シグナル伝達により、転写因子PU.1が発現して肺胞マクロファージの終末分化が起こり、成熟マクロファージとなる。
成熟マクロファージは、サーファクタントを取り込み、分解することにより肺胞のホメオスターシスを保つ。
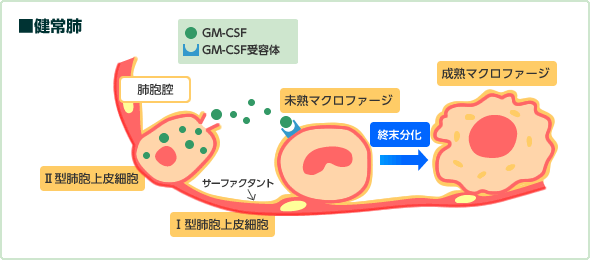
自己免疫性(特発性)肺胞蛋白症の肺では、II型肺胞上皮細胞から放出されるGM-CSFは肺胞内に豊富にある抗GM-CSF自己抗体により中和され、GM-CSFが未熟な肺胞マクロファージの受容体に結合するのを防ぐ。
そのために、肺胞マクロファージの終末分化または増殖は起こらず、サーファクタントの分解が障害される。
正常肺におけるサーファクタント代謝
サーファクタントはII型肺胞上皮細胞で合成される。
サーファクタント蛋白とリン脂質の複合体はlamellar bodyとして肺胞内に分泌され、肺胞上皮で格子状のtubular myelinとなって界面活性を示す。
サーファクタントは分解された後、肺胞マクロファージおよびII型肺胞上皮細胞で代謝される。
サーファクタント分解には、肺胞マクロファージが重要な役割を果たしている。
その肺胞マクロファージの終末分化には主としてII型肺胞上皮細胞が出すGM-CSFが必須である。
GM-CSFシグナル異常による肺胞蛋白症の発症
II型肺胞上皮細胞はGM-CSFを産生するが、肺胞腔内の抗GM-CSF自己抗体により中和され、生物活性を失う。
肺胞腔内の未熟なマクロファージはGM-CSF受容体をもっているが、中和されたGM-CSFは受容体に結合ができない。
したがって、肺胞マクロファージの終末分化が障害され、 肺胞マクロファージのサーファクタント代謝能が低下し、肺胞マクロファージはサーファクタントを蓄積して肥大しやがて破裂する。
肺胞内には、分解されないサーファクタントや細胞断片が蓄積する。
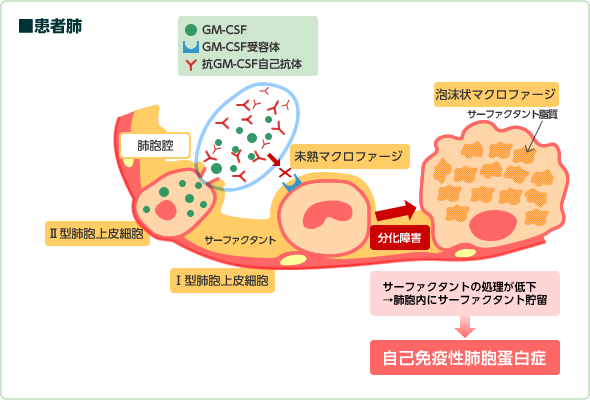
引用:Wikipedia GM-CSF
GM-CSF(Granulocyte Macrophage colony-stimulating Factor:顆粒球単球コロニー刺激因子)は、多能性造血幹細胞に分化を促すサイトカインの一種。
IL(インターロイキン)-3,5などと協力し、多能性造血幹細胞を骨髄系前駆細胞(CFU-GEMM)に分化させ、これを前期赤芽球系前駆細胞(BFU-E)、顆粒球単球コロニー形成細胞(CFU-GM)、好酸球コロニー形成細胞(CFU-Eo)、好塩基球コロニー形成細胞(CFU-Ba)らに分化させる。
更に、CFU-GMを好中球と単球に、CFU-Eoを好酸球に分化させる働きを持つ。(CFU-BaはIL-3,5により好塩基球に誘導される)
このように主に細胞性免疫の主役である白血球(顆粒球、単球)の分化誘導作用をもつため、免疫賦活や骨髄刺激に用いられることもある。
Th細胞等が産生していることがわかっている。
引用:Wikipedia 肺サーファクタント
肺サーファクタント(はいサーファクタント、英語: Pulmonary surfactant、肺表面活性物質)とは、肺胞の空気が入る側へと分泌されている界面活性剤である。
なお、肺サーファクタントは単一の成分ではなく、リン脂質を主成分とした混合物である。
肺サーファクタントは肺呼吸をするに当たって、肺胞を広げるのに必要なエネルギーを少なくしている。
肺胞はだいたい球形をしており、肺胞の空気が入る側に発生する表面張力は、肺胞を潰して空気を追い出す方向に作用する。
この表面張力によって肺胞内から空気が虚脱するのを防ぐために、肺を持った動物は、界面活性剤が持つ性質の1つである表面張力を緩和する作用を利用すべく、肺胞内に肺サーファクタントを分泌している。
組織液の表面張力は約50 (ダイン/cm)であるのに対し、肺サーファクタントの存在によって、実際の肺胞における表面張力は約20 (ダイン/cm)にまで緩和されている。
もしも肺サーファクタントが不足すると、肺胞が潰れやすいため呼吸困難に陥ることがある。
引用:https://www.kango-roo.com/sn/k/view/1616
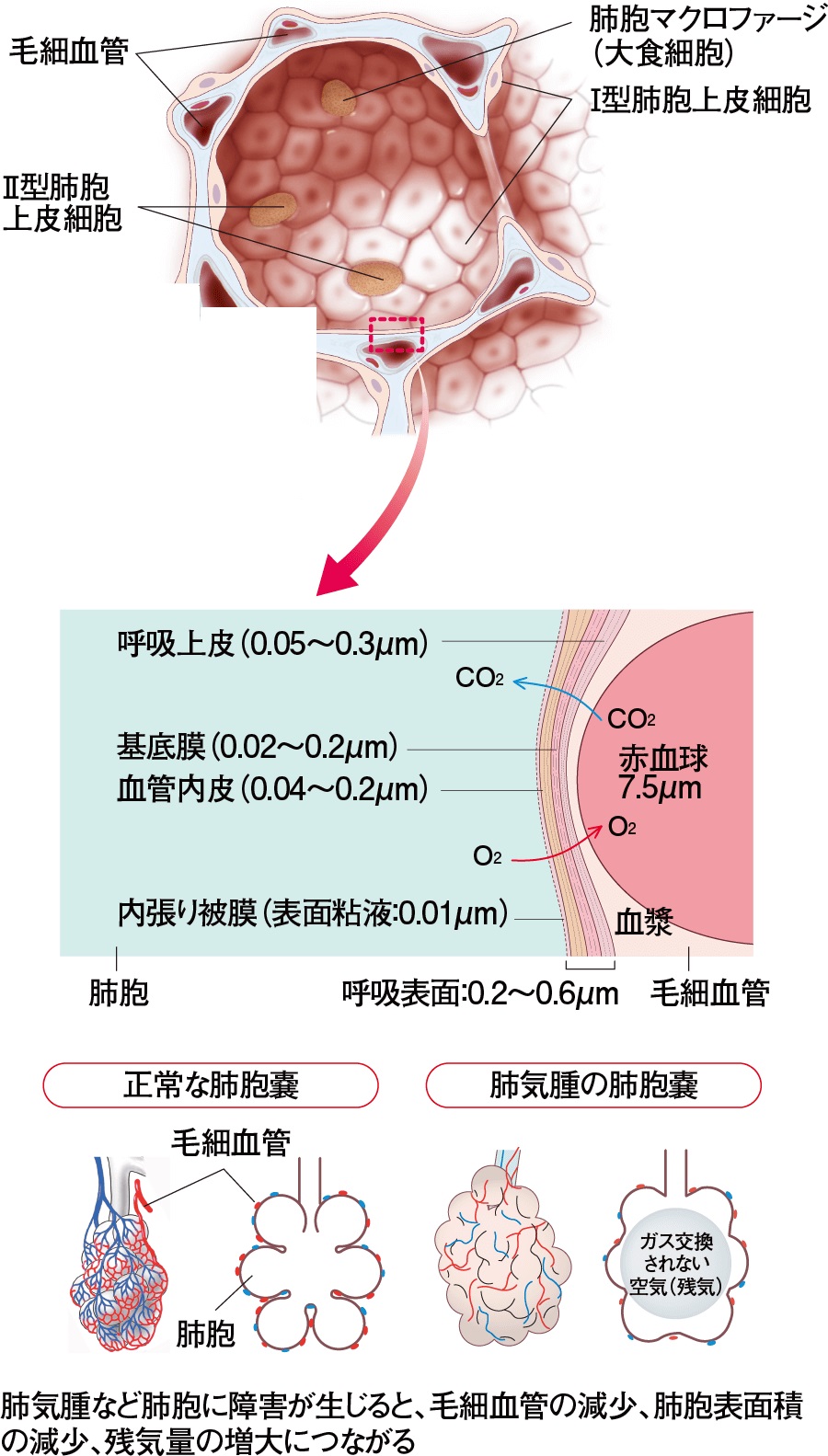
2020.4.5
目次へ
肺胞の再生について
引用:https://matsumoto25.net/2019/12/30/%e9%96%93%e8%b3%aa%e6%80%a7%e8%82%ba%e7%82%8e%e3%81%a8%e8%82%ba%e8%83%9e%e3%81%ae%e5%86%8d%e7%94%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
脳の中枢神経細胞にも幹細胞があるという事がわかったように、肺胞のⅠ型・Ⅱ型の細胞にも幹細胞があり、再生が可能ということが判明しました。私の知る限りでは、ひとたび死滅した細胞が再生できないのは、腎臓の足細胞だけであるのです。
肺は発生学的には、食道壁の一部より生じ、消化管と同じ起源を持ちます。
消化管とくに腸の上皮細胞が1日~数日で新しい細胞に入れ替わるのに対し、肺の気道上皮細胞のturn over(細胞の新旧の入れ替わり)は約100日と長いのです。
しかし、肺は外界に接している臓器であるため、肺損傷後の修復は素早く行われる必要があります。
なぜならば、肺胞の傷が残り続ければ、常に空気に含まれる病原体や毒物にさらされ、様々な肺炎になりやすいからです。ところが残念ながらこの肺の修復の詳細は未だ不明であるのです。
傷害を受けた肺胞では、その細胞に取って代わる新しい細胞の供給が必要です。
この新しい細胞の供給源となる元の細胞が肺の幹細胞であります。
これらの細胞が増殖するために母地となる適切な結合組織(基質)を作る細胞の存在も必要であり、さらにそれらの細胞を傷害部位に誘導させるための走化因子、増殖させるための増殖因子などの液性因子も不可欠です。
また、それらの幹細胞を目的とする肺組織の様々な細胞に分化させるための細胞内シグナルおよび転写因子の発動も重要でありますが、今なお完全には解明されていません。
骨髄由来幹細胞が肺の炎症により動員され、傷害部位に集積し、肺胞上皮細胞・肺毛細血管内皮細胞に分化または融合することもわかりました。
一般の肺炎症例においても、骨髄由来細胞が肺炎後の治癒にかかわっていることもわかりました。
肺胞マクロファージ(alveolar macrophage)は、血管から袋状の肺胞の内面に出たマクロファージであります。
肺胞マクロファージは、大気中から肺胞に侵入した粒子状物質やたばこ煙、呼吸器内に侵入した微生物を、マクロファージの細胞骨格を形成するアクチンというタンパクを働かせ、肺胞マクロファージ自体の細胞膜を粒子に沿わせ伸展することによって粒子を細胞内に取り込み、呼吸器を守る役割を持っています。
通常のマクロファージは組織内で活動しますが、肺胞マクロファ?ジだけは組織の外へ出て、肺胞の内壁で活動します。
1個の肺胞の表面には平均 50個の肺胞マクロファージがいます。
つまり、人間は左右に6億個~7億個の肺胞を持っていますから、7億×5=350億個の肺胞マクロファージを持っているのです。
ちなみに、すべての肺胞の表面積を合わせると平均70平方メートルにもなります。
肺胞の間質(隔壁)には膨大な毛細血管があります。
その毛細血管に運ばれてきた肝臓で作られた補体が肺胞の結合組織に漏れ出てきます。
この補体と複合抗原が結びつき、再び毛細血管や毛細リンパ管から吸収されて肺関連のリンパ節に運ばれます。
そのリンパ節には、イレッサ(抗がん剤)と結びついたキャリアタンパクの複合抗原だけを認識できるB細胞がいれば、その複合抗原が結合した補体と結びつくことができるのです。
実は B細胞は、補体と結びつくレセプター(CR2)を持っているのです。
このB細胞のCR2に補体とイレッサの複合体が結びつくと、B細胞もイレッサを認識できます。
リンパ節でT細胞もB細胞もイレッサを敵と認識すると、B細胞はイレッサに対する抗体を作り始めます。
この抗体はリンパ管から再び肺胞の結合組織(間質)にまで運びだされます。
抗体はオプソニン作用があり、肺胞の間質や肺胞の内面にいる好中球や肺胞マクロファージに食べられます。
これらの貪食細胞は溶けきれないイレッサを吐き出します。吐き出す時に、肺胞の組織に障害を与える活性酸素や様々な酵素も同時に吐き出します。このような強い作用を持つ化学物質が肺胞の組織を傷つけ、炎症が生じます。
大量のイレッサを飲み続けると、この炎症が激しくなり、肺胞が崩壊していきます。
酸素と二酸化炭素の交換を行う肺胞上皮細胞Ⅰ型のみならず、Ⅱ型も死んでしまいます。肺胞の上皮細胞Ⅱ型で作られるKL-6やSP-AやSP-Dが大量に血流に漏れ出てしまいます。
---------------------------
細胞の細部の動きが詳しい。イレッサというのは抗がん剤であるが、体にとって害にもなるようだ。
---------------------------
2020.4.7
目次へ
肺はどのようにして進化し、発生したのだろう。
引用:http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=126715
肺の起源は「消化管(腸)から飛び出した袋」のようなものであり、魚類の呼吸器官である「えら」から漸進的に進化したものではなく、消化器官の一部をむりやり呼吸器官に改造したものであった。
その原型はドジョウにも見ることができる。
ドジョウは水面から顔を出して空気を吸いこみ、「腸」で酸素を吸収することができ、そのため水中が酸素不足になっても腸呼吸で生きながらえることができる。たまにお尻から出す空気泡もドジョウの腸呼吸の証。
魚類における原始の肺は、ハイギョに見ることができる。
ハイギョはえら呼吸をする魚類だが肺呼吸も出来る。
乾期には泥の中で夏眠するが、これは、季節によって水の流れがなくなり水中の酸素が突然減ったりするような劣悪な環境に棲んでいた淡水魚が空気から酸素を吸収するように適応した形態と見られる。
両生類は、幼生期はえら呼吸、成体は肺呼吸を基本としているが、肺だけでは全呼吸をまかなえず、皮膚呼吸にも依存している(カエルは全呼吸の1/2~1/3が皮膚呼吸)。
両生類の肺は、基本的に魚類と同じ単純な袋状。
は虫類になると、ほぼ肺に依存した呼吸が可能な構造に複雑化して、内壁は海綿状にまで発達している。
哺乳類の肺は非常に複雑な構造を持つ。
気管支の分枝の先にある肺胞という小さな袋の壁でガス交換を行うが、著しく広い表面積の獲得により酸素摂取能力は非常に高い。
また、知能(共認機能・観念機能)を著しく発達させた人類の脳が消費する酸素量は、肺の吸収する酸素の20%にも達するが、こうした大量酸素消費に対応できる素地は,ほ乳類誕生期の『長期低酸素時代』に獲得された。
引用:https://rehabilizyoho.com/category22/en443.html
水中では、浮力によって、地上の6分の1しか重力の影響を受けません。
そのため、尻尾とヒレ、エラを動かすだけで、生物は血液を全身に送ることができました。そのため、血圧は低い状態でも問題ありませんでした。
しかし、陸上に上がることで、重力の影響を強く受けるようになりました。
その結果、尻尾やヒレ、エラだけの運動では、血液の循環を十分に補うことができなくなりました。
さらに、下手すると自重によって潰れて死んでしまう可能性も出てきました。
そこで、陸上に上がった生物は、まずのたうちまわることで、血圧を上昇させていました。
これにより、結果的に自重を支えることができ、全身に血液を送ることもできるようになったのです。
そして、2つ目が、肺呼吸が必要になったことです。
水中では、水があったため、えら呼吸で体内に酸素を取り入れることができました。しかし、陸上に上がると、えら呼吸では、酸素を得ることができません。
そのため、他の方法で酸素を取り込まなければなりません。
えら呼吸から肺呼吸への変化も、のたうちまわり、血圧が上昇したことで、可能となりました。
実際に、このような適応は、短期間の間で行われます。そして、適応が完了した生物はその後、陸上生活が1時間以上行えるようになるようです。
これは、某大学の付属病院で行われた研究で明らかになりました。
実験は、麻酔薬の入った海水にサメを入れるというものです。
そのサメは、どうにかその海水から逃げようと、暴れて陸上に逃げようとします。
それを無理やり抑えて麻酔をかけます。
麻酔がかかった状態で、ある手術を行います。もちろん、これは陸上で行いますので、いくら麻酔がかかっているとはいっても、えら呼吸では、サメは数十分で息絶えそうになります。
しかし、このように、「麻酔入りの海水につける → 暴れる」ということを繰り返すたびに、サメの血圧は上昇していきました。そして、5回目の手術では、1時間以上陸上にいても、全く問題なく、陸上で麻酔が覚めるような状況になっていたとのことです。つまり、空気呼吸が行えていたということです。
水中で生活していた生物の骨は、まだ軟骨の状態でした。しかし、陸上で生活している動物を調べると、骨はほとんど硬骨です。
この様な骨の変化も、上陸という環境の変化によって起こったものです。
上陸すると、必然的に血圧が上昇します。血圧が上がるということは、血液の流れが強くなるということです。
血流があると、血液と、血管壁や周囲の臓器の間に「活動電流」と呼ばれる、電気が生み出されます。
この活動電流によって、軟骨は硬骨に変化します。
硬骨の主成分は「アパタイト」と呼ばれるものです。
一定以上の活動電流が生じると、アパタイトの存在下で軟骨を形成していた細胞の遺伝子が刺激されます。そのことによって、遺伝子が変化し、内骨格の軟骨が硬骨化するということです。
生物の骨が軟骨であったころ、血液内の成分を生産する「造血巣(ぞうけつす)」は脾臓にありました。
このような骨の変化によって、元々は造血巣が、骨の中の骨髄に移動しました。
引用:Wikipedia 鰾(うきぶくろ)
鰾(ひょう、うきぶくろ、Swim bladder)は、硬骨魚が持つ、気体の詰まった袋状の器官である。
気体で浮力を得るほか、いくつかの補助的な機能を持つ。四肢動物の肺と相同である。
鰾は本来は消化管から分岐した器官で、消化管とは気道で繋がった開鰾(有気管鰾)であった。
しかし一部の魚類では、気道を失い消化管から離れた閉鰾(無気管鰾)となっている。
開鰾魚では、水面に顔を出して空気を直接気管から鰾に取り込むが、閉鰾魚では、鰾の周囲にある奇網からガス腺と呼ばれる細胞を介してガスを取り込む。
原始的な条鰭類であるポリプテルス目、ガー目、アミア目、および肉鰭類のハイギョでは、鰾は肺としての機能を失っておらず、これらの魚類は鰓呼吸とは別に肺呼吸もおこなう。
そのためこれらの鰾は肺と呼ばれることもある(特にハイギョの場合)。
これらの鰾(肺)の気道は食道の腹側に通じており、鰾は腹側(ポリプテルス目)または背側(ガー目、ハイギョ)に、ほとんどは左右1対ある(オーストラリアハイギョは1つ)。
これらに対しチョウザメ目・真骨類(条鰭類の他の全ての目を含む)は基本的に、呼吸機能を失った完全な鰾を持つ。
これらの鰾の気道は食道の背側に通じている。
鰾は背側にあり、また本来1対あった鰾が融合するか片方が失われ、1つになっている。
現生シーラカンスであるラティメリアは、脂肪で満たされた鰾を持つ。
ただしシーラカンスは、気体で満たされた鰾を持つ条鰭類よりも肺を持つハイギョに近い。
ラティメリアはシーラカンスの中では例外で絶滅した多くのシーラカンスはハイギョのような肺を持っていたとする説もある。
鰾は四肢動物やハイギョの肺と相同な器官である。
ダーウィンの時代には、魚類より四肢動物のほうが進化的な生物であるという理由から、鰾から肺が進化したと思われていた。
しかし、20世紀後半に硬骨類の進化の歴史が明らかになるにつれ、逆に、原始的な硬骨魚類は肺を持ち、一部の硬骨魚類で肺が鰾に変化したことが明らかになった。
脊椎動物は本来は海洋生物だったが、淡水へと進出した系統から硬骨魚類が誕生し、初期の硬骨魚類は、溶存酸素量が低下しやすい淡水生活の中で空気呼吸の必要から肺を発達させた。
その後、水中生活へ特に適応した系統が肺を鰾へと変えたと考えられる。
完全な鰾への進化は、条鰭類のうち真骨類とチョウザメ目のみ起こった。
他の条鰭類であるポリプテルス目、ガー目、アミア目の鰾(肺)は肺としての機能を残し、肺呼吸もおこなう。
条鰭類の姉妹群である肉鰭類では、肺がそのまま保たれた。
ハイギョや、系統的には四肢動物がそうである。
ただし現生シーラカンスのラティメリアは、肺は脂肪で満たされた鰾となっている(絶滅したシーラカンスについては不明である)。
肺を持つ魚類では、体を巡った血液は肺でガス交換をしてから心臓に還るため、心筋には十分な酸素が供給される。
しかし肺を失った魚類では、肺でのガス交換がないので、激しい運動時には心筋は酸素不足となり、持久力に欠ける。
にもかかわらず現在、肺の代わりに鰾を持つ魚類のほうが種数・個体数において成功しているのは、海鳥など飛翔する魚食動物の登場により、海面に上がって呼吸することが危険になったためともされる。
脊椎動物は本来は海洋生物だったが、淡水へと進出した系統から硬骨魚類が誕生し、初期の硬骨魚類は、溶存酸素量が低下しやすい淡水生活の中で空気呼吸の必要から肺を発達させた。その後、水中生活へ特に適応した系統が肺を鰾へと変えたと考えられる。
完全な鰾への進化は、条鰭類のうち真骨類とチョウザメ目のみ起こった。
他の条鰭類であるポリプテルス目、ガー目、アミア目の鰾(肺)は肺としての機能を残し、肺呼吸もおこなう。
サメ・エイなどの軟骨魚類は、硬骨魚類が肺を獲得する前に分岐したので、肺も鰾も持たない。
軟骨魚類は、肝臓に密度0.86の脂質であるスクアレンを蓄積することで浮力を得ている。
そのため、軟骨魚類の肝臓は巨大である。シロワニなどは口を通じて消化管に空気を入れることでも浮力を得る。
ハイギョは、条鰭類が肺を鰾に変化させる前に分岐したので、肺を持つ。ただしこれは原始的な条鰭類が持つ鰾(肺)と本質的に同じ器官であり、鰾と呼ばれることもある。
真骨類は祖先的に鰾を持つが、一部のものは二次的に鰾を失った。
底生性のアイナメ、ハゼ・カサゴ類の多く、カレイ目の成魚、活発に遊泳しないアンコウやコバンザメ、高い水圧のため気体での浮力の調節が困難な深海魚の多くなどである。
-------------------------------
消化管から肺が発生し、肺からうきぶくろが進化したことになる。
もう少し具体的に知りたい。
-------------------------------
引用:http://www.dev-neurobio.med.tohoku.ac.jp/students/lecture/pdf/med_dev/2017/med_dev_2017_19.pdf
肺の形状は:
.jpg)
肺の発生は:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
----------------------------------
まことに自然は計画的で正確である。
----------------------------------
2020.4.8
目次へ
肺胞の中に侵入したウイルスが、マクロファージに処理される過程を見てみたい。
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/membrane1976/27/5/27_5_244/_pdf
肺胞マクロファージは肺胞の中でユニークな位置付けにある組織特異的マクロファージである.
異物という実体が無い場合でも,免疫系は恒常性の制御に重要な働きをしている.
腫瘍壊死因子(TNF-α やTNF-β)が異物の侵入の無い胎児期にもあらゆる体細胞で構成的に発現している.
マクロファージは系統発生的にも高く保存された細胞であることが挙げられる.
人間での分布を見ると,ありとあらゆる臓器にマクロファージは存在している.
肺胞マクロファージと腸管マクロファージは,外部環境からの情報を受信出来る位置にあることになる.
肺胞マクロファージや腸管マクロファージは外部環境情報を受信して,これをプロセス
して細胞外に発信するという意味で恒常性制御に重要な役割を果たしているのではないかと考えられる.
空気は気道を通り,肺胞の隅々まで送り込まれる.
当然空気中に存在する微粒子も肺胞に送り込まれる.
肺胞に送り込まれる微粒子には一定の大きさとか,表面の性格とかの物理化学的制限があるが,おおかたの微生物などは肺胞に送り込まれると考えて良い.
肺胞壁には,Type 1とType 2の肺上皮細胞がある.
Type 1はガス交換,Type 2はサーファクタントプロテインを分泌している.
肺胞マクロファージは肺胞壁ばかりでなく肺胞腔の中にも存在している.
組織特異的マクロファージといえども共通の幹細胞から発生し,増殖し,移動して更に分化し,最終的に各組織特異的マクロファージに成熟すると考えられている.
肺胞マクロファージは他の組織特異的マクロファージに比べ寿命が長いと言われていること,肺内で分裂,増殖を行うことなどから,肺胞内にも前駆細胞があるのではないかとされている.
人の肺は表面積で約90m2あるとされている.
この表面積は腸管の表面積400m2についで,一個体が外部環境と接する単一器官表面として2番目の広さを持っている.
肺胞マクロファージの数は,一つの肺胞当たり10~50個,肺全体で2~3×1010個あると計算されている.
人間の全細胞数は約60兆と言われているので,約0.1%程度を占めていることになる.
.
肺胞マクロファージは外部環境と直接接点を持つので,外部環境刺激に応答して容易に活性化される.
活性化されると,― 般にサイトカイン産生が増強する.
O2ラジカルやNOなどの産生が増強する.
癌細胞傷害活性も増強するなど,いわゆる非特異的といわれる生体防御反応を増強することにつながる.
マクロファージが産生する代表的なサイトカインであるTNF-α の産生をみると,グラム陰性菌の細胞壁成分であるリポポリサッカライド(以下LPS)で肺胞マクロファージを刺激すると強力にTNF-α を産生することがわかる.
次に一酸化窒素,NOはバクテリアやウィルス等の侵入病原体に対する重要な傷害因子であるが,やはりLPS刺激で強い産生誘導が起こる.
TNF-α は膜結合型TNF-aの存在が知られている.
そして,この膜結合型TNF-α も生物活性を発現する.
膜結合型TNF-α を持つマクロファージは,一種のレギュレーターとして機能し,LPSに対する細胞応答を正にも負にも制御できる.
通常,微生物はマクロファージに貧食されると,食胞はH+-ATPaseの働きで酸性となり,ついでリソソームと融合して,リソソーム由来のプロテアーゼ例えばカテプシンDなどの働きで分解され処理される.
ところが,生菌を取り込んだ場合には食胞とリソソームの融合が起こらず,結核菌は食胞内で生き続ける.
これが結核菌の慢性感染の状態である.
-----------------------------
貪食したマクロファージが、血液またはリンパ液にもどるのかがわからない。
-----------------------------
引用:http://kachikukansen.org/kaiho2/PDF/1-3-105.pdf
肺での感染防御機構も自然免疫と獲得免疫に大別される。
徴生物の侵入門戸の気道ではまず粘膜上皮細胞が病原体をとらえ、外へと運び出す機能を持つ繊毛をそなえている。
マクロファージは気管支、肺胞、肺間質に存在し、サーファクタント等を介して病原体をとらえて消化し、喀痰とともに排出する。
----------------------
なるほど、喀痰か
----------------------
肺胞マクロファージは抑制性サイトカインを産生して過剰な炎症による肺上皮障害を防御する恒常性維持機構としても働く。
気管支粘膜にはマスト細胞が多く存在する。
感染局所でマスト細胞が活性化されると、顆粒内のヒスタミンやセロトニン等の血管透過性因子が放出され生体防御を担う細胞性因子や液性因子が血管外へと放出される。
自然免疫リンパ球(innate lymphocytes)と呼ばれるナチュラルキラー(natural killer;NK)細胞、γδ型T 細胞やNK マーカーをもったNKT 細胞は細菌の感染細胞の発現
する細菌由来または自己細胞由来の成分を認識して活性化され、感染細胞を傷害する。
気管支周辺のリンパ組織も粘膜関連リンパ組織の特徴をそなえている。
抗原を認識したCD4+Th 細胞はインターフェロン-γ(IFN-γ)を産生して細胞内寄生病原体の排除に働くTh1 細胞、インターロイキン4(IL-4)、IL-5 を産生してB 細胞にIgA を産生せるTh2 細胞、IL-17 を産生して好中球を集族するTh17 細胞、さらにFβ/IL-10 を産生して肺の恒常性維持にはたらく調節性Treg 細胞がある。
CD8+T 細胞はそのキラー活性でウィルス感染細胞を排除するが、過剰の応答で肺障害を引き起こす。
慢性感染症ではPD-1 などの抑制分子発現して疲弊エフェクターT 細胞となり過剰反応を自ら抑制する。
自然免疫を担う細胞性因子の代表として、好中球やマクロファージなどの食細胞が挙げられる。
これらの細胞は、細菌由来のくり返しパターン、病原体関連分子パターンpathogen-associated molecular pattern(PAMP)を認識するパターン認識受容体Pattern recognition receptor(PRR)で、迅速に貪食、排除を行う。
自然免疫リンパ球(innate lymphocytes)と呼ばれるナチュラルキラー(natural killer;NK)細胞、γδ型T 細胞やNK マーカーをもったNKT 細胞は細菌の感染細胞の発現する細菌由来または自己細胞由来の成分を認識して活性化され、感染細胞を傷害する一方で、サイトカインを産生して獲得免疫を方向づける自然免疫と獲得免疫との橋渡し的役割を担う。
獲得免疫を担うT 細胞およびB 細胞は細菌由来の抗原で活性化され、直接的に細胞傷害活性で感染細胞を排除し、サイトカインや抗体を産生して自然免疫と共同で、効率よく細菌の排除を行う。
細菌が完全に排除され、戦いが終了するとほとんどの活性化リンパ球はアポトーシスで細胞死を起こし、免疫反応が終息する。
一部のリンパ球は記憶細胞となり、再感染時には迅速に応答して感染防御を行う。
細菌の侵入を防ぐ第一線のバリアーとしてまず皮膚や粘膜の機械的バリアーがある。上皮細胞間はアドヘレンス・ジャンクション、タイトジャンクション、デスモソームといった特殊化した接着構造を形成して病原体の侵入を防ぐ。
気管支上皮線毛の運動は細菌を粘液とともに痰として体外に追い出す。
上皮系から産生される物質は化学的バリアーとして防御に働く。
気管の粘膜上皮はムチン層で被覆されており、病原細菌の侵入を阻害している。
細気管支までにみられる杯細胞や細気管支以降にみられるクララ細胞からはムチンのみならず、抗菌ペプチドであるαデフェンシンが産生される。
粘液中のリゾチームはグラム陽性菌の細胞壁の成分であるムコペプチドのN- アセチルグルコサミン(N-acetyl glucosamine)とN- アセチルムラミン酸(N-acetyl muramic
acid)間の結合を切ることによって殺菌する。
ラクトフェリンは鉄をキレートして細菌の増殖をふせぐ。
肺胞の表面張力を減少させる肺サーファクタントはII 型肺胞上皮細胞から産生され、そのタンパク質成分には、肺サーファクタントタンパク質(SP)-A ~ D(SP-A ~ D)が
ある。
SPA とSPD はC タイプレクチンのコレクチンファミリーに属しており、パターン認識
分子として細菌表面に結合し、また補体のレクチン経路を活性化して貪食を促進する。
常在細菌叢は生物学的バリアーとして感染防御に重要な役割を果たしている。
その感染症防止の機序としては、炭素源、エネルギー源の競合、還元電位の著名な低下、pH の低下、乳酸や遊離脂肪酸の産生およびバクテリオシン(コリシン)などの抗生物質様産物の産生などが考えられる。
鼻咽腔には多数の微生物が存在する。
鼻前庭部には好気性菌として表皮ブドウ球菌(Staphylococcus epidermidis) のほか、コリネバクテリウム属(Corynebacterium)黄色ブドウ球菌(S. aureus)がしばしば見いだされる。
この黄色ブドウ球菌のなかでとくにメチシリン耐性株(MRSA)の病院内感染における
感染源として重要視される。鼻腔は多くの呼吸器系感染症の原因微生物の入口であるため、一時的にではあるが、肺炎球菌(Streptococcus pneumonia)、インフルエンザ桿菌(Haemophilus influenza)、髄膜炎菌(Neiseria meningitides)などの病原微生物が定着する場所でもある。
これらの菌が定着しても、必ずしも発病するとはかぎらないが、宿主の免疫不全で発病する危険がある。
気管、気管支、肺胞などの下部気道には菌は少ない。
気管や気管支においては上皮細胞の線毛(繊毛)の運動によって微生物は排出され、肺胞では肺胞マクロファージにより処理されるためである。
上皮系によるバリアーを乗り越えて組織内に侵入してきた病原細菌に対して、まず補体が働く。
細菌の侵入では細菌表面でまず第2 経路が直接活性化され、つづいてサーファクタント蛋白質がレクチン経路を活性化する。
種々の活性断片を産生しながら、最終的にはC5b-9 複合体(膜侵襲結合体)となり、ナイセリア(Neisseria)などの一部の細菌の細胞壁にトンネル構造を作り溶菌する。
補体の活性化断片(C3a、C5a)は、組織内のマスト細胞からヒスタミンなどを放出させて、血管の透過性を亢進させる。
その結果、血管内の好中球や単球などが血管外に遊出し、さらに走化性因子であるC5a によって引き寄せられて、炎症部位、すなわち異物侵入部位に集合する。
細菌表面に補体の活性断片(C3b、iC3b)が付着すると、細菌は組織内の好中球や
マクロファージなどの食細胞の補体レセプター(CR1、CR3 など)を介して認識される。
マスト細胞がToll 様レセプター(TLR)等のパターン認識レセプター(PRR)で細菌成分を認識するとサイトカインが産生される。
サイトカインには腫瘍壊死因子tumor necrosis factor(TNF)-α、IL-1、IL-6 などの様々の炎症性サイトカインがあり、血管透過性因子として働き、さらに食細胞の血中からの放出を促進する。
感染によって誘導されるサイトカインのなかにはケモカインと呼ばれるファミリーに属するものが、マクロファージのみならず、内皮細胞、皮膚のケラチノサイト、線維芽細胞や平滑筋等により産生される。
ケモカインは白血球の血管外移動に重要な役割を担う。
ケモカインファミリーはαとβに分類され、αグループではIL-8が代表で有り、マクロファージ走化因子はβグループの代表である。
これらケモカインは白血球に対して血流中の細胞の動きを富め、濃度勾配に従って感染局所に細胞を動員させる。
ウィルス感染のみならず細菌感染によってもI 型IFN-αとβが産生される。
IFN-αは白血球が、IFN-βはおもに線維芽細胞がその産生細胞である。
I 型IFN はウィルス感染防御機構として働く一方で、IL-10 の産生を促進して過剰
な炎症による正常組織傷害を防止していると考えられる。
肺には気管支マクロファージ、肺胞マクロファージ、間質マクロファージの3 つのマクロ
ファージが存在す
起源はすべて血液単球由来と考えられる。
マクロファージは一般にその機能より、M1 型とM2 型に分類される。
M1 マクロファージはIFN-γなどのTh1 サイトカインに反応して、細胞内寄生性病原体を排除し、M2 マクロファージはIL-4 などのTh2に反応して死細胞を貪食する。
肺胞マクロファージはF4/80 + CD11bintermediateCD11c+ CD200R のマーカーをもち、病原体排除のために感染防御の第1 線として働く一方で、炎症を抑制して肺上皮細胞の再生を促進することによって肺の恒常性維持に働く。
リポ多糖体(LPS)への低応答性、MHC クラスII とcoaccessory molecules(CD80、CD86)の低下による抗原提示不全、さらに抑制サイトカインであるIL-10、TGF-βを産生する。
またNO 産生による炎症性サイトカイン産生を抑制する。
これらマクロファージや血中から遊走してきた好中球は細菌由来高分子多糖体やリポタンパク等のPAMPs を一群のPRR によって認識する。
貪食された細菌は食胞( ファゴソームphagosome)として細胞内にとりこまれる。
ファゴソームは細胞膜が被膜化したもので、その中では酵素依存性の活性酸素や一酸化窒素(NO)と酵素非依存性の塩基性蛋白質、ラクトフェリン、リゾチームなどが、細胞内殺菌を担っている。
異物と食細胞間の結合によって膜のNADPH オキシダーゼが活性化され、O2-(superoxide anion)などの活性酸素reactive oxygen intermediate(ROI)が産生され、強い殺菌作用を示す。
ファゴソームがリソソームと融合してファゴリソソームphagolysosome が形成されるとミエロペルオキシダーゼmyeloperoxidase(MPO)やハロゲンによって次亜塩素酸(HOCl-)等が生成される。
一方、細菌は活性酸素に対してスーパーオキシドジスムターゼsuperoxide dismutase(SOD) やカタラーゼ(catalase)を有することによって抵抗する。
LPS やIFN-γで活性化されたマクロファージはNO 合成酵素が発現し、NO に代表される活性窒素reactive nitrogen intermediate(RNI)が産生され結核菌等が比較的抵抗性の高い細胞内寄生性細菌に対して傷害する。
--------------------------
病原体を貪食したマクロファージは、アポトーシスによって死亡し、痰に含まれて体外に排出される、ということだ。
肺胞の構造を見てみると、
気管支の上皮細胞には繊毛があるが、肺胞Ⅰ型上皮細胞とⅡ型上皮細胞には繊毛があるのだろうか。
--------------------------
引用:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/life/%E5%A4%A7%E6%B0%97%E6%B1%9A%E6%9F%93%E3%81%A8%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89.pdf
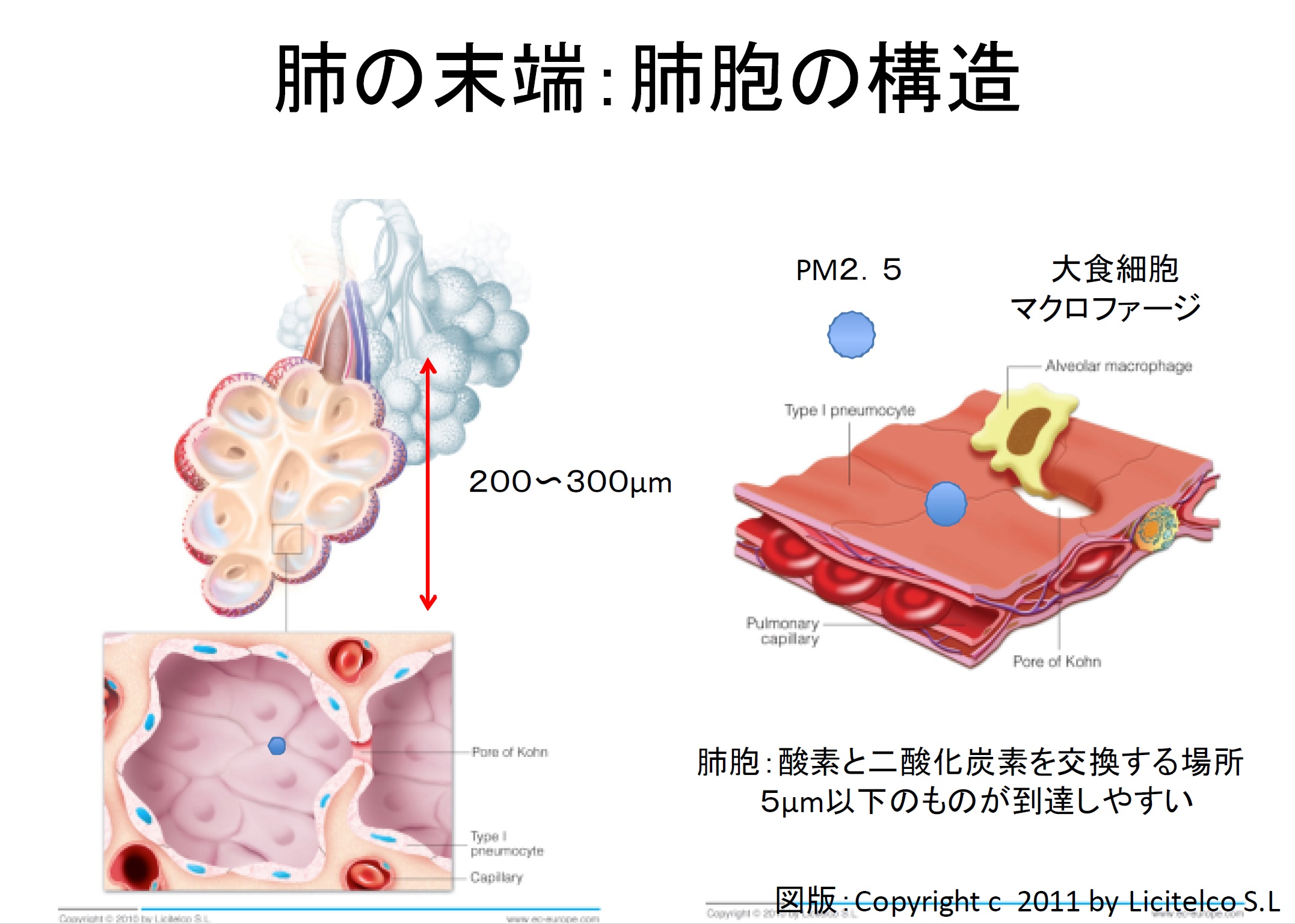
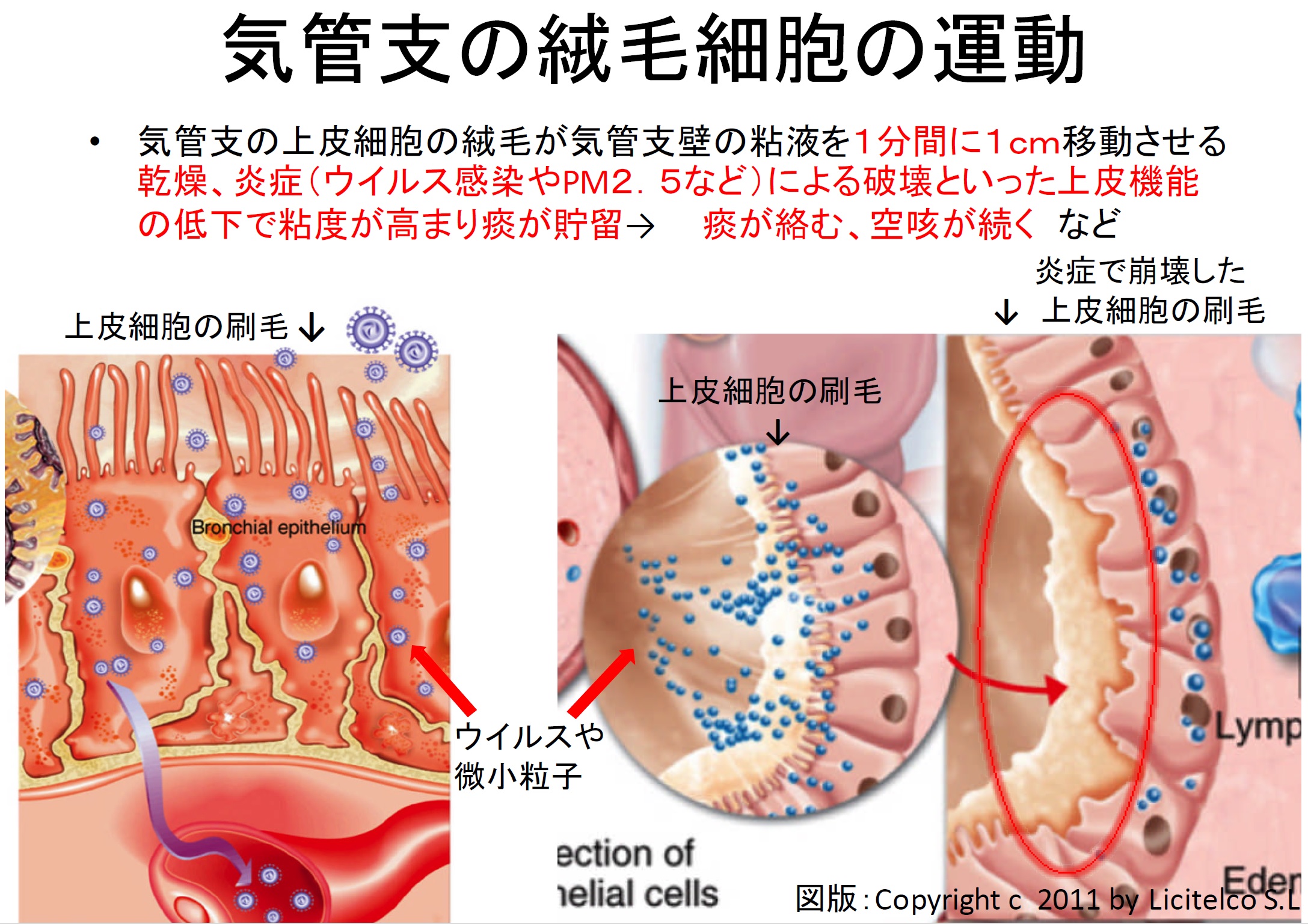
--------------------------
いままで調べたところを、わかりやすく理解したい。
--------------------------
引用:https://kotobank.jp/word/%E5%91%BC%E5%90%B8%E5%99%A8%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%BF%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%8D-792079
◎呼吸器のしくみ
肺は左右に2つあって、右肺は、上葉(じょうよう)、中葉(ちゅうよう)、下葉(かよう)に分かれ、左肺は、上葉と下葉に分かれています。
右肺のほうが左肺より少し重いのですが、体重60kg程度のおとなでは、片方だけで350から400gほどの重さがあります。
肺は、空気の取り入れと放出をおもな役目としている気道(きどう)と、酸素を血液中に取り入れて血液中の二酸化炭素を排出するガス交換(こうかん)をおもな役目とする肺胞(はいほう)とに分けることができます。
気道の大部分と肺胞の全部は、肋骨(ろっこつ)、脊椎(せきつい)、肋間筋(ろっかんきん)、横隔膜(おうかくまく)に囲まれてできた、胸郭(きょうかく)と呼ぶカゴのようなものの中に収められています。そして、胸郭が収縮・拡張運動をくり返すことによって、肺の中に空気が取り入れられたり、押し出されたりするポンプのようなはたらきがなされます。
●気道(きどう)
気道とは、空気中の酸素を肺胞に導き入れ、肺胞内の二酸化炭素を外界へ排出する導管のことです。
気道は、口や鼻孔(びこう)から順に、口腔(こうくう)→鼻腔(びくう)・副鼻腔(ふくびくう)→咽頭(いんとう)→喉頭(こうとう)→気管(きかん)→気管支(きかんし)→細気管支(さいきかんし)という経路になっていますが、鼻腔・副鼻腔から喉頭までを上気道(じょうきどう)、気管から細気管支までを下気道(かきどう)と呼びます。
気管支は、2本、2本としだいに分かれていき、平均すると16回の枝分かれをしたのち、細い終末気管支となります。終末細気管支には、ガス交換の機能がありませんので、非呼吸細気管支と呼ばれます。
●呼吸細気管支(こきゅうさいきかんし)
終末細気管支と肺胞の間に呼吸細気管支があります。
呼吸細気管支の周囲には、少数ですが、肺胞が付着しており、ガス交換が行なわれています。
●肺胞(はいほう)
肺胞は、肺にきている動静脈(どうじょうみゃく)の毛細血管(もうさいけっかん)に付着している小さな泡のような組織です。
成人では約3億個の肺胞があり、ガス交換を行なっています。
肺胞の薄い壁は、つぎのようなはたらきのちがういくつかの細胞からできています。
肺胞上皮細胞(はいほうじょうひさいぼう) Ⅰ型とⅡ型があります。
Ⅰ型肺胞上皮細胞は肺胞壁の96%を占める細胞で、ガス交換を行なっています。
Ⅱ型肺胞上皮細胞は肺胞壁の5%を占める立方形の細胞で、肺胞の表面を滑らかにし、肺胞がつぶれずに空気の出入りができるようにする物質(肺胞表面活性物質(はいほうひょうめんかっせいぶっしつ))の産生と分泌(ぶんぴつ)を行なっています。
また、この細胞はⅠ型肺胞上皮細胞に変化します。
肺胞(はいほう)マクロファージ 肺胞の壁を移動しながら、肺胞内に侵入した異物をのみこんで処理したり(貪食(どんしょく))、殺菌したりする大型の細胞です。
●肺間質(はいかんしつ)
呼吸という肺のはたらきには直接には関与しない組織を肺の間質と呼びます。正確にいうと、肺胞上皮細胞下の基底膜(きていまく)と、毛細血管内皮細胞とを境とするまばらな結合組織からなる部分で、肺胞と毛細血管を結合させている組織です。
肺胞の中に炎症がおこった場合を肺炎(はいえん)といい、肺間質に炎症がおこった場合は間質性肺炎(かんしつせいはいえん)と呼びます。
●肺の血管
からだ全体の組織に栄養や酸素などを運び(動脈)、老廃物や二酸化炭素などを回収する(静脈)血液の循環・流れを大循環系(だいじゅんかんけい)といいますが、これとは別に、ガス交換のために肺と心臓との間にある血液の循環・流れを小循環系(しょうじゅんかんけい)と呼んでいます。
そのため、肺の血管には、肺血管系(小循環系)と気管支血管系(大循環系)の2つがあります。
肺血管系(はいけっかんけい) 肺のもっとも重要なはたらきであるガス交換を担当している血管です。
(心臓の右心室(うしんしつ))→肺動脈→肺毛細血管→肺静脈→(心臓の左心房(さしんぼう))の経路で流れています。
酸素が少なく二酸化炭素の多い静脈血の流れる肺動脈(ふつうの動脈とは機能が反対であることに注意)は、右心室から出て、気道系と平行して走り、毛細血管となる部分でガス交換(二酸化炭素の放出と酸素の取り入れ)を行ない、酸素が多く二酸化炭素の少ない動脈血となって肺静脈に入ります(ふつうの静脈とは反対であることに注意)。
肺静脈は気道系とは関係なく走っており、左心房にもどります。
気管支血管系(きかんしけっかんけい) 呼吸器の各臓器への酸素と栄養の供給、二酸化炭素と老廃物の回収を受け持っている血管です。
気管支動脈は、胸部大動脈から分かれ、食道(しょくどう)、縦隔(じゅうかく)、肺門(はいもん)の部分にあるリンパ節などに小枝をだしながら、肺門部にいたり、主気管支に沿って肺内に入り、毛細血管になります。
呼吸細気管支までの気管支壁と肺動静脈、リンパ節、神経などの機能維持に関与しています。
●肺のリンパ系
リンパ液の流れるリンパ系は、体液量のバランスを保つはたらきを担っています。
肺胞にはリンパ管はありませんが、肺の毛細血管からもれ出てきた組織液(体液)は、間質の間を流れてリンパ管に流れ込みます。
そして、リンパ節、またリンパ管を経て、最終的には静脈に入る経路をとっています。
●胸膜(きょうまく)
胸郭の大部分は、皮膚(ひふ)、肋骨(ろっこつ)、肋間筋(ろっかんきん)、内側をおおう胸膜からなる胸壁(きょうへき)です。
胸膜は、外側の胸膜(壁側(へきそく)胸膜)と内側の胸膜(肺側(はいそく)胸膜)とで成りたっています。
健康な人でも、壁側胸膜で胸水(きょうすい)がつくられ、肺側胸膜から吸収されていて、胸腔内(きょうくうない)には、常に10~20m?の胸水が存在します。
◎呼吸器のはたらき
呼吸器には、①呼吸=酸素と二酸化炭素の交換をする、②防御=からだを外界から守る、③代謝=必要な物質をつくる、の3つのはたらきがあります。
●呼吸機能
呼吸をすると空気は気道(呼吸細気管支)から肺胞に入り、肺胞壁で空気中の酸素と二酸化炭素の交換が行なわれます。
肺胞の周りには、毛細血管がはりめぐらされていて、二酸化炭素を多く含んだ静脈血を、酸素を取り込んだ動脈血に変えるのです。
酸素が気体から液体に移り(拡散(かくさん))、取り込まれた酸素は肺血管系によって心臓に到達して、全身に送り出されます。
二酸化炭素の排出は、これと逆の過程で行なわれます。脳の呼吸中枢(こきゅうちゅうすう)と呼ばれる部分が、神経・内分泌系を通じてこのような過程をコントロールしています。
●防御作用
肺には、1日に1万リットルもの空気が出入りしています。
したがって、肺は吸入される空気とともに運び込まれるさまざまの異物(いぶつ)にさらされます。
これらの異物は、有害なものから比較的無害なものまで、さまざまです。
また、吸入した空気に含まれる異物に加えて、口の中(口腔(こうくう))や咽頭(いんとう)で分泌されたものが、気管・気管支にまで吸引されることもあります。
異物は、小粒子(しょうりゅうし)、有害ガス、微生物の3つに分類できます。
とくに口腔や咽頭には細菌類が常在していますから、肺に吸引された分泌物が思わぬ細菌の侵入源となることもあります。
また、肺の毛細血管には、肺血管系(小循環系)を通じて、微生物を含む各種の物質、抗原(こうげん)、抗体(こうたい)、免疫複合体(めんえきふくごうたい)などが侵入してくる可能性もあります。
このように、肺は、外因性、あるいは内因性物質によってさまざまな障害が頻繁(ひんぱん)におこっても不思議がないようにみえます。
ところが実際には、種々のしくみによって、外来の異物の排除が行なわれたり、異物と生体の反応がコントロールされたりして、肺は守られているのです。
肺の防御作用には、免疫反応の関係しない防御作用(浄化作用)と、免疫反応の関係する防御作用があります。
浄化作用は鼻腔から肺胞にいたる肺のあらゆるところで行なわれています。
免疫反応とは、以前に体内に侵入したことがある異物(抗原)に抗体ができており、再び同じ異物(抗原)が入ると抗原抗体反応がおこり、抗原である異物を処理してしまう作用ですが、肺のあらゆるところでみられるはたらきです。
このように、肺の防御作用には大きく2種類ありますが、より大きなはたらきをしているのは浄化作用です。
●代謝作用(たいしゃさよう)
肺では、肺のはたらきを維持するエネルギーをつくるのに必要な代謝だけでなく、肺表面活性物質の産生、さまざまな血管に作用する物質の産生や代謝、また、いろいろな臓器の調節にかかわっているプロスタグランジンの産生や代謝なども行なわれています。
◎おもな呼吸器疾患の症状
呼吸器の病気では、せき、たん、血(けっ)たん、喀血(かっけつ)、呼吸困難、胸痛などの症状がみられます。
●せき(咳)
気道の中に侵入してきた異物を排除するための反射的な反応で、呼吸器が外来性の異物に侵入されることを防いでいる重要なからだのしくみです。
せきには、たんをともなっている場合(湿性咳(しっせいがい))と、たんをともなってはいない場合(乾性咳(かんせいがい)あるいはからせき)があります。病気の種類によって、乾性になったり、湿性になったりします。
●たん(痰)
気道の分泌物に、細かなちりや、ほこり、細菌、気道からはがれた細胞などが加わった混合物です。
健康な人では、たんに気づくことは、あまりなく、たんに気づくのは気道の分泌物過多、気道の閉塞(へいそく)など、たんを出すしくみがうまくいかない場合です。
喫煙者では、軽い気道の炎症がたえずおこっているので、たんがみられることが少なくありません。
細菌やウイルスなどによる気道の感染がおこると、たんが増加します。
また、肺の中でアレルギー反応がおこった場合には、水様のたんがみられます。
2020.4.9
目次へ
肺胞腔の中で、異物、細菌、ウイルスなどを貪食してアポトーシスしたマクロファージが痰として体外に排出されるということだが、肺胞上皮細胞にも繊毛があるのだろうか。
それとも、Ⅱ型肺胞上皮細胞が傷害を受けてサーファクタントの分泌が減少して肺胞が萎み、その結果、肺胞腔内の死滅したマクロファージが気管支に追い出され、それからは気管支の絨毛細胞の運動で痰として排出されるのだろうか。
もしそうだとすると、萎んだ肺胞は再生するのだろうか。
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jst/52/1/52_031/_pdf
肺は肝臓などと異なり,一般に再生しない臓器と考えられている。
その一方で,細胞レベルでは肺傷害ののちに修復される過程で,幹細胞(または前駆細胞)が肺組織へと分化する現象が確認され,機能回復という意味での再生現象は確認されつつある。
骨髄に幹細胞があることは広く知られている。
この骨髄由来の間葉系幹細胞が心筋細胞や血管内皮細胞,神経細胞など他の組織において分化し,組織再生に寄与していることが明らかになっていることから同様の
再生機序が肺においても期待された。
Kleeberger らは骨髄移植後のヒト肺において,ドナー由来の細胞がレシピエントのII 型肺胞上皮細胞や気管支にあることを示した。
動物モデルでも,骨髄由来の間葉系幹細胞が肺の傷害部位に局在し,肺細胞としての形質を示し組織修復に寄与していると報告された。
その一方で,しばしば骨髄由来の細胞は上皮転換し組織に組み込まれることなくその組織修復機能・保護機能を示すことから,直接的な再生というよりも液性因子などを
介した間接的な再生に寄与しているとも考えられている。
これらの知見をもとに,間葉系幹細胞による細胞移植の治験が行われているが,現在のところその結果は限定的で肺移植に代わるものとは言い難い。
より直接的に傷害肺の修復に関与する細胞ソースとして,組織幹細胞も注目されている。
以前よりII 型肺胞上皮細胞は肺胞を主に構成しているI 型肺胞上皮細胞に分化することに加え,肺胞におけるサーファクタントの産生や恒常性の維持に関与していることが知られている。
動物レベルではII 型肺胞上皮の気道移入モデルでブレオマイシン肺傷害モデルが修復されることが示された。
特発性間質性肺炎において,ヒトを対象とした臨床試験も始まっておりその安全性が検証されている。
さらに,倫理的な問題や免疫系の問題をクリアし,安定して供給可能なiPS 細胞由来のII型肺胞上皮細胞にも注目が集まっている。
細胞レベルでは分化にも成功しており,今後の細胞移植治療への応用が期待されている。
II 型肺胞上皮細胞は肺胞における前駆細胞であり,多能性は持たない。したがってより上流にある多能性幹細胞に修復を超えた再生の期待がかかっている。
2011 年に報告されたヒト肺幹細胞36)は上皮のみならず,血管内皮など他の肺の構成要素への分化が確認された。
2015 年に報告されたKrt5 陽性細胞は,肺胞上皮だけでなく気管支上皮にも分化することが確認されている。
これらの細胞による包括的な再生は,将来的に移植に代わる新しい治療のアプローチとなる可能性を秘めている。
----------------------------
肺胞上皮細胞は再生するようだ。
----------------------------
引用:https://jpn.kibrisdoktor.com/3899617-alveolar-macrophages-in-sputum-normal-and-abnormalities-causes-of-change-in-quantity-effects
人が息を吸うと、最初に鼻の副鼻腔の中のほこりが空気から完全に取り除かれ、次に汚染その他の異物の粒子が原則として気管の壁に落ち着きます。
その後、気管支内で濾過が続けられ、そこでは、特殊な細胞によって分泌される粘液中に外来の微視的断片が沈み込み、繊毛によって呼吸器系から追い出される。
汚染および微生物からの気管支洗浄のために、繊毛は毎秒千回振動する。 (蚊は、ほぼ同じ周波数で飛行しているときに羽を振る)
これらのフィルターをすべて通過した後でも、肺に入る空気はまったく100パーセントきれいなわけではありません。
まだ微視的なほこりなどと共に微生物が存在する可能性があります。
実際、これらはマクロファージによって貪欲にされ消化されます。
肺胞マクロファージは、食作用を起こした後すぐに死ぬが、その前に、呼吸細気管支(肺胞に通じる最小の気管支)の基部に行って粘液に浸透し、排出される。
----------------------------
肺胞腔内には繊毛はなく、肺胞マクロファージは自分で気管支の基部に移動し、そこで粘液に潜り込んでから、死ぬようだ。
なんという自己犠牲。
----------------------------
2020.4.10
目次へ
新型コロナウイルスの場合、肺胞の中が異常を起こすのが原因かと思っていたが、間質性肺炎を起こすのが主因か。
引用:https://ameblo.jp/indianlegend/entry-12570833782.html
肺胞がブドウの房のように構成されているのを、小葉という。
小葉同士の間を間質といい、間質性肺炎では間質が病変の主体となり、円生と繊維化が起きる。
線維化とは膠原繊維ができてくることで、このために肺胞がふくらみにくくなる。
これが肺の実質まで進展すると、肺実質そのものをつぶし、肺組織の構築が変わる。
引用:https://kanwa.tokyo/coronavirus-interstitial-pneumoniae
確かに、新型コロナウイルスは、間質性の炎症を起こします。
しかし「新型コロナウイルスは間質性肺炎である」という説は正しいのでしょうか?
ウイルスは2つのタイプの肺炎を起こしえます。
●呼吸器系ウイルスによる肺炎
病変が経気道的に拡がり、気管支、細気管支、肺胞に病変が認められ、初期には気管支肺炎に類似した所見。
※代表的ウイルス;インフルエンザウイルス、ヒトRSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、パラインフルエンザウイルス、アデノウイルス、SARSウイルス
●ウイルス血症に伴う肺炎
すりガラス様陰影、網状影、小粒状陰影などがびまん性に認められる。血液に乗って肺に到達し間質性の炎症を起こす。
※代表的ウイルス;サイトメガロウイルス、 水痘・帯状疱疹ウイルス、単純ヘルペスウイルス、 麻疹ウイルス
前者は気道を通って肺にやって来て、気管支や肺の実質(肺胞という肺の中の小さな袋)を侵します。
後者は血液に乗って肺に到達し、肺胞の外側の壁の部分(間質)を侵すのです。
しかし前者であっても、肺の間質にまで影響を及ぼすことがあります。
そのため、ウイルス性肺炎も様々な肺炎像を呈し、例えば新型コロナウイルスもそうであるとすでに指摘されています。
重症の間質の炎症から肺の線維化を起こす
ウイルス性肺炎も重症でなければ一過性の間質などの炎症で改善してきます。
しかし時には、強い間質の炎症から、肺が繊維化といって硬くなってしまうことがあるのです。
ウイルスでの線維化が報告されています。
・サイトメガロウイルス、アデノウイルス、麻疹ウイルス、SARS(重症急性呼吸器症候群)ウイルス
なかでもSARSは、ウイルスによる肺の線維化が注目されるようになったある種代表的な病気です。
ウイルス性の肺炎は、全例が線維化を来すわけではありません。
一般的にはウイルス性の肺炎は「間質性肺炎」と呼ばないことが多いです。
また、間質性肺炎と診断したものが、新型インフルエンザによる肺炎とわかったため診断を変更した文献もあります。
特発性間質性肺炎は原因不明の進行性の間質性肺疾患です。
次第に肺が線維化し呼吸不全を来し、予後も厳しい病気です。
このように原因不明の進行性病変が、新型コロナウイルスによる肺炎で(必ず)起こると心配されてしまったようです。
しかしこれは別の病態であり、新型コロナウイルス肺炎の軽症や中等症でこのような線維化を起こすことは一般に考えにくいと思われます。
肺の線維化のマーカーであるKL-6やSP-Dがあまり上がっていない事例もあったり、肺胞上皮傷害に伴う線維化(間質性変化)を主体としたものではなく高度炎症が主体の可能性などが指摘されています。
特発性間質性肺炎とはまた違った病態であることが透けて見えます。
---------------------------------
この所見では新型コロナウイルスが間質性肺炎を起こす可能性は低いようだ。
しかし、次のような所見もある。
---------------------------------
引用:https://news.goo.ne.jp/article/postseven/trend/postseven-1548812.html
目、鼻、口などの粘膜を通じて体内に侵入したウイルスの多くは、鼻や咽喉などの上気道で食い止められる。すると咳やくしゃみといった風邪に似た症状は出るものの、通常は重症化しないと考えられる。
しかし、ウイルスが上気道から下気道を通過して肺に到達すると「肺炎」を罹患して重症化リスクが一気に高まる。
「肺炎は、原因となる微生物の種類で分類されます」と説明するのは、神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科部長の小倉高志医師だ。
「肺炎球菌や黄色ブドウ球菌などの細菌が原因で発症する『細菌性肺炎』は、湿った咳とともに黄色や緑色を帯びた痰が出ることが特徴です。
マイコプラズマやクラミジアなどの微生物が原因で発症する『非定型肺炎』は、乾いた咳が長く続きます。
インフルエンザウイルスや麻疹ウイルスなど様々なウイルスが原因で起こる『ウイルス性肺炎』は、風邪の症状に続いて激しい咳や高熱、倦怠感が生じます。もちろん、新型コロナウイルスによる肺炎はウイルス性肺炎の一種です」
「細菌性肺炎は、気道の末端にある『肺胞』という小さな袋の中に炎症を起こす『肺胞性肺炎』の形をとります。この肺炎はCTで濃い陰影を示します。
一方で肺胞と血管の間にある『間質』に炎症を起こす『間質性肺炎』は、間質が線維化して硬くなり、肺から体内に酸素を取り込めなくなって呼吸困難に陥るケースがあります。間質性肺炎はCTでは肺胞性肺炎とは異なるすりガラスのようなぼやけた陰影を示します」(小倉医師)
今回の新型コロナのようなウイルス感染の場合は間質性肺炎が主体とされ、武漢で発症した日本人が急性間質性肺炎と診断された症例がある。
「どのタイプの肺炎も基本的に糖尿病や心疾患、呼吸器疾患などの慢性疾患を持つ人や、病気の治療中などで免疫力が低下している人が発症しやすい」(小倉医師)
新型コロナウイルスで重症化リスクがあると指摘される因子と重なってくるところが多いのだ。
--------------------------------
間質か肺胞か、いずれかにまたは両方に炎症を起こしていると思われる。
--------------------------------
2020.4.13
目次へ
もうすこし調べてみたい。
引用:https://sinsd.com/post-4682
新型コロナウイルスは約8割の人が感染しても症状が軽いようです。
逆に、2割の方は重症である上に、さっきまで新聞を読んでいた患者が2時間後には急変して亡くなるというケースもあるようです。
この重症化で重要なポイントはサイトカインストームだと考えるのが妥当だと考えています。
サイトカインストームは「サイトカイン」の「嵐」という意味ですが、要は新型コロナウイルスに感染したとき、サイトカインが大量分泌されると重症化すると考えていいと思います。
サイトカインは細胞から分泌される低分子のタンパク質で生理活性物質の総称です。
ホルモンと同じように体に必要な生理作用を及ぼしますが、ホルモンが全身性である一方で、サイトカインは分泌した細胞近辺で生理作用を発揮します。
例えば、ウイルスに感染した細胞が炎症を促すサイトカインを分泌します。
すると、その周囲の血管が拡張しそこから血漿成分(血液)が間質液に漏れ出します。
このとき、同時に免疫細胞が漏れ出してウイルスと戦ってくれます。
肺は「肺胞」と呼ばれる袋(細胞)が集まっている臓器です。
肺胞と肺胞の隙間には血管やリンパ管、それらを支える間質で満たされています。(実際は、肺胞と血管は密着している部分が多くあります)
呼吸をすると、空気中の酸素が気管と気管支を通じて肺胞に入ります。
この酸素が間質に漏れ、それが血管に吸収されて心臓に集まり、全身に運ばれます。
一般に「肺炎」の多くは「細菌」が原因で起きる細菌性肺炎です。
鼻や口から細菌が侵入し、気管を通って肺胞にたどり着いて感染します。
肺胞が炎症物質(サイトカイン)を放出し、その周囲の血管が拡張します。
そこから血漿成分が漏れ出し免疫細胞が細菌を退治しようと働きます。
この滲出した血漿成分が肺胞を水浸しにします。
こうなると空気を吸っても酸素が湿潤した血漿成分に邪魔され、血管に取り込めなくなります。それで息苦しくなります。
肺胞に入った液体は痰になります。
新型コロナなど「ウイルス性」肺炎では、免疫が暴走することで起きる炎症が重症化に大きな影響を与えていると疑われています。
これがサイトカインストームで、これらは「間質」や「血管」に炎症を起こして傷つけていることがわかっています。
新型コロナウイルス肺炎に関しても、死亡した方の血管や間質からはウイルスが検出されなかったという報告が出ています。
このことからも、ウイルスによる肺の直接的な傷害よりもサイトカインストームのダメージが大きいことを示唆しています。
・オメガ6:炎症を促す。血を固める。アレルギー促進
・オメガ3:炎症を鎮める。血液サラサラ。アレルギー抑制
この事実と上記の死亡患者からの報告を重ね合わせると、重症化には次のようなメカニズムが働いていると想像できます。
1.死亡した方の血管や間質からウイルスは検出されなかった
2.肺胞からは炎症性サイトカインが放出されている
3.肺胞にオメガ6が多ければ過剰にサイトカインが放出
4.たどり着いた免疫細胞はサイトカインからの情報に過剰に反応
5.その結果、正常組織である間質や血管を傷つけてしまう
ここでの重要なポイントは、新型コロナウイルスは肺に感染しますが、これによる自律神経の緊張により全身の細胞にそのシグナルが伝達されることです。
そのシグナルにより、全身の細胞に入るオメガ6が炎症性サイトカインを放出する。
だからこそ、本来局所的な働きをするサイトカインの免疫反応の弊害が全身で起き、免疫細胞による正常細胞への攻撃が続くと考えられます。
理屈はアレルギー症状と同じです。
例えば、本来は花粉でアレルギーは起きません。
しかし、オメガ6が多ければ炎症性サイトカインが過剰に分泌されてしまいます。
免疫細胞は、炎症性サイトカインのシグナルが続く限り過剰に働きます。
大雑把に言えば、免疫細胞の攻撃はタンパク質(異物)の消化です。
そこに病原菌などがいるなら別ですが、いないところでそんな反応が起きれば正常組織が痛むのは自然なことでしょう。
つまり、アレルギーは専門家の言うような「免疫の暴走」ではありません。炎症性サイトカインの大量分泌により、免疫は正常に反応しているだけなのです。
--------------------------------------
オメガ6、オメガ3とは?
--------------------------------------
引用:Wikipedia ω-6脂肪酸
ω-6脂肪酸(オメガ-6 しぼうさん、ω-6 fatty acids、ω6とも表記、オメガ-シックス、Omega-6)または、n-6脂肪酸(n-6 fatty acids)は、不飽和脂肪酸の分類の一つで、一般に炭素-炭素二重結合がω-6位(脂肪酸のメチル末端から6番目の結合の意味)にあるものを指す。
リノール酸は同じω-6系のγ-リノレン酸やアラキドン酸などへ代謝され、プロスタグランジンE2のような生理物質の材料となる。
リノール酸は、ヒトが体内で合成できないため必須脂肪酸であるが、通常の食生活で欠乏することはなく、むしろ摂取しすぎることがある。
ω-6脂肪酸の生物学的役割の大部分は、体内の組織で見られる様々な受容体へ結合するn-6エイコサノイドへの変換の仲介である。
ω-6脂肪酸からの多数の生理活性物質の生成反応はアラキドン酸から滝のように流れ落ちる如く生成されることからアラキドン酸カスケードと呼ばれる。
日本人の食事摂取基準(2015年版)では、健康な人でのω-6脂肪酸の欠乏症の報告はなく、推定平均必要量を定めるためのデータはなく、目安量が設定され1日10g前後、摂取上限を設定するためのデータもないが、過剰摂取した場合にはリスクが考えられる。
日本人が摂取しているω-6脂肪酸のほとんど(98%)はリノール酸である。
引用:Wikipedia ω-3脂肪酸
人間の栄養学でω-3脂肪酸の必要性について注目されてきたのは1970年代から1980年代からであり、摂取基準が示されるのは2000年以降となる。栄養素の研究の中でも比較的新しいものである。
αリノレン酸はヒトの体内で合成できない必須脂肪酸であり、そこから合成されるドコサヘキサエン酸(DHA)は神経系の機能に関わっている。
ヒトは、ω-3脂肪酸をデノボ合成することはできないが、18炭素ω-3脂肪酸のα-リノレン酸から20-, 22-炭素の不飽和ω-3脂肪酸を形成することができる。
これらの不飽和化の増加は、使用される不飽和化酵素が共通しているためリノール酸から誘導される必須なω-6脂肪酸と競合する。
体内で起こるα-リノレン酸からの長いω-3脂肪酸の合成はω-6類似体によって競合的に抑制される。
したがって、ω-3脂肪酸が食物から直接得られたとき、またはω-6類似体の量がω-3の量を大きく上回らないとき、組織内での長鎖ω-3脂肪酸の蓄積は効率的である。
日本人の食事摂取基準(2010年版)では、男性においては前立腺がんの罹患リスクのためα-リノレン酸の過剰摂取は注意が必要とされている。
EPA及びDHAについては1日に合計で1g以上の摂取が望ましいとされている。
なお、前立腺がんの罹患リスクは、特に乳製品や肉類由来のα-リノレン酸との関連が示唆されている。
ω-3脂肪酸とω-6脂肪酸の望ましい摂取比率は1:1から1:4であると報告されている。
-----------------------------
食事内容に留意して、免疫活性を正常にする、ということかな。
-----------------------------
2020.4.15
目次へ
経鼻粘膜投与型ワクチンについて、もう少し調べてみたい。
引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/nskkk/56/3/56_3_191/_pdf/-char/ja
ウイルスや病原菌の侵入口である粘膜面には粘膜免疫が存在し、IgA応答や細胞障害性T細胞(CTL)を誘導する。
ある粘膜組織で誘導されたIgA産生細胞やCTLは他の粘膜組織にも帰巣(ホーミング)する。
とくに、分泌型IgA産生細胞は、腸管関連リンパ組織、鼻咽頭関連リンパ組織および気管支関連リンパ組織などの誘導組織で誘導され、実行組織である腸管粘膜固有層、呼吸器粘膜固有層などにホーミングする。
抗原により直接暴露された粘膜組織において最も強いホーミングが起こり、強い免疫応答がみられ、それに準じた免疫応答が隣接する粘膜組織でみられる。
腸管や鼻咽頭からの抗原は、M細胞に取り込まれてマクロファージや樹状細胞などの抗原提示細胞に送られ、その後、B細胞およびT細胞に提示される。
感作されたB細胞やT細胞はホーミングを開始して体内を循環し、各実行組織に到達する。
B細胞が産生するIgAは、上皮細胞で産生される分泌片と結合して、分泌型IgAとして各粘膜面に分泌され、侵入したウイルス、細菌、細菌毒竿、アレルゲンなどと免疫結合体をつくり、これらを排除する。
粘膜経由の感染症に対する最適な防御は、粘膜面と全身系で免疫を誘導することである。
腸管や鼻咽喉などの粘膜面をターゲットにして、経口あるいは経鼻的な粘膜に投与されたワクチン「粘膜ワクチン」は、粘膜面での感染侵入防止と、全身系免疫での防御の両方が誘導できる。
--------------------------
経鼻粘膜投与型ワクチンが感染防止に有効であるようだ。ぜひ早く完成してほしい。
--------------------------
<
br>
2020.4.17
目次へ
経鼻粘膜投与型ワクチンを調べてみたい。
引用:https://nsmc.hosp.go.jp/Subject/26/juku/juku013files/cyoukou/hasegawa.pdf
何故インフルエンザには次世代ワクチンが必要か?
・インフルエンザウイルス感染後の発症、重症化を予防できるが感染防御するものではない。
・ワクチン株と流行株が一致したときには有効であるが、株が一致しない場合には効果が低い。
・新型インフルエンザウイルスのパンデミックにおいては流行株を予測することは不可能である。
・H5N1 沈降全粒子不活化ワクチン(アルミニウムアジュバント)は発熱問題で小児に対し使用できない。
自然感染によって誘導される免疫は、不活化ワクチンの注射によるものよりも、変異ウイルス感染に対する交叉防御能が高い。
(1960年代から知られていた事実)
IgA抗体を誘導する経鼻ワクチンの開発研究
1)弱毒生ウイルスワクチン
2003年、米国使用認可(*2~49歳の世代に限定して使用)。
2)経鼻不活化ワクチン
経鼻不活化ワクチンの試み開始
不活化ワクチンのみの経鼻投与ではIgA抗体の誘導効率が低い。
●鼻からウイルスが見つからない→ 感染していない
●異なるウイルス株に対しても効果あり
◎HCの種類でIgA1とIgA2が存在
◎血清中IgA抗体は単量体
◎粘膜上にはSCと結合した分泌型IgA抗体が存在
◎分泌型IgA抗体は二量体dIgAが主体
◎粘膜上には、二量体より大きい多量体pIgAも存在
◎経鼻インフルエンザワクチンは粘膜上に分泌型IgA抗体を誘導し感染を阻止する。
◎鼻腔粘膜上に誘導される分泌型IgA抗体は交叉防御効果があり血中のIgG抗体と比較し変異ウイルスに対しても有効である。
◎不活化全粒子ワクチンの経鼻接種によりヒトにおいて血中に加え鼻腔粘膜上にインフルエンザウイルスを中和する抗体が誘導される。
◎経鼻ワクチンにより誘導される分泌型IgA抗体は二量体、四量体、更に多量体化しインフルエンザウイルスの中和に寄与している。
経鼻インフルエンザワクチンは鼻粘膜上に分泌型多量体IgA抗体を誘導する事によりインフルエンザウイルスに対する感染防御、交叉防御に寄与する。
-------------------------------
これは、2014年の国立感染症研究所の資料。経鼻インフルエンザワクチンの実現が待たれる。
もう一度、IgAを調べてみたい。
-------------------------------
引用:Wikipedia 免疫グロブリンA
免疫グロブリンA(めんえきグロブリンA、英: Immunoglobulin A, IgA)は、哺乳類および鳥類に存在する免疫グロブリンの一種であり、2つの重鎖(α鎖)と2つの軽鎖(κ鎖およびλ鎖)から構成される。
IgA分子は2つの抗原結合部位を有しているが、気道や腸管などの外分泌液中ではJ鎖と呼ばれるポリペプチドを介して結合することにより2量体を形成して存在しているため4箇所の抗原結合部位を持つ。
2量体IgA(分泌型IgA、SIgA)は粘膜免疫の主役であり、消化管や呼吸器における免疫機構の最前線として機能している。
IgAをコードする遺伝子にはIgA1とIgA2の2種類が存在するが、血清中に存在する単量体あるいは2量体IgA(血清型IgA)にはIgA1が約90%と圧倒的に多い。
その一方で分泌型IgAではIgA2の割合が30-50%と血清型に比べて多くなっている。
全IgA中における血清IgAの占める割合は10-20%程度であり、IgAのほとんどは二量体として存在している。
また、分泌型IgAは初乳中に含有され、新生児の消化管を細菌・ウイルス感染から守る働きを有している(母子免疫)。
母子免疫には免疫グロブリンGも関与していることが知られているが、こちらは胎盤を介して胎児に移行する。
ヒトにおけるIgAの産生量は各種免疫グロブリンの中でもIgGに次いで2番目に多い。
分子量16万(単量体)。
粘膜は常時抗原や微生物にさらされており、これらから粘膜面を防御する局所免疫機構が存在する。
これを粘膜免疫防御系(英: Mucosa-associated Lymphoid Tissue, MALT)と呼び、分泌型IgAがその一部を構成している。
代表的なMALTとして消化管免疫防御系(GALT)、気道免疫防御系(BALT)および鼻腔免疫防御系(NALT)が知られている。
粘膜免疫機構はIgAの産生誘導を行う誘導組織とIgAが分泌・機能する実効組織、そしてそれらをつなぐ帰巣経路から構成され、これらを合わせてCMIS(Common Mucosal Immune System)と呼ぶ。
誘導組織において粘膜面に存在する抗原提示細胞はリンパ球を活性化させ、遊走させる働きを持っている。
リンパ球はリンパ節で分化した後に実効組織に到達し、IgAを産生する。
この際、一度誘導組織を離れたリンパ球は再び同じ組織に戻ってくる傾向を持ち、これをリンパ球のホーミング(帰巣現象)と呼ぶ。
----------------------------
一度誘導組織を離れたリンパ球は再び同じ組織に戻ってくる傾向を持ち、これをリンパ球のホーミングという。なるほど。
----------------------------
IgAは実効組織の粘膜固有層に存在するIgA産生形質細胞(プラズマ細胞)により二量体として産生され、分泌される。
形質細胞はリンパ球の一種であるB細胞から分化し抗体産生能を持つ細胞であり、通常IgMを産生する能力を持っている。
この細胞がIgA産生能を獲得するためにはサイトカインの刺激を受ける必要があり、B細胞がトランスフォーミング増殖因子(TGF)-βやインターロイキン-4の作用を受けることにより免疫グロブリンのクラススイッチが誘導される。
クラススイッチを終えた細胞はさらにインターロイキン-5およびインターロイキン-6の刺激を受けてIgA産生能を持つ形質細胞に分化する。
これらの過程を通して見ると、IgA産生形質細胞への分化にはTh2サイトカインが重要な働きをしていることが分かる。
IgAは同様に形質細胞により産生されるJ鎖と結合し2量体として分泌される。
2量体IgAはその後粘膜上皮細胞の基底膜側に発現している分泌成分(英: Secretory Component, SC)と結合して上皮細胞内へ取り込まれ、管腔側へと分泌される。
分泌成分はIgAをタンパク質分解酵素による分解から保護する役割を有している。
IgAはこれらの系を介して粘膜面への微生物の侵入を防ぎ、生体防御機構において重要な役割を果たしている。
2020.4.18
目次へ
カテキンがウイルスの感染予防に効果があるという。調べてみよう。
引用:「狭山茶物語」 狭山茶業振興協力会
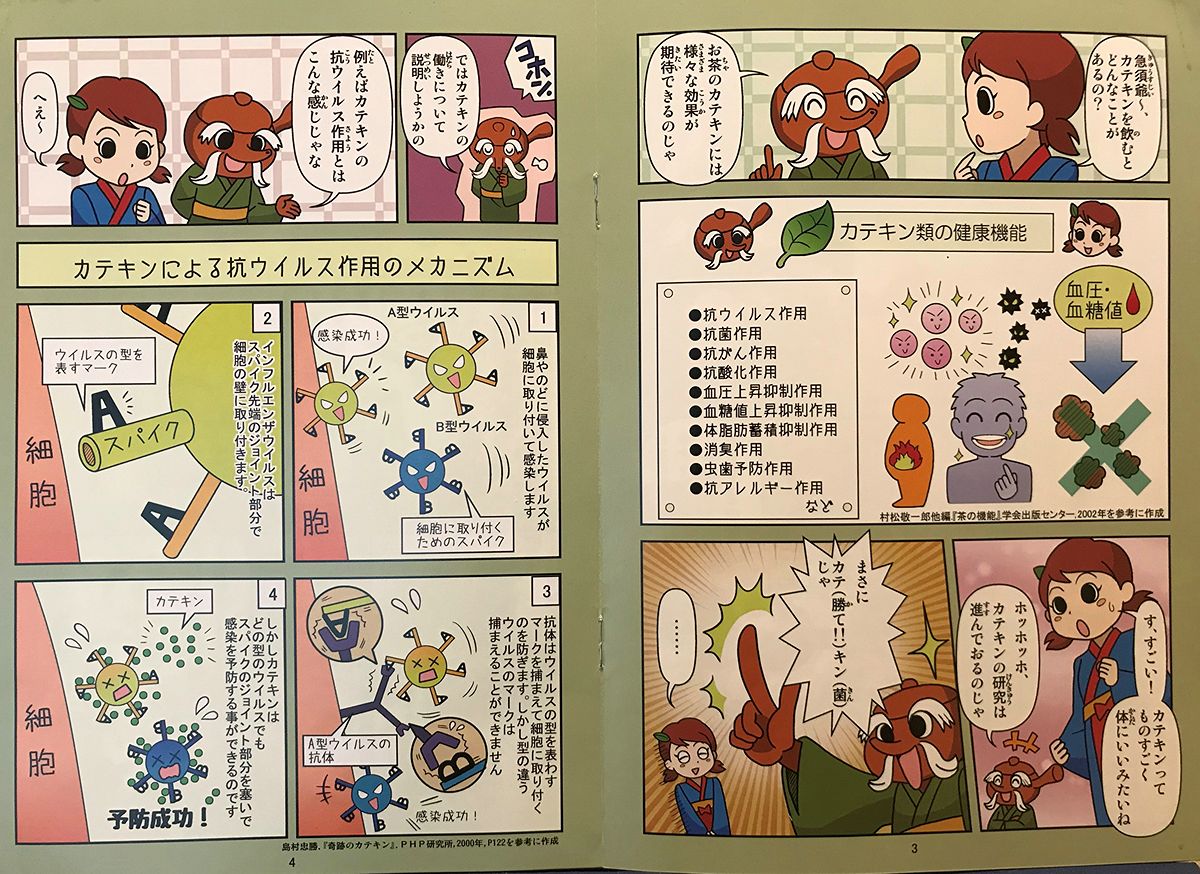
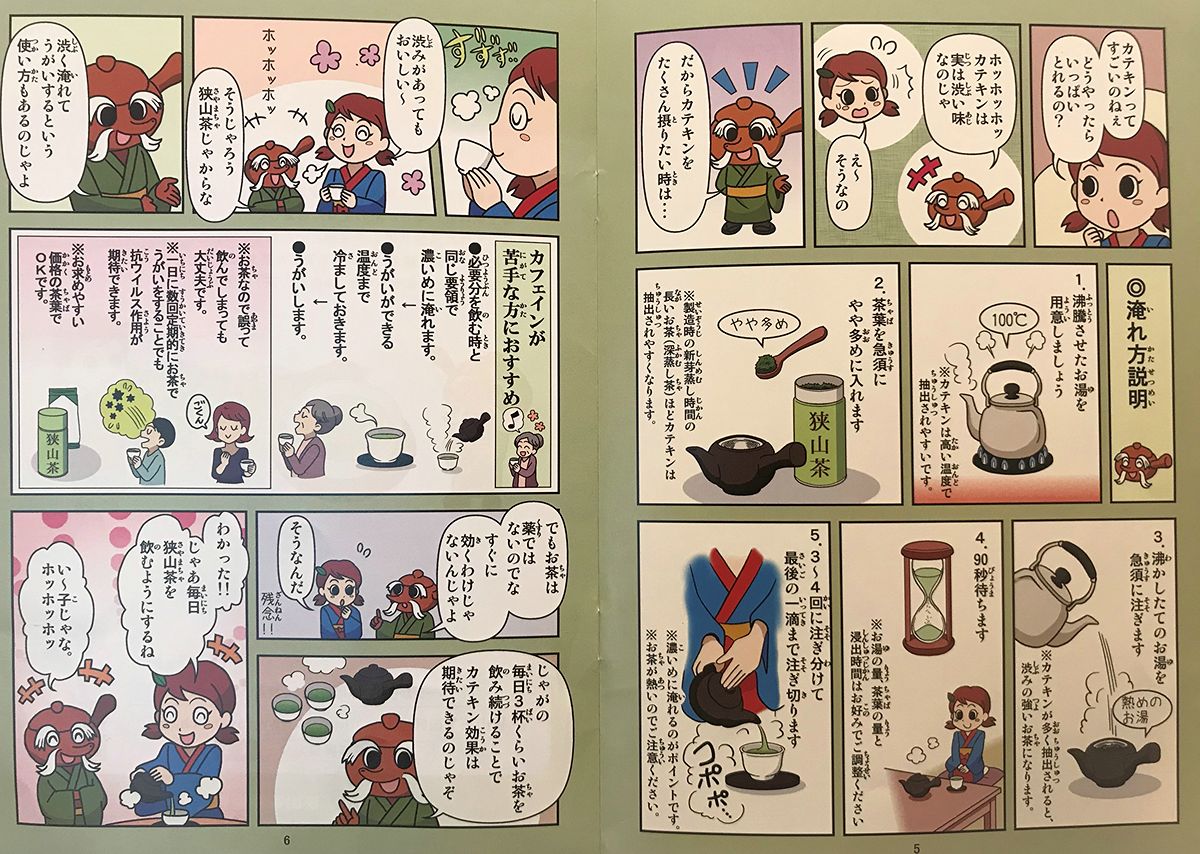
引用:Wikipedia カテキン
カテキン (catechin) は、狭義には化学式C15H14O6 で表される化合物であり、フラボノイドの1種である。分子量は 290.27。
広義にはその誘導体となる一連のポリフェノールも含み、この意味での使用例の方が多い。広義のカテキンは茶の渋み成分である。
これらは酸化によって重合しタンニンとなる。
茶カテキンの主要成分は、エピカテキン(epicatechin、EC) とそのヒドロキシ体のエピガロカテキン (epigallocatechin、EGC)、およびそれらの没食子酸エステルであるエピカテキンガラート (epicatechin gallate、没食子酸エピカテキン、ECg) とエピガロカテキンガラート(epigallocatechin gallate、没食子酸エピガロカテキン、EGCg)の4つである。
これらの化合物は緑茶の渋み成分として含有量は EGCg>EGC>ECg>EC の順であり、合計すると茶葉中の水分を除いた総重量中の13~30%程度を占める。
紅茶を作る際の発酵の工程では、カテキンはポリフェノールオキシダーゼ(polyphenol oxidase)によって酸化重合し、テアフラビンやテアルビジンへと変化する。
--------------------------------
カテキンとスパイクの関係についての科学的な論文が見つからない。
スパイクタンパク質に関する論文が見つかったので、見てみる。
--------------------------------
引用:https://phys.org/news/2020-02-revealed-protein-spike-ncov-coronavirus.html
Researchers in the United States have unveiled the structure of the "spike protein" of 2019-nCoV-the virus behind the current coronavirus disease outbreak.
Despite the fact that researchers have already pieced together the virus's genetic sequence, the World Health Organisation has warned that a vaccine is still 18 months away.
But knowing the structure of the virus's spike protein gives us crucial information about exactly how the virus infects host cells.
This could be a vital piece of the puzzle in making the hoped-for vaccine a reality.
What is a spike protein?
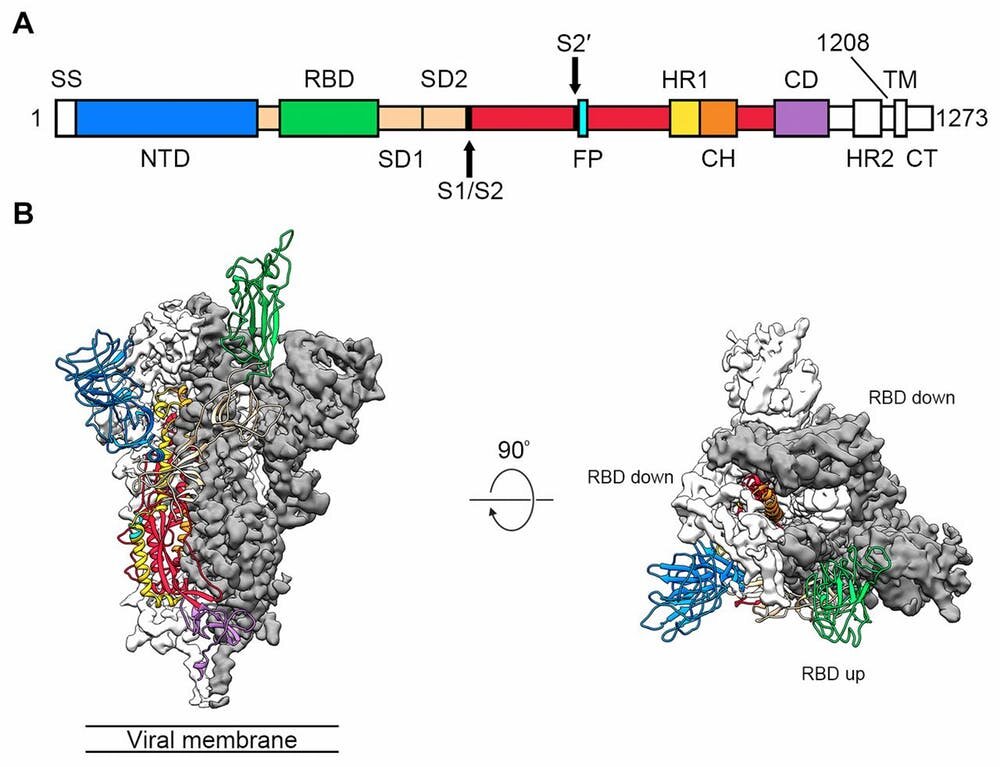
A viral spike protein is like a key that "unlocks the door" to gain access to the cells of a specific host-humans, in this case.
To understand how to deal with 2019-nCoV, we first need to understand what this key looks like, and what "keyhole" it targets on human cells.
This is exactly what the new paper, published overnight in Science, is all about.
The researchers, led by Jason McLellan of the University of Texas at Austin, defined the structure of 2019-nCoV's spike protein using a technique called cryogenic electron microscopy 極低温電子顕微鏡法, or "Cryo-EM". This involves cooling the protein to below -150℃, so that it crystallises and then its structure can be determined with near-atomic resolution.
They also identified the "keyhole", the host cell receptor 宿主細胞受容体: it is a human protein called angiotensin converting enzyme 2 アンジオテンシン変換酵素2 (ACE2).
This is the same human receptor protein targeted by the earlier SARS coronavirus. 初期のSARSコロナウイルスが標的とした同じヒト受容体タンパク質
But, disturbingly, the researchers found that 2019-nCoV binds to ACE2 with much higher affinity 親和性 (10-20 times higher!) than SARS. In other words, 2019-nCoV's "key" is a lot "stickier 粘着性" than the SARS one.
It's like a SARS "key" covered in superglue.
This means that once it's in the lock, it's far less likely to be shaken loose and is therefore presumably more effective at invading our cells.
So what about a vaccine?
The researchers reasoned that, given that both viruses attack the same protein on human cells, it would be worth seeing whether the already available antibodies against SARS-CoV would work against 2019-nCoV.
Unfortunately, they didn't work.
ACE2
引用:Wikipedia アンジオテンシン変換酵素
アンジオテンシン変換酵素(-へんかんこうそ; 英: angiotensin-converting enzyme、ACE、EC 3.4.15.1)とは不活性体であるアンジオテンシンI (英: angiotensin I、Ang I) を、生理活性を持つアンジオテンシンII (英: angiotensin II、Ang II) に変換する反応を触媒する酵素(プロテアーゼ)である。
アンジオテンシン変換酵素(以下「ACE」)はその活性中心(HExxH)に亜鉛を有するメタロプロテアーゼの一種であり、細胞膜上に存在する。
ACEには2つの異なるタイプが存在し、それぞれ somatic ACE (sACE) と germinal ACE (gACE) と呼ばれる。
sACEは全身の細胞に広く分布するのに対して、gACEは発現している組織が限られており、精巣に発現していることが知られている。
また、sACEは活性部位をN末端側とC末端側に2つ持つのに対し、gACEは活性部位を1つしか持たない。
sACEのN末端及びC末端の活性中心部位はそれぞれアミノ酸配列は同じであるにもかかわらず、基質に対する反応性など性質が異なる点が存在する。
ACE2 (アンジオテンシン変換酵素2) はACEと構造が類似しているものの別物であり、ACE2は主にアンジオテンシンIIからアンジオテンシン-(1-7)への変換を行って血圧上昇のレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系を抑制する。
ACE2には敗血症などによる肺損傷からの保護作用がある。
またACE2は小腸上皮においてB0AT1と結合し、トリプトファンを吸収する中性アミノ酸輸送体として動作し、これによって抗菌ペプチドが発現されると見られている。
ACE2ノックアウトマウスは腸炎を引き起こすが、トリプトファンまたはニコチンアミドの摂取によってこの腸炎を軽減できる。
ACE2は十二指腸、小腸、胆嚢、腎臓、精巣に高く発現しており、副腎、結腸、直腸、精嚢に低く発現している。
肺炎などを引き起こすSARSコロナウイルスおよび2019新型コロナウイルスはACE2を宿主細胞受容体として利用する。
増殖したSARSコロナウイルスはACE2の発現を低下させ、急性肺不全など重大な症状を引き起こす。
-------------------------------
スパイクタンパク質の構造が判明したのであれば、ワクチンの作成も近いだろう。
-------------------------------
2020.4.19
目次へ
アビガンの原料のマロン酸ジエチルを調べてみる。
引用:Wikipedia マロン酸ジエチル
マロン酸ジエチル(Diethyl malonate)またはDEMは、マロン酸のジエチルエステルである。
ブドウやイチゴに含まれるリンゴ様臭の無色液体で、香水の成分としても用いられる。
バルビツール酸、人工香料、ビタミンB1、ビタミンB6等のほか、ファビピラビルの製造にも用いられる。
マロン酸は比較的単純なジカルボン酸であり、2つのカルボキシ基が接近している。
マロン酸からマロン酸ジエチルを形成する際には、両方のカルボキシ基のヒドロキシ基がエトキシ基に置き換わる。
マロン酸部分の中央にあるメチレン基は、2つのカルボニル炭素の隣にある。
カルボニル基の隣の炭素原子上にある水素原子は、アルキル基の隣の炭素原子上にある水素原子の最大30桁も酸性が強い。
2つのカルボニル基と隣り合う炭素原子上の水素原子は、間のメチレン基からプロトンが除去されて生じるカルバニオンを安定化させるため、酸性はさらに高まる。
---------------------------
もう一度アビガンを見てみる。
---------------------------
引用:Wikipedia ファビピラビル
ファビピラビル(英: Favipiravir)は、富山大学医学部教授の白木公康と富士フイルムホールディングス傘下の富山化学工業(現:富士フイルム富山化学)が共同研究で開発した核酸アナログでRNA依存性RNAポリメラーゼ阻害剤である。
開発コードのT-705、あるいは商品名であるアビガン(Avigan)の名前でも呼ばれる。
ファビピラビルはプロドラッグであり、投与後に細胞内のin vivo(生体内)環境で、三リン酸化されて、ファビピラビル・リボフラノシル-5'-三リン酸 (favipiravir-RTP) となり、これがRNAウイルスのRNA依存性RNAポリメラーゼ(RdRP、RNA複製酵素)にプリンヌクレオシド(アデノシンおよびグアノシン)と競合して取り込まれ、取り込まれた部位以降のRNA鎖の伸長を阻害するchain terminator(伸長阻止薬)として作用する 。
抗インフルエンザウイルス薬としては細胞内におけるウイルスRNAの複製を妨げることで増殖を防ぐ仕組みで、タミフルなどの既存薬とは作用機序が異なる。
そのためインフルエンザウイルスの種類を問わず抗ウイルス作用が期待できる。
(たとえばタミフルはB型インフルエンザウイルスに対しては効果が劣り、C型インフルエンザウイルスには効果がない)
またインフルエンザウイルスのみならず、エボラ出血熱ウイルス(後述)やノロウイルス、SFTSウイルスなどへの適用性に関する試験・研究も行われており、ケンブリッジ大学教授のイアン・グッドフェローらの研究チームは2014年10月21日、マウスを使った実験でノロウイルスの減少・消失を確認したとの発表を行った。
さらにウエストナイル熱ウイルス、黄熱ウイルスなどのRNAウイルスにも効果があると考えられており、同研究チームは「治療だけでなく感染予防にも効果的である可能性がある」とコメントしている。
-------------------------------
「胸部CTで肺病変があれば,発症後6日にはアビガン治療を開始していただきたい」という開発者の見解を尊重する。
-------------------------------
2020.4.20
目次へ
ファビピラビルを調べてみたい。
引用:http://www.chemotherapy.or.jp/journal/jjc/06505/065050736.pdf
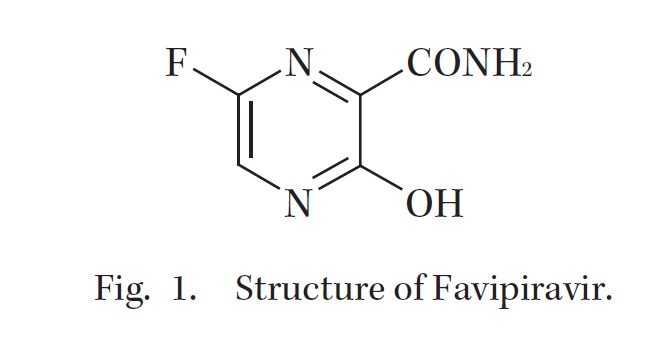
ファビピラビルは,RNA ウイルスのRNA 依存性RNA ポリメラーゼ(RdRp)を選択的に強く阻害する。
新規な抗ウイルス薬であり,その作用機序は,細胞内に取り込まれたファビピラビルが細胞内酵素により代謝・変換され,ファビピラビル・リボフラノシル三リン酸体(favipiravir-ribofuranosyl-5’-
triphosphate)となり,RdRp を選択的に阻害するものである。
また,ファビピラビルは広範囲なRNAウイルスにin vitro や動物モデルで効果を示すが,RdRp の触媒領域がRNA ウイルス間で広く保存されることがこの現象を支持している。
ファビピラビルは,既存薬耐性株を含むすべての型のインフルエンザウイルスに対して活性を示すだけでなく,出血熱の原因となるアレナウイルス,ブニヤウイルス,およびフィロウイルスなどの広範囲なRNA ウイルスに対しても効果を示す。
ファビピラビルはin vitro の細胞感染試験において,インフルエンザウイルスの吸着期や遊離期には作用せず複製中期に作用すること,ならびにプリン系核酸の添加により抗ウイルス活性が減弱することから,ファビピラビルあるいは代謝物が擬似塩基としてインフルエンザウイルスの遺伝子複製に作用している可能性が示唆された。
また,ファビピラビルの14C ラベル体を用いた試験から,細胞内にリボースおよびリン酸が付加したファビピラビルの一リン酸体(ファビピラビルRMP),ならびに三リン酸体(ファビピラビルRTP)が確認されたことから,ファビピラビルRTP がインフルエンザウイルスのRNA 依存性RNA ポリメラーゼ(RdRp)を阻害する作用様式が推定された。
次にインフルエンザウイルスRdRpに対する作用を検証するため,同作用が報告されているリバビリン三リン酸体(リバビリンTP)9)と比較検討した。
ファビピラビルRTP は用量依存的にインフルエンザウイルスRdRp 活性を阻害
し,50% 阻害濃度(IC50)は0.14 μ M であり,リバビリンTP の2.4 μ M より10 倍以上強く阻害することが確認された。
また,その後のRdRp 阻害様式の検討から,ファビピラビルRTP の1 分子がウイルスRNA 鎖に取り込まれ,その後の鎖伸長を阻害する,いわゆるチェーンターミネーターとして作用していることが示された。
なお,遺伝子複製に関連するポリメラーゼは哺乳類細胞などで複数知られているが,ファビピラビルの阻害作用はウイルスのRdRp に特異的で,ヒトのDNA 依存性DNA ポリメラーゼ(α ,β ,γ )ならびにDNA 依存性RNA ポリメラーゼに対してはほとんど阻害作用を示さないことが示されている。
ファビピラビルは宿主細胞内の酵素によりファビピラビルRTP へと変換され,インフルエンザウイルスのRdRp を阻害する。
インフルエンザウイルスはマイナス一本鎖のRNA を遺伝子としてもつウイルスであり,このマイナス鎖ゲノムRNA(vRNA)を鋳型にして,RdRp 複合体がmRNAへの転写ならびに,子孫vRNA を複製する際の中間体であるプラス鎖の相補RNA(cRNA)を合成する。
その際にファビピラビルRTP はGTP およびATP と競合してウイルスRNA 鎖に取り込まれ,mRNA やcRNA,vRNAの不完全な合成を引き起こしていると考えている。
すなわちファビピラビルはRdRp 活性を阻害することにより,ウイルスのゲノム複製と蛋白合成を同時阻害するdual inhibitor(ダブル阻害剤)として作用していると考えられる。
2020.4.26
目次へ
もう一度、IgAのことを調べてみよう。
引用:https://lifecarekk.com/wp-content/uploads/2020/03/新型コロナウイルスに対抗するIgA抗体.pdf
皮膚のような硬い角層で覆われていない喉の“粘膜”は、ウイルスなどが侵入をしやすい場所です。
外敵の侵入を防ぐ防波堤である“粘膜”で主体的に活躍している免疫物質が「IgA」抗体です。
「抗体」は侵入してきたウイルスなどに密着して、これを無力化するように働く免疫物質(タンパク質)で、免疫グロブリンとも呼ばれます。
「IgA」は特定のウイルスや細菌だけに反応するのではなく、様々な種類の病原体に反応する(攻撃する)という、守備範囲の広さが特徴です。
「IgA」が低下するとウイルスや細菌に対する抵抗力が低下して、“ウイルス”は上気道感染(風邪)から肺に入りこみ「肺炎」が発症します。「IgA」は、鼻汁・涙液・唾液・消化管など全身の“粘膜”に存在します。
「IgA」が低いときは、“疲労感”も高まっています。
又、母乳には「IgA」が特に多く含まれ、赤ちゃんを「感染」から守っているのです。
「IgA」は“加齢”と共に低下するため、「高齢」になると「肺炎」に罹りやすくなります。
「IgA」抗体を増やす事は、“コロナウイルス”などに対抗する免疫の要です。
「IgA」抗体は鼻汁、唾液や消化管などの表面の粘膜中に分泌され、これらの粘膜表面
で外敵の侵入を阻止します。
「IgA」は特に“腸”に多く存在します。
これは、食べ物と共にウイルスや細菌などが侵入しやすいためだと考えられています。
グルタミン・ビタミンA&B6は、「IgA」抗体の分泌を増加させ、「ウイルス」や「細菌」などを捉えます。
体内において最も産生量の多い「IgA」抗体は、分泌型「IgA」抗体として「ウイルス」などの粘膜組織を標的とした“感染症”に対する生体防衛の最前線を担っています。
分泌型「IgA」抗体は、血液中に存在する「IgG」抗体とは異なり“多量体”を形成しています。
“多量体”を形成する大きな分泌型「IgA」抗体は、“二量体”よりも高いウイルス中和活性を有し、又、離れた抗原性の「ウイルス」に対しても威力を持っています。
グルタミン・ビタミンA・B6は、「IgA」抗体の分泌を増加させます。
「グルタミン」は腸管や腎臓の“粘膜細胞”で栄養の吸収に必要な“エネルギー”となるアミノ酸です。
「グルタミン」は筋肉組織で作られ(30g/日)、腸管や腎臓で利用されますが、筋肉が衰えてくる「高齢者」は不足してきます。
そこで、腸管で栄養の吸収を良くするために、「グルタミン」をビタミンB6・A と共に補給する必要があります。
腸粘膜細胞の増殖を促進する上皮増殖因子(EGF)の活性化には「グルタミン」が必要といわれています。
「グルタミン」は免疫機能、特に「腸管免疫」に密接に関わっています。
又、「グルタミン」は腸管の“粘膜細胞”で「ビタミンA」と共に「IgA 抗体」産生に関与し、必要な腸内細菌(共生菌)を選択的に確保するため“腸内フローラ”を整え「癌」や「糖尿病」などからも体を守る働きがあるといわれています。
更に、「グルタミン」は“リンパ球”などを活性化します。一方、リウマチなどの「自己免疫疾患」における過剰免疫の抑制にも有効であるといわれ、免疫を調整する万能選手ともいえます。
「IgA」抗体が十分にできないと、“ワクチン効果”ができません!
「IgA」抗体は、必須アミノ酸の「リジン」などが主成分です。
-----------------------
IgAの産生についてもう一度調べてみたい。
-----------------------
引用:Wikipedia 免疫グロブリンA
粘膜は常時抗原や微生物にさらされており、これらから粘膜面を防御する局所免疫機構が存在する。
これを粘膜免疫防御系(英: Mucosa-associated Lymphoid Tissue, MALT)と呼び、分泌型IgAがその一部を構成している。
代表的なMALTとして消化管免疫防御系(GALT)、気道免疫防御系(BALT)および鼻腔免疫防御系(NALT)が知られている。
粘膜免疫機構はIgAの産生誘導を行う誘導組織とIgAが分泌・機能する実効組織、そしてそれらをつなぐ帰巣経路から構成され、これらを合わせてCMIS(Common Mucosal Immune System)と呼ぶ。
誘導組織において粘膜面に存在する抗原提示細胞はリンパ球を活性化させ、遊走させる働きを持っている。
リンパ球はリンパ節で分化した後に実効組織に到達し、IgAを産生する。
この際、一度誘導組織を離れたリンパ球は再び同じ組織に戻ってくる傾向を持ち、これをリンパ球のホーミング(帰巣現象)と呼ぶ。
IgAは実効組織の粘膜固有層に存在するIgA産生形質細胞(プラズマ細胞)により二量体として産生され、分泌される。
形質細胞はリンパ球の一種であるB細胞から分化し抗体産生能を持つ細胞であり、通常IgMを産生する能力を持っている。
この細胞がIgA産生能を獲得するためにはサイトカインの刺激を受ける必要があり、B細胞がトランスフォーミング増殖因子(TGF)-βやインターロイキン-4の作用を受けることにより免疫グロブリンのクラススイッチが誘導される。
クラススイッチを終えた細胞はさらにインターロイキン-5およびインターロイキン-6の刺激を受けてIgA産生能を持つ形質細胞に分化する。
これらの過程を通して見るとIgA産生形質細胞への分化にはTh2サイトカインが重要な働きをしていることが分かる。
IgAは同様に形質細胞により産生されるJ鎖と結合し2量体として分泌される。
2量体IgAはその後粘膜上皮細胞の基底膜側に発現している分泌成分(英: Secretory Component, SC)と結合して上皮細胞内へ取り込まれ、管腔側へと分泌される。
分泌成分はIgAをタンパク質分解酵素による分解から保護する役割を有している。
IgAはこれらの系を介して粘膜面への微生物の侵入を防ぎ、生体防御機構において重要な役割を果たしている。
近年、IgAに対するFc受容体であるFcαR(CD89)の遺伝子がクローニングされた。
血清中IgAは好酸球やマクロファージ等の細胞表面に存在するFcαRを介して細胞活性化を引き起こし、食作用や抗体依存性細胞傷害(ADCC)、炎症メディエータの遊離促進などの機構を介して免疫反応に関与していることが示唆されている。
2020.4.29
目次へ
スパイクタンパク質について見てみる。
引用:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.07.029132v1.full.pdf
A virus gone viral拡散.
First case of COVID-19 was reported in December 2019 at Wuhan (China) and then it has spread worldwide becoming a pandemic, with maximum death cases in Italy, although initially, the maximum mortality was reported from China.
Spike protein, one of the key proteins of SARS-CoV2 is involved directly with virus infection as it is involved in receptor recognition, attachment, binding and entry .
Sequence analyses of the spike protein can give us a plethora過多 of information which can be instrumental in drug and vaccine development.
In the present piece of work, we retrieved S protein sequences of the SARS-CoV2 from different geographical locations to identify notable features of S protein especially in Indian isolates.
These analyses include identification of mutational signatures and their correlation with virus infection.
Our analyses show unique point mutations in the spike protein of the Indian subtypes.
To compare the Indian isolates, we aligned the S protein sequences of these isolates with Wuhan isolates and a sequence from Italy.
While Wuhan and Italian isolates matched completely, we found few mutations in case of Indian isolates 29 and 166 as shown in Figure 2.
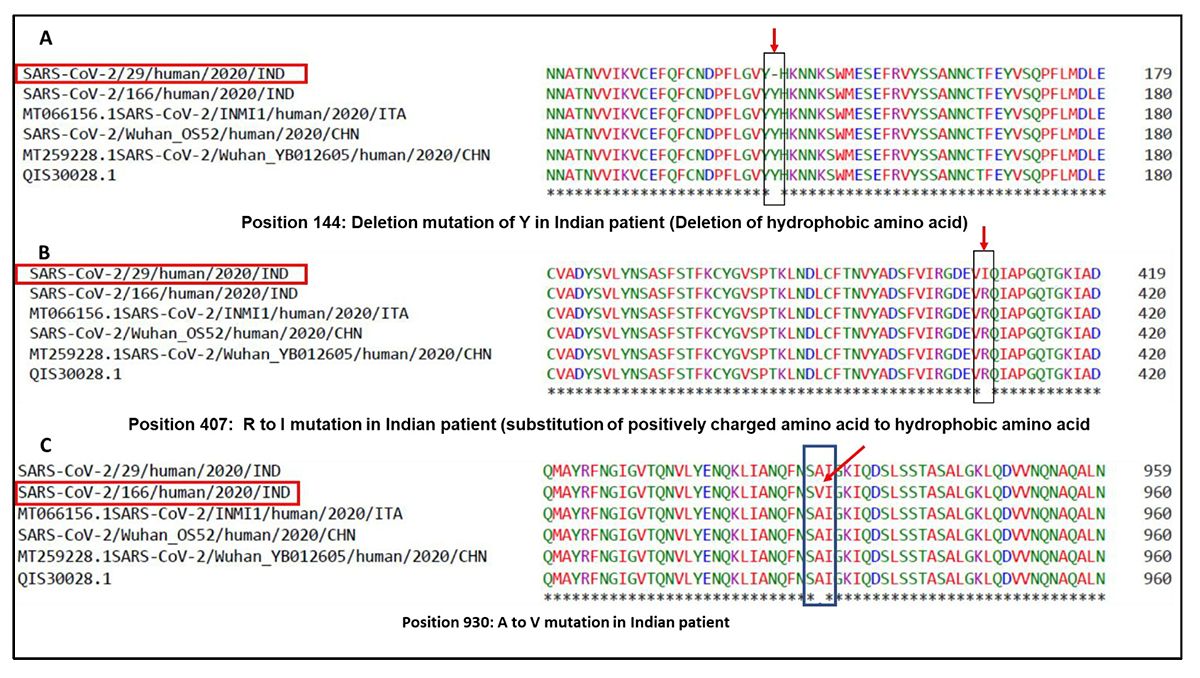
Figure 2: Multiple Sequence Alignment of Spike protein sequences of Indian, Wuhan and Italian isolates.
Spike protein sequences of Indian Isolates available in GenBank were aligned using CLUSTAL Omega online tool with colour coding option and the multiple sequence alignment result has been shown above.
The Indian isolates having mutations have been highlighted with red boxes.
The mutations have been marked with red arrows.
Panel A: Deletion mutation of Y(Tyrosine) in isolate 29. チロシンが欠如
Panel B: Substitution mutation R(Arginine) ->I (Isoleucine) at position 407 in isolate 29. アルギニンがイソロイシンに変異
Panel C: Substitution mutation of A(Alanine) ->V(Valine) at position 930 in isolate 166.アラニンがバリンに変異
引用:Wikipedia チロシン、アルギニン、イソロイシン、アラニン、バリン
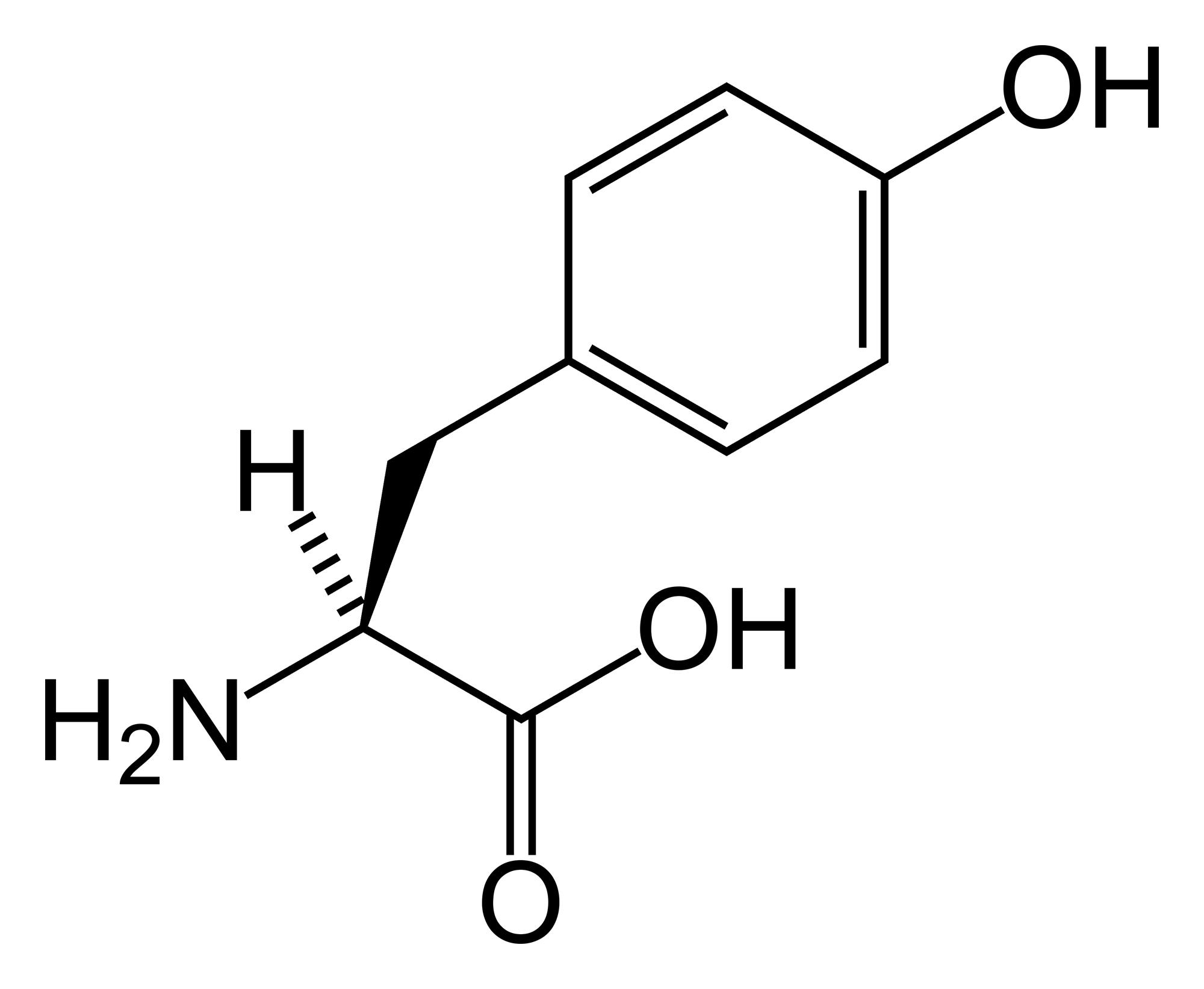 Tyrosine
Tyrosine
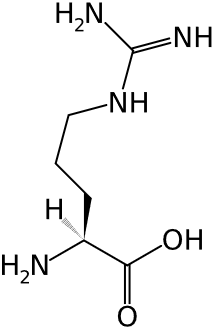 Arginine
Arginine
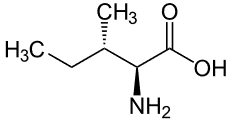 Isoleucine
Isoleucine
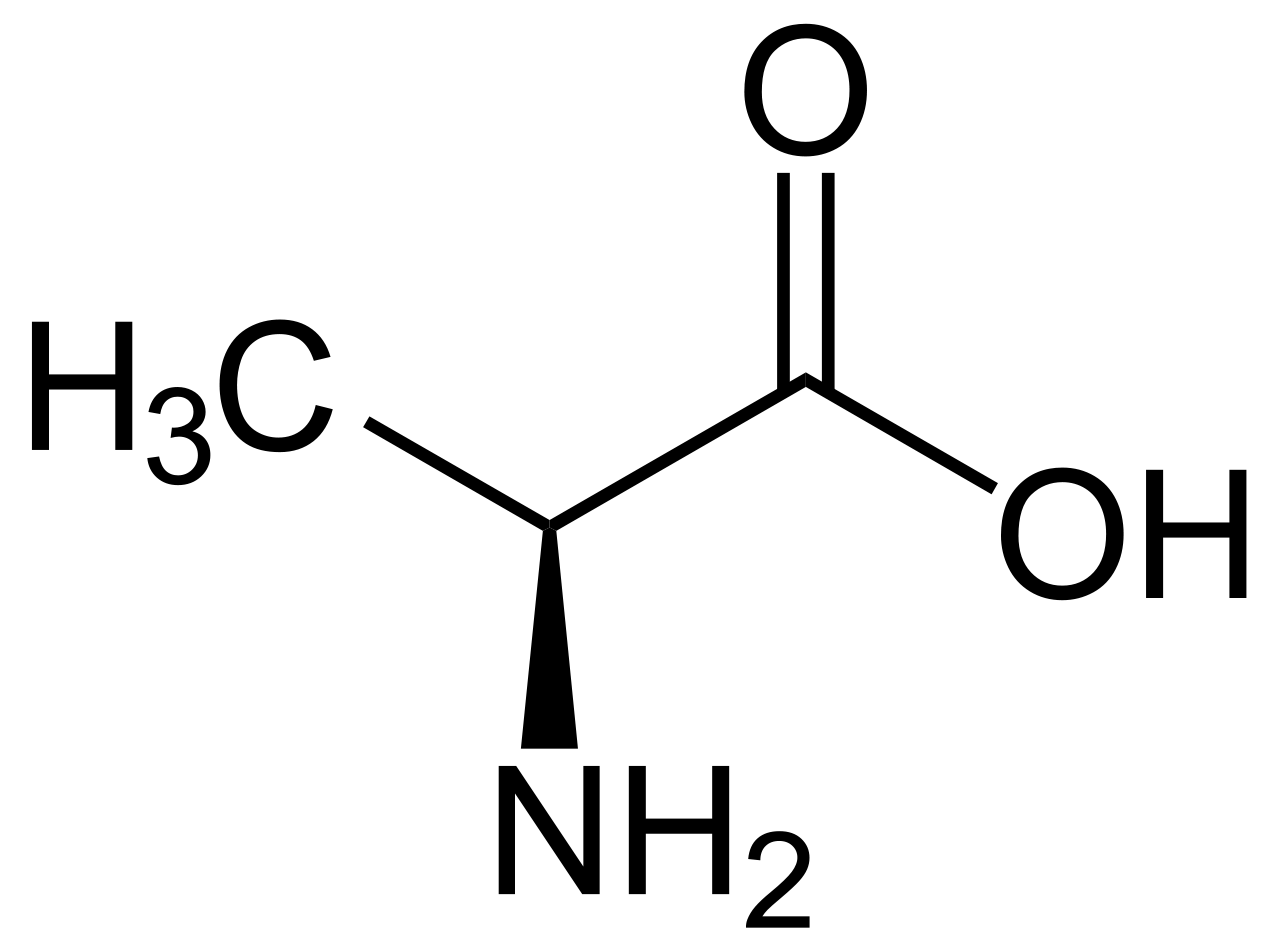 Alanine
Alanine
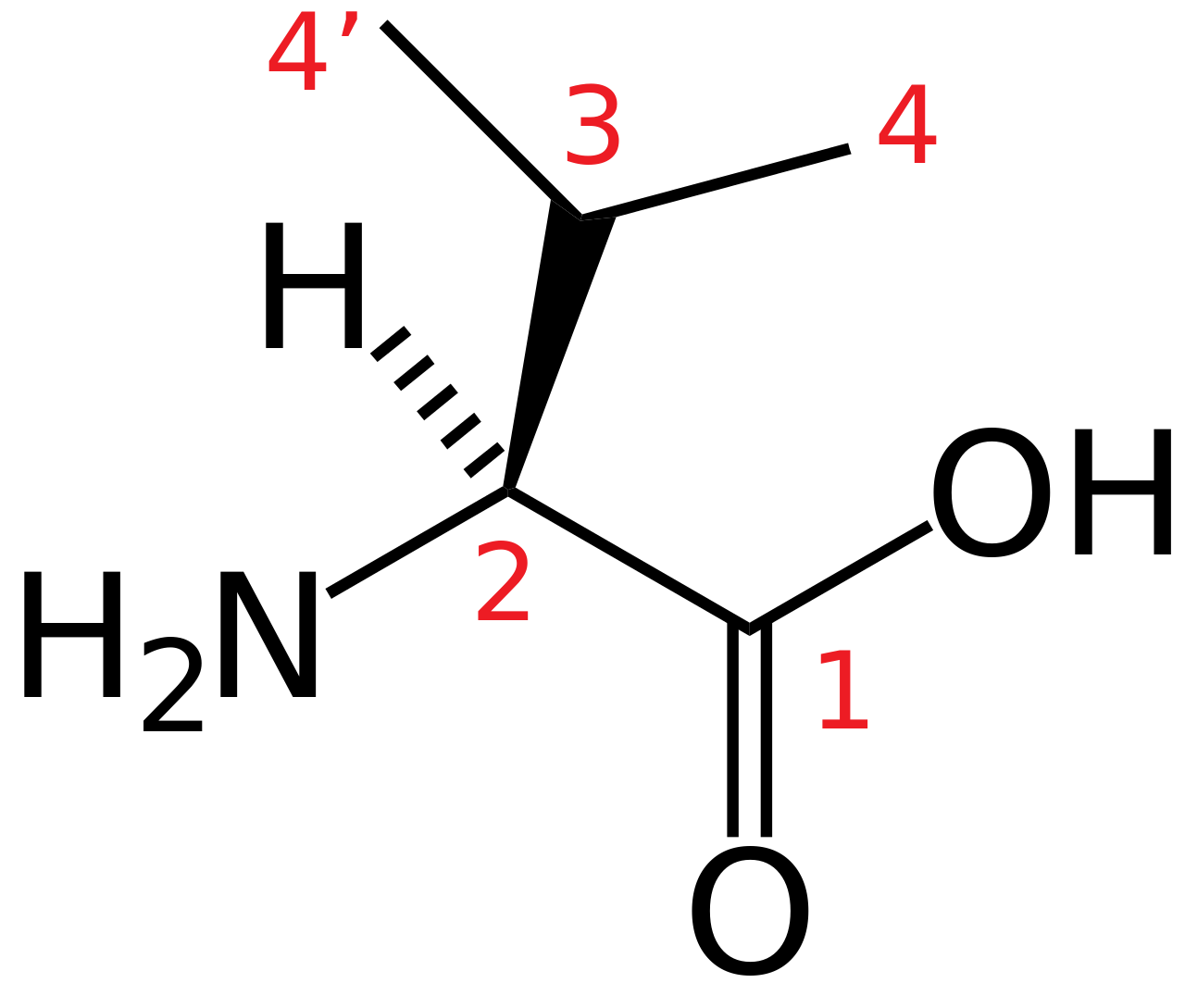 Valine
Valine
-----------------------------
COVID-19のスパイクタンパク質は、アミノ酸の配列に変化があるものが出ている。
-----------------------------
2020.5.4
目次へ
引用:http://www.twmu.ac.jp/IOR/diagnosis/ra/medication/biologics/actemra.html
「アクテムラ」は日本で開発された唯一の国産生物学的製剤で、最先端のバイオテクノロジー技術によって国内で製造されています。
国内では約1万名以上の患者様に投与されており( 2011年4月現在)、海外では2009年1月にヨーロッパで、2010年1月にはアメリカでも承認を取得し、使用が開始されています。
「アクテムラ」は他の生物学的製剤とは異なり、インターロイキン6(IL-6)というサイトカインの働きを抑える「抗ヒトインターロイキン6モノクローナル抗体製剤」です。
IL-6は炎症に関与するサイトカインで関節リウマチでは体内で過剰に作られ、炎症に由来する様々な症状を引き起こしています。
「アクテムラ」はIL-6が結合する受容体に結合して、IL-6が受容体に結合するのをブロックすることで炎症に由来する様々な症状を抑え、関節破壊の進行を抑制し、日常生活動作を改善します。
「アクテムラ」の効果には個人差がありますが、現在までの経験ではほとんどの患者さんで一定以上の効果が認められています。
ただし「アクテムラ」は関節リウマチを根治させる薬剤ではありませんので、長期間にわたり投与を継続する必要があると考えられています。
「アクテムラ」は他の生物学的製剤同様に免疫機能を抑制させることで炎症を抑える効果を発揮するため、感染症にかかりやすくなることがあります。
通常、感染症にかかると発熱や血液検査で炎症マーカー(CRPや血沈などの炎症を評価する指標)が上昇しますが、「アクテムラ」は炎症を強力に抑制するため、炎症がわかりにくくなります。
軽いかぜだと思って放置していると重症化することも考えられますので、かぜの症状(発熱、息苦しさ、のどの痛み、咳、たん、鼻水など)を感じた場合は、例え軽度でも次の診療日を待たず、すぐに主治医、看護師、薬剤師にお申し出ください。
「アクテムラ」は点滴でも皮下注射でも投与可能な生物学的製剤です。
皮下注射は2週間に1度の間隔で、 点滴は4週間に1度の間隔での投与となり、1回の点滴時間は1時間程度です。
点滴投与の場合、体重1kg当たり8mgを投与しますので体重に応じて使用する薬の量が変わります。
80mgバイアルで約1万8千円、200mgバイアルで約4万4千円、400mgバイアルで約8万8千円です。
皮下注射は体重による増減はなく1本約3万8千円です。
約3割負担の場合、1ヶ月あたり2万~4万円程度となり、これに再診料・検査料・処方箋料などが加わります。
体重によっては標準使用量で最も安価な生物学的製剤となります。
----------------------------------
アクテムラの効用は理解できた。
これと、コロナの感染の関係は?
----------------------------------
引用:https://www.47news.jp/4773706.html
免疫学者の平野俊夫・量子科学技術研究開発機構理事長が1日までに共同通信のインタビューに応じ、新型コロナウイルス感染者の命を脅かす重篤な肺炎は免疫の暴走が原因で、この仕組みに関与するインターロイキン6(IL6)という物質を薬で抑えることで治療が可能になるとの見方を示した。
平野氏はIL6発見者の一人。
関節リウマチ治療薬「アクテムラ」にはIL6の働きを抑える作用があり、重症の新型コロナ感染症に対する治験が世界で始まっている。
感染が分かった人の2割が重症化しており「治験が成功すれば多くの人の死亡が回避でき、社会活動の再開も可能になるのではないか」と期待を語った。
世界でさまざまな治療薬の候補が挙がっているが、平野氏は「2種類に分けて考えるべきだ」と指摘。
一つは治験中のインフルエンザ治療薬「アビガン」のようにウイルスの増殖などを阻む抗ウイルス薬で、感染後の早い時期に投与し、悪化を防ぐことを目指す。
もう一つは感染が引き金となって起きる免疫の暴走を抑える薬で、アクテムラもこのタイプだ。
「こうした薬は感染初期に使うと、ウイルスと戦っている免疫を抑えてしまう恐れがある」といい、重症化した患者の死亡を回避するのに有効と期待される。
治験の結果は夏から秋にかけ、相次ぎ発表されるとみている。
平野氏は「流行が終息に向かうには大半の人が感染するかワクチンを打つかして免疫をつける必要があるが、ワクチンはできるとしても早くて1年、通常2~3年かかる」と推測、まずは治療薬で致死率を下げるのが現実的だとする。
「効果のある抗ウイルス薬ができれば重症になる患者はぐっと減る。それでも重症になる人は出るので、重篤な肺炎に対する薬は必要だ」と指摘した。
引用:https://www.sankei.com/life/news/200503/lif2005030074-n1.html
量子科学技術研究開発機構理事長で免疫学が専門の平野俊夫氏らは、免疫がウイルスを打ち負かそうとするあまり過剰に働き、いわば暴走して炎症が広がり重篤化する可能性を突き止めた。
免疫の働きを高める「インターロイキン(IL)6」というタンパク質が体内で過剰に分泌されると、免疫細胞はウイルスに感染した細胞だけでなく、正常な細胞も攻撃してしまう。
死亡した患者はIL6の血中濃度が顕著に上昇していたとの報告もあり、重篤化の一因として指標に使える可能性がある。
感染初期は免疫力を高める必要があるが、重篤化すると逆に免疫を抑える治療が必要になるとみられる。
そこで有望視されるのが、中外製薬のIL6阻害薬「アクテムラ」だ。
関節リウマチなどに使う薬で、同社は新型コロナ向けに治験を行う。
平野氏は「新型コロナは免疫の暴走を抑えられれば怖くない病気だと思う。治験が効果的に進むことを期待している」と話す。
新型コロナは呼吸器だけでなく、全身にさまざまな症状が現れる特徴がある。
ウイルスが細胞に侵入する際の足掛かりとなる「受容体」というタンパク質が全身の臓器にあるためだ。
ウイルスの表面にはスパイク状の突起がある。
鍵と鍵穴の関係のように、これが細胞の受容体とぴったり合うとウイルスは侵入して増殖し、その臓器に炎症などが起きて病気になる。
鍵穴となる受容体はウイルスの種類によって異なり、新型コロナは「アンジオテンシン変換酵素(ACE)2」という物質だ。
国立感染症研究所の元室長でコロナウイルスに詳しい田口文広氏は「この受容体は呼吸器や鼻腔(びくう)、口腔、腸管などいろいろな臓器の細胞に存在する」と指摘する。
新型コロナは嗅覚や味覚の異常を訴える患者が多いことが注目されているが、これは鼻や口の中の細胞が感染して破壊されるためとみられている。
この受容体は血管の内皮細胞にもあり、そこで炎症が起きると血栓ができて、脳梗塞など重篤な合併症につながるケースが報告されている。
--------------------------
アクテムラはIL6阻害薬であるという。
適切な時期に処方すれば効果があるようだ。
--------------------------
引用:https://doctor.mynavi.jp/contents/column/news-i284/
中外製薬は4月8日、新型コロナウイルス肺炎(COVID-19肺炎)治療薬としての承認取得に向け、ヒト化抗IL-6受容体抗体「アクテムラ」(一般名:トシリズマブ)の国内治験(国内第III相臨床試験)を実施すると発表した。
治験の対象は、国内の重症COVID-19肺炎の入院患者。
中外製薬は「今後試験の詳細を確定の上、速やかな患者登録の開始を目指す」としている。
アクテムラは、中外製薬が創製した国産初の抗体医薬品。
炎症性サイトカインの一種であるIL-6の作用を阻害する働きを持ち、国内では関節リウマチ、キャッスルマン病などの治療薬として承認されている。
海外では、重症COVID-19肺炎の入院患者約330例を対象に「アクテムラと標準的な医療措置の併用」の安全性・有効性を評価する第III相臨床試験の開始を親会社のロシュ社(スイス)が3月19日に発表している。
重症COVID-19肺炎へのアクテムラの効果については国内の研究者・臨床医から期待する声が上がっており、ノーベル医学生理学賞受賞者の本庶佑京大特別教授も4月6日付で公表したCOVID-19対策の緊急提言で、①急性期には抗ウイルス剤「アビガン」、②重症肺炎時の炎症反応の暴走時にはトシリズマブ(アクテムラ)─などを実地導入すべきと訴えている。
-------------------------
期待する。
IL-6とは?
-------------------------
引用・Wikipedia インターロイキン-6
インターロイキン-6(英: Interleukin-6, 略称: IL-6)はT細胞やマクロファージ等の細胞により産生されるレクチン(糖鎖に結合活性を示すタンパク質の総称)であり、液性免疫を制御するサイトカイン(細胞から分泌される低分子のタンパク質で生理活性物質の総称。生理活性蛋白質とも呼ばれ、細胞間相互作用に関与し周囲の細胞に影響を与える。)の一つである。
IL-6は種々の生理現象や炎症・免疫疾患の発症メカニズムに関与していることが明らかになった。
IL-6受容体は分子量130kDaの糖タンパク質であるgp130(CD130)と会合して細胞内にシグナルを伝える。
IL-6は脂肪細胞から分泌され、脂質代謝に関与するアディポカイン(英:Adipokine)と呼ばれるグループに属する。
IL-6はT細胞やB細胞、線維芽細胞、単球、内皮細胞、メサンギウム細胞(腎臓の血管周囲に存在する特殊な細胞)などの様々な細胞により産生される。
マクロファージは細胞表面のToll様受容体を介してリポポリサッカライド(LPS:脂質及び多糖から構成される糖脂質であり、ヒトや動物など他の生物の細胞に作用すると、多彩な生物活性を発現する。)の刺激を受けることによりIL-6をはじめとした様々なサイトカインを分泌することが知られている。
また、扁桃腺リンパ球や線維芽細胞においてはプロテインキナーゼC依存的なシグナルによりIL-6の発現が亢進することが報告されている。
IL-6は造血や炎症反応などにおいて重要な役割を果たすサイトカインであり、IL-8やMCP-1などのケモカインの産生亢進及びICAM-1、VCAM-1などの細胞接着分子の発現亢進、B細胞から抗体産生細胞への分化促進などの生理作用を示す。
また、IL-6は活性化した樹状細胞から分泌され、制御性T細胞の活性を抑えることが知られている一方で、T細胞サブセットの一つであるTh17細胞への分化促進を行う。
IL-6はハイブリドーマ(複数の細胞が融合してできた融合細胞のこと。特にモノクローナル抗体を産生する、B細胞と骨髄腫がん細胞の融合細胞を指すことが多い。)の増殖においても必要な因子である。
----------------------------
まことに人体の細胞は複雑かつ精緻に連携している。
----------------------------
2020.5.5
目次へ
ヒドロキシクロロキンという抗マラリア剤がある。
引用:Wikipedia ヒドロキシクロロキン
ヒドロキシクロロキン(英: Hydroxychloroquine)は抗マラリア剤かつ全身性・皮膚エリテマトーデス治療薬である。
海外では関節リウマチの炎症の軽減にも用いられる。
ヒドロキシクロロキン(HCQ)は長い間マラリア治療薬として用いられてきた。
また全身性エリテマトーデス、関節リウマチやシェーグレン症候群、円板状エリテマトーデス等の自己免疫性疾患、晩発性皮膚ポルフィリン症の治療にも用いられる。
日本で承認されている効能・効果は皮膚エリテマトーデスおよび全身性エリテマトーデスである。
ヒドロキシクロロキンは抗原が存在する細胞のリソソームのpHを上昇させる。
炎症時には、HCQは形質細胞様樹状細胞(PDC)上のトール様受容体を阻害する。
トール様受容体9(TLR 9)はDNA(CpG-DNA)を含む免疫複合体を認識するが、インターフェロン産生を誘導し、樹状細胞を成熟させて抗原をT細胞に提示する。
HCQはTLRのシグナル伝達を減弱させ、樹状細胞の活性化ならびに炎症過程を抑制する。
HCQはまたライム病慢性期の関節炎の治療にも使用される。
おそらく抗スピロヘータ活性と抗炎症活性を併せ持ち、リウマチ性疾患の治療と同様の原理で適用可能である。
重大な副作用として添付文書に記載されているものは、網膜症、黄斑症、黄斑変性、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑、紅皮症(剥脱性皮膚炎)、薬剤性過敏症症候群、急性汎発性発疹性膿疱症、血小板減少症、無顆粒球症、白血球減少症、再生不良性貧血、心筋症、ミオパチー、ニューロミオパチー、低血糖である。
抗マラリア薬は一般に親油性弱塩基であり、マラリア原虫の原形質膜を容易に通過する。
非イオン型塩基はリソソーム(酸性の細胞内小胞)に集積し、そこでプロトンを付加されて外部に拡散できなくなり、最終的に培地の1,000倍の濃度に達する。
そのため、リソソームのpHは4から6に上昇する。
pHが変化するとリソソームの酸性プロテアーゼが不活性となり、蛋白質分解機能が低下する。
リソソーム内のpHが高いと多くの免疫学的・非免疫学的細胞内プロセシング、糖鎖付加、蛋白質分泌が低下する。
これらの変化が免疫細胞の走化性や食作用の低下、好中球のスーパーオキシド産生減少をもたらすと思われる。
HCQは2価の弱塩基で、脂質膜を通過し、酸性の細胞質顆粒に優先的に濃縮される。
マクロファージや他の抗原提示細胞内の小胞のpHが上昇すると、抗原ペプチド認識および/またはその後の過程での(あらゆる)自己抗原とクラスII MHC分子との結合、ならびに、細胞膜へのペプチド-MHC複合体の輸送が制限される。
近年、HCQがTLR9ファミリー受容体の刺激を阻害するという新たな作用機序が報告された。
TLRは自然免疫系を活性化して炎症を誘導する微生物生産物の細胞受容体である。
他のキノリン系抗マラリア薬と同様、HCQの作用は完全には解明されていない。
一般的に受け入れられているものは、細胞毒性を有するヘムの凝集を促進する役割を持つヘモゾインの生体内結晶生成の阻害であるとする説である。
遊離ヘムが寄生虫の体内に蓄積し、死亡させるとされる。
ヘモゾインはいくつかの吸血性寄生虫によって血液の消化物から形成される廃棄物である。
マラリア原虫、住血吸虫、一部のサシガメといった吸血動物は、ヘモグロビンを消化して大量の遊離ヘムを放出する。
ヘムはヘモグロビンの補欠分子族で、ポルフィリン環の中央に鉄原子を含んでいる。
遊離ヘムは細胞に対して毒性があるため、寄生虫はそれをヘモゾインと呼ばれる不溶性結晶へと変換する。
-------------------------
マラリアとは?
-------------------------
引用:Wikipedia マラリア原虫
マラリア原虫(まらりあげんちゅう)はアピコンプレックス門に属する寄生性原生生物。
脊椎動物の赤血球内に寄生してマラリアを引き起こす病原体で、吸血昆虫と脊椎動物を行き来する複雑な生活環を持っている。
分類学的にはプラスモジウム属(Plasmodium)におよそ200種が知られており、そのうち少なくとも10種がヒトに感染する。
媒介者はハマダラカ(まれにサシチョウバエ)で、吸血の際に唾液とともに侵入したスポロゾイト(種虫、sporozoite)が、まず肝臓の細胞内でシゾゴニー(増員生殖、schizogony)を行い数を増やす。
種によっては肝臓内でヒプノゾイト(hypnozoite、休眠体)となり数十年に渡って休眠する場合がある。
肝臓から血液中に移行して赤血球内で無性生殖を繰り返し、この時に赤血球が破壊されるために発熱や貧血といった症状が出る。
ときおり生殖母体 (gametocyte) が生じて、吸血に伴って媒介者に移り、その消化管内で配偶子(gamete) を生じて有性生殖が行われる。
接合子には運動能があってオーキネート(ookinete、虫様体)と呼ばれ、それが消化管上皮細胞に侵入してスポロゴニー (sporogony) が行われる。
減数分裂を経て生じたオーシスト (oocyst) は破裂してスポロゾイトを放出し、それが体腔液中を漂って唾液腺に集合する。
つまり脊椎動物は中間宿主で、媒介昆虫が終宿主である。
--------------------
なんという不思議な生物
--------------------
2020.5.6
目次へ
イベルメクチンという薬がある。
引用:Wikipedia イベルメクチン
イベルメクチン(英: ivermectin)は、マクロライド類に属する環状ラクトン経口駆虫薬。
腸管糞線虫症の経口駆虫薬、疥癬、毛包虫症の治療薬でもある。
商品名はストロメクトール(日本ではMSD社製造、マルホ社販売)。
放線菌が生成するアベルメクチンの化学誘導体。
静岡県伊東市内のゴルフ場近くで採取した土壌から、大村智により発見された新種の放線菌「ストレプトマイセス・アベルメクチニウス」(Streptomyces avermitilis)が産生する物質を元に、MSDが創薬した。
線虫のシナプス前神経終末において、γ-アミノ酪酸 (GABA) の遊離を促進することにより、節後神経シナプスの刺激を遮断する。
吸虫や条虫では、末梢神経伝達物質としてGABAを利用しないため無効。
イヌでは、犬糸状虫症の予防のために使用される。
犬糸状虫のミクロフィラリアが血中に存在しているイヌにイベルメクチンを投与すると、ミクロフィラリアが一度に死滅し、発熱やショックを引き起こす場合がある。
したがって、イベルメクチンを予防薬として使用する際は、犬糸状虫の感染の有無を検査する必要がある。
イベルメクチンは、無脊椎動物の神経・筋細胞に存在するグルタミン酸作動性Cl-チャネルに特異的かつ高い親和性を持ち結合し、Cl-に対する細胞膜の透過性を上昇させる。
これにより、Cl-が細胞内に流入するため神経細胞や筋細胞の過分極が生じ、寄生虫が麻痺を起こし死滅する。
イベルメクチンはクリアランスが極めて低く、また血中イベルメクチンの93%程度はアルブミンと結合している。
肝臓で代謝を受けたイベルメクチンはヒドロキシル誘導体となるが、これら誘導体の水溶性は低く、ほとんど尿中排泄されない。
このような化学的・薬理学的性質から、血中半減期はかなり長く(およそ47時間程度)、なおかつ上記の通り、致命的な副反応はほとんど見られないために、臨床上大変有用な薬物である。
また、経口投与後のイベルメクチンは、脂肪細胞と肝臓細胞に局在する。
そのため脂溶性が著しく高いと予想され、すなわちBBB(血液脳関門)を容易に通過できるはずであるが、実臨床において中枢神経系の抑制を示すことは殆どない。
これは、脳血管内皮細胞に発現しているタンパク質である、P糖タンパク質(MDR1)によるイベルメクチンの細胞外汲み出し機能によると考えられている。
2020年4月4日、オーストラリア南東部メルボルンのモナッシュ大学の研究チームは、イベルメクチンに2019新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を抑制する効果があったと発表した。
1回量のイベルメクチンで同ウイルスの複製を48時間以内に止めることができた。
今後、臨床試験を行い、できるだけ早くCOVID-19(新型コロナ肺炎)の治療薬として応用したいとしている。
-------------------------------
ワクチンや集団免疫が実現するまでには、是非とも創薬で快復してほしい。
新しい希望。
-------------------------------
2020.5.9
目次へ
フサンという薬がある。
引用:https://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/about/press/page_00060.html
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の原因ウイルスSARS-CoV-2の感染の最初の段階であるウイルス外膜と、感染する細胞の細胞膜との融合を阻止することで、ウイルスの侵入過程を効率的に阻止する可能性がある薬剤としてナファモスタット(Nafamostat mesylate、商品名フサン)を同定した。
SARS-CoV-2などのコロナウイルスは、脂質二重層と外膜タンパク質からなるエンベロープ(外膜)でウイルスゲノムRNAが囲まれている。
SARS-CoV-2はエンベロープに存在するSpikeタンパク質(Sタンパク質)が細胞膜の受容体(ACE2受容体)に結合したあと、ヒトの細胞への侵入を開始する。
Sタンパク質はFurinと想定されるヒト細胞由来のプロテアーゼ(タンパク質分解酵素)によりS1とS2に切断される。
その後S1が受容体であるACE2受容体に結合する。
もう一方の断片S2はヒト細胞表面のセリンプロテアーゼであるTMPRSS2で切断され、その結果膜融合が進行する。
HoffmannらによりSARS-CoV-2の感染にはACE2とTMPRSS2が気道細胞において必須であることが発表された。
井上らは、2016年にMERS-CoV Sタンパク質、受容体CD26、TMPRSS2に依存した膜融合系を用いてセリンプロテアーゼ阻害剤であるナファモスタットが膜融合を効率よく抑制してMERS-CoVの感染阻害剤になることを提唱した。
そこで今回、293FT細胞(ヒト胎児腎臓由来)を用いてSARS-CoV-2 Sタンパク質、受容体ACE2、TMPRSS2に依存した膜融合測定系を用いて、ナファモスタットがSARS-CoV-2 Sタンパク質による膜融合を抑制するかどうか検討した。
その結果ナファモスタットは10から1000 nMの濃度域で濃度依存的に抑制した。
つぎにACE2やTMPRSS2を内在的に発現し、ヒトで感染が起こるさいに重要な感染細胞と考えられる気道上皮細胞由来のCalu-3細胞を用いて同様の実験を行ったところ、さらに低濃度の1-10 nMで顕著に膜融合を抑制した。
この濃度域はMERS-CoV Sタンパク質による膜融合に対する抑制濃度域とほぼ同じである。
さらに井上らはナファモスタットと類似のタンパク質分解阻害剤であるカモスタットの作用を比較検討したところ、SARS-CoV-2 Sタンパク質による融合において、ナファモスタットはカモスタットのおよそ10分の1の濃度で阻害効果を示すことが明らかになった。
以上から、臨床的に用いられているタンパク分解阻害剤の中ではナファモスタットが最も強力であり、COVID-19に有効であると期待される。
ナファモスタット、カモスタットともに膵炎などの治療薬剤として本邦で開発され、すでに国内で長年にわたって処方されてきた薬剤である。
ナファモスタットは臨床では点滴静注で投与されるが、投与後の血中濃度は今回の実験で得られたSARS-CoV-2 Sタンパク質の膜融合を阻害する濃度を超えることが推測され、臨床的にウイルスのヒト細胞内への侵入を抑えることが期待される。
カモスタットは経口剤であり、内服後の血中濃度はナファモスタットに劣ると思われるが、他の新型コロナウイルス薬剤と併用することで効果が期待できるかもしれない。
井上らは、2016年にMERS-CoV Sタンパク質、受容体CD26、TMPRSS2に依存した膜融合系を用いてセリンプロテアーゼ阻害剤であるナファモスタットが膜融合を効率よく抑制してMERS-CoVの感染阻害剤になることを提唱した。
そこで今回、293FT細胞(ヒト胎児腎臓由来)を用いてSARS-CoV-2 Sタンパク質、受容体ACE2、TMPRSS2に依存した膜融合測定系を用いて、ナファモスタットがSARS-CoV-2 Sタンパク質による膜融合を抑制するかどうか検討した。
その結果ナファモスタットは10から1000 nMの濃度域で濃度依存的に抑制した。
つぎにACE2やTMPRSS2を内在的に発現し、ヒトで感染が起こるさいに重要な感染細胞と考えられる気道上皮細胞由来のCalu-3細胞を用いて同様の実験を行ったところ、さらに低濃度の1-10 nMで顕著に膜融合を抑制した。
この濃度域はMERS-CoV Sタンパク質による膜融合に対する抑制濃度域とほぼ同じである。
さらに井上らはナファモスタットと類似のタンパク質分解阻害剤であるカモスタットの作用を比較検討したところ、SARS-CoV-2 Sタンパク質による融合において、ナファモスタットはカモスタットのおよそ10分の1の濃度で阻害効果を示すことが明らかになった。
以上から、臨床的に用いられているタンパク分解阻害剤の中ではナファモスタットが最も強力であり、COVID-19に有効であると期待される。
ナファモスタット、カモスタットともに膵炎などの治療薬剤として本邦で開発され、すでに国内で長年にわたって処方されてきた薬剤である。
ナファモスタットは臨床では点滴静注で投与されるが、投与後の血中濃度は今回の実験で得られたSARS-CoV-2 Sタンパク質の膜融合を阻害する濃度を超えることが推測され、臨床的にウイルスのヒト細胞内への侵入を抑えることが期待される。
カモスタットは経口剤であり、内服後の血中濃度はナファモスタットに劣ると思われるが、他の新型コロナウイルス薬剤と併用することで効果が期待できるかもしれない。
2020.5.16
目次へ
経鼻ワクチンのことをもう少し調べてみたい。
引用:https://www.amed.go.jp/news/release_20190104.html
国立感染症研究所
生体内において最も産生量の多い抗体であるIgA抗体は、インフルエンザ等の粘膜組織を標的とした感染症に対する生体防御の最前線で機能しています。
経鼻不活化インフルエンザワクチンを接種すると、ヒト呼吸器粘膜上にはウイルス特異的な単量体、二量体、三量体、四量体および四量体以上の多量体のSIgA抗体が誘導されることが解っています。
三量体、四量体および四量体以上の多量体抗体は、単量体や二量体抗体に比べ抗インフルエンザウイルス活性が高い(高機能である)ことから、これらの抗体は感染防御に一定の役割を担っており、経鼻ワクチンの有効性発現機構においても重要であると考えられています。
インフルエンザウイルスのように変異を起こしやすい病原体は、ウイルス粒子表面の抗原を変異させることにより抗体などの免疫を回避することが知られています。
インフルエンザウイルスが毎年のように流行を繰り返す理由の1つは、この抗原変異によるものですが、粘膜上に分布するSIgA抗体は多量体化することにより交叉反応性(元々の抗体の産生反応を引き起こした原因である抗原以外の別の抗原に結合すること)を向上させ、1種類の可変領域を有する抗体が抗原性の異なる多様なウイルスに対応できると言われています。
単量体の抗体の反応性や機能は、抗体の「腕」の部分の可変領域と言われる部分で決定されます。
強く結合できるウイルスに対しては、高い抗ウイルス活性を示しますが、結合が弱いウイルスに対して弱い抗ウイルス活性しか示しません。
一方、この抗体を四量体化させると(腕の数が2本から8本に増える)、元々の結合が強いウイルスに対する抗ウイルス活性は変化しませんでしたが、元々の結合が弱いウイルスに対する結合力が強くなるとともに抗ウイルス活性が最大で数十倍まで高くなりました。
以上の結果は、四量体SIgA抗体は、抗体の特異性を決定する可変領域を変化させることなく抗体の標的域(交叉性)を拡張することができることを意味しており、このことこそがSIgAが四量体化することの生物学的な意義と考えられます。
---------------------------
このようなワクチンは今回、開発中なのか。
---------------------------
引用:https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP533632_R00C20A5000000/
発表日:2020年5月1日
1.国立感染症研究所との共同研究開発について
IDファーマと国立感染症研究所は、IDファーマが基盤技術として保有するセンダイウイルスベクターを用いて、エイズをはじめとする感染症ワクチンの研究開発を長年にわたり共同で行っており、その共同研究課題の一つとして、新型コロナウイルスに対する新しいワクチンについても共同で研究開発を進めています。
本共同研究開発では、国立感染症研究所のもつ新型コロナウイルスのゲノム情報を基に、IDファーマがセンダイウイルスベクター技術を用いて新型コロナウイルスに対する新規ワクチンを作製し、国立感染症研究所において当該ワクチンの前臨床試験、臨床試験等を実施いたします。
2.文部科学省への申請について
新規ワクチンを作製するにあたっては、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(略称「カルタヘナ法」)」の規定により、文部科学省への本件確認申請が必要であり、この度、同省へ本件確認申請書を提出いたしました。
-----------------------------
これが経鼻ワクチンの開発なのだろうか。
-----------------------------
2020.5.20
目次へ
ウィルスに抗体が反応するというが、実際、どうやって初期抗体ができるのだろうか。
再びそのウイルスが侵入してきたとき、膨大な数の抗体の中から、合致する抗体を特定できたとして、その抗体を多量に産生する仕組みはどうなっているのだろう。
引用:Wikipedia 抗体
抗体が抗原と結合する際、抗原の一部分(エピトープ)のみを認識して結合する。
抗体はエピトープの立体構造を厳密に認識して結合し、エピトープのアミノ酸配列の違いはもちろんのこと、荷電の差、光学異性体、立体異性体の違いでも結合しなくなる。
エピトープと結合する抗体側の部分をパラトープという。
エピトープとパラトープの間には、水素結合、静電気力、ファンデルワールス力、疎水結合などの引力がかかり、これらの力により安定して結合する。
このエピトープとパラトープの間の結合力のことをアフィニティ affinity という。
ただし、抗体は基本の4本鎖構造においては、抗原と結合する部位は2カ所であるが、IgMは五量体、IgAは二量体を形成するのでさらに多くの抗原認識部位を持っている。
また、抗原によってはエピトープを複数もつ。
このため抗体によっては、抗原と抗体は1か所で結合したり(1価)、同時に複数か所で認識したりする(多価)。
このように抗原と抗体が結合するときの結合力の総和をアビディティ avidity と呼ぶ。
多価の結合の際、結合力が相乗的に働くため、アビディティはアフィニティよりも高くなる。
マクロファージや好中球といった食細胞は、もともと細菌や死んだ細胞に結合する能力を持っているが、こういった細菌や死細胞に抗体や補体(抗体および貪食細胞を補助する免疫システム を構成するタンパク質)が結合すると、食細胞がもつ補体受容体やFc受容体を介して結合し、食作用を促進する。
これをオプソニン作用という。
あらゆる抗原に対応するために、体内では可変領域の異なる重鎖と軽鎖を何百・何千万種類と用意する。
このような抗体の多様性をどのようにして作り出しているのかは、長い間不明であった。
1897年エールリヒは、もともとさまざまな抗原に対する鋳型を細胞表面にもっている細胞があり、その鋳型が抗原に出会うと、それが刺激となってその抗原に対する抗体を産生すると考えた(側鎖説)が、ラントシュタイナーは、新しく人工合成された化合物に対しても抗体が作用することを示し、この世になかった物質に対する鋳型をもともと細胞が持っていたとは考えにくく、抗体の多様性は側鎖説だけでは説明がつかないと考えた。
その後、抗体は抗原に出会うとそれに結合できるように自らの姿を変えることができるという説(鋳型説)や、抗原の刺激により抗体が後天的に作られるという説(指令説)が唱えられたが、1959年エーデルマンが免疫グロブリンの基本構造を解明し、また1958年クリックにより、タンパクは遺伝子の情報に基づいて作られることが明らかになる(セントラルドグマ)と、鋳型説・指令説は否定的と考えられた。
それに代わってバーネットの提唱したクローン選択説(1957年)が受け入れられるようになった。
つまり、リンパ球はそれぞれ1種類の抗体しか作ることができず、そのため体内には非常に多くの種類のリンパ球が先天的に用意されている。
そして抗原が体内に侵入すると、その抗原と結合できるリンパ球が選ばれて増殖し(クローン)、この抗原に対する抗体を産生する、という説である。
この説は種々の実験によって正当性が証明されていったが、クローン選択説もエールリヒの側鎖説と同じように、全く未知の抗原に対応できるような抗体を、遺伝子はどうやって用意できるのか、という点は不明であった。
非常に多くの種類の抗体の構造がひとつひとつ全て遺伝子に書き込まれているとは考えにくかった。
1976年利根川らは免疫グロブリンの遺伝子再構成という現象を発見し、この抗体の多様性に関する遺伝子レベルの謎に答えを出した。
その他、体細胞超変異、遺伝子変換、クラススイッチ組み換えといった現象も抗体の多様性に関与していることが知られている。
----------------------------------
遺伝子再構成、か。
----------------------------------
B細胞に分化する前の生殖細胞の遺伝子では、重鎖可変領域 (VH) をコードする遺伝子は、VH遺伝子部分、DH遺伝子部分、JH遺伝子部分の3つに分かれており、この3つの遺伝子部分にそれぞれ、可変領域の遺伝子断片が複数個コードされている。
抗体を産生するB細胞の重鎖可変領域の遺伝子は、VH遺伝子部分にコードされているいくつかの遺伝子断片の中から1種類、DH遺伝子部分から1種類、JH遺伝子部分から1種類が選ばれて、それが組み立てられてつくられる。
VH遺伝子部分に50の遺伝子断片、DH遺伝子部分に30の遺伝子断片、JH遺伝子部分に6種類の遺伝子断片があるとすると、その組み合わせは50×30×6 = 9000種類となる。
軽鎖可変領域 (VL) をコードする遺伝子は、重鎖よりも少なく、VL遺伝子部分、JL遺伝子部分の2つの部分からなる。
同じようにVL遺伝子部分に35の遺伝子断片、JL遺伝子部分に5つの遺伝子断片があるとすると、その組み合わせは35×5 = 175種類となる。
そして、9000種類の重鎖と175種類の軽鎖の組み合わせは9000×175 = 150万種類以上となる。このように、重鎖のV、D、J、軽鎖のVとJの遺伝子断片の組み合わせで多様な遺伝子をもつB細胞ができ、それぞれ異なった種類のB細胞がそれぞれ異なった抗体を作ることで多様な抗体がつくられる。
これをV(D)J遺伝子再構成といい、主にヒトやマウスでみられる。
各細胞につき、遺伝子再構成が起こるのは相同染色体の片方だけであり、再構成がないほうの遺伝子は不活化される。
幹細胞が分化して体のさまざまな細胞に分化していくが、この分化した細胞を体細胞という。
幹細胞が体細胞に分化していくときにごく稀に遺伝子に変異が起こることがある(体細胞変異)。
B細胞は変異の頻度が極めて高く、1万倍にも及ぶ。
これは末梢の成熟したB細胞の中で、T細胞依存性抗原で活性されたB細胞は胚中心を形成し、この微小環境内で免疫グロブリン遺伝子のV領域が、AID(activation-induced cytidine deaminase)により様々な塩基置換を引き起こされるためである。
このメカニズムを体細胞超変異といい、ヒトやマウスにおいて抗体の多様性や親和性の成熟に関与している。
V(D)J遺伝子再構成等の過程を経て生まれたB細胞は、抗原の刺激を受けると成熟化し、増殖する。
この際、重鎖定常領域 (CH) をコードする遺伝子にDNA改変が起こり、最初IgMを分泌していたB細胞はIgG等他のクラスの免疫グロブリンを産生する。
同じ可変領域を異なる定常領域と組み合わせることにより、さらに多様な抗体を作り出す。
このことをクラススイッチ組み換えという。
----------------------------------
遺伝子のパーツの組み合わせで数百万通りの抗体ができるということか。
抗原に出会った抗体が適合したとき、再産生する仕組みは?
適合する抗体がなかったとき、新規に産生する仕組みは?
----------------------------------
2020.6.1
目次へ
ウイルスの侵入について。
引用:http://jsv.umin.jp/journal/v65-1pdf/virus65-1_127-134.pdf
細胞がウイルスの侵入をどう感知して,それがウイルス特異的な免疫応答の誘導にどう役立っているのか?を理解することは,効果的なワクチン開発に不可欠である.
インフルエンザウイルスはその表面抗原として標的細胞への接着に必要なヘマグルチニン
(HA)と,増殖したウイルスが細胞から遊離する時に必要なノイラミニダーゼ(NA)の2 種類の糖タンパク質を持つ.
これらHA とNA は同一の亜型内で毎年少しずつその抗原性を変化させるために(連続抗原変異,antigenic drift),ウイルスは巧みにヒトの免疫機構から逃れ流行し続ける.
インフルエンザウイルスに罹患したヒトは,その後数年間にわたって小さい変異のインフルエンザウイルスに再度感染しにくいことが疫学的に知られている(交叉防御効果).
この防御能は主にインフルエンザウイルスが自然感染した際に誘導される鼻粘膜上のウイルス特異的な分泌型IgA抗体によるものと考えられている.
鼻粘膜上にウイルス特異的な分泌型IgA 抗体を誘導するため,現行の不活化インフルエンザワクチン(HA ワクチン)を鼻腔内に噴霧して,粘膜免疫を誘導する試みが我が国を含むいくつかの国で続けられている.
しかしインフルエンザウイルスに罹患した経験のない小児や免疫力が低下した高齢者においてはワクチンのみの接種では充分に粘膜免疫を誘導できない.
この問題を解決するには,適当なアジュバントと共にこの不活化ワクチンを経鼻投与する必要がある.
インフルエンザウイルスは,少なくとも3つの自然免疫受容体によって認識されている.
①TLR7(動物の細胞表面にある受容体タンパク質で、種々の病原体を感知して自然免疫(獲得免疫と異なり、一般の病原体を排除する非特異的な免疫作用)を作動させる機能がある。) はエンドゾーム内でインフルエンザウイルスのゲノムRNA を認識する.
②細胞質中のRIG-I(ヒトの自然免疫系で働くタンパク質の分子。ウイルスが細胞内に進入した時にウイルス由来のRNAを認識し、抗ウイルス作用を示すI型インターフェロン産生の誘導を引き起こす、細胞質内に存在するRNAヘリカーゼ(核酸をほどく酵素))は,ウイルスのゲノムRNA を認識する.
③これとは対照的に, インフルエンザウイルスRNA はNLRP3(免疫系タンパク質の1つで、インフラマソームと呼ばれるタンパク質複合体の構成成分で、炎症応答を促進する。)を活性化しない.
インフルエンザウイルスによるNLRP3 inflammasome の活性化には,インフルエンザ
ウイルスM2 タンパク質のH+ チャネル活性が必要である.
M2 タンパク質は,トランスゴルジ内のH+ を細胞質中へ流出させてNLRP3 inflammasome を活性化させていた.
弱酸性のトランスゴルジ内のpH をM2 タンパク質が中和することは,インフルエンザウイルスHA タンパク質の正しい立体構造を保つため(感染性のあるウイルス粒子を産生するため)に必要である.
このことは宿主側が,効率的なウイルスの増殖に必要なウイルス側の戦略を逆手にとり,宿主のウイルス認識機構に利用している可能性を示唆している.
他にも,ピコルナウイルス科の脳心筋炎ウイルス(EMCV),ポリオウイルス,エンテロウイルス71 型,ヒトライノウイルスの2B タンパク質がNLRP3 inflammasomeを活性化させること,RS ウイルス(respiratory syncytial virus)のSH タンパク質がIL-1β の産生を促進させることが報告されており,このようなviroporin(ウイルスがコードするイオンチャネルタンパク質)は,RNA ウイルスがNLRP3 inflammasome を活性化させるメカニズムのひとつであると考えられる.
インフルエンザウイルスによるNLRP3 inflammasomeの活性化には,ミトコンドリアの膜電位(連結したミトコンドリア)が必要であるが,インフルエンザウイルスPB1-F2 タンパク質は,ミトコンドリア外膜上のTom40 チャネルにより膜間スペースへ輸送され,ミトコンドリアの膜電位を低下(連結したミトコンドリアを断片化)させることにより,NLRP3 inflammasome の活性化を抑制していた.
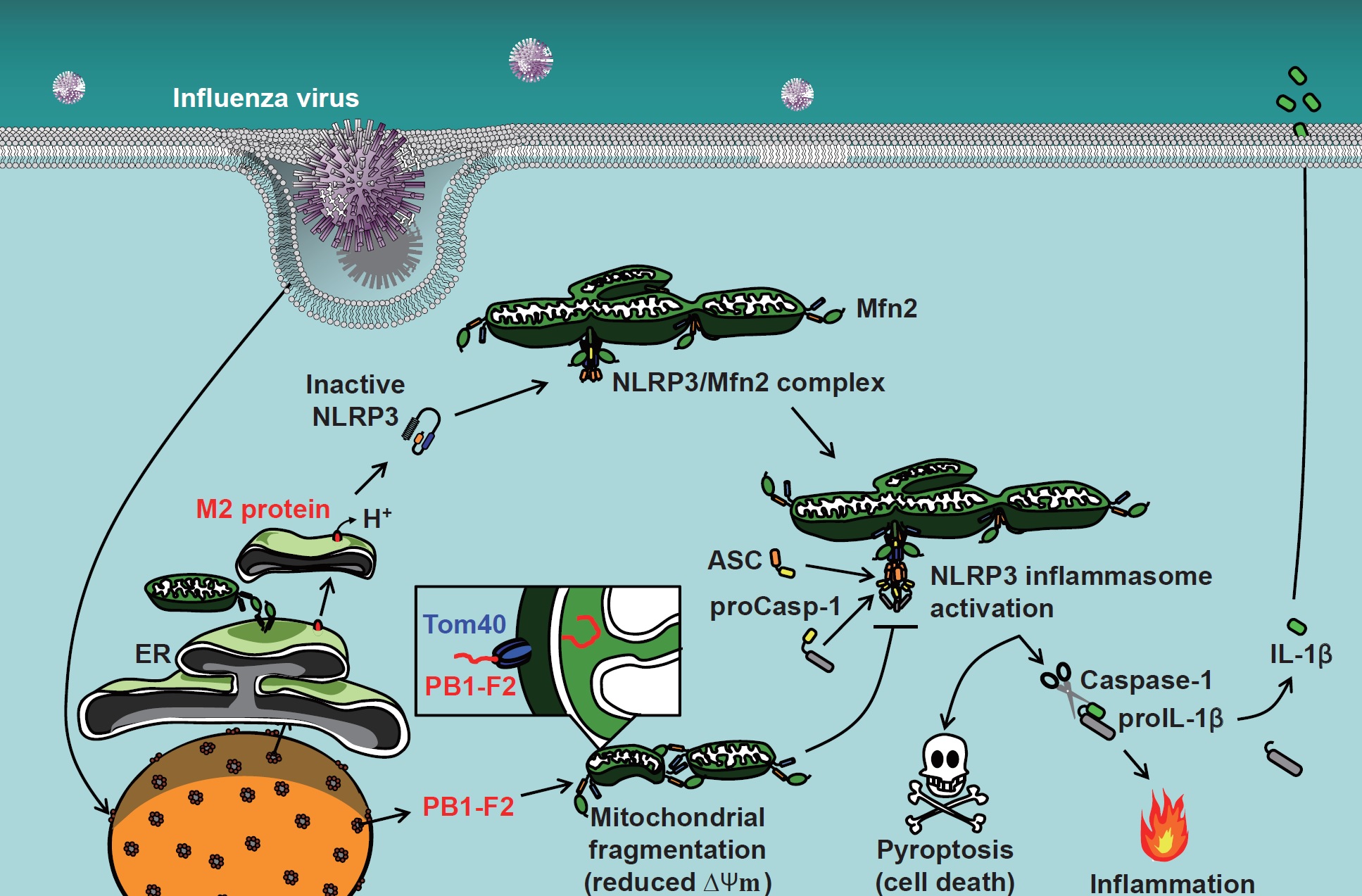
インフルエンザウイルスM2 タンパク質は,トランスゴルジ中のH+ を細胞質中に流出させてNLRP3 を活性化させている.
活性化したNLRP3 は,ミトコンドリア外膜タンパク質のmitofusin 2 (Mfn2) と相互作用して,これを足場にアダプタータンパク質のASC や未成熟型caspase-1 が集合し,NLRP3 inflammasome を形成する.
これにより活性化したcaspase-1 は,caspase-1 依存的な細胞死(pyroptosis)や炎症性サイトカインのIL-1β,IL-18 の成熟化と分泌を促進させる.
インフルエンザウイルスPB1-F2 タンパク質は,Tom40 チャネルによりミトコンドリアの膜間スペースへ輸送され,ミトコンドリアの膜電位を低下(ミトコンドリアの断片化)させることにより,NLRP3 inflammasome の形成を抑制している.
2020.10.22 モノクロナール抗体
目次へ
引用:Wikipedia
モノクローナル抗体(モノクローナルこうたい)とは、単一の抗体産生細胞に由来するクローンから得られた抗体、あるいは抗体分子である。
通常の抗体(ポリクローナル抗体)は抗原で免疫した動物の血清から調製するため、いろいろな抗体分子種の混合物となるが、モノクローナル抗体は抗体分子種が均一である。
抗原は複数のエピトープ(抗原決定基)を持つことが多く、ポリクローナル抗体は各々のエピトープに対する抗体の混合物となるため、厳密には抗原特異性が互いに異なる抗体分子が含まれている。
これに対し、モノクローナル抗体では用いる抗原のエピトープが単一であるため、抗原特異性も単一である。
通常、抗体産生細胞と骨髄腫細胞とを細胞融合させることで自律増殖能を持たせた融合細胞ハイブリドーマ (hybridoma) を作成し、目的の抗原特異性をもつ融合細胞のみを選別(スクリーニング)し、これを抗原細胞とする。
この抗原細胞を培養し、分泌物を精製して目的のモノクローナル抗体が作製される。1975年にモノクローナル抗体の作製方法を発明したジョルジュ・J・F・ケーラーとセーサル・ミルスタインは、1984年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。
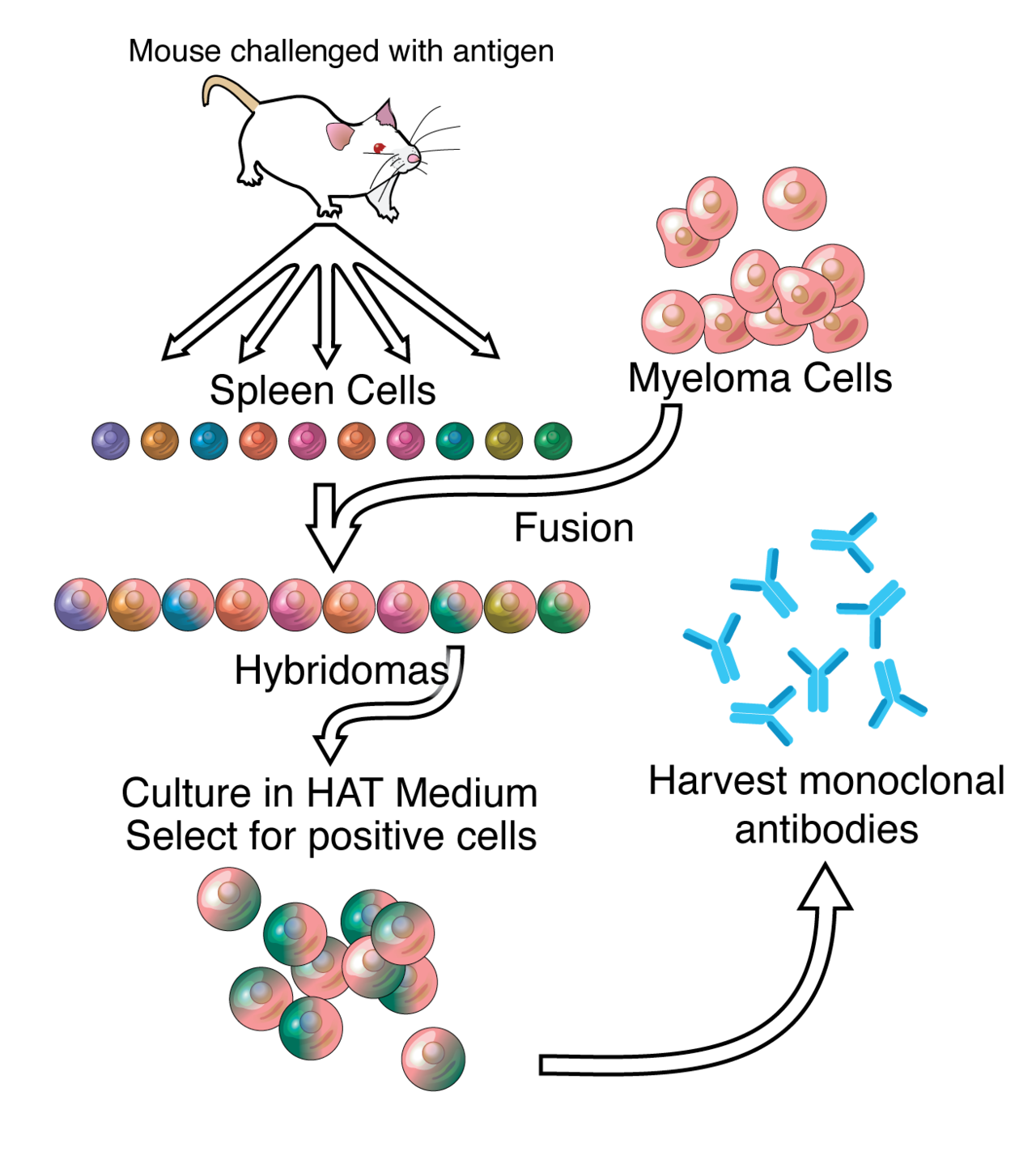
はじめに
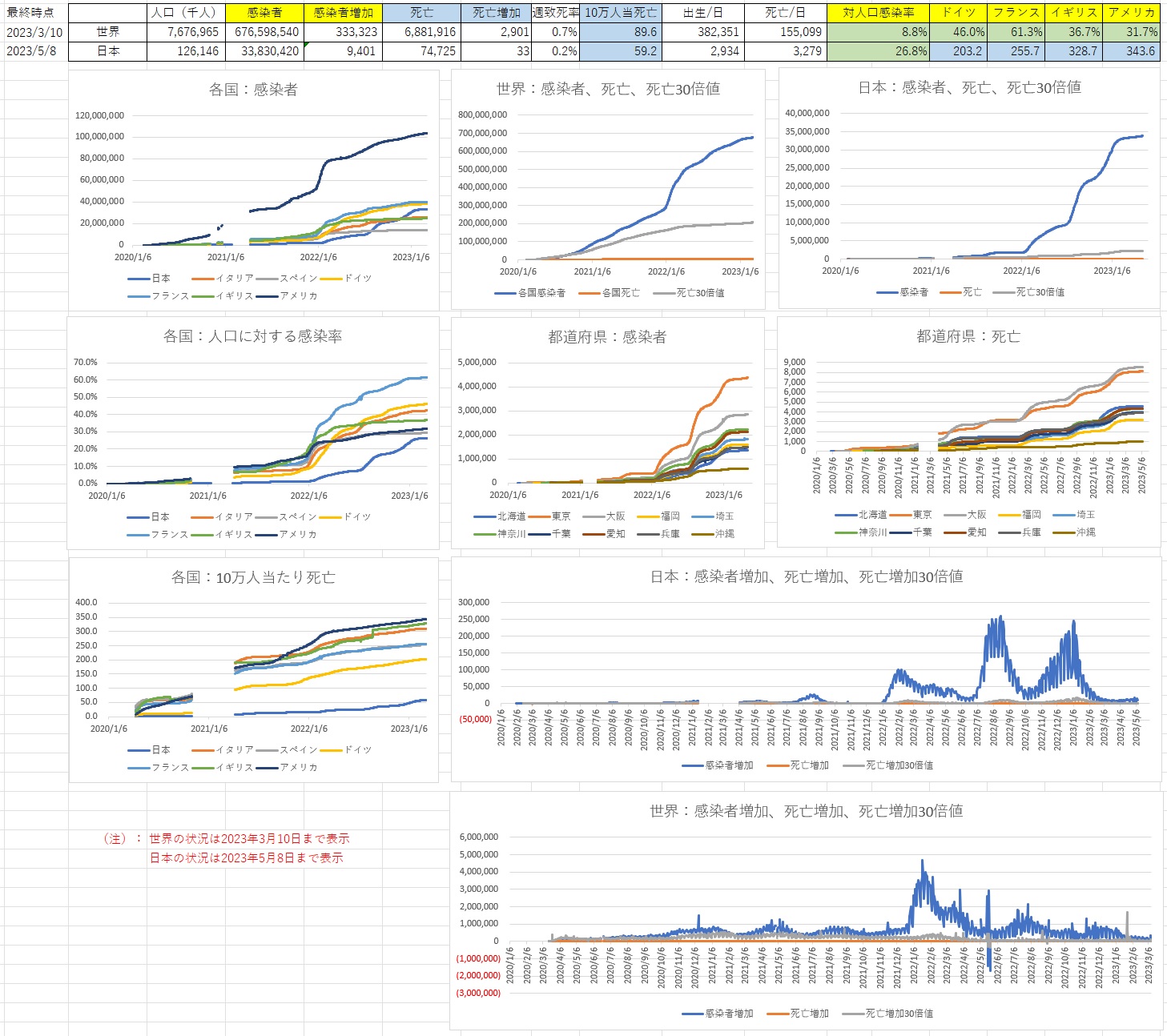
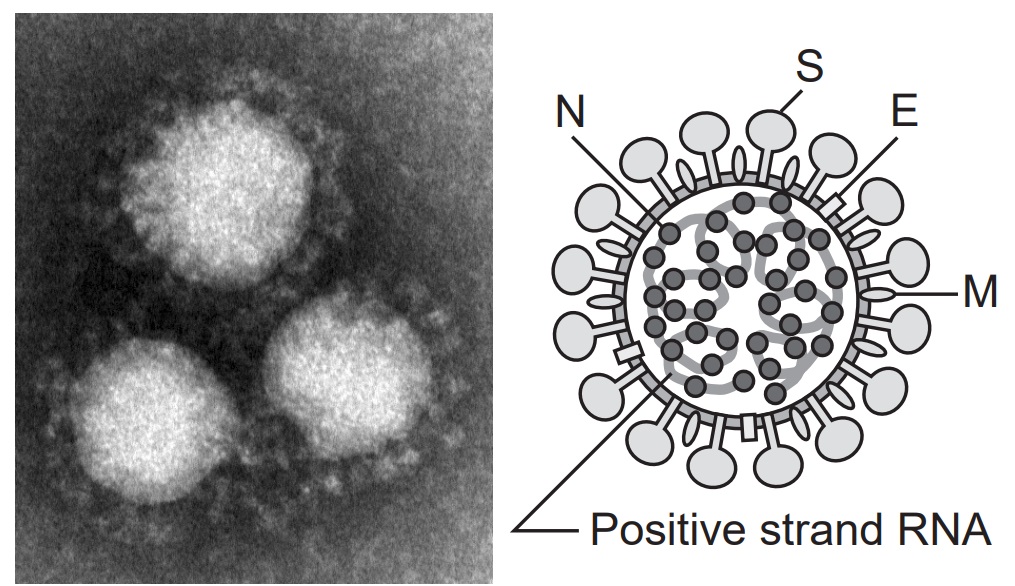
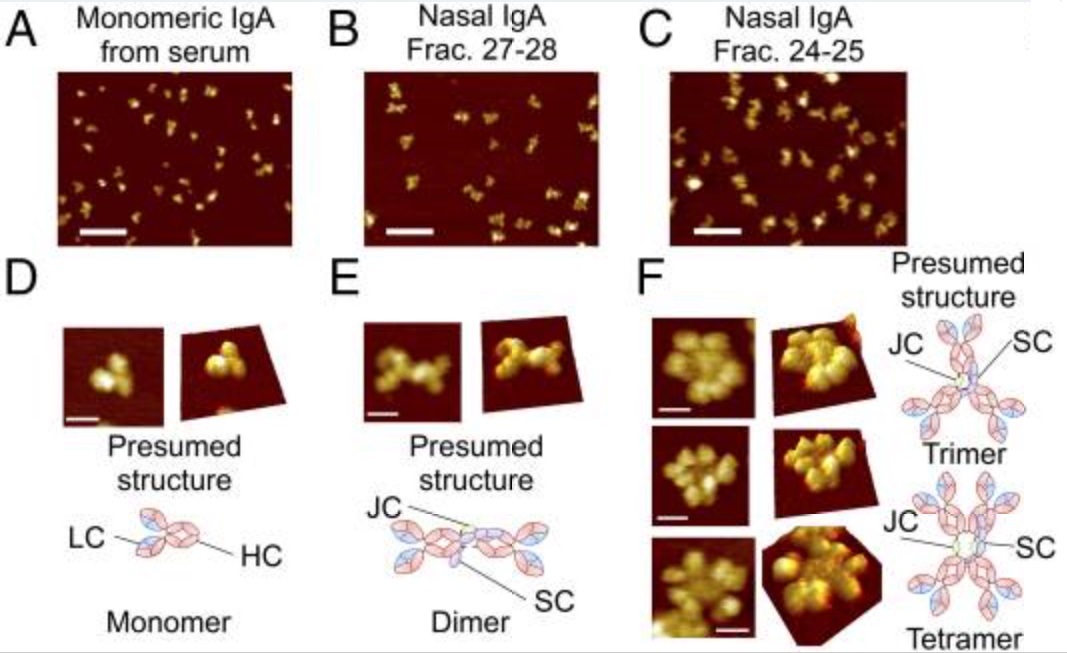
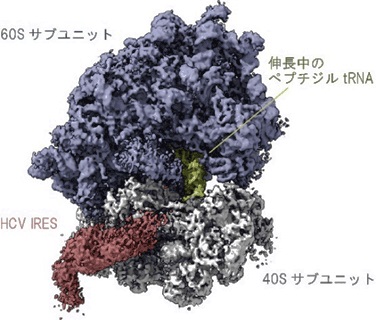
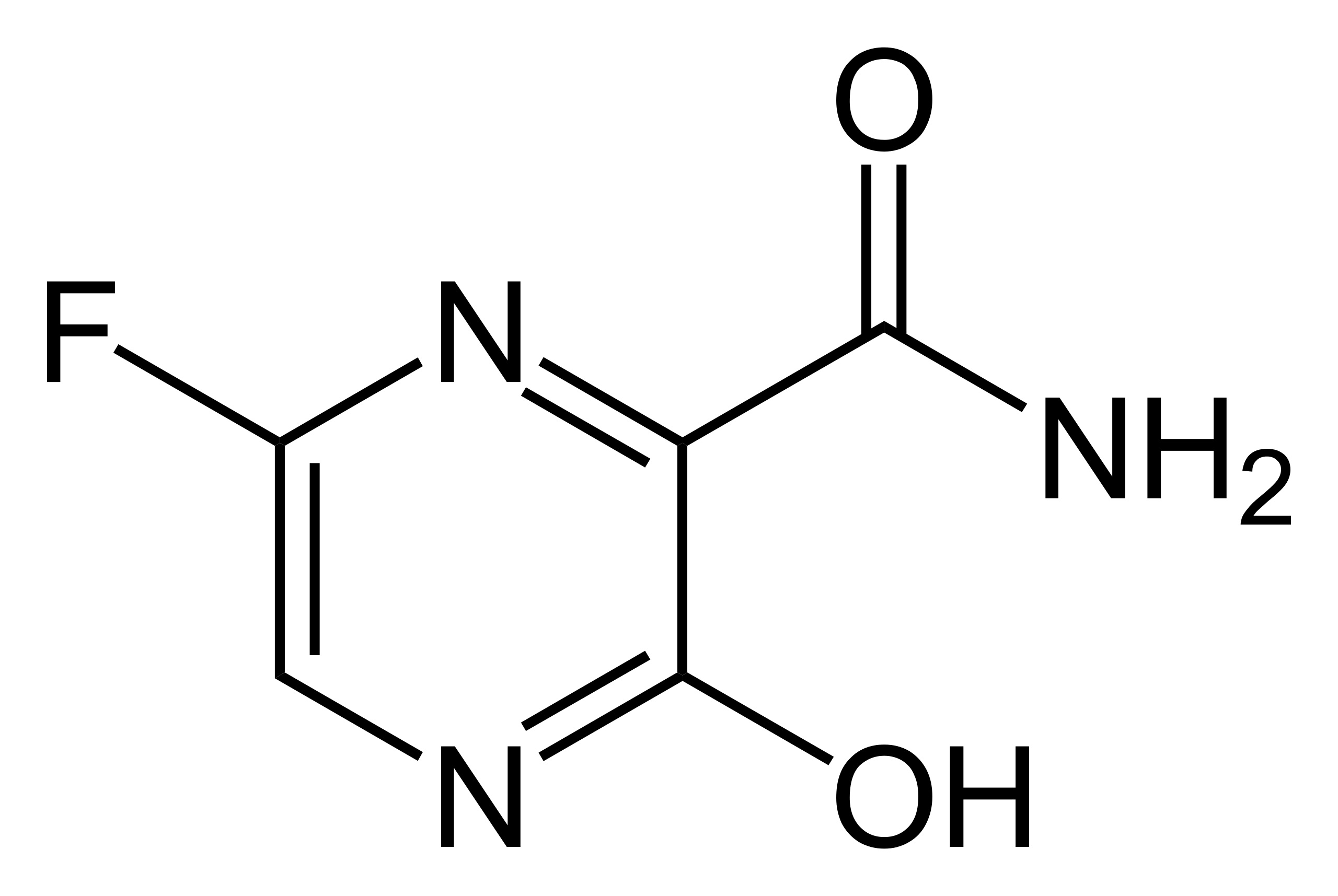
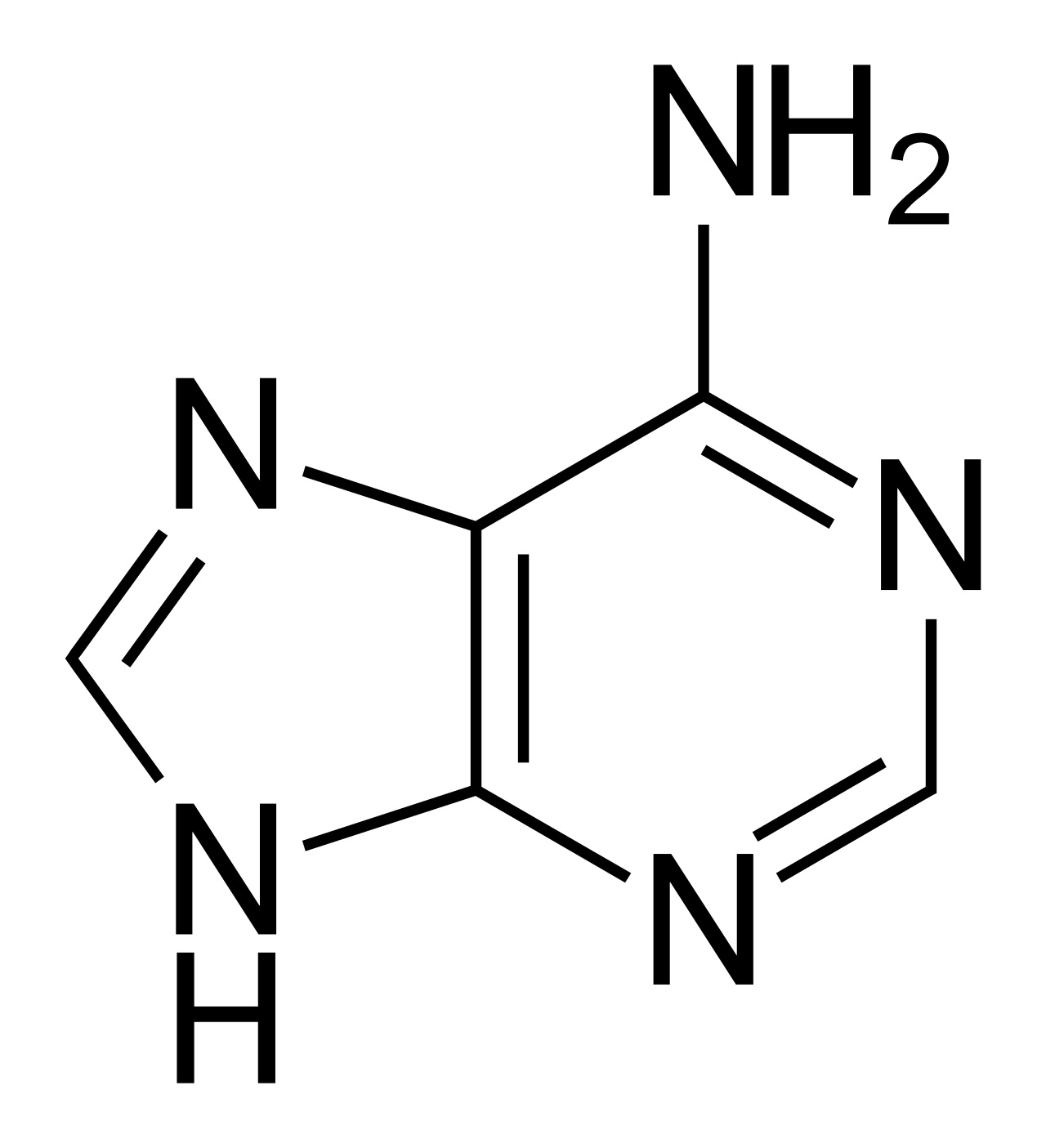
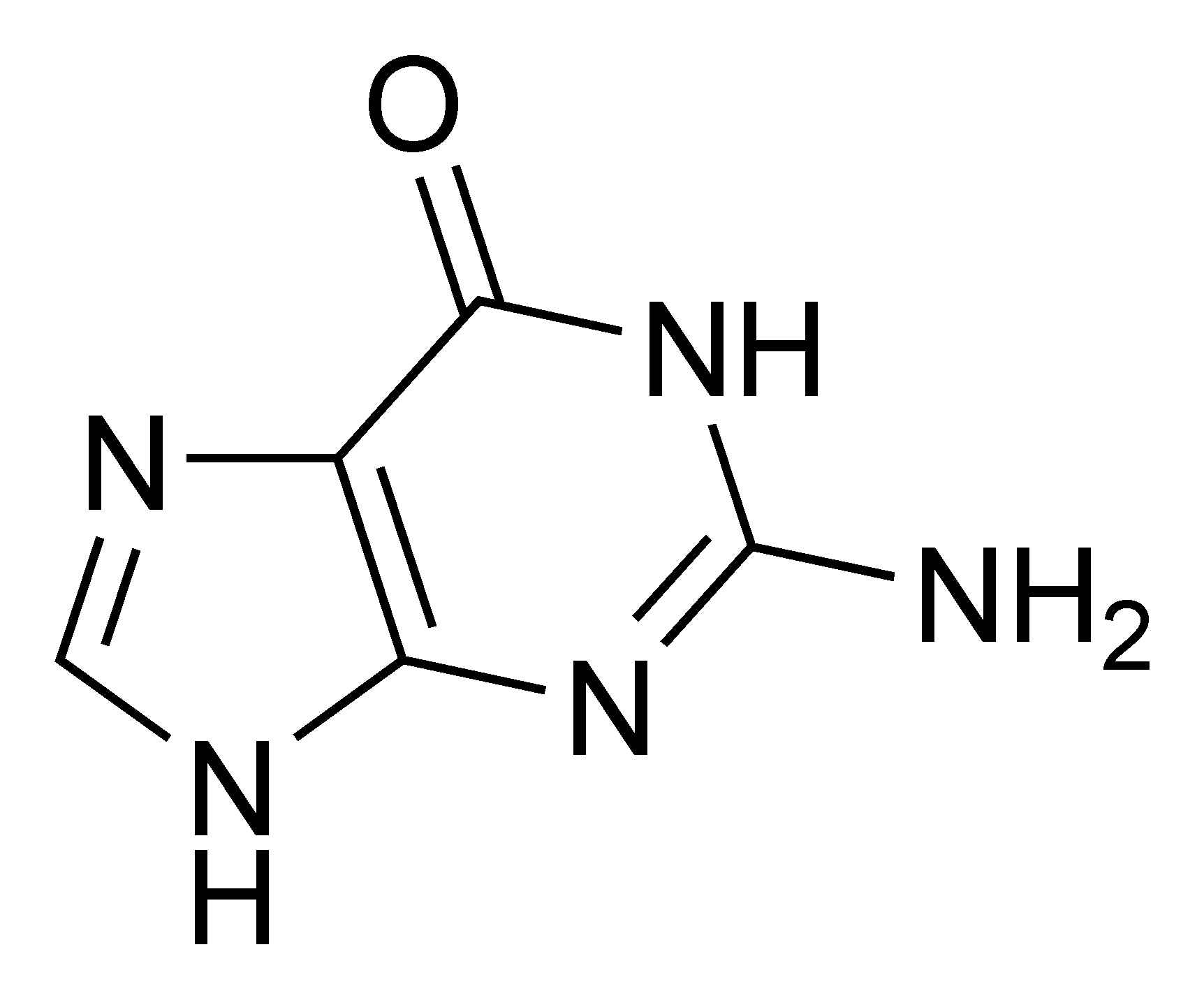
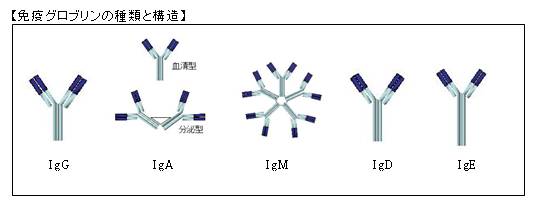
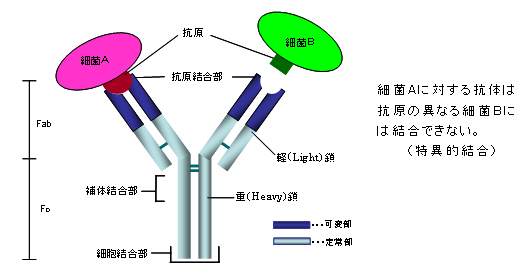
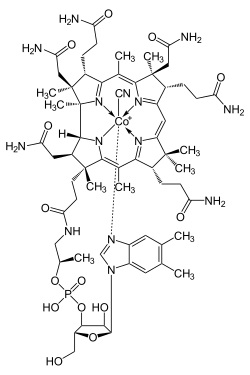
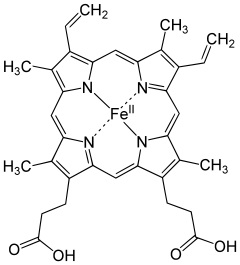
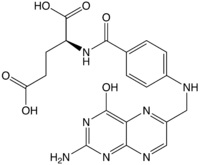
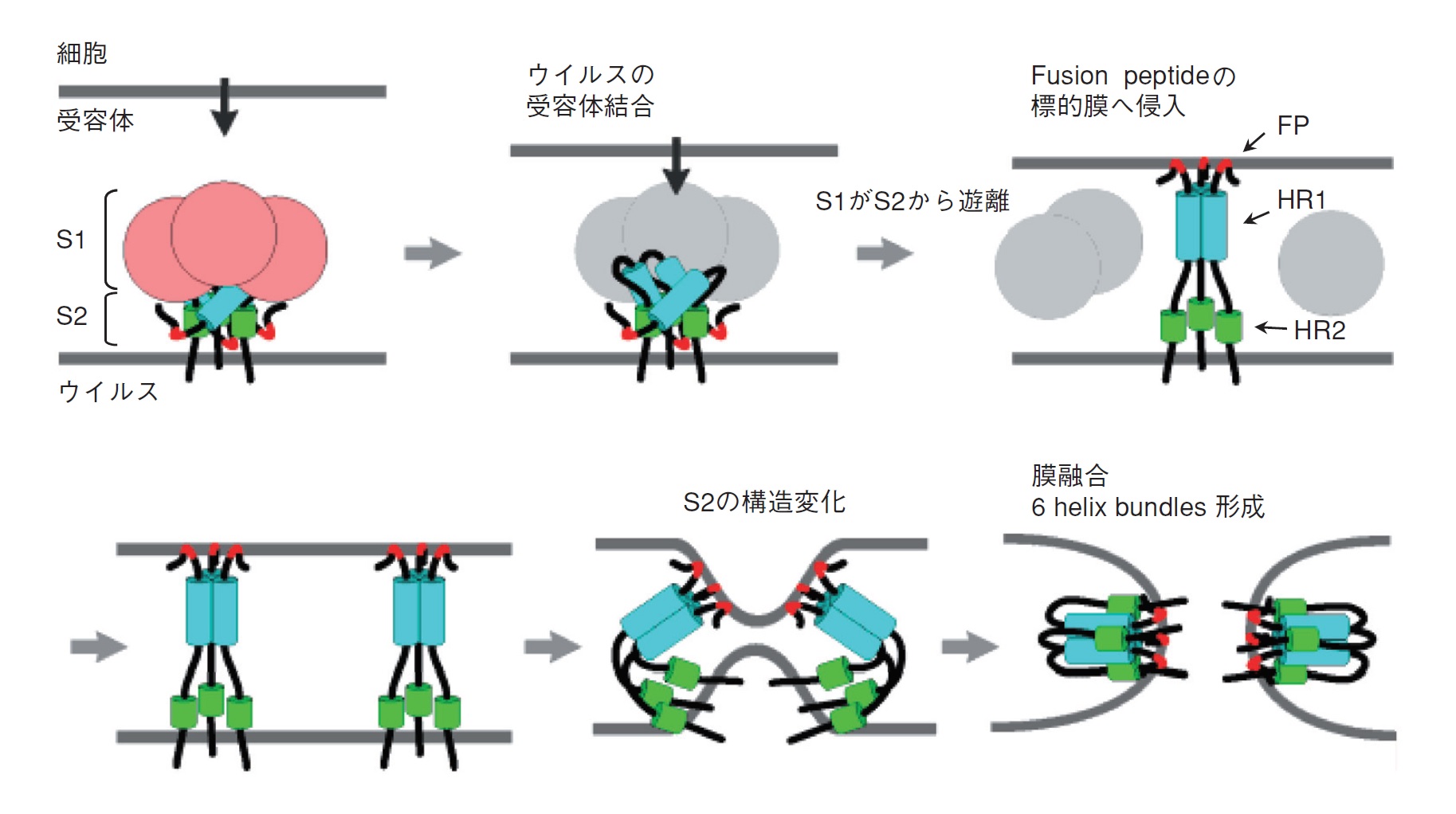
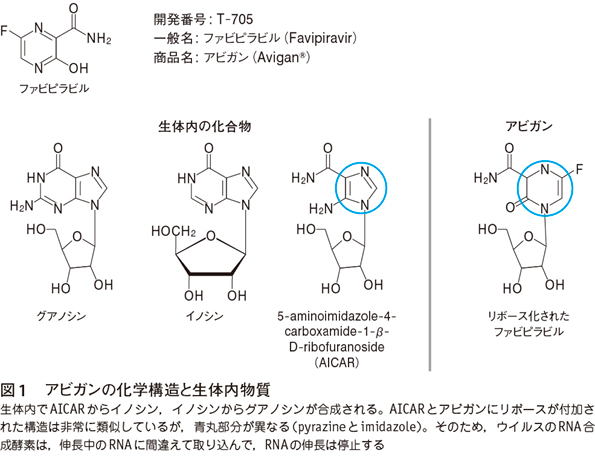
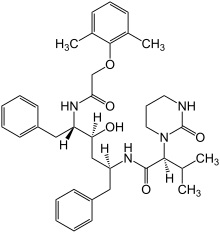
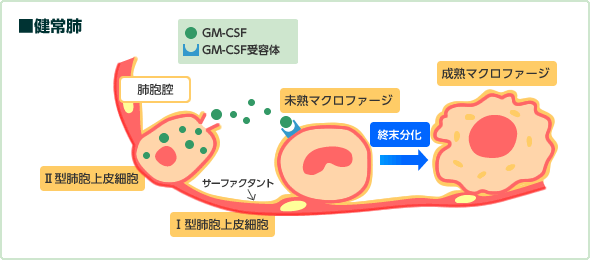
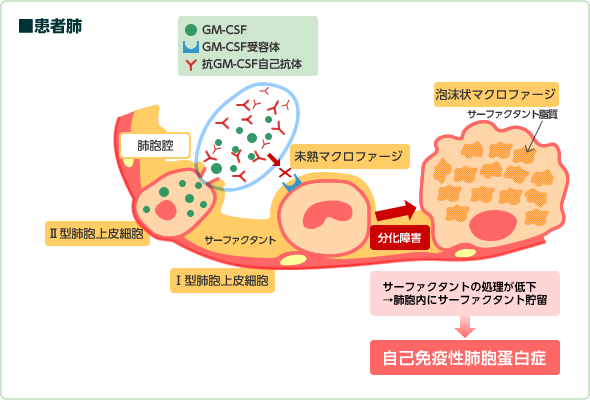
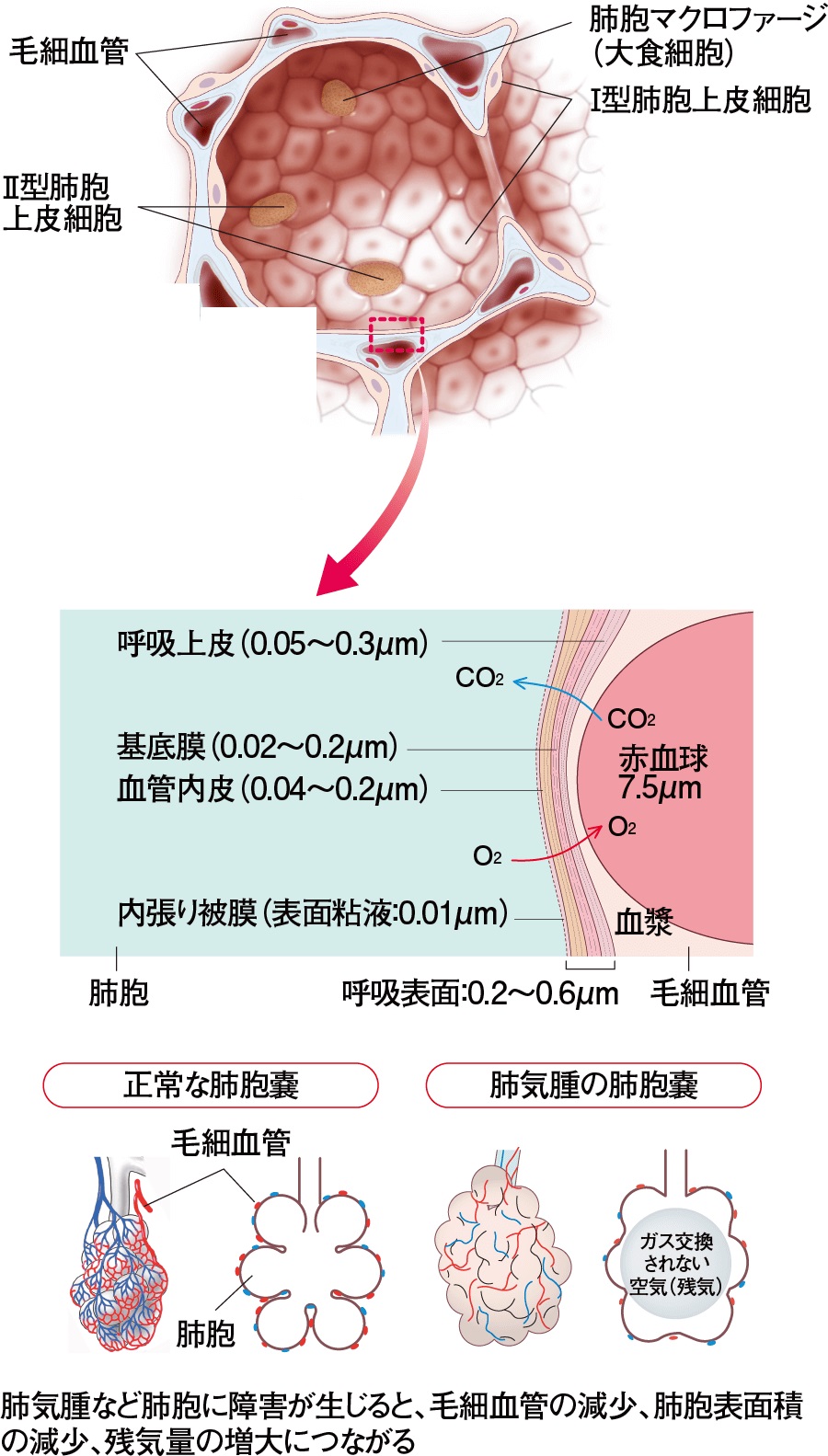
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
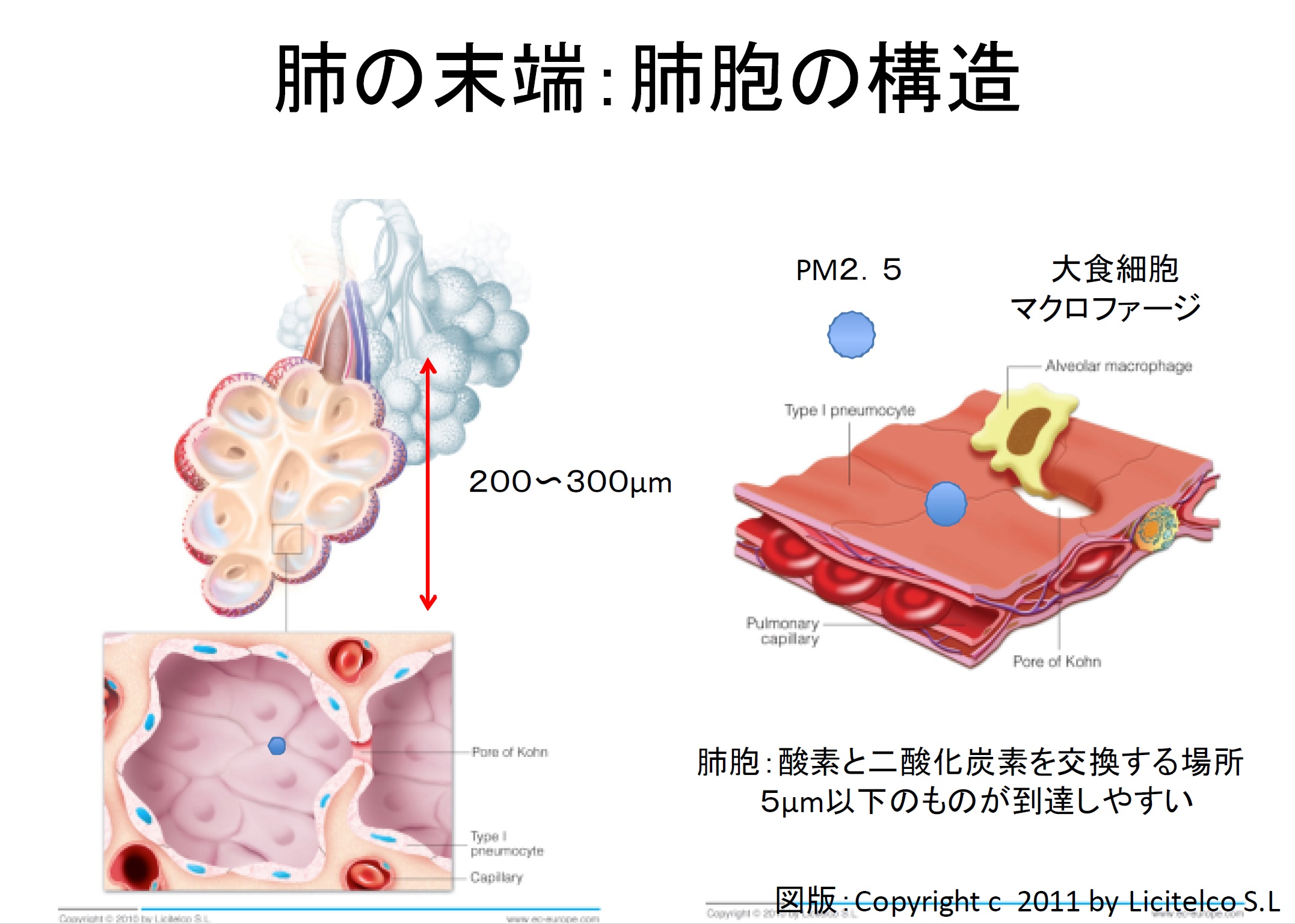
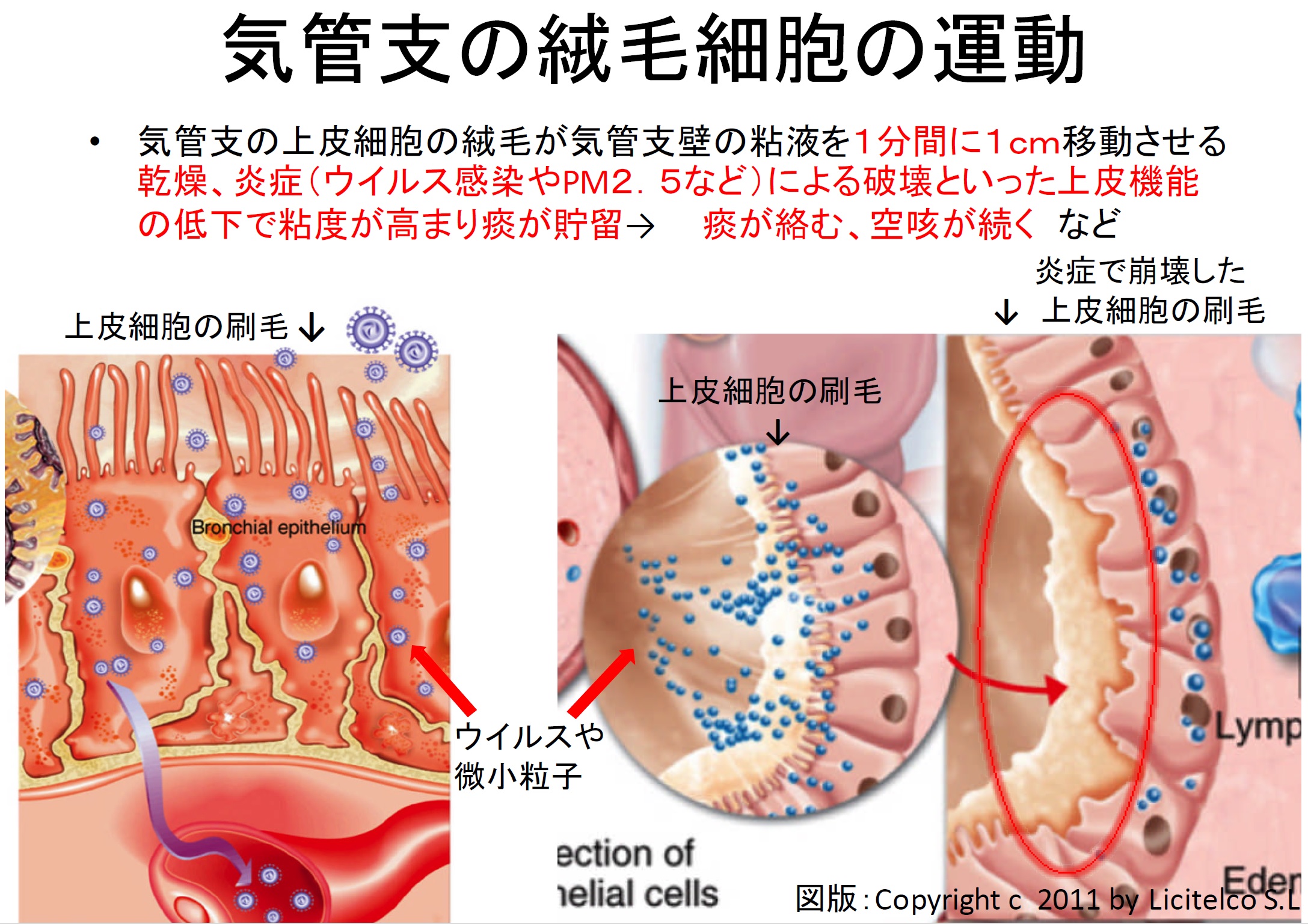
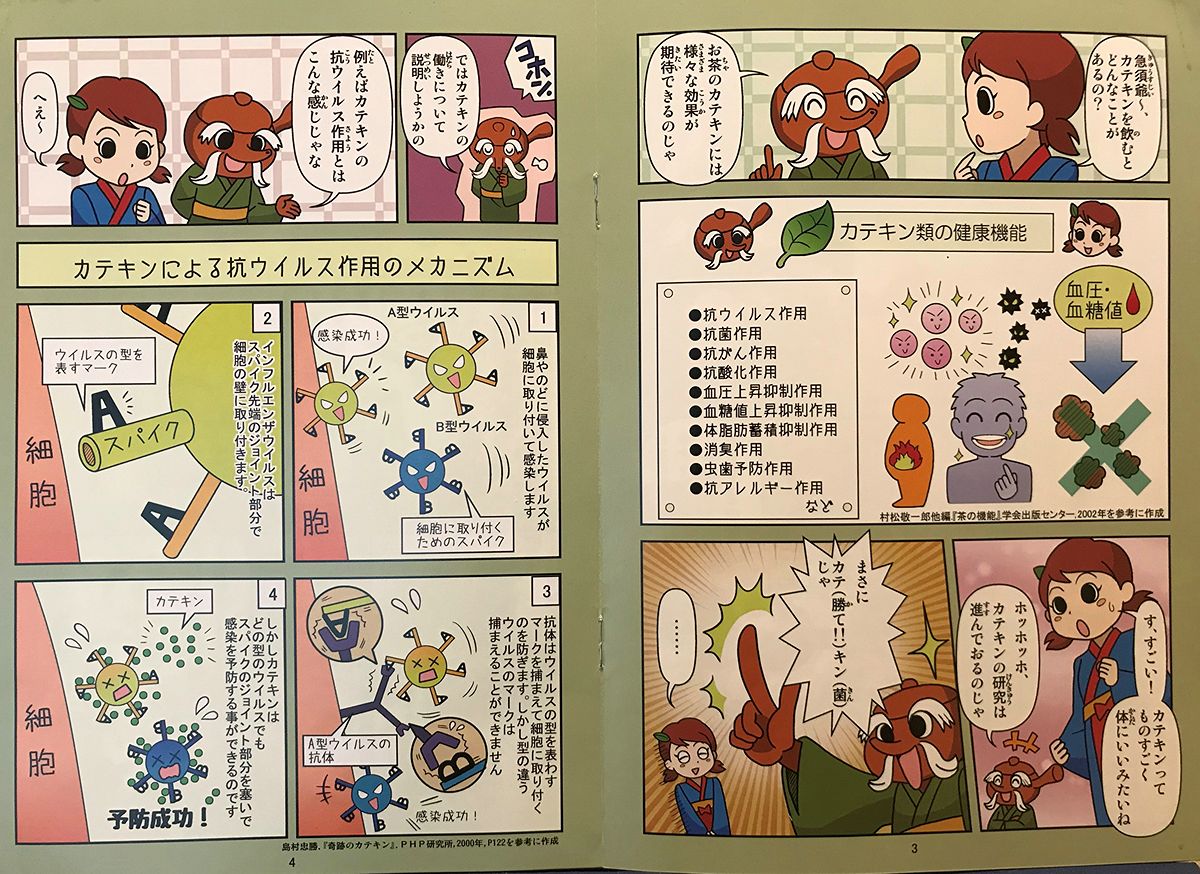
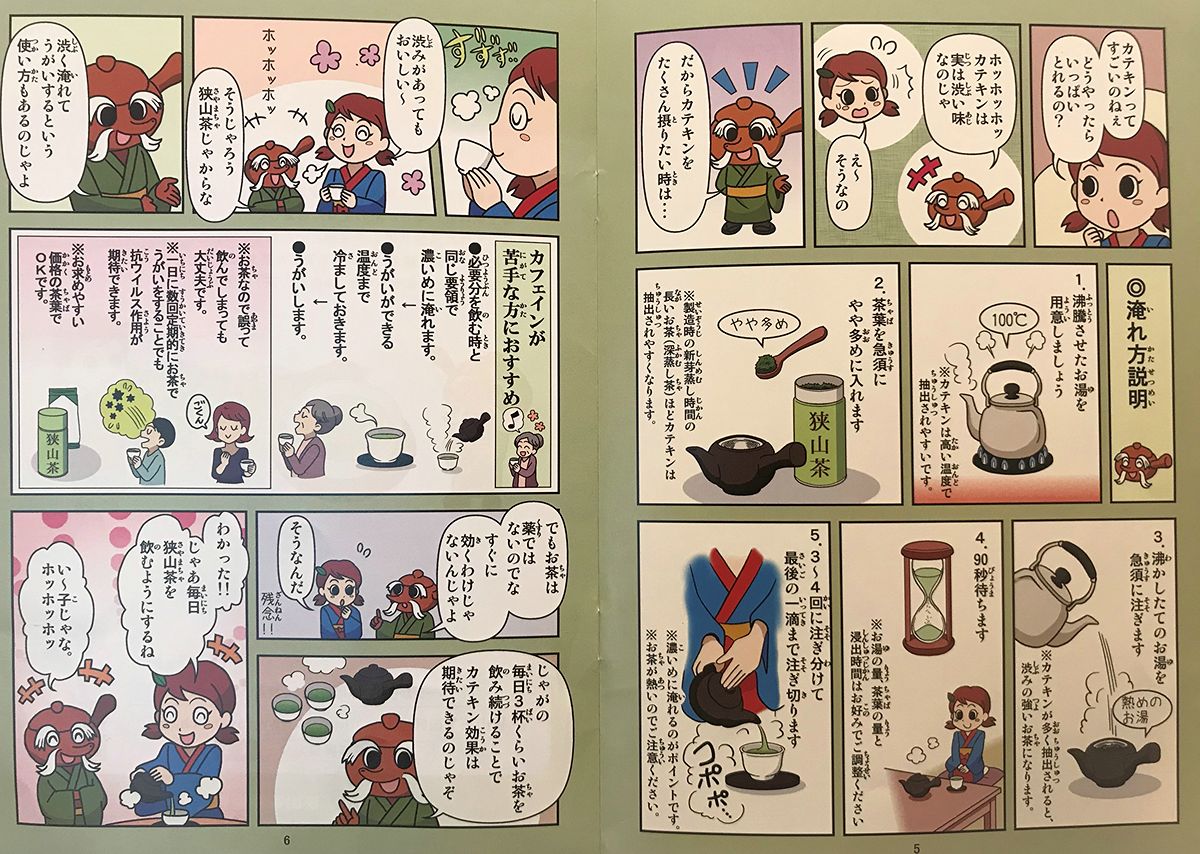
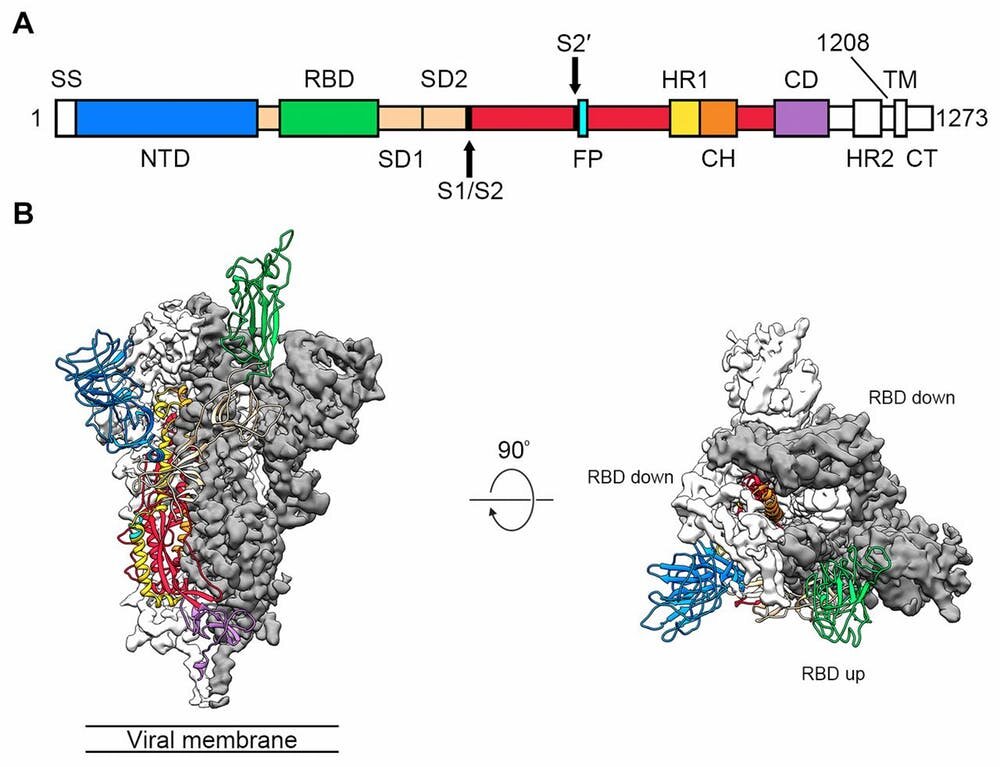
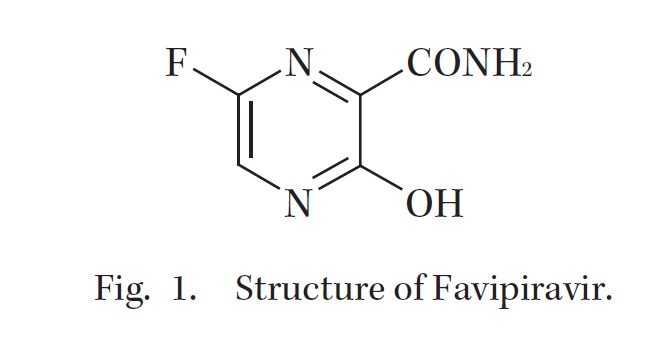
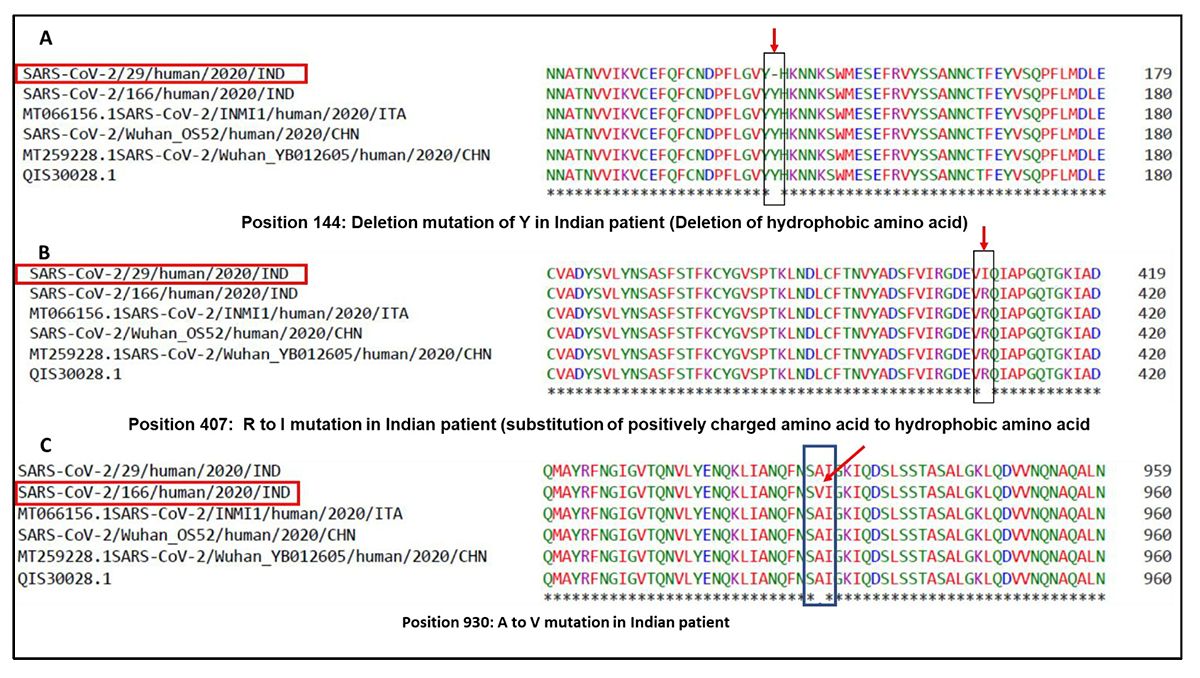
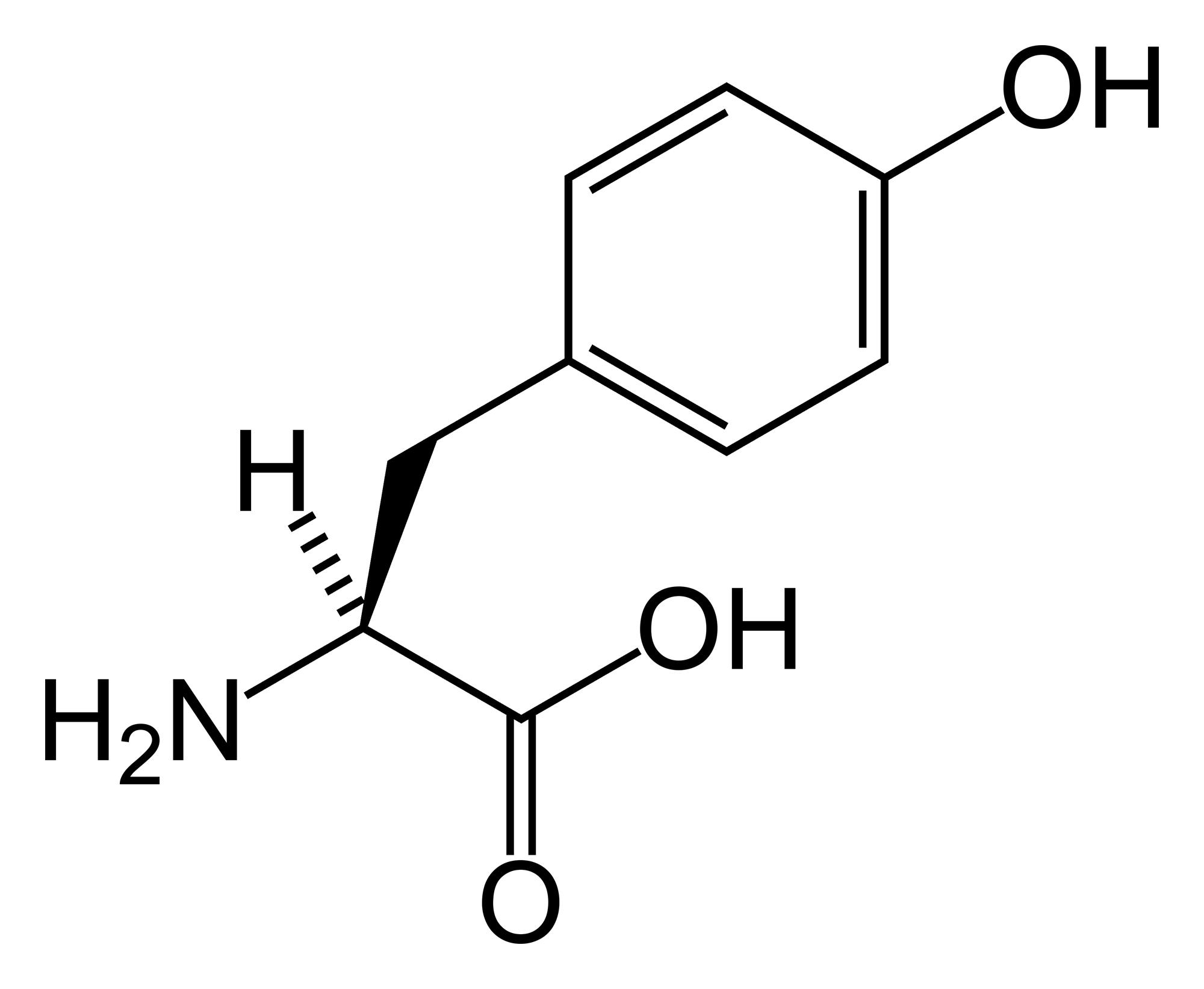 Tyrosine
Tyrosine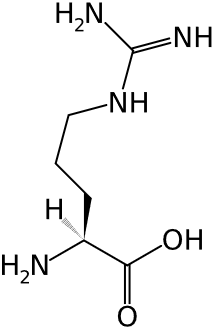 Arginine
Arginine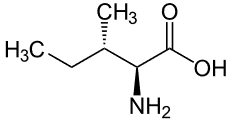 Isoleucine
Isoleucine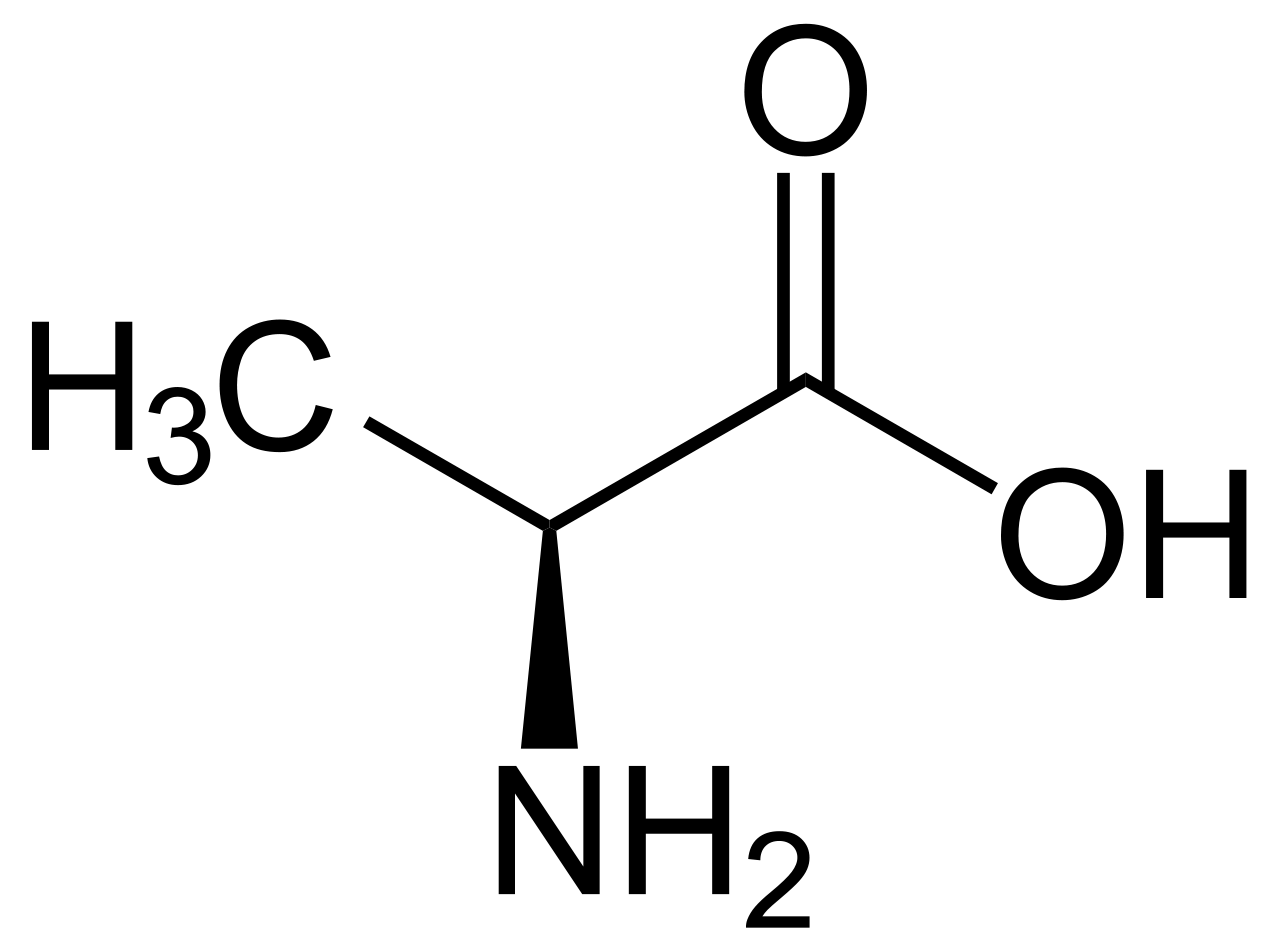 Alanine
Alanine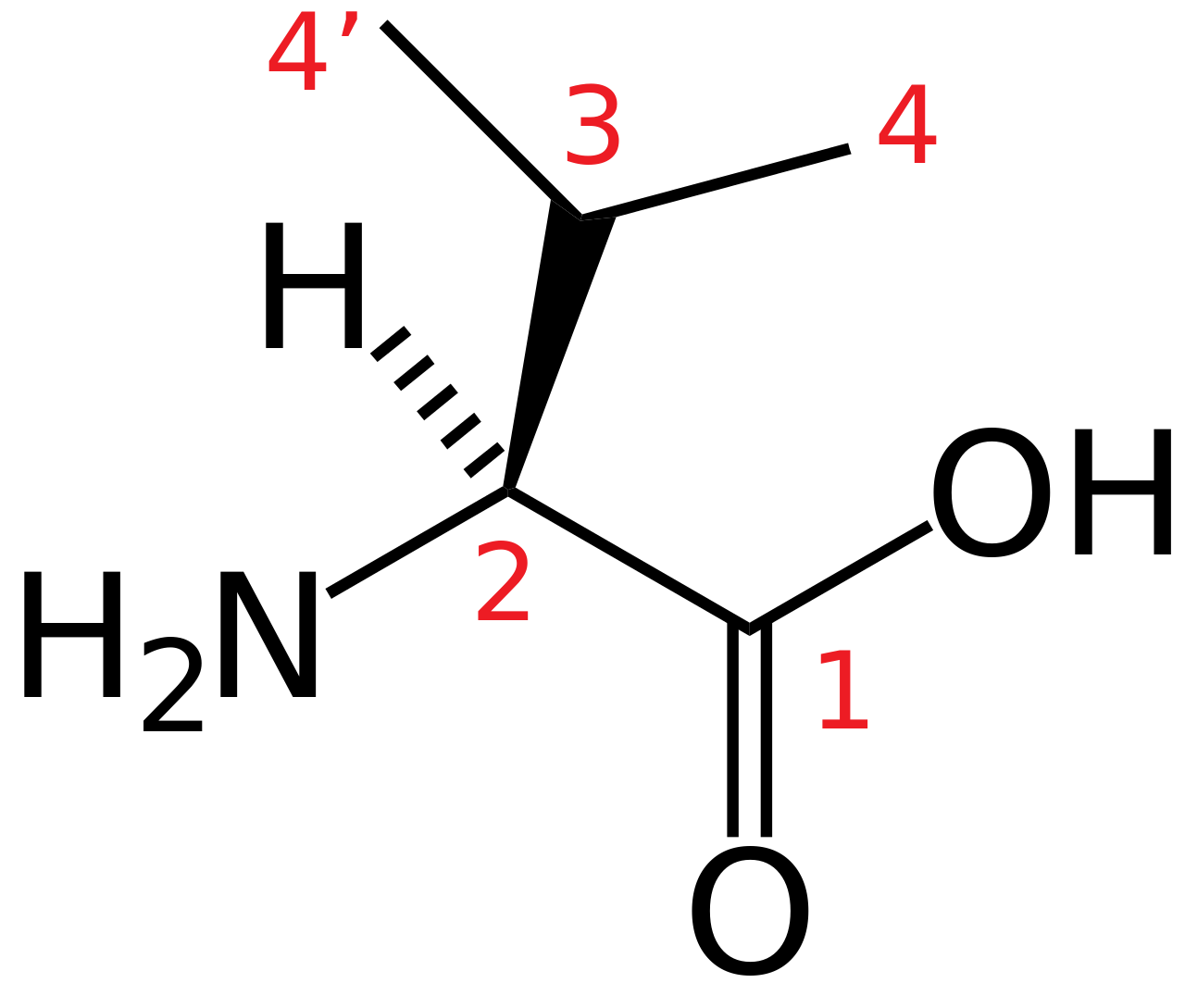 Valine
Valine