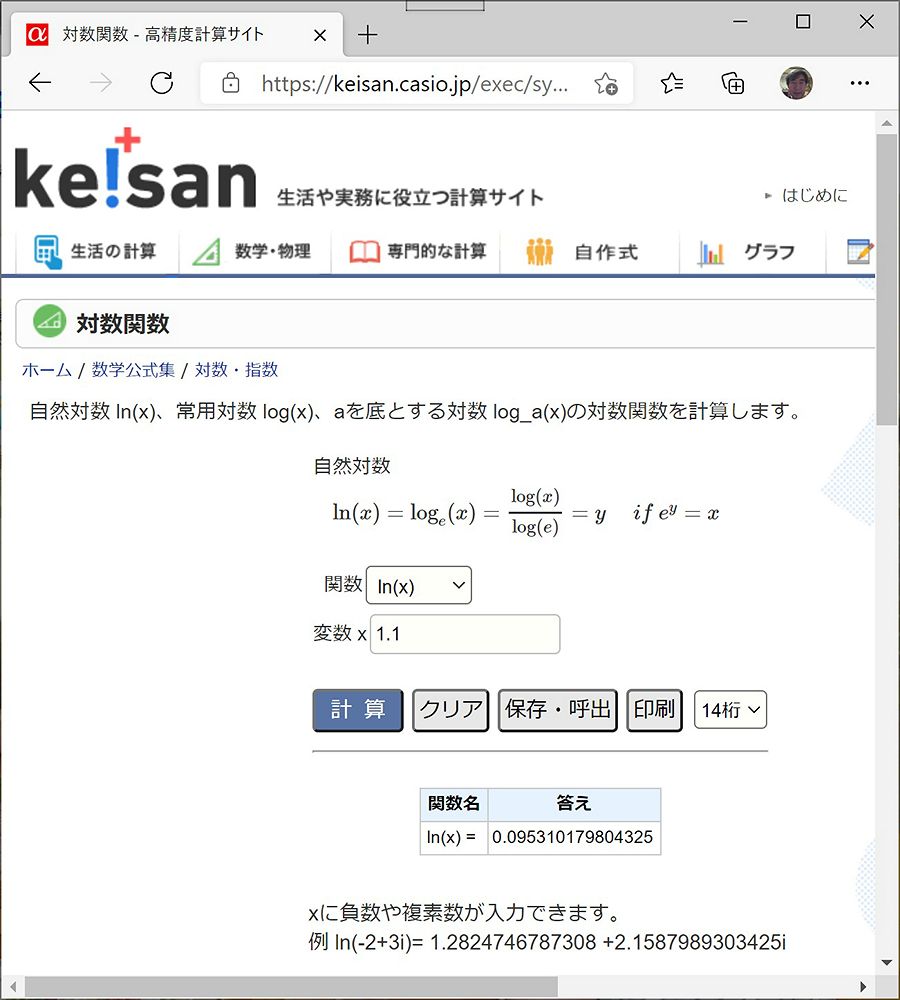���ǂ�
�����̏��ǂ��
------------------------------------------
2021.3.5���j��
�Z���狭�����߂�ꂽ�u�����̏�v�i�g�c�����A���C��w�o�ŕ��j��ǂݎn�߂��B
���w������ɖ߂��ēǂ�ł���B�ʔ����B
--------------------------------------
.jpg)
--------------------------------------
�ځ@��
�l�C�s�A��e�̌v�Z
�����̌v�Z
�~�����̌v�Z
�O�p���̌v�Z
�l�C�s�A��e�̌v�Z
�ڎ���
527�y�[�W�ɏ�����Ă��邱�ƁF
�w����y=10^x�ɂ��āA
�O���t��̓_�i0,1�j�ɂ�����ڐ��̌X��K���A
���悻�@K=2.3026
�ŗ^�����邱�Ƃ��킩�����B
���m�Ɍ����ƁA
X=0����1/65536�����i���̐��������ւ̑�����h���A
h=0.00003513527
�ŁA���҂̔�h/x��
K=2.30263505472
�ɂȂ�B
�Ƃ������ƂŁA�������炪�킩��Ȃ��Ƃ��낾���A
10^(1/K)=10^(1/2.3026)
���A���ʂ̐��i�l�C�s�A���j�ɂȂ�Ƃ����B
�m���ɁA10^(1/2.3026)=2.71826423 �E�E�E�E�@�l�C�s�A��e�Ɏ��Ă�
�����ŁA�����̊�b���v���o���Čv�Z���Ă݂��B
y=10^x
������y'�Ƃ��āA
y'=(10^(x+h)-10^x)/h
�@=(10^x*10^h-10^x)/h
�@=10^x(10^h-1))/h
x=0�̂Ƃ�
y'=(10^h-1))/h
�@
h�@�@�@�@�@�@y'
0.1...............2.589254118
0.01.............2.329299227
0.001...........2.30523807
0.0001.........2.3028501
0.00001.......2.302611
10^(1/2.302611)=2.718251245
�Ȃ�قǁI
y=2^x �Ȃ�ǂ���
y'=(2^(x+h)-2^x)/h
x=0�̂Ƃ�
y'=(2^h-1))/h
h�@�@�@�@�@�@y'
0.1..............0.7177346
0.01............0.695555004
0.001..........0.69338745
0.0001........0.6931711
0.00001......0.693148
2^(1/0.693148)=2.718278615
y=1.1^x �Ȃ�ǂ���
y'=(1.1^(x+h)-1.1^x)/h
x=0�̂Ƃ�
y'=(1.1^h-1))/h
h�@�@�@�@�@�@y'
0.1..............0.0957658271
0.01............0.095355613
0.001..........0.09531471
0.0001........0.09531
0.00001......0.09531
1.1^(1/0.09531)=2.718286957
�Ƃ������Ƃ́A
y=a^x�@�ɂ����āA
x=0�@�̂Ƃ��A
e=a^(1/y')
y=1^x �Ȃ�ǂ���
y'=(1^(x+h)-1^x)/h
x=0�̂Ƃ�
y'=(1^h-1))/h
h�@�@�@�@�@�@y'
0.1..............0
0.01............0
0.001..........0
0.0001........0
0.00001......0
1^(1/0)=error
�Ȃ�قǁI
�ł́A�}�C�i�X�l�́A
y=(-2)^x �Ȃ�ǂ���
y'=((-2)^(x+h)-(-2)^x)/h
x=0�̂Ƃ�
y'=((-2)^h-1))/h
h�@�@�@�@�@�@y'
0.1..............error
�Ȃ�قǁA�@a>1�@���������ȁB
�܂Ƃ߂�ƁA
------------------------------
�w����y=a^x�̓���y'�ɂ��āA
x=0�̂Ƃ��A
e=a^(1/y')
------------------------------
e=a^(1/y')�̗��ӂ����R�ΐ��ie���j�ɂ��āA
loge=loga^(1/y')
loge=1
loga^(1/y')=1/y'loga
�ƂȂ��āA
1=1/y'loga
y'=loga�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@
a=1.1�̂Ƃ��A
loga�͂ǂ������l�ɂȂ邾�낤���B
�ΐ����̌v�Z�T�C�g���g���ƁA
���p�Fhttps://keisan.casio.jp/exec/system/1260332465
�ΐ����̌v�Z
�ϐ����Ɂ@1.1�@�����āA
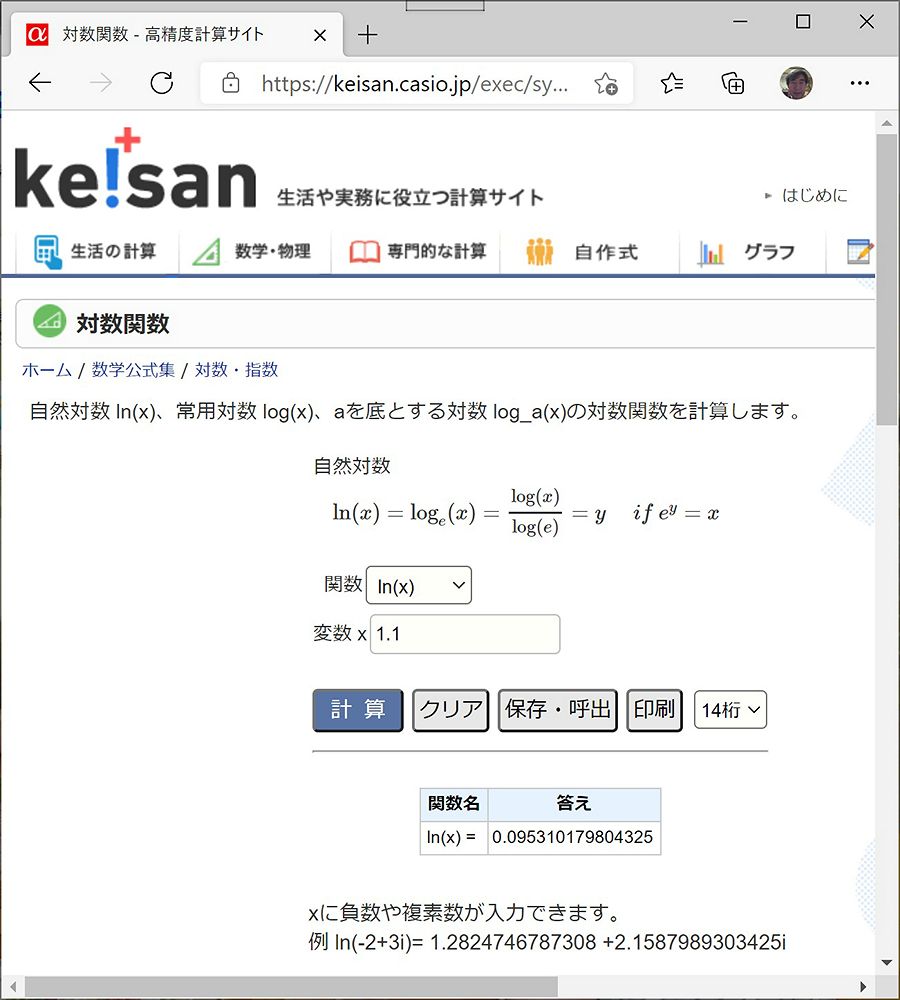
log1.1=0.095310179804325
1.1^(1/0.095310179804325)=2.718281829
e�̒l�ɋ߂Â��Ă���I
e=2.71828182846...
�w�����̔�������������ƁA
---------------------------
�C�ӂ�a>0�ɑ��āA
y=a^x �̓����́A
y'=a^xloga
---------------------------
x=0�@�̂Ƃ��A
y'=a^xloga=a^0loga=loga
y'=loga�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�A
�@�ɓ������A�n�j�B
�����̌v�Z
�ڎ���
e�̕��͂��̂��炢�ɂ��āA���悢�拕���̃y�[�W��ǂ�ł������B
2021.3.6�y�j��
���č����͋����̌v�Z�B
562�y�[�W��ǂ�ŁAEXCEL�Ōv�Z���Ă݂��B

���ڕW��
e^ix=i�@�̂Ƃ���x�̒l�����߂�B
���O��
x<<1�̂Ƃ��Ae^x�̎��̋ߎ��������藧�Bp.541,p560
e^x:=1+x+1/2x^2
x=ix�̂Ƃ��F
e^ix:=1-1/2x^2+ix
����1�i�K��
x=1/1024
e^(i/1024)=0.99999952316+i0.00097656250
e^(i/1024)����e^i�܂ŁA
e^(i/1024)^2=e^(i/512)�Ƃ����悤�ɏ���2�悵�Ď����Ƌ������v�Z���A
�Ō��e^i�����߂�ƁA
e^(i/1)=e^i=0.54030217061+i0.84147106834
����2�i�K��
e^i�̎���0.54030217061�Ƌ���0.00097656250�ɂ��āA
������2��+������2��́A
0.54030217061^2+0.84147106834^2=0.9999998031:=1
�Ƃ������Ƃ́A
��Βl��1�ia^2+b^2=1�j�ł��鋕��a+ib�ɑ��āA
����Ɋ|����� i �ƂȂ鋕��x+iy�́A
(a+ib)(x+iy)=i
x+iy=i/(a+ib)=i(a-ib)/((a+ib)(a-ib))=i(a-ib)/(a^2+b^2)=i(a-ib)/1=b+ia
x+iy=b+ia
�����ŁA
a+ib=b+ai�ł��邱�Ƃ𗘗p���āA
e^i�̎����Ƌ������������A
e^i�̎�����0�ɁA������1�ɋ߂Â��܂ŋߎ��v�Z���s���B
e^i=0.54030217061+i0.84147106834
�����Ƌ������������āA
0.84147106834+i0.54030217061
����ɋ߂��̂́Ae^(i/2)
�������|���Z����ƁAi�̋ߎ��l�ƂȂ邩��A
e^i*e^(i/2)=0.07073696355+i.99749499929
�ȉ����l�Ɍv�Z���Ă䂭�ƁA
e^i*e^(i/2)*e^(i/16)*e^(i/128)=0.00048357718+i0.99999987869
������0�ɋ߂Â��A������1�ɋ߂Â��Ă���B
e^(i/128)�̎��̌v�Z�́A
e^(i/?)=0.99999987869+i0.00048357718
e^i*e^(i/2)*e^(i/16)*e^(i/128)*e^(i/?)=0.00000000000+i0.99999999123:=i1
�ƂȂ��āA����������Ȃ�0�ɋ߂Â��A����������Ȃ�1�ɋ߂Â��B
�܂�A
e^i*e^(i/2)*e^(i/16)*e^(i/128)*e^(i/?):=i1
e^i(1+1/2+1/16+1/128+1/?):=i1
�Ƃ������Ƃ́A
e^ix=i�@�ɂȂ�̂́A
x=1+1/2+1/16+1/128+1/? �̂Ƃ��B
�����ŁA
1+1/2+1/16+1/128+1/?�̒l�́A
1.57079607712
���Ȃ킿�A��/2=1.57079632680�ɋ߂Â��B
�����ʁ�
e^(i*��/2)=i
���ӂ�2�悵�āA
e^i��=i^2=-1
����ŁA��ɐi�߂�B
------------------------------------
�~�����̌v�Z
�ڎ���
���āA403�y�[�W�ɏ]���ĉ~�������v�Z����ƁA
���a1�̒P�ʉ~�ƁA��(6*2^n)�p�`�̊W�́A�O�����̒藝�ɂ��A
�~�̒��S���猷a_n�ƌ����_�܂ł̒�����x �A���̓_���甼�a1�܂ł̒�����y�Ƃ���(x+y=1)�A
1^2=(a_n/2)^2+x^2�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@
a_(n+1)^2=(a_n/2)^2+y^2�E�E�E�E�A
�A-�@
a_(n+1)^2=1-x^2+y^2
y=1-x��������ƁA
a_(n+1)^2=1-x^2+(1-x)^2=2-2x
�E�E�E�E�B
�@���A
x=��(1-(a_n/2)^2)=��(1-a_n^2/4)
������B�ɑ�����āA
a_(n+1)^2=2-2x=2-2��(1-a_n^2/4)=2-��(4-4(a_n^2/4))=2-��(4-a_n^2)
�]���āA
a_(n+1)=��(2-��(4-a_n^2))
�������A���̌v�Z���Ōv�Z���Ă䂭�ƁA
n=49152���猅���������������B
�����ŁA405�y�[�W�ɏ]���A
���ꕪ�q�ɓ�����(2+��(4-a_n^2))���|����ƁA
a_(n+1)=��(2-��(4-a_n^2))*��(2+��(4-a_n^2))/��(2+��(4-a_n^2))
�@�@�@�@=��(2^2-(4-a_n^2))/��(2+��(4-a_n^2))
�@�@�@�@=��(a_n^2)/��(2+��(4-a_n^2))
�@�@�@�@=a_n/��(2+��(4-a_n^2))
����Ōv�Z����ƁA
n=1572864�܂Ō��������Ȃ��B
�����ʁ�

�����͂����܂ŁB
------------------------------------
�O�p���̌v�Z
�ڎ���
582�y�[�W�ɐi�ށB
���f�����ʏ�̒P�ʉ~�ɂ��āB
��Βl��1�ł��镡�f����Z�ŕ\���ƁA
Z=A+iB,�@�@|Z|=��(A^2+B^2)=1
�����Ƌ����p�O�p�`�̒�ӂƑΕӂƂ݂Ȃ��ƁA�Εӂ͌��_��Z�����Ԓ����ƂȂ�B
���̒����Ǝ����i��Ӂj������p���Ƃŕ\���ƁA
sin��=B/1=B
cos��=A/1=A
���������āA
Z=A;+iB=cos��+isinB
���āA�����Ő�قnjv�Z����������EXCEL�ɖ߂��āA
������cos�ƁA������sin�����W�A���Ƃ��Čv�Z���Ă݂�ƁA
�����ɏ����_�ȉ�6���T��5���܂ň�v���Ă���B

�܂�A
e^i��=cos��+isin��
�����͂����܂ŁB
2021.3.12���j��
x�����W�A���ŕ\���ƁAe^ix=cosx+isinx�ł��邱�Ƃ��킩�����B
�ł́A���̏ؖ��́H
�e�C���[�W�J��̕��������Ƃ�����B
���p�Fhttps://manabitimes.jp/math/1001
���l=���̂����_�ł̓�������v�Z�����l�̖����a
�e�C���[�̒藝�F
�@f(x)��a<=x<=b�ɂ����āA
�@n������\�ȂƂ��A
�@f(b) =��_(k=0,n-1)f'k(a)(b-a)^k/k! + f'n(c)(b-a)^n/n!
�@����c(a < c < b)�����݂���B
���ϒl�̒藝�̈�ʉ��ł���Ƃ����B
���ϒl�̒藝�F
�@���[a,b]�ŘA���A(a,b)�Ŕ����\�Ȋ�f(x)�ɑ��āA
�@ (f(b)-f(a))/(b-a) = f'(c)
�@����c���A���[a,b]�ɑ��݂���B
�@f(b) = f'(c)(b-a) + f(a)
�@f(b)
n=1�̂Ƃ�
f(b)=f(a)+f'(c)(b-a)
n=2�̂Ƃ�
f(b)=f(a)+f'(a)(b-a)+f''(c)(b-a)^2/2!
�͂��߂�
.jpg)